
このところ相次いで訃報を耳にする。6月にポール・スミス、ジョニー・スミス、サム・モスト、メトロノーム・レコードの創設者アンダーシュ・バーマン、7月にベンクト・ハルベルク、今月に入ってからジョージ・デューク、マリアン・マクパートランド、藤圭子、無名時代のビートルズをアメリカでプロモートした、というよりジャズファンにはオーネット・コールマンのマネージメントを手掛けた、と言ったほうがピンとくるだろうか、シド・バーンスタイン・・・
そしてこの10月に来日公演が予定されていたシダー・ウォルトンが、19日に亡くなった。58年にジジ・グライスを皮切りにルー・ドナルドソン、J.J.ジョンソの各バンドで勉強を重ね、62年にアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズが三管編成に切り替えた重要な時期に迎えられたピアニストだ。名門コンボの第二期黄金時代を支えたピアニストとなると派手に映るが、これが可愛そうなくら地味な存在だった。前任は特に日本で人気が高いボビー・ティモンズ、そしてフロントにはフレディ・ハバード、ウエイン・ショーター、カーティス・フラーという強力なホーンのバックでは目立たないのも無理はない。
65年に退団後はアビー・リンカーンの伴奏を務め、その後もイースタン・リベリオンや自己のトリオで活躍しているので常にジャズシーンにいたことになる。日本で人気が出てきたのは74年に来日した折、新宿ピットインで録音したレコードが出てからと思う。フュージョン全盛の時代にあって、サム・ジョーンズとビリー・ヒギンズで組んだトリオは新鮮であり、ファンキーという伝統に基づいたピアノの心地よさを改めて教えてくれたような気がする。写真は92年の作品で一緒に来日が予定されていたベースのデビッド・ウィリアムスと盟友のヒギンズがサポートしているが、「鈴の音」と形容されるタッチに磨きがかかり特段に美しい。シダイに良くなるシダーである。
58年にピアニストとしてスタートを切っているので、その活動期間は半世紀以上になるが、ジャズシーンは大きく変わった。流行に合わせてスタイルを変えたプレイヤーもいれば、その波に乗れなくて消えたミュージシャンもいる。一方でスタイルを守り抜いた人もいた。筋が通ったピアノは変わる必要もないし、ファンはその変わらないピアノをひたすら愛する。燻し銀のピアニスト、シダー・ウォルトン、享年79歳。合掌。
そしてこの10月に来日公演が予定されていたシダー・ウォルトンが、19日に亡くなった。58年にジジ・グライスを皮切りにルー・ドナルドソン、J.J.ジョンソの各バンドで勉強を重ね、62年にアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズが三管編成に切り替えた重要な時期に迎えられたピアニストだ。名門コンボの第二期黄金時代を支えたピアニストとなると派手に映るが、これが可愛そうなくら地味な存在だった。前任は特に日本で人気が高いボビー・ティモンズ、そしてフロントにはフレディ・ハバード、ウエイン・ショーター、カーティス・フラーという強力なホーンのバックでは目立たないのも無理はない。
65年に退団後はアビー・リンカーンの伴奏を務め、その後もイースタン・リベリオンや自己のトリオで活躍しているので常にジャズシーンにいたことになる。日本で人気が出てきたのは74年に来日した折、新宿ピットインで録音したレコードが出てからと思う。フュージョン全盛の時代にあって、サム・ジョーンズとビリー・ヒギンズで組んだトリオは新鮮であり、ファンキーという伝統に基づいたピアノの心地よさを改めて教えてくれたような気がする。写真は92年の作品で一緒に来日が予定されていたベースのデビッド・ウィリアムスと盟友のヒギンズがサポートしているが、「鈴の音」と形容されるタッチに磨きがかかり特段に美しい。シダイに良くなるシダーである。
58年にピアニストとしてスタートを切っているので、その活動期間は半世紀以上になるが、ジャズシーンは大きく変わった。流行に合わせてスタイルを変えたプレイヤーもいれば、その波に乗れなくて消えたミュージシャンもいる。一方でスタイルを守り抜いた人もいた。筋が通ったピアノは変わる必要もないし、ファンはその変わらないピアノをひたすら愛する。燻し銀のピアニスト、シダー・ウォルトン、享年79歳。合掌。










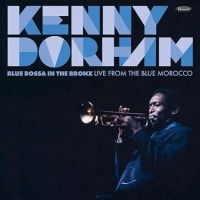

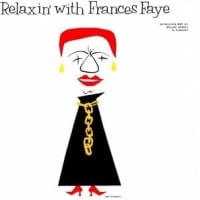

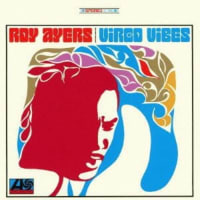

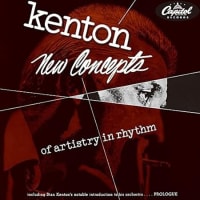


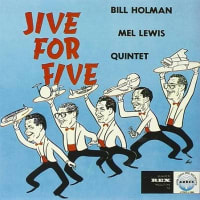





シダー・ウォルトンを最初に聴いたのはメッセンジャーズの「スリー・ブラインド・マイス」でしたが、ピアノは誰?と聞かれても答えられないほど地味でした。これがシダーのピアノかと衝撃を受けたのはピットインのライブ盤でした。ピットインにいた人が羨ましい。今週はシダー・ウォルトンを偲んでお気に入りのアルバムをリーダー作、サイド作問わずお寄せください。
管理人 Cedar Walton Best 3
Pit Inn (East Wind)
Manhattan Afternoon (Criss Cross Jazz)
First Set (Steeple Chase)
リーダー作とサイド作を合わせるとおそらく100枚以上を残していると思われますが、地味に聴こえるものでもやはり光るものがあります。
今週も皆様のコメントをお待ちしております。
Cedar Walton Quartet - Naima pt 1
http://www.youtube.com/watch?v=uU1s3IjhM3w
亡くなった翌日がたまたま自分のカルテットのライブでしたので急遽追悼の意を込めて5曲シダーさんの曲を演奏しました。我々が普段よくやるのはボリビアですが今回はボリビアではない5曲を選びました。改めてやってみるととても難しかったです。「なめたらあかんよ」とシダーさんに言われてるような気がしました。
昨夜はデイ・バイ・デイで良い演奏をありがとうございました。スピークロウとラヴァーマンの2曲でしたが、密度は濃かったですね。
作曲家としてのシダーは、他のプレイヤーがあまり取り上げないことから話題になりませんが、よく練られた曲ばかりです。演奏者としては難曲ほど決まったときの喜びが大きいことでしょう。またそんな素晴らしいライブを楽しみにしております。
FBで、いつもお世話になっております。
昨年7月に守屋純子さんのコンボで
演奏しておられるのを、青山B&Sで聴きました。
近藤さん、岡崎さん、片岡さん、納さん、守屋女史、
皆さん素晴らしかったです!
シダー・ウォルトン、よく聴くのは
「Something For Lester / Ray Brown」
「Centerpirce / Milt Jackson」あたりでしょうか。
シダーの曲というと、なんといっても
Holy Land が真っ先に思い浮かびます。
近藤さんは、あのアルト・サックスの近藤さんです。土曜日に熱帯JAZZ楽団のメンバーとして来札された折にデイ・バイ・デイに寄られ、2曲でしたがハウストリオと演奏されました。素晴らしかったですよ。
レイ・ブラウンやミルト・ジャクソンのアルバムにも参加しておりましたね。この2枚は適材といえるピアノを披露しております。
「Holy Land」は名曲ですが、 「Bolivia」、「Ojos De Rojo」、「Mode For Joe」も良い曲ですね。もっと多くのプレイヤーが取り上げるべきと思います。
何しろ、Dukeさんの言う、そのピットインの録音ライブの現場にも、1963年のJMの時も、全部現場に居たものとして・・・私はスリーブラインドマイスのシダーを評価してます。
ティモンズのノリノリの雰囲気はありませんでしたが、That's Old Feelingの抑えたノリは好きでしたし、只者ではないと思ったものです。
1、Pit Inn (East Wind)
これは決まり、
2、スリーブラインドマイス(UA)
3、サマーノウズ(EW)
3はアートファーマーがリーダーですが、内容も良いし・・。
次点が
First Set (Steeple Chase)
・・・という事です。
ついにこのブログにも近藤和彦さんが登場ですか!
近藤さん、私、近藤さんの明治の先輩である大隅寿男の後援会の世話人をしております。
いつも御茶ノ水ジャズ祭の楽屋ではお世話になっております。
また、秋の明治大学での「御茶ノ水ジャズ祭」でお世話になる事でしょう。宜しく。
やはりピットインの録音ライブの現場におられましたか。レコードでもあれだけ伝わるものがありますので、さぞかし現場は数倍の迫力だったのでしょう。もし、このレコーディングがなければ日本での評価は低いままだったかもしれません。
スリーブラインドマイスのシダーはフロントが強力なことから地味な印象を受けますが、よく聴くと知的です。ブレイキー親分が大きく編成を変えた意図を汲んだソロといえるでしょう。
ファーマーのサマーノウズにも参加しておりましたね。今思えばイースト・ウィンドというレーベルは時代の先を行っておりました。
近藤和彦さんのアルトは今回初めて聴きましたが、デイバイ・デイの温度が変わるほど熱かったです。機会があればじっくり聴きたいですね。
「ニュー・ディール」ですね。探してみましょう。
シダー・ウォルトンは、ミルト・ジャクソン=レイ・ブラウンのグループで来日した時に一回だけ聴きました。まだ若いと思っていたので、残念です。一番めは、やはりピットインです。
①Pit Inn (East Wind)
②First Set (Steeple Chase)
③Ray Brown / Something For Lester (Comtenporary)
最近聴いた、Donald Byrd / Slow Drag (Blue Note)もサイドメンのものとしていいところに挙げられます。シダーが2曲(「Book's Bossa」と「The Loner」)を提供し、彼のソロもよいものでした。