
6月27日Ⓒクラツーツアーで、田代山~帝釈山を縦走してきた。
6:40 東京駅発 東北🚄 那須塩原下車 🚌 11:00 田代山登山口

11:05 田代山、猿倉登山口 


 雨が降っています、午後になれば雨は上がるとの予報
雨が降っています、午後になれば雨は上がるとの予報

タニウツギ

田代山湿原まで標高差500m上ります

ゴゼンタチバナの宝庫でした。
4枚葉は花芽なし、6枚葉が咲くそうです(東北i♀ガイド談)

 アカモノ
アカモノ

 トゲブキ:ウコギ科とウラジロヨウラク:ツツジ科
トゲブキ:ウコギ科とウラジロヨウラク:ツツジ科

残ってました

日光連山?

 バイケイソウ
バイケイソウ

アズマシャクナゲ

オニアザミ:キク科

ネバリノギラン:夏(秋によく見る花ですが)

12:30 田代山湿原

ヒメシャクナゲ

花はツマトリソウ、赤い葉はイワカガミ、チングルマの葉も

チングルマ

オノエラン

12:45 田代山:1927m 
山頂に大湿原を持つ田代山。山上の楽園とも呼ばれ、シーズンには多くの花々で
埋めつくされる。その一角の栂の森に囲まれた弘法堂には田代山大明神と
 弘法大師が祀られている。
弘法大師が祀られている。
日 光連山、会津
光連山、会津 駒ケ岳、燧
駒ケ岳、燧 ケ岳の展望が素晴らしい。
ケ岳の展望が素晴らしい。

タテヤマリンドウの花と ”実”です
”実”です

木道の先に会津駒ヶ岳:2132m
イワナシ、イチヨウラン、モウセンゴケ、ワタスゲ等があった。

イワ カガミ
カガミ

 弘法大師堂兼避難小屋:
弘法大師堂兼避難小屋:

 昼食、雨は
昼食、雨は 上がりました
上がりました
13:20 帝釈山へ  まず下ります
まず下ります

 ギンリョウソウ(も多かった)
ギンリョウソウ(も多かった)
オオシラビソの林、足元はヌカルミ、滑る木段に注意して・・・・・。


オサバグサ(筬葉草):ケシ科
シダの葉を思わせる葉の形が特徴ある。その葉を機織りに用いる
筬に見立てたもの。草丈は15~20㎝、花も小さい。

エンレイソウ:ユリ科 ・・・登り返して

ミツバオウレン:キンポウゲ科

ムラサキヤシオ

15:30 帝釈山:2060m 
福島県と栃木県の境、帝釈山脈の主峰。
山頂には駒御堂権現が祀られ、桧枝岐の住民はこの山を守護神としていた。
360度の眺望だが、雲が多かったので 



ツマトリソウ:サクラソウ科

木道とオサバグサ

16:25 馬坂峠:1790m
迎えのバスで那須塩原駅へ、20:30 の新幹線で帰途に
*
行程:累積標高差700m/5.5km/5時間20分
7:49 那須塩原駅 🚌 11:00 猿倉登山口 ⇒12:30(田代山湿原)
⇒12:45 田代山 ⇒13:20 弘法大師堂・昼食 ⇒(オオシラビソの林)
⇒15:30 帝釈山 ⇒16:25 馬坂峠 = 🚌 =20:20 那須塩原駅
日本二百名山 帝釈山44 完登











 鈴
鈴 鹿
鹿 名古屋駅現地集合のⓂaitabi”
名古屋駅現地集合のⓂaitabi” 大名”ツアーだった)
大名”ツアーだった)
 一ノ谷山荘中登山口へ
一ノ谷山荘中登山口へ RWで湯の山温泉へ降りた。
RWで湯の山温泉へ降りた。
 空、雨の心配はないようだ。
空、雨の心配はないようだ。





 我々はこの斜面をほぼ
我々はこの斜面をほぼ 直登します。
直登します。













 登ってきました
登ってきました
 アカヤシオ
アカヤシオ

 踏んで・
踏んで・ ・
・
 フデリンドウと
フデリンドウと






 無理だった。
無理だった。
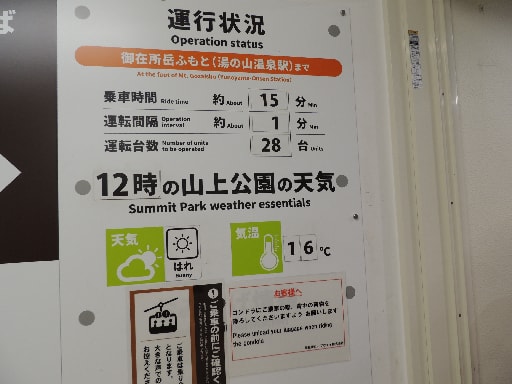
 分で降りた
分で降りた




 休みを経て、"気分
休みを経て、"気分 西武線横瀬駅へ降りた。
西武線横瀬駅へ降りた。
 迷った。
迷った。


 ダンコウバイ
ダンコウバイ



 手入れ)
手入れ)


 稜線へ
稜線へ

 大持山:1294m 右)
大持山:1294m 右) 子持山:1273m
子持山:1273m



 落葉樹林帯へ
落葉樹林帯へ
 子持山
子持山
 御岳神社
御岳神社 









 昼を食べて表参道を下山
昼を食べて表参道を下山


 発
発







 命
命







 ヒメオドリコソウ
ヒメオドリコソウ






 もさす想定外の展開、「戸隠神社・奥社」の先、高妻山登山口を右に、
もさす想定外の展開、「戸隠神社・奥社」の先、高妻山登山口を右に、 映える戸隠山も車窓から
映える戸隠山も車窓から 見えた。
見えた。

 雨は降っていません
雨は降っていません

 かぶれるよ!!!
かぶれるよ!!!


















 ,
,

 葉も
葉も
 戸隠神社・中社が登山口
戸隠神社・中社が登山口




 サブルート)
サブルート)
 錦秋の登山道(老々男女
錦秋の登山道(老々男女
 戸隠山が
戸隠山が





 ニセピークだった)
ニセピークだった)


 跡が
跡が










 南登山道(メインルート)へ
南登山道(メインルート)へ

 黄
黄
 葉・紅
葉・紅 葉、
葉、



 JALシティ長野へ
JALシティ長野へ

 鳥の照焼き、
鳥の照焼き、 美味でした。
美味でした。
 予報が出ていますが・・・・・。
予報が出ていますが・・・・・。