◆1.真実の音楽を求めて & 2.わが人生と芸術の学校
この二つの章はショスタコーヴィチが「この回想は自分自身ではなく他の人々についての回想だ」と言いながらも、幼少期含めた生涯を通覧して語るうちの、主にペテルブルグ音楽院在学期が中心だ。
無論、恩師グラズノフの想い出が触れられているし、全編を通し、随所に、ショスタコーヴィチがグラズノフに感謝し、深い敬慕の念を抱いていたかが滲み出ている。
興味深いのは、プロコフィエフが発表した「スキタイ組曲」をグラズノフが評価せず演奏会の席を立って帰ってしまったこと。また、コルサコフに与えられた管弦楽法の宿題で間違いを指摘されたのに「ほら、老人が怒った」と茶化すなど、他の学生の前で失礼な振る舞いをした情景が描かれ、生涯を通じて不仲だった背景は師への侮辱に端を発したのか?と思わせる部分だ。
プロコフィエフについて、ショスタコーヴィチは2章で約6頁相当分(2段組み邦訳ベース)を割き、細かく描いている。とりわけ、一度はソ連を出てパリに住んだプロコフィエフが共産党当局の
甘言に載せられソ連へ戻ったあとの二人の確執は、無論まだ生まれておらず執筆当時30代半ばの若造に過ぎなかったヴォルコフに創作できる筈は無く、火花を散らしたショスタコーヴィチ本人で
なければ描けまい。
2章には当時の先輩作曲家や指揮者に加え、オペラ劇場演出家・メイエルホリドまで含めた興味深い逸話が山ほどある。中でも、プロコフィエフ以上に多くの頁をショスタコーヴィチが割いている
音楽院教授・ソレルチンスキーに関する逸話は面白い。それは、ソレルチンスキーがスクリャービン(1872-1915)は評価しないと講演会の場で述べたことを取り上げたショスタコーヴィチ自身は、
スクリャービンのさらに先輩であるムソルグスキー(1839-1881)やリムスキー・コルサコフ(1844-1908)、其の薫陶を受けたグラズノフ、こういった一連の水脈を大事に思い評価していた点だ。
対照的にショスタコーヴィチは、ムソルグスキーやリムスキー・コルサコフとほぼ同世代のチャイコフスキー(1840-1893)について全く触れておらず、論評していない。これは何を意味するのか?
どの頁か忘れたが、ショスタコーヴィチ自身がチャイコフスキーの名に触れた部分は(誰かの書斎だか事務所だかでチャイコフスキーの肖像画を眺めた・・)ここしかない。チャイコフスキーの音楽についてすら何も語っていないので、余りのあっけなさに驚き、気付いた次第である。・・・・何故なのだろう? 私なりに考えるうち、次の2箇所にヒントがあると思えたので引用する。
ウイーンの作曲家・ベルクが作ったオペラ『ヴェツェク』の中で歌う予定の女性歌手が扁桃腺炎で喉を傷めたのに、ベルクがレーニングラードに来てくれているからと、当局は歌うのを命じた。
【1】<他の国だったら恐らく初演は延期されることだろうが、此の国では有り得ない。外国人の前で我々はどうして恥を晒すことができようか、というわけである。>・・・次の一節が重要だ。
<これは、わが国では外国人と外国の全てのものが軽蔑されているせいではないかと思う。不健全な自尊心は不健全な崇拝の裏返しである。そして同じ一人の人間の心の中に、自尊心と崇拝が仲良く
共存している。その良い例がマヤコフスキーだ。彼は詩の中でパリやアメリカに唾を吐きかけたにも拘わらず、パリでシャツを買うのが好きだった>(同71頁)
【2】音楽院作曲科の教師・シュティンベルグの想い出にある<シュティンベルグの娘がコルサコフの夫であり、コルサコフ家ではチャイコフスキーへの激しい嫌悪が溢れていた。>何故なら
<チャイコフスキーがすぐ傍で作曲していたため、コルサコフは委縮して全く作曲できなかった。チャイコフスキーが死ぬと、10年間書けなかったオペラを書き始めたが、その主題は
チャイコフスキーの残したオペラの改編だった。また、プロコフィエフが、チャイコフスキーの交響曲第一番の総譜に音程の誤りを見つけたとコルサコフに見せたところ、大喜びした>(同104頁)
⇒ ”チャイコフスキーがすぐ傍で作曲していたため、コルサコフは委縮して”・・・の意味はよくわからないが、物理的ではなく精神的に圧倒されていたと解釈すべきであろう。
【1・2】を踏まえ、以下は私の推測。知っての通り、チャイコフスキーの音楽は19世紀までに西欧が培ってきた作曲書法を受け継ぐ正統的なモノであり、「ロシア5人組」が打ち出そうとした民族色
を前面に出す試みとは相容れなかった。若き日のコルサコフは「5人組」と近かったが、チャイコフスキーの死を境に、寧ろ正統派的本流ともいえる作風に変わった。グラズノフ、ストラヴィンスキー、
アレンスキー、そしてプロコフィエフなどを輩出した教育者でもあり、其の流れにあるショスタコーヴィチはもっとコルサコフやグラズノフを通じてチャイコフスキーへの敬意を抱いても良さそうだが、
そうではない。
其の背景?まずはロシア革命期に育ったショスタコーヴィチにとり、チャイコフスキーは半世紀以上前に”終わった人”であり、且つ、西欧かぶれを「プチブル根性」「帝国主義の走狗」と批判する世を
生き抜くうえで、チャイコフスキーに触れる事自体が危なかったのではないか? たぶん、若くしてそれを敏感に悟り、彼は批判に晒されながらも何とか処刑を免れたのだろう。
事実上、パリへ亡命した恩師やストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ラフマニノフなどを横目に【1】を弁えつつも、ショスタコーヴィチの心中は重く複雑至極であったろう。
通読して感服するのは、ショスタコーヴィチは観察眼鋭く、言葉の選択が沈着冷静であること。然しながら、西欧の作曲家の批評・コメントにおいて「ヨーロッパ的な~」という形容がよく出てくる。
そこに私は、社会主義革命下の”反西欧”空気だけではない、彼自身に潜む≪ 異郷感覚 ≫も見てとるのだ。
さて明日は、3から5章まで、スターリン支配下ソ連の恐怖社会をショスタコーヴィチがどう生き抜いたのか? おぞましく、吐き気すら催すが、ここを歩んでみたい。 < つづく >
この二つの章はショスタコーヴィチが「この回想は自分自身ではなく他の人々についての回想だ」と言いながらも、幼少期含めた生涯を通覧して語るうちの、主にペテルブルグ音楽院在学期が中心だ。
無論、恩師グラズノフの想い出が触れられているし、全編を通し、随所に、ショスタコーヴィチがグラズノフに感謝し、深い敬慕の念を抱いていたかが滲み出ている。
興味深いのは、プロコフィエフが発表した「スキタイ組曲」をグラズノフが評価せず演奏会の席を立って帰ってしまったこと。また、コルサコフに与えられた管弦楽法の宿題で間違いを指摘されたのに「ほら、老人が怒った」と茶化すなど、他の学生の前で失礼な振る舞いをした情景が描かれ、生涯を通じて不仲だった背景は師への侮辱に端を発したのか?と思わせる部分だ。
プロコフィエフについて、ショスタコーヴィチは2章で約6頁相当分(2段組み邦訳ベース)を割き、細かく描いている。とりわけ、一度はソ連を出てパリに住んだプロコフィエフが共産党当局の
甘言に載せられソ連へ戻ったあとの二人の確執は、無論まだ生まれておらず執筆当時30代半ばの若造に過ぎなかったヴォルコフに創作できる筈は無く、火花を散らしたショスタコーヴィチ本人で
なければ描けまい。
2章には当時の先輩作曲家や指揮者に加え、オペラ劇場演出家・メイエルホリドまで含めた興味深い逸話が山ほどある。中でも、プロコフィエフ以上に多くの頁をショスタコーヴィチが割いている
音楽院教授・ソレルチンスキーに関する逸話は面白い。それは、ソレルチンスキーがスクリャービン(1872-1915)は評価しないと講演会の場で述べたことを取り上げたショスタコーヴィチ自身は、
スクリャービンのさらに先輩であるムソルグスキー(1839-1881)やリムスキー・コルサコフ(1844-1908)、其の薫陶を受けたグラズノフ、こういった一連の水脈を大事に思い評価していた点だ。
対照的にショスタコーヴィチは、ムソルグスキーやリムスキー・コルサコフとほぼ同世代のチャイコフスキー(1840-1893)について全く触れておらず、論評していない。これは何を意味するのか?
どの頁か忘れたが、ショスタコーヴィチ自身がチャイコフスキーの名に触れた部分は(誰かの書斎だか事務所だかでチャイコフスキーの肖像画を眺めた・・)ここしかない。チャイコフスキーの音楽についてすら何も語っていないので、余りのあっけなさに驚き、気付いた次第である。・・・・何故なのだろう? 私なりに考えるうち、次の2箇所にヒントがあると思えたので引用する。
ウイーンの作曲家・ベルクが作ったオペラ『ヴェツェク』の中で歌う予定の女性歌手が扁桃腺炎で喉を傷めたのに、ベルクがレーニングラードに来てくれているからと、当局は歌うのを命じた。
【1】<他の国だったら恐らく初演は延期されることだろうが、此の国では有り得ない。外国人の前で我々はどうして恥を晒すことができようか、というわけである。>・・・次の一節が重要だ。
<これは、わが国では外国人と外国の全てのものが軽蔑されているせいではないかと思う。不健全な自尊心は不健全な崇拝の裏返しである。そして同じ一人の人間の心の中に、自尊心と崇拝が仲良く
共存している。その良い例がマヤコフスキーだ。彼は詩の中でパリやアメリカに唾を吐きかけたにも拘わらず、パリでシャツを買うのが好きだった>(同71頁)
【2】音楽院作曲科の教師・シュティンベルグの想い出にある<シュティンベルグの娘がコルサコフの夫であり、コルサコフ家ではチャイコフスキーへの激しい嫌悪が溢れていた。>何故なら
<チャイコフスキーがすぐ傍で作曲していたため、コルサコフは委縮して全く作曲できなかった。チャイコフスキーが死ぬと、10年間書けなかったオペラを書き始めたが、その主題は
チャイコフスキーの残したオペラの改編だった。また、プロコフィエフが、チャイコフスキーの交響曲第一番の総譜に音程の誤りを見つけたとコルサコフに見せたところ、大喜びした>(同104頁)
⇒ ”チャイコフスキーがすぐ傍で作曲していたため、コルサコフは委縮して”・・・の意味はよくわからないが、物理的ではなく精神的に圧倒されていたと解釈すべきであろう。
【1・2】を踏まえ、以下は私の推測。知っての通り、チャイコフスキーの音楽は19世紀までに西欧が培ってきた作曲書法を受け継ぐ正統的なモノであり、「ロシア5人組」が打ち出そうとした民族色
を前面に出す試みとは相容れなかった。若き日のコルサコフは「5人組」と近かったが、チャイコフスキーの死を境に、寧ろ正統派的本流ともいえる作風に変わった。グラズノフ、ストラヴィンスキー、
アレンスキー、そしてプロコフィエフなどを輩出した教育者でもあり、其の流れにあるショスタコーヴィチはもっとコルサコフやグラズノフを通じてチャイコフスキーへの敬意を抱いても良さそうだが、
そうではない。
其の背景?まずはロシア革命期に育ったショスタコーヴィチにとり、チャイコフスキーは半世紀以上前に”終わった人”であり、且つ、西欧かぶれを「プチブル根性」「帝国主義の走狗」と批判する世を
生き抜くうえで、チャイコフスキーに触れる事自体が危なかったのではないか? たぶん、若くしてそれを敏感に悟り、彼は批判に晒されながらも何とか処刑を免れたのだろう。
事実上、パリへ亡命した恩師やストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ラフマニノフなどを横目に【1】を弁えつつも、ショスタコーヴィチの心中は重く複雑至極であったろう。
通読して感服するのは、ショスタコーヴィチは観察眼鋭く、言葉の選択が沈着冷静であること。然しながら、西欧の作曲家の批評・コメントにおいて「ヨーロッパ的な~」という形容がよく出てくる。
そこに私は、社会主義革命下の”反西欧”空気だけではない、彼自身に潜む≪ 異郷感覚 ≫も見てとるのだ。
さて明日は、3から5章まで、スターリン支配下ソ連の恐怖社会をショスタコーヴィチがどう生き抜いたのか? おぞましく、吐き気すら催すが、ここを歩んでみたい。 < つづく >










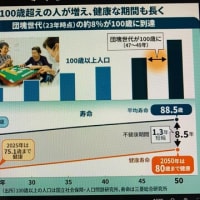














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます