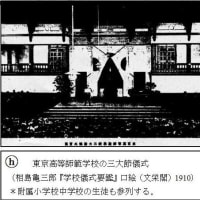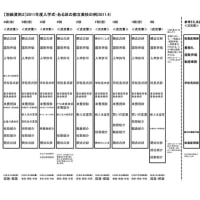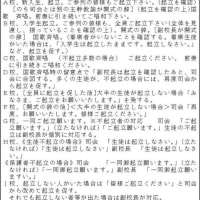◎信夫郡松川村石合の女泣石(1923)
本年七月八日の当ブログに、「松川事件と『女泣石』」というコラムを書いた。松川事件の現場に、「女泣石」〈メナキイシ〉という奇石が存在するのは、偶然ではないということを述べた。事件の首謀者が、犯行場所を選定する際、あるいは、関係のメンバーにその場所を伝達する際、この奇石が目印とされたという見方を示したのである。
その後、『土の鈴』第一八輯(一九二三年四月)に、「女泣石と女形石」という文章が載っていることに気づいた。本日は、これを紹介したい。筆者は、俳人の富士崎放江(一八七四~一九三〇)である。
なお、『土の鈴』は、民俗学者の本山桂川(一八八八~一九七四)が、長崎市で編集・発行していた雑誌で、非売品。
女泣石と女形石 放江庵主人
東北本線の上り列車が福島駅を発車しまして十五分、金谷川駅を通過してから約一哩〈マイル〉も走つた頃、視線を左側の窓前に放つて居りますと、千頃〈センケイ〉の桑圃が水田に尽きて小丘を為して居ります。その土崩れした崖の根元から、突兀〈トツコツ〉として一大巨石が天に朝すと申せばチト大袈裟ですが、怪偉な雄姿を聳やかして居るのを見るのであります。長さは六尺しかありませんが―発掘したら余程長いものでせう―楕円型より少し長目で、周りは二タ抱〈フタカカエ〉慥に〈タシカニ〉あります、そしてその尖端に亀裂がありまして、全容は驚大な男根の亀頭に酷似して居るのであります。
この石のある地域は、福島県信夫郡〈シノブグン〉松川村字石合〈アザ・イシアイ〉で、字名もこの石のある所から命名されたものらしいのであります。自然の悪戯〈イタズラ〉とは云へ、聊か〈イササカ〉ならず滑稽に感ぜられるのでありますが、土地人に依つて、遠い音から一種の霊異と崇信が伝へられてあります。それは原人以来、已に〈スデニ〉陳腐に申し伝へられて居る性器崇拝なのでありますが、その信仰を更に露骨に表現せしむべく、懐胎を念求する婦人は自分の肌をこの石の一部に抱着せしめて、その体温で石の肌が徴温を呈するまで念々抱擁を続ければ、必ずこれに霊感して受胎するといふのであります。併し灯台下暗しのい故か、土地人の信仰はそれ程でもありませんが、隣郡から聞き伝へて、時折参詣イヤ祈願してゐる婦人を見受けるそうです。何しろ桑畑と水田の間にありますので、白昼之を抱擁する程熱烈な信仰者もありますまいが、たゞ祈念だけしてゆくものは月に五六人位見受けると、そこの桑畑に枯枝を束ねて居る耕夫が話して呉れました。が幸に祈願が成就して、玉の如〈ヨウ〉なのが生れたからとて、お礼参りに来てもお供物も捧げられないし、マサカ鳥居も建てられないのですから、閭人はたゞ壟圃〈ロウホ〉中の一大頑石としか見て居らんのであります。併し不思議なことにはこの石の在る所へ通ずる田の畔〈アゼ〉よりか稍〈ヤヤ〉広い道が、西と南に二筋、しかも坦々と踏みつけられてあるのを見ますと、窃か〈ヒソカ〉にお百度位踏んで居る熱心な信者が屹度〈キット〉あることを証明されるのであります。
話は異ひ〈チガイ〉ますが、あのスキーで近頃有名になつた隣県〔山形県〕の五色〈ゴシキ〉温泉は、あかん坊の出来る温泉といふて昔から名高いのでありますが、これは浴槽の中に抱石〈ダキイシ〉ご云ふ一と抱え〈イトカカエ〉位の滑々〈スベスベ〉した石があるのであります。温泉の中にあるので、これに裸のまゝ抱付いて居たとて一向差支〈サシツカエ〉ありませんけれども、松川の女泣石は四方空澗な田園の中に在るのですから甚だ抱付きにくいのであります。でありますから僅か三里しか隔てゝ居らぬ福島の市民にもこの石の所在すら知つて居る者は稀なのであります。
女沈石どいふ名称は、婦人が泣いて祈願するといふ意であると土老が申して居りますけれども、宮居〈ミヤイ〉さへない露出の崇拝神でありますから縁起も由緒も昔からな〔か〕つたのでありませう。
【一行アキ】
この男性神に対立して、福島市を距る〈ヘダツル〉東約一里の地点(信夫郡岡山村大字山口字女形〈アザ・オナガタ〉)――県道の坂みちを開鑿〈カイサク〉した傍側を、約三尺程深く削込んだ所に安置してある「女形石〈オナガタイシ〉」の現存してるは何といふ奇因縁でせう。この石は三四年前までは、スグこの道の下の鈴木半四郎さんの屋敷前に転がつて居たのですが、通行の男女が恰度〈チョウド〉腰を掛けるによいので、疲れを休めたりなどして居りました。不思議にもこれに腰をかけたものは屹度怪我をするとか、下〈シモ〉の病に罹つたり〈カカッタリ〉しますので、これは字名〈アザナ〉の根元たる名石であるのに、腰をかけたりなどするから罰〈バチ〉が当るのであらう今に石神の怒〈イカリ〉が強くなつて大罰の当らぬうちに他の所へ奉祀しようではないかと相談があつて、村の青年団有志も手伝ひ、現在の所へ舁ぎ上げて安置したのださうです。石の高さは約二尺位で、幅は二尺七八寸の横広がりです。そしてその形状は桃の実の断面を見るやうに頂点から一尺二寸ほど割れがありまして、石肌の荒らい花崗質の苔石であります。併し松川村の陽石の如〈ゴトク〉に、その形状が真に迫つて居りませんが、裂割したあたりに苔が生え蒸して凹面を掩うて居るさまは、聊かながら髣髴させて居ります。それを一昨年の旧十一月十五日同村の老神職山口道智翁(七十五歳)が御魂鎮めをしましてから、毎年この日を祭日と定め奉祀することになつたのであります。そして此の石に何神の御霊を鎮魂したかと聞けば天宇受〔売〕命〈アマノウズメノミコト〉だと道智翁が真面目に答へられたのには、勿体ないことですが噴飯さず〈フクダサズ〉には居られなかつたのであります。いかに陰石だとて数ある女神の中から特に天宇受売命を択抜して鎮魂したのは道智翁一代の御手柄であらうと村の人々も言囃して居ります。爾来女の病気なら何んでも祈念して平癒せぬと云ふことなく、現に慢性の子宮病が立所〈タチドコロ〉に快癒して愛児を挙げた霊験が同村にも二三いやちこ〔灼然〕がられて居ると道智翁の御託宣であります。
信夫一国誌といふ古い本に、山の形が恰度ホドに似て居るから山口村女形といふと書いてあるさうですから、可なり古くからこの石の存在が認められて居たらしいのであります。
附記 本稿の骨子は昨年四月報知新聞福島版に連載された「信仰ロマンス」の材料で、同記事の筆者有馬暁鼓君の快諾を得て抄録したのであります。写真も同君が撮影されたのを頂きました。
このあとも、『土の鈴』の記事の紹介を続けたいと思っていますが、明日に限っては、『クイズ年鑑 1955年(前期)』に話を戻します。