「ボウリング・フォー・コロンバイン」 2002年 カナダ / アメリカ

監督 マイケル・ムーア
出演 マイケル・ムーア
チャールトン・ヘストン
マリリン・マンソン
マット・ストーン
ジョージ・W・ブッシュ
ストーリー
マイケル・ムーア監督はコロンバイン高校での銃乱射事件をめぐるメディア報道と社会の反応に疑問を抱き、精力的な行動力とユーモアを武器に企業や著名人に取材し、さまざまな角度から米国銃社会を検証していく。
コロンバイン高校銃乱射事件の被害者、犯人が心酔していた歌手のマリリン・マンソンや全米ライフル協会(NRA)会長(当時)のチャールトン・ヘストン、『サウスパーク』の制作者マット・ストーン、清教徒のアメリカ大陸移住から現在までの銃社会の歴史検証や、コロンバイン市民らへのインタビューを行う。
そして、アメリカの隣国で隠れた銃器大国のカナダ、日本やイギリスなどの他の先進国との比較から、事件の背景と銃社会アメリカのいびつで異常な姿をあぶり出してゆく。
本作では銃規制を訴えてはいるが、しかしカナダはアメリカ以上に銃の普及率が高いのに、銃犯罪の発生率が低いのはなぜなのかという今まであまり疑問を待たれずにいたことにも、ある程度核心に迫る探求を試みる。
アメリカ建国の経緯に大きくまつわる先住民族インディアンの迫害・黒人奴隷強制使役以来、アメリカ国民の大勢を占める白人が彼らからの復讐を未来永劫恐れ続ける一種の狂気の連鎖が銃社会容認の根源にあるという解釈を導き出す。
作品中でムーアは、事件の被害者を伴ってアメリカ第2の大手スーパーマーケット・チェーンストアであるKマートの本社を訪れ、交渉の末全ての店舗で銃弾の販売をやめさせることに成功した。
寸評
コロンバイン高校銃乱射事件は1999年4月20日に発生した。
同校の生徒だったエリック・ハリスとディラン・クレボルドが銃を乱射し、12名の生徒と1名の教師を射殺した後、両名は自殺した。
重軽傷者も24名にのぼる衝撃的な事件で、日本でも大々的に報道されアメリカの銃社会が論じられた。
タイトルの「ボウリング・フォー・コロンバイン」だが、コロンバインは勿論コロンバイン高校のことであるが、その前のボウリングが意味深となっている。
一つはボウリングのピンが人の形に似ていて射撃の的になっていることによる。
もう一つは加害者たちが心酔していたロック歌手のマリリン・マンソンの影響が論じられているのに、彼らが犯行の直前に興じていたボウリングについては論じられていないと言う事への皮肉となっている。
猟銃などを除いて基本的に銃の所持が禁止されている日本から見ればアメリカの銃社会は異常である。
その銃社会を取り上げたドキュメンタリーであるが、テーマの割にはユーモアも交えた内容でインタビュー相手も、構成も練られたもので、アニメーションも交えて主張は分かりやすく見応えがある。
どうやらマイケル・ムーアはアメリカの銃社会と射殺事件の多さは差別とマスコミによる恐怖心を植え付ける洗脳にあると思っているようだ。
『サウスパーク』というテレビ番組の創設者マット・ストーンは射殺現場や携帯電話を警官に投げつける映像の方が視聴率がとれるのだと言う。
銃を所持している女性は、強盗が入った時に警察に電話するのは警官が銃を持っているからで、自分たちはその手間を省いているのだと真顔で語る。
日本でも警官を呼ぶだろうが、それは警官が拳銃を持っているからではなく、警察には逮捕特権があるからだ。
アメリカにおける暴力事件の逮捕映像は大抵の場合黒人である。
犯罪のニュースが流れると犯人像は黒人が連想されてしまう。
テレビが視聴者がそのように思ってしまうような映像を流し続け、隣人があたかも危険人物であるかのような報道を繰り返すことによって、人々は自衛のために銃を手にする。
マイケル・ムーアは同じように銃社会であるカナダにおいてはなぜ銃による射殺事件が少ないのかと疑問を投げかける。
NRAのチャールトン・ヘストンはアメリカの暴力の歴史だと語る。
明確な答えはない。
それでもスーパーで弾丸を販売している状態は、我々から見れば明らかに異常だ。
インタビューの中では銃の種類が色々出てくるが説明はない。
アメリカ人にとっては周知のことなのだろう。
カナダ人はアメリカは好戦的で話し合おうとしないと言う。
自分の土地に入ったというだけで銃を撃つと言う。
その姿勢は他国への軍事介入につながるもので、彼らの主張に一理あると感じる。

監督 マイケル・ムーア
出演 マイケル・ムーア
チャールトン・ヘストン
マリリン・マンソン
マット・ストーン
ジョージ・W・ブッシュ
ストーリー
マイケル・ムーア監督はコロンバイン高校での銃乱射事件をめぐるメディア報道と社会の反応に疑問を抱き、精力的な行動力とユーモアを武器に企業や著名人に取材し、さまざまな角度から米国銃社会を検証していく。
コロンバイン高校銃乱射事件の被害者、犯人が心酔していた歌手のマリリン・マンソンや全米ライフル協会(NRA)会長(当時)のチャールトン・ヘストン、『サウスパーク』の制作者マット・ストーン、清教徒のアメリカ大陸移住から現在までの銃社会の歴史検証や、コロンバイン市民らへのインタビューを行う。
そして、アメリカの隣国で隠れた銃器大国のカナダ、日本やイギリスなどの他の先進国との比較から、事件の背景と銃社会アメリカのいびつで異常な姿をあぶり出してゆく。
本作では銃規制を訴えてはいるが、しかしカナダはアメリカ以上に銃の普及率が高いのに、銃犯罪の発生率が低いのはなぜなのかという今まであまり疑問を待たれずにいたことにも、ある程度核心に迫る探求を試みる。
アメリカ建国の経緯に大きくまつわる先住民族インディアンの迫害・黒人奴隷強制使役以来、アメリカ国民の大勢を占める白人が彼らからの復讐を未来永劫恐れ続ける一種の狂気の連鎖が銃社会容認の根源にあるという解釈を導き出す。
作品中でムーアは、事件の被害者を伴ってアメリカ第2の大手スーパーマーケット・チェーンストアであるKマートの本社を訪れ、交渉の末全ての店舗で銃弾の販売をやめさせることに成功した。
寸評
コロンバイン高校銃乱射事件は1999年4月20日に発生した。
同校の生徒だったエリック・ハリスとディラン・クレボルドが銃を乱射し、12名の生徒と1名の教師を射殺した後、両名は自殺した。
重軽傷者も24名にのぼる衝撃的な事件で、日本でも大々的に報道されアメリカの銃社会が論じられた。
タイトルの「ボウリング・フォー・コロンバイン」だが、コロンバインは勿論コロンバイン高校のことであるが、その前のボウリングが意味深となっている。
一つはボウリングのピンが人の形に似ていて射撃の的になっていることによる。
もう一つは加害者たちが心酔していたロック歌手のマリリン・マンソンの影響が論じられているのに、彼らが犯行の直前に興じていたボウリングについては論じられていないと言う事への皮肉となっている。
猟銃などを除いて基本的に銃の所持が禁止されている日本から見ればアメリカの銃社会は異常である。
その銃社会を取り上げたドキュメンタリーであるが、テーマの割にはユーモアも交えた内容でインタビュー相手も、構成も練られたもので、アニメーションも交えて主張は分かりやすく見応えがある。
どうやらマイケル・ムーアはアメリカの銃社会と射殺事件の多さは差別とマスコミによる恐怖心を植え付ける洗脳にあると思っているようだ。
『サウスパーク』というテレビ番組の創設者マット・ストーンは射殺現場や携帯電話を警官に投げつける映像の方が視聴率がとれるのだと言う。
銃を所持している女性は、強盗が入った時に警察に電話するのは警官が銃を持っているからで、自分たちはその手間を省いているのだと真顔で語る。
日本でも警官を呼ぶだろうが、それは警官が拳銃を持っているからではなく、警察には逮捕特権があるからだ。
アメリカにおける暴力事件の逮捕映像は大抵の場合黒人である。
犯罪のニュースが流れると犯人像は黒人が連想されてしまう。
テレビが視聴者がそのように思ってしまうような映像を流し続け、隣人があたかも危険人物であるかのような報道を繰り返すことによって、人々は自衛のために銃を手にする。
マイケル・ムーアは同じように銃社会であるカナダにおいてはなぜ銃による射殺事件が少ないのかと疑問を投げかける。
NRAのチャールトン・ヘストンはアメリカの暴力の歴史だと語る。
明確な答えはない。
それでもスーパーで弾丸を販売している状態は、我々から見れば明らかに異常だ。
インタビューの中では銃の種類が色々出てくるが説明はない。
アメリカ人にとっては周知のことなのだろう。
カナダ人はアメリカは好戦的で話し合おうとしないと言う。
自分の土地に入ったというだけで銃を撃つと言う。
その姿勢は他国への軍事介入につながるもので、彼らの主張に一理あると感じる。










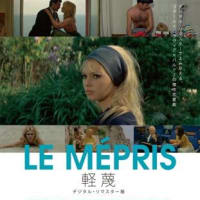
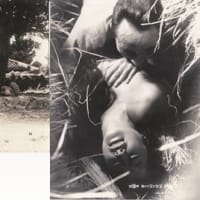

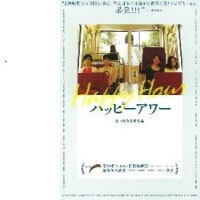
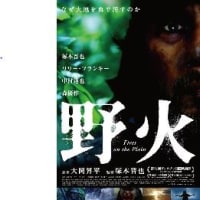
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます