古代出雲王朝では、主王(オオナモチ大穴持)、副王(少彦または少名彦)の二人の王で 治められていた。
古代出雲王朝八代目オオナモチ(大穴持ー主王)の八千矛(記紀では大国主命と書かれた 俗に言う大黒様)と、八代目スクナヒコ(少彦ー副王)の八重波都身(記紀では言代主と書かれ 俗に言う恵比寿さん)の二人は相前後して、シナからの渡来人 徐福らに 言葉巧みに誘い出され 拉致され幽閉されて 命を絶たれた。紀元前3世紀末のことである。
当時のシナ大陸秦国から沢山の 秦国人(海童と呼ばれた若者や先進技術を持った職人たち)を連れてやってきた、徐福は 記紀では素戔嗚と書かれ、和名をホアカリとかニギハヤヒと名乗った。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
徐福の家来の穂日(ホヒ)は、事前に徐福の出雲上陸の許可を
八千矛(大国主)から取り付けて、そのまま出雲王国で働いていたらしい。
穂日に言葉巧みに誘い出された大国主は 出雲の「園の長浜」で
行方不明となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結局大国主は日本海に面した 猪目洞窟に幽閉され命を絶たれたという。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猪目の海 岩場が続く。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猪目集落
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路標識
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟案内標識
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路から洞窟を見る
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟入り口
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟から海を見る。東の方角を向いている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲国風土記に書かれた「黄泉の穴」
大国主(第八代出雲王の八千矛)が幽閉され、命を絶たれたこの洞窟は
あの世へと続くと、信じられていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一方 大国主異変の知らせを早船で言代主に知らせるべく
美保の沼川姫屋敷に滞在していた 言代主へ 穂日の息子「タケヒナドリ」が
知らせに行き 言代主も誘い出されて そのまま行方不明となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

言代主(第八代出雲副王ー少名彦八重波都身)は王の海(中海)を西へ向かったまま行方不明となったという。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その時の早船の知らせの様子を今に伝える
美保神社「諸手舟(モロタブネ)神事」
詳しくはこちら http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/2010/10/post_bd19.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残雪の大山と粟島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

粟島は今は田圃の中だが、古来中海の中の小島だった。
江戸中期の干拓で 周りが田圃になったという。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社参道。正面の小山の上に社がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登る。186段あるそうだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

門を潜ると境内だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿はもちろん大社造だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿裏手に「出雲大社遥拝所」がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遥拝所には「大注連縄」が架けてある。
古代出雲族が信仰した「龍蛇神」のようだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

粟島の裏手には、中海が広がり 水鳥公園がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中海への階段を下りる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟がある。志都の岩屋だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し離れて中海から粟島と洞窟を見る。
今たっている場所はもともと海だったのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大汝(おおなむちー正式には大穴持と書き出雲王朝の主王をさす役職名でここでは第八代の 大国主の命を言う)も少彦名(少彦 もしくは少名彦の間違いと思われるー出雲王朝の副王をさし、ここでは第八代の言代主をいう)も二人とも 洞窟、岩屋に閉じ込められたことを言っていると思われる。
記紀で大国主と書かれたのは、第八代オオナモチ八千矛で、記紀に言代主と書かれたのは
第八代少彦の八重波都身だ。

※斎木雲州著 大元出版 「出雲とやまとのあけぼの」より

伯耆の国風土記には 「少彦の命(八重波都身つまり言代主俗に言う恵比寿さん)
は粟の穂にはじかれてあの世へ旅立たれた。それが粟島」と書かれている。
万葉集の頃までは、大国主も言代主も 岩屋で殺されたことが
まだ人々の記憶にあったのだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ブログ古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」トップページはこちら
http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウエブのトップページはこちら
http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/">http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
古代出雲王朝八代目オオナモチ(大穴持ー主王)の八千矛(記紀では大国主命と書かれた 俗に言う大黒様)と、八代目スクナヒコ(少彦ー副王)の八重波都身(記紀では言代主と書かれ 俗に言う恵比寿さん)の二人は相前後して、シナからの渡来人 徐福らに 言葉巧みに誘い出され 拉致され幽閉されて 命を絶たれた。紀元前3世紀末のことである。
当時のシナ大陸秦国から沢山の 秦国人(海童と呼ばれた若者や先進技術を持った職人たち)を連れてやってきた、徐福は 記紀では素戔嗚と書かれ、和名をホアカリとかニギハヤヒと名乗った。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
徐福の家来の穂日(ホヒ)は、事前に徐福の出雲上陸の許可を
八千矛(大国主)から取り付けて、そのまま出雲王国で働いていたらしい。
穂日に言葉巧みに誘い出された大国主は 出雲の「園の長浜」で
行方不明となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

結局大国主は日本海に面した 猪目洞窟に幽閉され命を絶たれたという。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猪目の海 岩場が続く。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

猪目集落
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路標識
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟案内標識
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路から洞窟を見る
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟入り口
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟から海を見る。東の方角を向いている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出雲国風土記に書かれた「黄泉の穴」
大国主(第八代出雲王の八千矛)が幽閉され、命を絶たれたこの洞窟は
あの世へと続くと、信じられていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一方 大国主異変の知らせを早船で言代主に知らせるべく
美保の沼川姫屋敷に滞在していた 言代主へ 穂日の息子「タケヒナドリ」が
知らせに行き 言代主も誘い出されて そのまま行方不明となった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

言代主(第八代出雲副王ー少名彦八重波都身)は王の海(中海)を西へ向かったまま行方不明となったという。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その時の早船の知らせの様子を今に伝える
美保神社「諸手舟(モロタブネ)神事」
詳しくはこちら http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/2010/10/post_bd19.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

残雪の大山と粟島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

粟島は今は田圃の中だが、古来中海の中の小島だった。
江戸中期の干拓で 周りが田圃になったという。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社参道。正面の小山の上に社がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登る。186段あるそうだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

門を潜ると境内だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿はもちろん大社造だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿裏手に「出雲大社遥拝所」がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遥拝所には「大注連縄」が架けてある。
古代出雲族が信仰した「龍蛇神」のようだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

粟島の裏手には、中海が広がり 水鳥公園がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中海への階段を下りる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞窟がある。志都の岩屋だ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少し離れて中海から粟島と洞窟を見る。
今たっている場所はもともと海だったのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大汝(おおなむちー正式には大穴持と書き出雲王朝の主王をさす役職名でここでは第八代の 大国主の命を言う)も少彦名(少彦 もしくは少名彦の間違いと思われるー出雲王朝の副王をさし、ここでは第八代の言代主をいう)も二人とも 洞窟、岩屋に閉じ込められたことを言っていると思われる。
記紀で大国主と書かれたのは、第八代オオナモチ八千矛で、記紀に言代主と書かれたのは
第八代少彦の八重波都身だ。

※斎木雲州著 大元出版 「出雲とやまとのあけぼの」より

伯耆の国風土記には 「少彦の命(八重波都身つまり言代主俗に言う恵比寿さん)
は粟の穂にはじかれてあの世へ旅立たれた。それが粟島」と書かれている。
万葉集の頃までは、大国主も言代主も 岩屋で殺されたことが
まだ人々の記憶にあったのだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「ブログ古代出雲王朝ゆかりの地を訪ねて」トップページはこちら
http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウエブのトップページはこちら
http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/">http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー













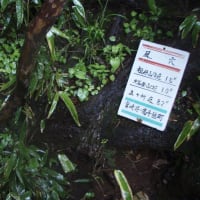






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます