堀江敏幸「送り火」(センター2007年)②
階段のすぐ近くに物入れがあるため、陽平さんは取り出しやすいようにとそのまえに自分の机を置いていた。だから子どもたちの顔を見るより先に、彼らのほうをむいて坐っている陽平さんの、針金でも入っているんじゃないかと疑いたくなるくらいまっすぐな背中と鶏(とり)ガラみたいにほそい首筋を拝まなければならないのだが、手本をしたためているときも朱を入れているときも、硯(すずり)で墨をすっているときも、子どもたちと言葉を交わしているときも、まだ(注2)枕(まくら)を話しているだけで本編に入っていない噺(はなし)家(か)みたいに座布団から垂直に頭がのびていて、その姿勢がまったく変化せず、食事の際も変わらないものだから、たまに傾いているとかえって不自然な感じがするのだった。
陽平さんのことを。めっちゃ見てますね。
しかし、Cとりわけ絹代さんを惹(ひ)きつけたのは、教室ぜんたいに染みいりはじめた独特の匂(にお)いだった。子どもたちはみな既製の墨汁を使っており、時間をかけて墨を磨るのは陽平先生だけだったけれど、七、八人の子どもが何枚も下書きし、よさそうなものを脇(わき)にひろげた新聞紙のうえで乾かしていると、夏場はともかく、窓を閉め切った冬場などは乾いた墨と湿った墨が微妙に混じりあい、甘やかなのになぜか命の絶えた生き物を連想させるその不気味な匂いがつよくなり、絹代さんの記憶を過去に引き戻した。
書道教室が始まり、陽平さんも気になり、墨の匂いに惹きつけられます。
墨の「甘やかなのになぜか命の絶えた生き物を連想させるその不気味な匂い」を嗅いだとき、絹代さんに幼いころの記憶がよみがえります。
映画なら、回想シーンに入るところです。
回想シーンの主人公は、子役が演じます。ぎりぎり許せる範囲なら、主人公が若作りして演じます。
どっちがわかりやすいですか?
男の俳優さんだと、けっこう年配の役者さんが、ふさふさのカツラをつけて、学生服を着たりすることがありますね。
でも、顔はメイクでもごまかしにくく、回想シーンであることはわかるけど、今ひとつ入り込めなかったりします。
先日観た「弥生、三月」で、アラサーの波瑠さんが、制服で17歳役を演じてましたがまったく違和感がなく、むしろ萌えました。
洋画の場合、邦画よりわかりにくいことないですか?
外国の役者さん、とくに女優さんは16、7歳であってもけっこうお姉さんに見えますし、基本的に年齢がわかりにくくないですか。
BGMや背景の映像にも、やはり邦画のそれほど理解できないことがある。
邦画ならば、たとえば繁華街の様子が映っただけで「昔の新宿かな」と気づいたり、昭和歌謡ぽい曲が流れてれば時代もイメージできます。
シーンが変わって、「○○年、どこそこ」みたいに説明してくれる作品もありますね。
小説は、基本的に、突然回想シーンに入ります。
一行開けもなく、「それは20年前の夏だった」との説明もふつうはありません。
ですから、「場面ごとが時系列で並んでいない」という小説の特徴を念頭において読む必要があります。
91行目あたりから、絹代さんの思い出のなかの映像になっています。
蚕のアップから入りたい場面ですね。
まだ小さかったころ、ここにも生き物がうごめいていたのだ。絹代という名前は祖父母がつけてくれたもので、彼らはこの古い家の二階で細々と養蚕を手がけ、生活の資をさずけてくれる大切な生き物を、親しみと敬意をこめて「おかいこさん」と呼んでいた。同居していた息子夫婦はともに会社勤めだったから、孫の絹代さんがあとを継ぐ可能性はほとんどなかった。あの時分はまだ片手間にでも養蚕にかかわっている家がいくらもあったし、そこで生まれた娘に絹子だの絹江だの絹代だのといった名前をつけることもないではなかったが、絹代さん自身は、二階の平台にならべられた浅い函(はこ)の底をわさわさとうごめいている白っぽい芋虫の親玉と自分の名前がむすびつけられるのを、あまり好ましく思っていなかった。
触ってごらん、と言われるままに触れたその虫の皮はずいぶんやわらかく、しかも丈夫そうだった。使いこんだ白い鹿(しか)革(がわ)の手袋の、ところどころ穴があいたふうの表面の匂いとかさつく音をこの書道教室に足を踏み入れた瞬間ふいに思い出し、匂いといっしょに、あのグロテスクな肌と糸の美しさの、驚くべきへだたりにも想(おも)いを馳(は)せた。あたしは肌がつるつるさらさらして絹みたいだから絹江になったの、絹代ちゃんとこみたいに蚕を飼ってるからつけられた名前じゃないよ、と一文字だけ名前を共有していたともだちが突っかかるように言った台詞(せりふ)が、絹代さんの頭にまだこびりついている。生家の周辺を離れれば、養蚕なんてもう、ふつうの女の子には気味の悪いものでしかない時代に入っていたのだ。それなのに、墨の匂いを嗅いだとたん、かつてのおどろおどろしい記憶がなつかしさをともなう思い出にすりかわったのである。
昔、この家の二階では蚕が飼われ、生活の糧となっていました。
幼いころの絹代さんは、白っぽく、もぞもぞ動いている蚕にふれてみて、気持ちわる! みたいに感じていたのですね。
自分の名前につけられた「絹」が「大切なもの」を表すことはわかっていても、それを生み出す「芋虫の親玉」と結びつくので、今ひとつ名前に愛着ももてなかったのです。
91行目ですうっと、回想シーンに入り、103行目でいったん元の時系列にもどり、すぐにもう一度回想シーンになり110行目「~いたのだ」で終わります。
今① → 昔 → 今②
のように場面が変わっていくとき、「今①」と「今②」は連続しています。その間に何十行、何頁の文章があっても、直接つながっています。
「今①」で起こった出来事の原因は、「昔」シーンで説明されます。
今① Cとりわけ絹代さんを惹(ひ)きつけたのは、教室ぜんたいに染みいりはじめた独特の匂(にお)いだった
昔 蚕 → グロテスク 気味が悪い
今② それなのに、墨の匂いを嗅いだとたん、
かつてのおどろおどろしい記憶がなつかしさをともなう思い出にすりかわったのである
問4 傍線部C「とりわけ絹代さんを惹きつけたのは、教室ぜんたいに染みいりはじめた独特の匂いだった」とあるが、「絹代さん」が匂いに惹きつけられたのはなぜか。
理由のまとめ部分である、「墨の匂いを嗅いだとたん、かつてのおどろおどろしい記憶がなつかしさをともなう思い出にすりかわったのである」と「=」の選択肢を選ばないといけません。
墨の匂いをかいだとき、「かつてのおどろおどろしさ」が、「なつかしいもの」に、「かわった」から、と書いてある選択肢を探します。
①「家族と過ごした幼年時代の記憶が」「子どもたちと一緒にいる楽しい時間と重なって」「よみがえってきた」から
②「グロテスクな … 蚕にまつわる記憶が」「家族とつながるなつかしい思い出に」「変化した」から
③「蚕に親しみと敬意を感じていたことを」「大切な生き物として」「思い出した」から
④「気味の悪い … 養蚕にかかわる思い出が」「陽平さんへのほのかな想いへと」「変質した」から
⑤「蚕を飼っていた忌まわしい記憶を呼び起こし」「そのときの生活を」「思い出した」から
正解は②です。
思い出は、つまり過去は、今の有り様によってその意味を変えることが可能だということですね。
問4を間違える人は、次の二つが原因です。
1、本文の時系列を読み取れない場合
2、本文の根拠部分と選択肢とを対応させられない場合
階段のすぐ近くに物入れがあるため、陽平さんは取り出しやすいようにとそのまえに自分の机を置いていた。だから子どもたちの顔を見るより先に、彼らのほうをむいて坐っている陽平さんの、針金でも入っているんじゃないかと疑いたくなるくらいまっすぐな背中と鶏(とり)ガラみたいにほそい首筋を拝まなければならないのだが、手本をしたためているときも朱を入れているときも、硯(すずり)で墨をすっているときも、子どもたちと言葉を交わしているときも、まだ(注2)枕(まくら)を話しているだけで本編に入っていない噺(はなし)家(か)みたいに座布団から垂直に頭がのびていて、その姿勢がまったく変化せず、食事の際も変わらないものだから、たまに傾いているとかえって不自然な感じがするのだった。
陽平さんのことを。めっちゃ見てますね。
しかし、Cとりわけ絹代さんを惹(ひ)きつけたのは、教室ぜんたいに染みいりはじめた独特の匂(にお)いだった。子どもたちはみな既製の墨汁を使っており、時間をかけて墨を磨るのは陽平先生だけだったけれど、七、八人の子どもが何枚も下書きし、よさそうなものを脇(わき)にひろげた新聞紙のうえで乾かしていると、夏場はともかく、窓を閉め切った冬場などは乾いた墨と湿った墨が微妙に混じりあい、甘やかなのになぜか命の絶えた生き物を連想させるその不気味な匂いがつよくなり、絹代さんの記憶を過去に引き戻した。
書道教室が始まり、陽平さんも気になり、墨の匂いに惹きつけられます。
墨の「甘やかなのになぜか命の絶えた生き物を連想させるその不気味な匂い」を嗅いだとき、絹代さんに幼いころの記憶がよみがえります。
映画なら、回想シーンに入るところです。
回想シーンの主人公は、子役が演じます。ぎりぎり許せる範囲なら、主人公が若作りして演じます。
どっちがわかりやすいですか?
男の俳優さんだと、けっこう年配の役者さんが、ふさふさのカツラをつけて、学生服を着たりすることがありますね。
でも、顔はメイクでもごまかしにくく、回想シーンであることはわかるけど、今ひとつ入り込めなかったりします。
先日観た「弥生、三月」で、アラサーの波瑠さんが、制服で17歳役を演じてましたがまったく違和感がなく、むしろ萌えました。
洋画の場合、邦画よりわかりにくいことないですか?
外国の役者さん、とくに女優さんは16、7歳であってもけっこうお姉さんに見えますし、基本的に年齢がわかりにくくないですか。
BGMや背景の映像にも、やはり邦画のそれほど理解できないことがある。
邦画ならば、たとえば繁華街の様子が映っただけで「昔の新宿かな」と気づいたり、昭和歌謡ぽい曲が流れてれば時代もイメージできます。
シーンが変わって、「○○年、どこそこ」みたいに説明してくれる作品もありますね。
小説は、基本的に、突然回想シーンに入ります。
一行開けもなく、「それは20年前の夏だった」との説明もふつうはありません。
ですから、「場面ごとが時系列で並んでいない」という小説の特徴を念頭において読む必要があります。
91行目あたりから、絹代さんの思い出のなかの映像になっています。
蚕のアップから入りたい場面ですね。
まだ小さかったころ、ここにも生き物がうごめいていたのだ。絹代という名前は祖父母がつけてくれたもので、彼らはこの古い家の二階で細々と養蚕を手がけ、生活の資をさずけてくれる大切な生き物を、親しみと敬意をこめて「おかいこさん」と呼んでいた。同居していた息子夫婦はともに会社勤めだったから、孫の絹代さんがあとを継ぐ可能性はほとんどなかった。あの時分はまだ片手間にでも養蚕にかかわっている家がいくらもあったし、そこで生まれた娘に絹子だの絹江だの絹代だのといった名前をつけることもないではなかったが、絹代さん自身は、二階の平台にならべられた浅い函(はこ)の底をわさわさとうごめいている白っぽい芋虫の親玉と自分の名前がむすびつけられるのを、あまり好ましく思っていなかった。
触ってごらん、と言われるままに触れたその虫の皮はずいぶんやわらかく、しかも丈夫そうだった。使いこんだ白い鹿(しか)革(がわ)の手袋の、ところどころ穴があいたふうの表面の匂いとかさつく音をこの書道教室に足を踏み入れた瞬間ふいに思い出し、匂いといっしょに、あのグロテスクな肌と糸の美しさの、驚くべきへだたりにも想(おも)いを馳(は)せた。あたしは肌がつるつるさらさらして絹みたいだから絹江になったの、絹代ちゃんとこみたいに蚕を飼ってるからつけられた名前じゃないよ、と一文字だけ名前を共有していたともだちが突っかかるように言った台詞(せりふ)が、絹代さんの頭にまだこびりついている。生家の周辺を離れれば、養蚕なんてもう、ふつうの女の子には気味の悪いものでしかない時代に入っていたのだ。それなのに、墨の匂いを嗅いだとたん、かつてのおどろおどろしい記憶がなつかしさをともなう思い出にすりかわったのである。
昔、この家の二階では蚕が飼われ、生活の糧となっていました。
幼いころの絹代さんは、白っぽく、もぞもぞ動いている蚕にふれてみて、気持ちわる! みたいに感じていたのですね。
自分の名前につけられた「絹」が「大切なもの」を表すことはわかっていても、それを生み出す「芋虫の親玉」と結びつくので、今ひとつ名前に愛着ももてなかったのです。
91行目ですうっと、回想シーンに入り、103行目でいったん元の時系列にもどり、すぐにもう一度回想シーンになり110行目「~いたのだ」で終わります。
今① → 昔 → 今②
のように場面が変わっていくとき、「今①」と「今②」は連続しています。その間に何十行、何頁の文章があっても、直接つながっています。
「今①」で起こった出来事の原因は、「昔」シーンで説明されます。
今① Cとりわけ絹代さんを惹(ひ)きつけたのは、教室ぜんたいに染みいりはじめた独特の匂(にお)いだった
昔 蚕 → グロテスク 気味が悪い
今② それなのに、墨の匂いを嗅いだとたん、
かつてのおどろおどろしい記憶がなつかしさをともなう思い出にすりかわったのである
問4 傍線部C「とりわけ絹代さんを惹きつけたのは、教室ぜんたいに染みいりはじめた独特の匂いだった」とあるが、「絹代さん」が匂いに惹きつけられたのはなぜか。
理由のまとめ部分である、「墨の匂いを嗅いだとたん、かつてのおどろおどろしい記憶がなつかしさをともなう思い出にすりかわったのである」と「=」の選択肢を選ばないといけません。
墨の匂いをかいだとき、「かつてのおどろおどろしさ」が、「なつかしいもの」に、「かわった」から、と書いてある選択肢を探します。
①「家族と過ごした幼年時代の記憶が」「子どもたちと一緒にいる楽しい時間と重なって」「よみがえってきた」から
②「グロテスクな … 蚕にまつわる記憶が」「家族とつながるなつかしい思い出に」「変化した」から
③「蚕に親しみと敬意を感じていたことを」「大切な生き物として」「思い出した」から
④「気味の悪い … 養蚕にかかわる思い出が」「陽平さんへのほのかな想いへと」「変質した」から
⑤「蚕を飼っていた忌まわしい記憶を呼び起こし」「そのときの生活を」「思い出した」から
正解は②です。
思い出は、つまり過去は、今の有り様によってその意味を変えることが可能だということですね。
問4を間違える人は、次の二つが原因です。
1、本文の時系列を読み取れない場合
2、本文の根拠部分と選択肢とを対応させられない場合










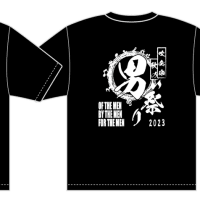




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます