11 下人は、やもりのように足音を盗んで、やっと急なはしごを、いちばん上の段まではうようにして上りつめた。そうして体をできるだけ、平らにしながら、首をできるだけ、前へ出して、恐る恐る、楼の内をのぞいてみた。
12 見ると、楼の内には、うわさに聞いたとおり、いくつかの死骸が、無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が、思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら、知れるのは、その中に裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には女も男もまじっているらしい。そうして、その死骸はみな、それが、かつて、生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて造った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ごろごろ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影をいっそう暗くしながら、永久におしのごとく黙っていた。
13 下人は、それらの死骸の腐乱した臭気に思わず、鼻を覆った。しかし、その手は、次の瞬間には、もう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである。
14 下人の目は、そのとき、初めて、その死骸の中にうずくまっている人間を見た。檜皮色の着物を着た、背の低い、やせた、白髪頭の、猿のような老婆である。その老婆は、右の手に火をともした松の木切れを持って、その死骸の一つの顔をのぞき込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、たぶん女の死骸であろう。
15 下人は、六分の恐怖と四分の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧記の記者の語を借りれば、「頭身の毛も太る」ように感じたのである。すると、老婆は、松の木切れを、床板の間に挿して、それから、今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど、猿の親が猿の子のしらみを取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。
Q21「ある強い感情」について
(a)具体的内容は何か。12字で抜き出せ。
(b)この「感情」をもたらしたものは何か。30字以内で記せ。
A21(a)六分の恐怖と四分の好奇心
(b)死骸の中にうずくまり、何かをしている不気味な老婆の存在。
Q22「下人は、なんの未練もなく、飢え死にを選んだことであろう」とあるのは、下人にどういう感情が生まれているからか。10字程度で抜き出せ。
A22 あらゆる悪に対する反感
事件 楼の上に人の気配を感じる
↓
心情 警戒心 不審
↓
行動 恐る恐る、楼の内をのぞく
事件 老婆目撃
↓
心情 ある強い感情 = 六分の恐怖と四分の好奇心
↓
行動 暫時(しばらく)息ができない
16 その髪の毛が、一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは、恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が、少しずつ動いてきた。――いや、この老婆に対すると言っては、語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分ごとに強さを増してきたのである。このとき、だれかがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか盗人になるかという問題を、改めて持ち出したら、おそらく下人は、なんの未練もなく、飢え死にを選んだことであろう。それほど、この男の悪を憎む心は、老婆の床に挿した松の木切れのように、勢いよく燃え上がり出していたのである。
17 下人には、もちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって、合理的には、それを善悪のいずれに片づけてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん、下人は、さっきまで、自分が、盗人になる気でいたことなぞは、とうに忘れているのである。
18 そこで、下人は、両足に力を入れて、いきなり、はしごから上へ飛び上がった。そうして聖柄の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。
19 老婆は、一目下人を見ると、まるで弩にでもはじかれたように、飛び上がった。
20 「おのれ、どこへ行く。」
21 下人は、老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手をふさいで、こうののしった。老婆は、それでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまた、それを行かすまいとして、押し戻す。二人は死骸の中で、しばらく、無言のまま、つかみ合った。しかし勝敗は、初めから、わかっている。下人はとうとう、老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど、鶏の脚のような、骨と皮ばかりの腕である。
22 「何をしていた。言え。言わぬと、これだぞよ。」
23 下人は、老婆を突き放すと、いきなり、太刀の鞘を払って、白い鋼の色を、その目の前へ突きつけた。けれども、老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を、眼球がまぶたの外へ出そうになるほど、見開いて、おしのように執拗く黙っている。これを見ると、下人は初めて明白に、この老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。あとに残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就したときの、安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで、下人は、老婆を、見下ろしながら、少し声を和らげてこう言った。
24 「おれは検非違使の庁の役人などではない。今し方この門の下を通りかかった旅の者だ。だからおまえに縄をかけて、どうしようというようなことはない。ただ、今時分、この門の上で、何をしていたのだか、それをおれに話しさえすればいいのだ。」
事件 老婆の行為を知る
↓
心情 恐怖が少しずつ消える
↓
老婆に対する激しい憎悪・あらゆる悪に対する反感(衝動的な正義感)
↓
行動 老婆にとびかかり、ねじ倒す
↓
事件 抵抗を諦めた老婆を見る
↓
心情 老婆の生死は自分の意志が支配しているという意識。〈優越感〉
安らかな得意と満足〈成就感〉
↓
行動 声をやわらげる
Q23「この意識」とはどういう意識か。30字以内で記せ。
A23 老婆の生死は完全に自分の意志が支配しているという意識。
Q24「少し声を和らげて」とあるが、その理由を40字以内で説明せよ。
A24 老婆を取り押さえたことで安らかな得意と満足を抱き、
気持ちに余裕が生まれたから。
Q25「今し方この門の下を通りかかった旅の者だ」と嘘をついたのはなぜか。2点答えよ。
A25 1 老婆を安心させて話しやすくするため
2 老婆の優位に立っている状態を維持するため










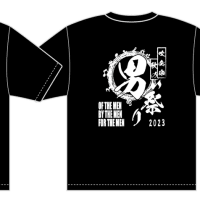





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます