3 小説の基本構造と「世間」
これまで作品の「世界」とか、主人公が見ている「社会」といった言葉を用いて論じてきた。しかし「世界」「社会」という用語では、作品を観念的にしかとらえられない。そこで、文学作品を読解するために「世間」という観点の導入を提案したい。身近に用いられる言葉だが、この「世間」を学問的に解明するという試みは、阿部謹也氏がはじめられた。あくまでも「社会」とは異なる「世間」とはどういうものか。
~ 本来は世界という意味ですから世界全体でなければなりませんが、いまでは日本の世間、世間の人々というときは、自分と関係がある、利害関係を持っている、そういう人間であって、今後利害関係を持つであろう人も含めた人間の集団の全体をいいます。自分が知らない人、自分が利害関係をいっさい持っていない人は世間に入りません。 (阿部謹也編著『世間学への招待』青弓社) ~
私たちは、近代国家に生きていると思っている。自由や権利を与えられた一個人、一市民として近代社会を生きていると思っている。しかし、現実に私たちの日常のありようを規定するのは、自分の属する「世間」である。学校、会社、地域さまざまな場所や集団で、私たちは「世間」にしばられている。「世間体など気にしない」とツッぱる若者たちでさえ、自分たち独自の強固な世間を形成して生きている。誰もが近代的市民であるという意識を漠然ともちながら、現実には「世間」を生きざるを得ない。
そこに葛藤が生まれる。近代小説の主人公は、そういう葛藤を端的に表す存在として描かれてきた。
小説は、基本的に次のような構造を持つものと考えている。
なんらかの「事件」が起こる。その事件によって主人公がなんらかの「心情」を抱く。そしてその心情に基づいて引き起こされる「言動」が描写される。「事件→心情→言動」の3点セットである。
では、事件はどういう時に起こるのか。それは、主人公が世間と関わりをもった時である。
典型的な例は、先に述べた「東大生が恋愛して心を病む」パターンに見られる。主人公が、自らの恋愛を結婚という形で成就するためには、必然的に世間との関わりを持たねばならない。青春期、つまりモラトリアム期を生きる主人公にとって、これはつらいことだ。自分一人の観念世界に生きるだけなら考えなくてもいいような世俗の様々なことについて、決断がせまられる。決断しないことを許される期間の終わりを感じ、また自らが嫌悪していた世間の中に自分自身も入って行かなくてはならないことを意識し、苦悩する。これが主人公と世間との関わりである。










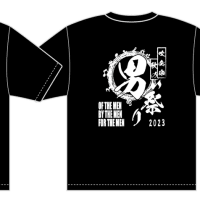





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます