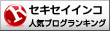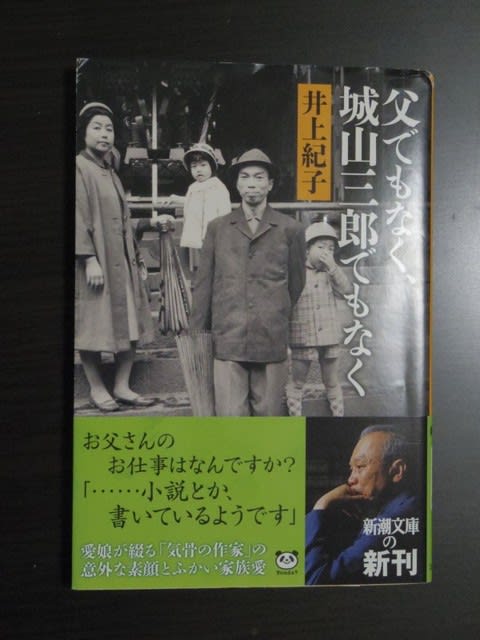成熟脳-脳の本番は56歳から始まる‐ 黒川伊保子 新潮文庫平成30年
何度かに分けてこの本について書いたが、この、脳の生涯に関するテーマが本書の主題である。
その前に、前回男性脳と女性脳に関することを書いた時の補足。実はあの記事を書いた時は相当頭にきたことがあって(私事ですが・)、筆が進まないまま(死語)あげてしまった。もうひとつ言いたいことがあった。男性の空間認識力の話。
男性は女性よりも「拡張感覚」が発達している。道具やメカをまるで神経がつながっているかのように自分のものとして操作する。バイクが手足の延長のようになってくる。そして長年連れ添った妻も。。自分の右手をわざわざ褒めたりはしないように、いつまでも女房をほめそやすようなことはしない。黒川氏は逆に、奥さんを人前で褒めていた年配の夫婦に違和感を感じたそうだ。本当に一体化した二人なら、あんなことは言わないと。
まあ人にもよりますけどね。。僕など車の車両感覚に慣れるまで1年ぐらいかかって、今でも駐車場でまっすぐ止められなくて自己嫌悪に陥ってます。。カメラなども慣れるまで相当時間がかかる。だから、しょっちゅう機材を変える人のことをすごいなあと思ったりする。
女性でも運転の上手な人は多いし、あれはどうなんだろう、ピアニストやヴァイオリニストはかなり女性の割合が多いのでは。。
「成熟脳」というのは、脳の生涯についての話。冒頭黒川氏が書いているように、さいきん物忘れをするようになったな、と気にしている方には耳寄りな?話題だ。
黒川氏の説によると、人生最初の28年間は入力に最も適した時期、その次は色々な経験をしたり、ときに失敗をして判断力を養う時期、そして56歳からはそれらが結実して、状況に応じた適切な判断ができる成熟脳となる。判断をするために不要と思われる情報は頭の中で「整理」されてしまっているから、すぐに思い出せないが、それでいいのだ。
60代とか70代になるともう言葉ではなく直感で物事がつかめるようになるので、旅や抽象度の高い能などの芸術鑑賞に適しているのだそうだ。もはや言葉は不要であり、それを人に説明する必要性すらなくなる。さらに80を超えて90代になると、脳が若返る傾向があるらしい。
ただし、人により寿命は異なる。脳は(肉体的な)寿命を知っているようで、死が近づくと自然に外界に対する反応が弱まっていく。
「脚が弱った身で、地球の果てまで行きたい冒険心があったら、きっとつらくてしょうがない。」
自分の親もそうだが、年配者に触れ合う機会が増えると、彼らは自分たち(の世代)とは違う原理で行動しているな、とふと思うことがある。ただ、彼らは彼らだけで生活することができず、自分たちの助けを要する。そこに摩擦が生じる。
よく「老害」などというが、それは間違いで、単に世代間がうまく結合していないからそうなっているに過ぎない。今は自動車が操作できない老人もいるし、詐欺に会う老人もいたりするが、各世代間でうまくつながることができれば、社会はより成熟したものに変わっていく可能性がある。
とはいえ、あれですけどね。実際会ってみるとってのはあるな。。