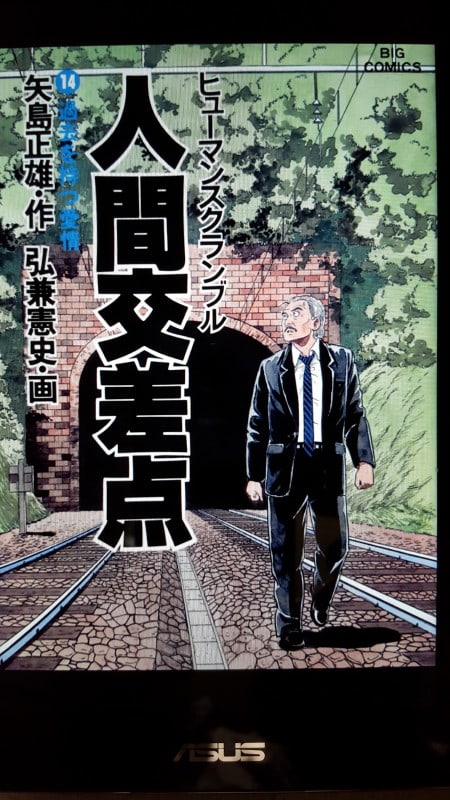立て続けに書いています。
今月の記事をちょっと見返してみたけど、どこにも出かけなかったせいか鳥と本の話ばかりですね・・。
外の写真がほとんどない。
数少ない外出の記事の一つが先週の「こがらし」ですが、冒頭に写っている腕時計は、中学の入学祝いに叔父に買ってもらったものだ。
昨年実家の引き出しから見つけて、数十年ぶりに使い始めた。多少止まったりすすんだりするものの、何とか使えていた。
OHが必要だとは思ったが、近くに適当な店がみあたらない。
いちどオアゾ丸善に入っている時計屋に見積もってもらったが、それなりに費用がかかるようなので、見送っていた(あそこは海外高級品を扱う店ですからね・・)。
先週土曜日、電車を降りたときに何かの弾みでベルトの留め金がはずれ、ゆっくりではあったがするすると落ちてしまった。
そのときはなんともなかったが、翌日、外出先で時計を見たら、止まっていた。
ゼンマイ切れかと思いふってみたが、秒針は動かない。前日の落下ショックのせいだろうか。。
時計が止まる直前に撮影したのが、「こがらし」の記事冒頭の写真だ。
SNSでどこかで修理したい、と書いたら、友達が近くの修理店を紹介してくれた。
とりあえず、修理ができそうだということになり少し安心。
そのお店には時間が取れたら行ってみることにして、とりあえず当面つかう時計がほしい。
いや、実はもう長いこと、腕時計は使っていなかったのですね。
高価な腕時計を持つ趣味もないし・・。カメラとか好きだから、結構はまりそうな気もするんですけどね。なぜかそっちには行かなかった。
でも、1年ほど使い出すと、やはりあった方がいいかと。
叔父の時計はセイコー5 ACTUSという、当時の若者向けの時計だ。このシリーズは60年代に発売され一世を風靡し、いろいろなバリエーションが展開された。
現在国内では製造販売を終了しているが、途上国を中心に以前人気があり、海外工場で継続して製造、販売されている。その一部が日本にも輸入され、比較的容易に入手できるらしい。
アマゾンその他のサイトを見たが、ものすごくたくさんの種類が販売されている・・。しかも6000円ぐらいからと、驚くほど安い。
というわけで、購入。

非常に立派なケースに入っている。
昔より立派かも知れない。5 ACTUSはたしか、プラスチックの青いケースに入っていた。

海外モデルとはいえ、セイコーの製品ということでちゃんと保証書もついている。

型番はSNK357KCという。基本的に同じものだが、文字盤などのちがいで相当のバリエーションがある。
本機の文字盤は濃いネイビー。写真ではわからないが(Q10にPLかましてISO800で撮りましたがノイズとして消されたかな)文字盤には”5”と盾の模様が透かしのように入っている。

ウェブを見ていると、バンドが安っぽい、という評価をよく見かける(金属無垢ではなく、プレスなので)、これは昔の5ACTUSもそうだった。
個人的にはそれほど見劣りするようには思えません。いくつかのサイトを見て、コマ調整を自分でやろうとしたが、かなり固くて挫折・・。翌日丸善の時計屋にお願いして調節してもらった。540円。

古い5ACTUSと並ぶ。アマゾンのサイトを見たときからわかっていたが、現代の5は全体にやや線が太く、角が少し甘いという感じがする。
竜頭は一段引っ張るとカレンダー調整(本機は英語とスペイン語。アラビア語のモデルもあるらしい)、二段引くと時刻調整になる。また、秒針は止められない。
5ACTUSではカレンダーは押して調整、秒針は竜頭を引っ張ると止まる。
でも、いいですね。僕には機械式を不便に思うようなことはないし、安いから、気をつけないとどんどん増えて行ってしまいそうな気がします。。
文字盤がグリーンの奴もいいですし、ダイバーズなんかもよさそう・。

止まった5ACTUSの修理は、友人に教えてもらったこちらにお願いしました。
完了は11月末くらいらしい。










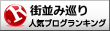
























 。
。