中川氏の本を読むのは、「カラヤンとフルトヴェングラー」、「カラヤン帝国興亡史」に続いて3冊目である。
新書版だが500ページにも及ぶ大著である。
これら一連の中川氏の著作に共通しているのは、音楽そのもの、演奏法とか芸術論とかについて書かれているわけでは無く、そこで活躍した人たちや、組織そのものの歴史を追うことを基調としていることだ。何となく「海外ドキュメンタリー・シリーズ」みたいな視点での語り口だが、これが面白い。オーケストラの歴史は、ヨーロッパにおいては特に、政治情勢、戦争の影響を強く受けており、それらと絡めて説明しているところも、とてもうまい。
もう一つ、この3冊に関して言えば、共通項として彼が掲げているのは「カラヤン」である。前書きで中川氏は、10大オーケストラを選ぶ基準として、カラヤンと何らかの形で関わりのあった(あるいは、大オーケストラなのに関わりがなかった)オーケストラを選んだのだという。
この視点、カラヤンという、一時はヨーロッパ楽壇を席巻した指揮者を通じて、オーケストラの歴史を語るという手法もとても面白い。もちろん今の一流の指揮者が、世界の一流オーケストラを指揮する機会は、昔よりはずっと多くなっていると思うが、カラヤンの時代には本当に限られた人だけができたことで、そこから物語を作り出すこともできやすいのだろう。
オーケストラというのは、はじめから今日の僕たちが知っている今の状態だったわけではなく、絶えず様々な変化と歴史の洗礼を受けてきたものだと言うことをあらためて再認識した。
19世紀には次々新しい音楽が作られ(もちろん今も作られてはいるが)、それに応じてオーケストラもその内容を変えてきたし、演奏そのものに対する考え方も次第に変わってきた。やがて録音技術が生まれ、交通も発達し、またオケを政治的に利用するという考え方も生まれるようになってきた。
ということは、これからもオーケストラが、ずっと今のままの状態で運営されていくということはないかもしれない、というより、21世紀は21世紀なりのありかたに変わっていくという方が自然な流れのはずだ。
すでに有名指揮者と演奏した古典名曲を、レコードとして大量に販売する、というビジネスの形は、すこしずつ変わってきている(ように思える)。
演奏家がかつてのように、個性豊かではなくなったと言うことについては、中川氏も巻末で触れている。中川氏は、「個性がないのは、みんなが幸福になったからなのだ。個性のあるオーケストラ、個性ある指揮者が、戦争と革命の不幸な時代がもたらしたものだとしたら、それを生むためには、まだも何千万もの人々が殺されなければならない。」と書いている。
僕はそこまで言い切ってしまうことには抵抗を感じる。個性という形で、何らかの高い芸術性が表現されやすいのだとすれば、幸福な我々の世代は芸術的に劣るものしか生み出せないのだろうか?そもそも、我々はかつての人たちに比べて、そんなに「幸福」なのだろうか?
とりあえず、この秋は中川氏シリーズを読み進んでいる。今は「10大ピアニスト」を読んでいる。










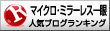























 。
。





































