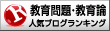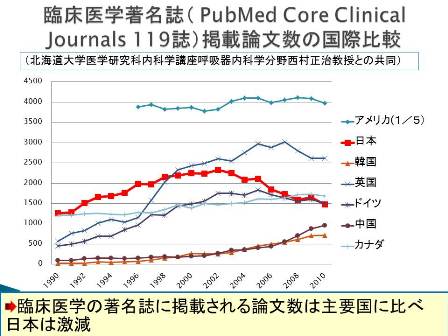ようやく大前研一氏の週刊ポスト誌2月10日号の記事も最後の部分にきました。
「・・・患者の位置づけが不明確な日本の大学病院は、もはや無用の長物になったと言わざるをえないだろう。
とにかく医師不足の問題は文科省や大学に任せていたら、是正できない。根本的な解決策は、厚労省が実務面から市場原理で医師を最適配分する仕組みを作り上げることに尽きるのだ。」
「患者の位置づけが不明確な日本の大学病院」という大前氏のご意見については、前回のブログでお話しましたように、今の大学病院では患者よりも研究を優先するということはありえず、患者の診療を第一としていますので、患者の位置づけは明確です。
国立大学附属病院長会議のHPを見てみましょう。http://www.univ-hosp.net/features.shtml
その「病院機能指標」にあげられている資料を見て頂きますと、国立大学病院がいかに診療に力をいれているかが、数値としてわかります。
また、「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~」には、「国立大学病院は,診療(医療),教育・研修,研究及び地域・社会貢献の4つの役割・機能を有する施設である。」と書かれており、「診療」が最初に来ていることからも、患者の診療を第一に位置付けていることがうかがえます。
大学病院の「地域・社会貢献」という点については、2月8日の本大学病院シリーズ(その1)および(その2)で一部ご紹介しましたが、私の「IDE現代の高等教育」誌掲載文「大学と地域医療」の続きの部分を、少し長くなりますが、紹介させていただきます。
IDE現代の高等教育2011年12月号「地域と結ぶ大学」の「大学と地域医療」より
2. 法人化をきっかけとした国立大学病院の診療機能の変化
(1)経営意識の向上と地域との連携
法人化により自律的経営が求められ、加えて交付金が削減されたことから、国立大学病院の経営意識は向上した。患者満足度の向上、医療安全、感染症対策等の診療機能の向上に力が注がれ、患者数や手術件数が増えた。また、地域医療機関からの紹介率・逆紹介率も向上し、地域医療機関とのネットワーク構築など、地域との連携が進んだ。
(2)地域医療の拠点病院としての整備
大学病院は従来から地域医療の拠点(地域医療の最後の砦)としての役割を果たしてきたが、国立大学病院では、国立であるが故の制約により、整備が遅れた面がある。例えば、国立大学病院は救命救急センターの設置が遅れたが、その障害の一つは、地方公共団体を経由する補助金が入らないことであった。地方財政再建促進特別措置法により、地方から国への寄付が原則として認められなかったからである。また、新しい診療科を創る場合は、国家公務員総定員法等により定員を増やすことが困難で、他の診療科を縮小せざるをえなかった。一方私立大学ではそのような制約を受けず、救命救急センターの整備は進んでいた。
これらの制約は法人化後緩和され、病院収益で賄える範囲で大学の裁量で人を増やせるようになった。また、地方財政再建促進特別措置法(07年からは地方公共団体の財政の健全化に関する法律)の特例として、国立大学病院への自治体からの寄付が認められるようになった。現在、国立大学病院に順次救命救急センターが設置され、ドクターヘリの体制も整備されつつある。
また、従来は国立大学病院に措置されなかった厚生労働省の補助金も、がん診療連携拠点病院整備事業において措置されるようになった。
この他、周産期母子医療センター、災害拠点病院、難病医療拠点病院、HIV拠点病院、感染症指定医療機関、肝疾患診療連携拠点病院等々、大学病院を地域医療の拠点と位置付ける整備が急速に進んでいる。
4. 地域医療貢献に関係した各種の取り組み
(1)遠隔医療
遠隔医療とは、大学病院と地域病院を通信で結び、画像診断、病理診断、手術などを大学の専門医が支援するシステムである。北海道を初めとして、へき地病院を多くかかえる地域では、成果が期待される地域医療貢献である。
(2)地域病院の教育病院化
欧米では、大学病院は、必ずしも大学が所有する病院とは限らない。わが国でも地域病院の医師に臨床教授等の称号を与え、学生や研修医に地域医療を教育する試みが法人化以前からなされていた。法人化後は、いくつかの大学病院でその実質化が進みつつある。
(3)総合医
欧米ではすでに確立している総合医(家庭医)の日本への導入はかなり遅れた。最近NHKテレビでも“総合医”を冠した番組が放映され、わが国でも認知が進むと思われる。
日本では、多くの医学生は卒後大学病院の専門診療科で養成され、地域の病院で働き、最終的に“何でも屋”として開業することが多かった。一言で言えば総合医は“何でも屋”を最初から養成するものである。小児から高齢者まで診療し、簡単な外科手術等を行い、医療チームとして365日24時間一次救急にも対応する。地域医療崩壊の今、住民が希求する専門職であると感じる。
わが国では大学病院に総合診療部が設置されたが、高度な医療を中心とする大学病院は、必ずしも総合医養成の場として適さない面があった。しかし、大学病院本院だけが教育の場ではなく、地域病院や診療所を教育病院として位置づけることにより、総合医の適切な養成が行われつつある。
この他にも各種の地域医療貢献の取り組みがあるが、紙幅の関係上割愛する。
5.東日本大震災への大学病院の貢献
今回の東日本大震災において、被災地にある東北大学、岩手医科大学、福島県立医科大学の大きな貢献はもちろん、全国の大学病院は国公私の隔たりなく、被災地の病院に物資を送付するとともに、ただちにDMAT(災害派遣医療チーム)を派遣し、引き続く医療支援に順次医療チームを派遣した。
また、福島原発事故に対して被ばく医療支援を長崎大学、広島大学、弘前大学等の大学病院が行ったことは特筆に値する。
今回の災害対応は、大学の地域医療貢献が、立地する地域だけに限らず、全国レベルであることを如実に示した。
ちょっと蛇足になりますが、上記文中の
「地方財政再建促進特別措置法(07年からは地方公共団体の財政の健全化に関する法律)の特例として、国立大学病院への自治体からの寄付が認められるようになった。現在、国立大学病院に順次救命救急センターが設置され、ドクターヘリの体制も整備されつつある。」
という個所については、私が三重大学長の時に、国立大学協会の病院経営小委員会の委員長として、この特例措置を関係省庁に毎年要請していたところ、当時の川崎二郎元厚生労働大臣が動いていただき、実現したものです。当初、この特例措置による実績がどれほどあがるのか心配するむきもあったのですが、杞憂に終わりました。
「また、従来は国立大学病院に措置されなかった厚生労働省の補助金も、がん診療連携拠点病院整備事業において措置されるようになった。」
ということも、川崎元厚労大臣のご尽力によります。それまでは、いわゆる縦割り行政によって、省庁をまたがる予算執行には障害があったんですね。厚労省と文科省医学教育課の課長交換人事もこの頃に実現しましたが、はやり、大学病院に対しては文科省と厚労省が一体となって事にあたるべきだと思います。
長々とご説明しましたが、とにかく今では、大学病院は地域医療の拠点病院として、地域にとって欠かすことのできない存在となっています。「大学病院はもはや無用の長物」という、大学病院の改善に日々努力している現場の職員にとってはたいへんショッキングなお言葉は、たぶん、最近の大学病院の目覚ましい変化の情報が大前氏にはうまく伝わっていなかったために発せられたのではないかと想像しています。
あと少しを残して、なかなか最後までいきませんが、ちょっと一服して次回に回すことにします。