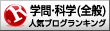前回のブログに対してUnknownさんから鋭いご指摘をいただきました。
「GDPと相関を示すのはプロセスイノベーションで、新規プロダクトイノベーションではないのですね。そして論文や公的研究開発投資と相関するのは新規プロダクトイノベーションなのだから、結局基礎研究はGDPとはあまり関係ないのでは?」
Unknownさんからのご指摘には2つの重要なポイントが含まれていると思います。1つは、「GDPと新規プロダクト・イノベーションが相関しないのか、するのか?」という点、2つ目は「基礎研究がGDPと関係があるのかないのか?」という点です。二つとも、たいへん重要なポイントだと思います。
1つ目のポイントについては、さっそくOECDのデータをひっくり返して、再度分析をすることにしました。その結果が今回の国大協草案(16)です。分かったことの一つは、前回のブログのデータで外れ値的な値を示していたイギリスを除くことによって、新規プロダクト・イノベーションの相関係数が改善するということです。また、イギリスを外れ値として除くことに妥当な理由があるかどうかという点についてGDPの推移を調べたところ、イノベーション以外の要因が大きくGDPに影響していることが伺われ、除くことが妥当と判断しました。そして、イノベーション実現割合と生産部門別の付加価値増加率との相関を調べたところ、新規イノベーション実現割合と有意の相関をする生産部門がいくつか存在することがわかりました。本来は、生産部門別のイノベーション実現割合と生産部門別の付加価値増加率を比較するべきなのですが、全体のイノベーション実現割合との相関であっても、ある程度のことは言えるのではないかと考えています。1つ目の問題点についての今回の検討結果をまとめると、「新規イノベーション実現割合はいくつかの生産部門の付加価値増加率と相関し、その結果GDPの増加(経済成長)に寄与していることが示唆される」ということになります。
Unknownさんの2つ目のご指摘である「基礎研究がGDPと関係があるのかないのか?」という点については、今回は検討できておらず、何ともいえません。仮に、基礎研究と応用研究に分けて論文数をカウントしたデータが入手できれば、今までの僕のデータにほり込めば、何らかの答えが出るかもしれません。学問分野別の論文数のデータは簡単に手に入るので、各学問分野別にGDPとの相関を検討するのは可能です。次に、一度やってみようかなと思います。
ただ、基礎研究と応用研究を区別した論文数となると、ちょっと難しいかもしれませんね。そのようなデータを入手できるかどうかという問題と、どこまでが基礎研究で、どこからが応用研究なのかという線引きが難しい面もあると思います。ノーベル賞を受賞したiPS細胞の研究にしても、基礎研究なのか応用研究なのか、判断が分かれるかもしれませんしね。要素技術、つまり、様々なイノベーションに応用ができる根幹的技術を開発できれば、経済成長にも大きく貢献できる可能性があるわけですが、これは、果たして基礎研究になるのか応用研究になるのか、僕にはよくわかりません。でも、例えば、天文学で新しい星を見つけたという論文は基礎研究でしょうね。そして、そのような論文がたくさんあっても、その論文数と短期GDPとが直接相関するとはさすがに思えません(ずっと先、たとえば50~100年後のGDPには関係している可能性は否定できませんが・・・)。ただ、基礎研究論文数が多い大学や国では、応用研究に携わる研究従事者も多く、企業への技術移転や共同研究・産学連携がさかんに行われているならば、間接的に基礎研究論文数とGDPが相関することもあり得ます。
いずれにせよ、Unknownさんからコメントをいただいたおかげで、国大協報告書に追加修正ができたわけなので、たいへん感謝するとともに、これは、草稿をブログ上で公開していることの効用だと思います。他の皆さんからもご意見やご指摘がいただけるとありがたいです。
***************************************************************
3)イノベーション実現率と生産部門別付加価値増加率との相関分析
次に、イノベーション実現割合と経済成長率の生産部門別の細目(生産部門別付加価値増加率)との相関を検討した。データは上記と同様、OECD.StatExtractsから入手した。GDP(付加価値)は購買力平価換算名目値(US$)を用いた。
ただし、ニュージーランドについては、2011年、2012年のデータが欠損しており、今回の分析では除外した。また、イギリスについては、前項の図75におけるプロダクト・イノベーション実現割合とGDP増加率の相関の散布図において外れ値的な値となること、および次に示す理由より除外し、オーストラリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、日本、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギーの12か国で分析することにした。
OECD.StatExtractsにおける各生産部門の内訳は以下のとおりであり、本報告における日本語表記を( )に示した。
・Gross domestic product (output approach)(GDP生産面)
・Agriculture, forestry and fishing(農林水産)
・Industry, including energy(鉱工エネルギー)
・of which: Manufacturing(うち製造)
・Construction(建設)
・Distributive trade, repairs; transport; accommod., food serv(流交通修理宿泊食サービス)
・Information and communication(情報通信)
・Financial and insurance activities(金融保険)
・Real estate activities(不動産)
・Prof., scientific, techn.; admin., support serv. Activities(専門技術経営支援サービス)
・Public admin.; compulsory s.s.; education; human health(行政社会保障教育健康)
・Other service activities(その他)
なお、OECDのInnovation in Firmsでは、農林水産業は調査対象に含まれていないことに留意する必要がある。また、本来は、各生産部門別にイノベーション実現割合と付加価値増加率を突き合わせて分析するべきであるが、今回は、農林水産業を除く企業全体のイノベーション実現率と、生産部門ごとの付加価値増加率の相関を検討しており、結果の解釈には注意が必要である。
図77に一人当たりGDPの推移を示す。

2009年にリーマンショックによると考えられる落ち込みが多くの国で見られる。日本の一人当たりGDPは12か国の中では最下位である。
図78に2005年を基点とする一人当たりGDPの推移を示した。

先ほどのデータと同様に多くの国で2009年に落ち込みが見られる。ただし、イギリスだけは、2009年の急激な下降以後、2012年までGDPが低迷したままであり、他の諸国のような回復が観察されない。
図79に金融部門の付加価値の推移を示したが、イギリスは2009年をピークに急激な低下を示しており、他の諸国とは大きく異なる動きを示している。

リーマンショックがイギリス経済に与えた影響の大きさの程が伺われ、前項のプロダクト・イノベーション実現割合とGDP増加率の散布図で外れ値をとる要因になっていると考えられる。
図80に、2005年の各国における各生産部門別の一人当たり付加価値のプロフィールを示した。

日本は鉱工業(エネルギーを含む)や製造業では、上位に位置している。専門技術経営支援サービス部門では、日本は欠損値となっている。「その他」の部門では、日本の値が突出して大きく、おそらく、「専門技術経営支援サービス」の値が、「その他」の部門に振り替えられているものと推測する。
日本の大きな特徴は、行政社会保障教育健康部門の付加価値が、OECD諸国に比較して極端に低いことである。日本の一人当たりGDPが先進国の中で低い理由は、この部門の付加価値の低いことが大きな要因の一つであると考えられる。
図81は2012年のプロフィールであるが、鉱工業(エネルギーを含む)や製造業における日本の優位性は失われている。日本の行政社会保障教育健康部門の付加価値は2005年に比較すると多少大きくなっているが、他諸国との差はさらに大きくなっている。

表31~34に、イノベーション実現割合と生産部門別付加価値増加率との相関分析の結果を示した。同時に、政府から公的(政府)機関と大学への研究開発資金(2003年)、および論文数(2002-2004平均値)との相関も示した。各相関係数の0.58が危険率5%、0.50が危険率10%の水準となっている。




今回の12か国を対象とする分析では、プロダクト・イノベーション実現率と経年後のGDP増加率との間には、前項表30(対象国14)と同様に、統計学的に有意の正相関が認められた。ただ、イギリスを除外したことで、相関係数は高くなった。
一方、プロセス・イノベーションとGDPの相関係数は低くなり、統計学的には有意性が失われた。
新規プロダクト・イノベーションとGDPとの相関係数は、プロセス・イノベーションとGDPの相関係数よりも高くなったものの、統計学的に有意となるまでには至らなかった。
このような、少数の対象国の入れ替わりで、相関係数の統計学的な有意性が変わることは、本研究のような、数の限られた国家を対象とする社会科学的分析の困難さを示すものと思われる。
プロダクト・イノベーション実現割合と付加価値増加率が良く相関(危険率5%以下)をする生産部門は、鉱工業(エネルギーを含む)、製造業、流通交通修理宿泊食サービス業、情報通信業、その他の部門であった。農林水産業、不動産業とも相関(危険率10%以下)すると考えられる。
プロセス・イノベーション実現割合は、製造業、流通交通修理宿泊食サービス業との相関係数が比較的高い(統計学的には有意でない)。
新規プロダクト・イノベーション実現割合は、農林水産業(危険率5%以下)、流通交通修理宿泊食サービス業(危険率10%以下)、情報通信業(危険率10%以下)、行政社会保障教育健康(統計学的には有意差なし)、その他の部門(危険率5%以下)との相関係数が比較的高い。なお、先にも述べたように、イノベーション実現割合の調査では農林水産業が含まれていない。
政府から大学への研究開発資金および論文数は、GDP増加率と有意の正相関をするが、相関係数は期間が短い方が高く、イノベーション実現割合が数年経過した後のGDP増加率との相関係数が高いことと、やや異なる挙動を示した。
政府から大学への研究開発資金と論文数が比較的良く相関する付加価値増加率の生産部門は、農林水産業、流通交通修理宿泊食サービス業、行政社会保障教育健康、その他の部門であり、新規プロダクト・イノベーション実現割合と相関する生産部門と共通しているものが多い。
政府から公的(政府)機関への研究開発資金と各生産部門の付加価値増加率との相関については正の相関をする部門はなかった。比較的強い負の相関をした部門は流通交通修理宿泊食サービス業であった(危険率5%以下)。
<含意>
今回のイノベーション実現率と生産部門別の付加価値増加率の分析では、イギリスがリーマンショックに起因すると思われる外れ値をとることから除外して分析をしたが、イギリスを含めた場合でも、プロセス・イノベーションと新規プロダクト・イノベーションの相関係数の有意性は変化するものの、概ね同様の傾向は読み取れる。
少数の国を入れ替えることで有意性が変化する現象は、数が限られ、また、複雑な因子が影響を及ぼす国家間の分析の困難さと限界を示すものと思われるが、他の分析等も合わせて考えると、プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーション、新規プロダクト・イノベーションの3つ共に、GDP増加率(経済成長)にプラスの影響を与える因子として考えることができると思われる。
各生産部門別の国民一人当たりGDPのプロフィールでは、2005年の時点では日本は鉱工業、製造業で高い順位にあったが、2012年ではこの分野で成長していない日本をいくつかの国が追い抜き、その優位性が失われた。
日本の大きな特徴の一つは、行政社会保障教育健康部門の付加価値が低いことであり、2012年にかけて、多少増加しているものの、他諸国との差は広がり、日本の一人当たりGDPの国際順位低下の要因の一つになっていると思われる。これは、日本政府が小さな政府を目指してそれを実現し、公務員の数の最も少ない先進国となり、教育費の公財政支出をOECD諸国の平均の2分の1という水準にとどめ、高齢化率の高い国家としては社会保障費・医療費の伸びを最小限に抑えてきた賜物かもしれない。しかしながら、果たして、その結果国民が豊かになったのかどうか、疑問を感じさせるプロフィールでもある。
今回は、農林水産業を除く企業全体のイノベーション実現割合と、生産部門ごとの付加価値増加率の相関を検討しており、結果の解釈には注意が必要である。しかし、およその傾向を推測することができるのではないかと考えている。
3つのイノベーション実現割合と各生産部門別の付加価値増加率とは、それぞれ微妙に相関の程度が異なっている。イノベーションは、どの生産部門においても、付加価値を増加させる重要な因子であると考えられるが、イノベーション実現割合の低かった生産部門や、イノベーション実現割合以外の要因が相対的に大きく付加価値に影響する生産部門においては、企業全体のイノベーション実現割合との相関係数は低くなるものと考えられる。
金融保険部門はイノベーション実現割合との相関が低い。これらの産業では、イノベーションよりも、それ以外の要因の方が付加価値増加率に大きく影響するものと容易に想像され、この結果は一般的な認識に合致する結果であると思われる。また、建設業や不動産業も、どちらかといえば相対的にイノベーション以外の要因に左右されやすい業種であると想像される。
鉱工業(エネルギーを含む)においては、プロダクト・イノベーション実現割合との相関は認められたが、新規イノベーション実現割合との相関は認められなかった。一般的には、これらの部門の付加価値においても新規プロダクト・イノベーションは重要な因子であると思われるが、鉱業などの新規プロダクト・イノベーションの困難な業種が含まれていることが一因ではないかと想像される。鉱業などを除いた「製造業」では、プロダクト・イノベーション実現割合との相関はより高くなり、プロセス・イノベーションや新規プロダクト・イノベーション実現率との相関も、統計学的に有意ではないが高くなる傾向にある。「製造業」で新規イノベーション実現割合の寄与が小さかったことが、これらの分析対象国の調査期間において、そもそも「製造業」の新規イノベーション実現割合が小さかったことによるのか、あるいは、実現割合が高かったにも関わらず付加価値増に結びつきにくかったのか、今回の分析では不明である。
新規プロダクト・イノベーションと相関の高い生産部門は、概ね、政府から大学への研究開発資金および論文数との相関も高く、これは、前項において、政府から大学への研究開発資金および論文数と新規プロダクト・イノベーション実現割合との間に相関が認められた結果と整合的な結果である。
新規イノベーション実現割合と比較的相関が強い生産部門としては、農林水産業、交通流通修理食サービス業、情報通信業、行政社会保障教育健康部門(有意ではない)、その他の部門であるが、これらの部門では、最近の成長著しい業種が含まれており、新規プロダクト・イノベーションの付加価値増加への寄与が大きいのではないかと推察される。また、大学の産学官民連携や大学発ベンチャーの産業分野を考えると、重工業というよりもバイオ、ICTなどの比較的軽い産業部門の比重が高いことも、これと整合的であるかもしれない。
このうち、農林水産業については、今回用いたイノベーション実現割合の調査対象となっていない部門であるが、新規プロダクト・イノベーション実現割合と良く相関した。一つの考え方としては、農林水産業以外の産業における新規プロダクト・イノベーション実現割合の高い国では、農林水産業においても新規プロダクト・イノベーション実現割合が高いという可能性である。そして、それに介在しているのが大学であると考えれば、一つの説明となるのではないだろうか。
専門技術経営支援サービス部門と各イノベーション実現割合との間には相関が認められないが、大学への研究開発資金や論文数との相関係数がやや高いことは(統計学的に有意ではない)、大学の役割を考える上で興味深い。
政府から公的(政府)機関への研究開発資金と各生産部門の付加価値増加率と正の相関をする部門はなかった。強い負の相関をする部門としては流通交通修理宿泊食サービス業がある。この部門と、政府から大学への研究資金や論文数との正の相関は強く、限られた政府予算の中で、大学への研究開発資金と公的(政府)機関への研究開発資金がシーソーゲームのような相反的関係にあるとするならば、大学の機能と強く相関する部門ほど、公的(政府)機関への研究開発資金とより強く負の相関をすることも理解できるかもしれない。
大学の機能を反映する指標(政府から大学への研究開発資金、論文数)は、概ね新規プロダクト・イノベーション実現割合と付加価値増加率が相関する生産部門と相関するが、微妙な違いもあるように思われる。その一つは、大学の機能を反映する指標の方が、やや早い時期のGDP増加率(付加価値増加率)と相関しやすいことである。今回のデータだけでは断定はできないが、これは、GDP上昇⇒大学への投資増加⇒大学の機能向上⇒イノベーション実現割合向上⇒付加価値増、という時間的な関係性を反映しているのかもしれない。
以上、各生産部門によって、イノベーション実現割合と付加価値増加率との相関の程度には差があり、また、プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーション、新規プロダクト・イノベーションの寄与の程度にも差があることが示唆された。つまり、大学の機能が経済成長(付加価値増)に寄与するとしても、その寄与の大きい生産部門と、大きくない生産部門が存在していると考えられる。
今回の分析結果を踏まえて、前項で示したパス仮説に付記・修正をするとすれば、
GDP増 ⇒ 政府から大学への研究開発投資増 ⇒ 大学の研究開発機能向上(FTE研究従事者数、論文数) ⇒ 生産部門(特に中小規模企業)の新規プロダクト・イノベーション実現割合向上 ⇒ 中長期付加価値増加率向上(特に新規プロダクト・イノベーション寄与の大きい生産部門) ⇒ GDP増
という好循環のスパイラル図が描ける。
また、「行政社会保障教育健康」部門のGDPがOECD諸国に比して突出して低いことを合わせて考えれば、現在政府が進めようとしているライフ・イノベーションの推進や規制緩和政策に加えて、高等教育部門への研究開発投資を、その総額を削減して「選択と集中」的配分をするのではなく、研究開発投資総額それ自体を増やす必要性が示唆される。
************************************************************
さて、今から鈴鹿医療科学大学のすぐ隣にある鈴鹿高専の「イノベーション交流プラザ」のオープニングセレモニーに顔を出してきます。高専も頑張ってるよ。