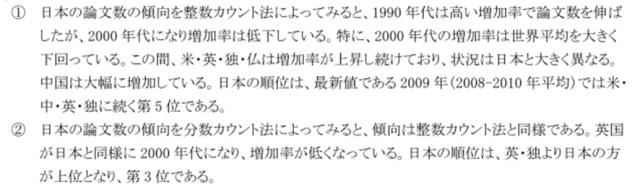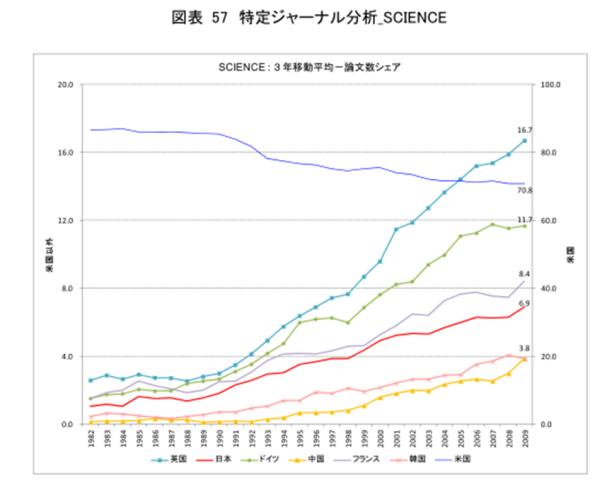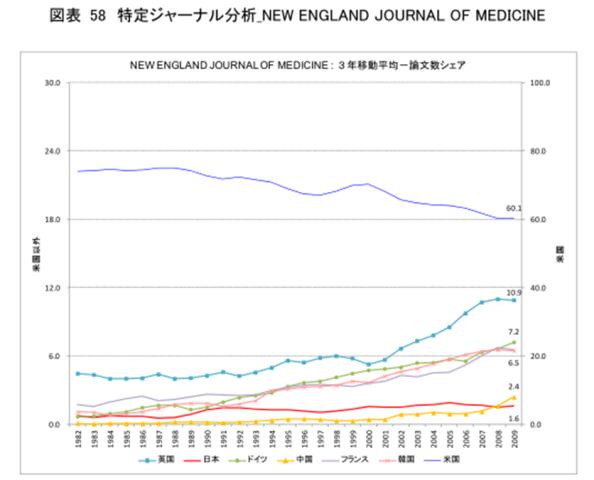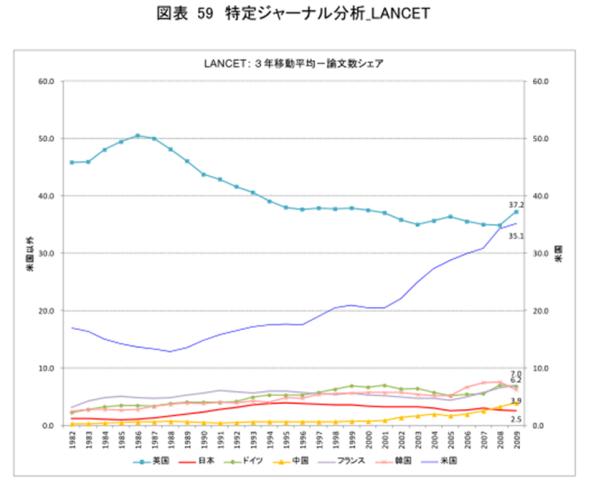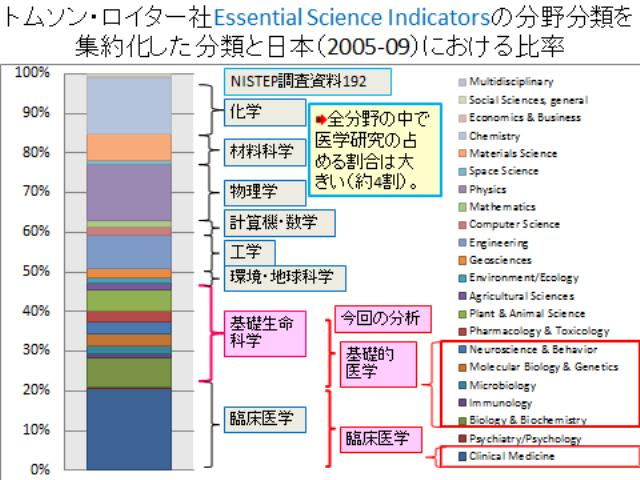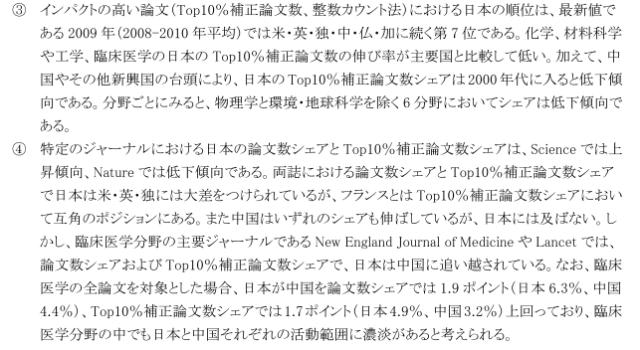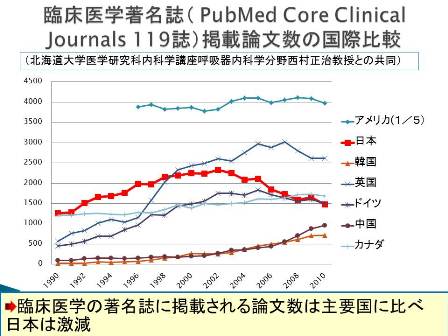(このブログは豊田個人の勝手な感想であり、豊田の所属する機関の見解ではない)
さて、前回のブログでは、大前研一氏の週刊ポスト(2月10日号)の記事の中の
「医師の不足や地域偏在の問題の元凶は、医師や病院が厚生労働省の管轄なのに、医学部を文科省が管轄していることにある。このシステムのままでは、いくら医学部の定員を増やしても、あるいは医学部を新設しても、医師が人員不足の診療科や地域に行くとは限らない。医師の養成は「医療行政」の問題だから、医学部は他の学部と切り離し、厚労省が必要な人材、場所、制度を作っていくべきなのだ。」
という、この記事の主旨が述べられている個所をご紹介し、また、私の「大学と地域医療」の一文から、医師不足や偏在について述べた個所をお示ししました。 果たして医学部を厚労省管轄にして問題は解決するのか?これから、この問題について考えてみたいと思います。
まず、大前氏は、「医学部」を厚労省管轄にすべきとおっしゃっているのですが、これは、かなり珍しいアイデアですね。附属病院だけを厚労省管轄にするというアイデアは、2004年の国立大学法人化に際しても議論されたと聞いています。また、海外ではそのような例があり、たとえばオーストラリアでは、医学部は文部省、付属病院は厚生省が管轄しています。ただし、それがいいのかどうかについては議論のあるところです。
次に、大前氏が医学部を厚労省管轄にするべきとされる具体的な理由を見ていきましょう。
「日本の場合、医師が何科の看板を掲げるかは自由である。医師免許を取得した者は人間の身体について全部理解しているスーパー・ゼネラリストであり、内科の診断もできれば外科の手術もできるという前提になっているからだ。
しかし、実際には大学在学中に専門分野を決めるので、血を見たり、手先の器用さが要求されたり、医療過誤で訴えられる可能性が高かったり、診療効率(患者の回転)が悪かったりする外科、産婦人科、形成外科、小児科などは人気がなく、聴診器を当てて薬を出すだけで済む内科は人気が高いのである。
この問題は医学部を「学問の府」とみなして、文科省が管轄している限り解決できないが、厚労省が管轄して患者の立場から考えればメスを入れることができると思う。つまり、医療行政の一環として診療科ごとに医師を養成し、医療現場の必要に応じて不人気な科の定員を増やし、人気がある科の定員を減らせばよいのである。
もしくは、外科医の給料を内科医の10倍にすればよい。医師の地域偏在についても、医師が不足している僻地などに赴任する場合は給料を格段に高くすればよいのである。
あるいは、不足している地域に15年以上赴任する場合は返済不要な奨学金を出す、などの策が自在に設計できる。そのように地域と専門分野別に給料や授業料などでインセンティブを与えれば、医師の最適配分が可能になるはずだ。」
つまり、診療科間および地域の医師の偏在の対策として、診療科の定員制の導入およびインセンティブ手法をあげておられます。
医師偏在問題については、すでに2009年6月3日付の財政制度等審議会の建議書「平成22年度予算編成の基本的考え方について」においても取り上げられています。医師の偏在には、ア地域間の偏在、イ診療科間の偏在、ウ病院・診療所(開業医)間の偏在の3つがあること、そして、対策としては、①医療費配分の見直し(経済的手法)、②医師の適正配置に向けた検討(規制的手法)、③医療従事者間の役割分担の見直し(高度な技能を有する看護師やコメディカルの活用)、の3つをあげています。
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia210603/zaiseia210603_01.pdf
経済的手法として、偏在により相対的に厳しくなっている部分に対し、経済的なインセンティブを付与することが考えられるとし、具体的には、診療報酬の配分や報酬体系を見直すとしています。
規制的手法の導入については、医師の職業選択の自由を制約するといった議論もあるものの、医師の養成には多額の税金が投入されていること等から、医師が地域や診療科を選ぶこと等について、完全に自由であることは必然ではない、と書かれています。そして、ドイツや他の国の例があげられています。
「諸外国を見た場合にも、例えばドイツでは、従来から保険医の開業には、10の地域や14の診療科ごとに定員枠を設け、開業の制限を行ってきた(規制的手法)ほか、今後は、保険医の過剰地域や過少地域においては、通常の1点当たり単価から減額又は増額されるシステムの導入も予定されている(経済的手法)。そのほか、医療提供体制について国際比較をしてみると、(研修医を含む)医師・保険医の地域や診療科の選択、その活動に当たっては、日本以外の主要国においては、制度的又は事実上の規制や制約といった公的な関与がある。」
これに対して、6月10日には、日本医師会が「財政制度等審議会建議に対する日本医師会の見解」を公表しています。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20090610_3.pdf
その中で「医師の診療科や開業地域の規制について」書かれた部分を引用します。
「財政審建議は、医師の偏在是正について、「医師が地域や診療科を選ぶこと等について、完全に自由であることは必然ではない」として、ドイツ、フランスの開業規制の例を示し、日本への規制の導入を示唆した。しかし、ドイツ、フランスは日本に比べてはるかに医師数が多い。
財務省は、診療科別医師数の増減のみを示したが、これは机上の計算であり、疾患別の患者数の増減や地域特性も考慮すべきである。たとえば産婦人科医師や外科医師の減少は、きわめて厳しい過重労働や訴訟リスクの高さなどが原因である。財政審は精神科医師数の増加を指摘しているが、その背景には3万人を超える自殺者、うつ病患者や認知症患者の増加がある。高齢化にともなって増える疾患などもある。
第一に医師不足の解消を図ること、第二に医師が診療科にかかわらず安心して働ける環境づくりを行い、さらに「地域で医師を育てる」仕組みづくりが必要である。」
また、6月11日には全国医学部長病院長会議が財政審の建議に対して、計画配置などの規制的手法ではなく、大学の調整力の回復や、労働環境の改善など医療のインフラ整備を行うべきという提言を発表しました。6月12日に、国立大学医学部長会議が麻生総理宛に要望書を出していますので、その関係個所を引用します。
http://www.chnmsj.jp/youbousyo%20H21%20zaiseiseido.pdf
「医師の適正配置に関して審議会が提言する規制的手法は導入されるべきではない。専門職に強制や規制を強化すれば、その社会や業務が健全に機能しなくなることはギリシア・ローマ以来の歴史が証明している。
審議会答申では開業の地域規制の例としてドイツの例を提示しているが、ドイツは他の種々の点で社会基盤が異なる上での開業医の規制であることは議論されていない。例えばドイツでは開業するのにホームドクターとしての専門医資格が必要であり、また州立大学医学部に教授が個人ベッドを持っている、などの現状がある。もし国家の医療制度をドイツに習うのであれば、全ての制度をドイツと同じにしなければ、その制度は機能しない。
また、米国の学生は国費の補助を受けてはいないという指摘があるが、ほとんどの学生は供与制の奨学金を受けているという事実は無視されている。海外の制度の一部を移入する議論は、各国の社会基盤の相違を踏まえて行われなければならない。医師に限らず、全ての学生の教育はその一部を国税によって賄われているが、国立大学医学部における教育には国税を使っているので学生の専門の決定や配置に関しては規制が導入されてもよいという意見は、基本的人権の見地から見ても誤りである。」
また、この年の8月1日には著名な医療経済学者である二木立・日本福祉大学教授が医師提供の仕組みについてコメントしておられます。
http://www.inhcc.org/jp/research/news/niki/20090801-niki-no060.html
「私が言いたいのは、医療の提供体制については、国家が統制してはいけないということ。医師は自律性がないと力を発揮できない職業だ。僻地勤務義務化などの規制強化は、大きな過ちをもたらすと思う。」
「新臨床研修制度の期間短縮を主導したのは大学病院で、すべての病院団体は期間短縮には反対した。同制度は、劣悪だった研修医の待遇を改善し、プライマリケア医としての能力を高めるという所期の目的を達成しているというのが大方の評価だ。制度発足後、研修医の臨床能力が高くなったことは、いろいろな調査で判明している。今の制度の大枠は維持すべきだと思う。
ただし、医師不足に直面した地方の大学病院による同制度への批判にも一理ある。医師の地域偏在の解決には、医学部の地域枠(地元出身者の優先入学枠)の大幅拡大が不可欠だ。同時に、医師会や病院団体、医学会などが加わった、都道府県単位での医師配置に関する緩やかな枠組み作りも検討すべきだ。
根本的な問題解決は医師の数が増えることだが、6~7年、あるいは10年かかる。併せて、日本学術会議が昨年提唱した全科共通基準の専門医制度の確立も必要だ。今のような自由放任型の学会専門医制度ではなく、必要数を定める制度にすべき。そうなれば、診療科目ごとの偏在も是正されていくだろう。」
以上のような医師偏在についての議論を考え合わせると、日本の医療供給体制の歴史や外国とのあまりにも大きな違いを考えると、診療科の定員制をただちに強硬に実施することは、厚労省が医学部を管轄するかしないかに関係なく、困難な情勢であると思われます。
インセンティブ制度については、”外科医の給与を内科医の10倍にすればよい”、というような極端な表現ではありませんが、以前から検討されています。実際、産科医に対しては、安倍政権の時に、待遇改善を条件として産科の診療報酬がすでに上げられていますね。一部の大学病院では産科医の給与が他の医師よりも多くなっています。そして、その効果も徐々に表れつつあるのではないかと感じられます。
また、外科医については、平成22年度の診療報酬改定で外科手術を中心に引き上げられました。ただし、外科の収益増を外科医の給与に反映するかどうかは各病院の判断にゆだねられており、現実にはあまり変わっていないのではないかと思われます。これは厚労省が医学部を管轄する・しないに無関係のファクターです。
大前氏は経済的インセンティブの必要性を強調するために、”外科医の給与を内科医の10倍にすればよい”という極端な表現をしておられますが、全体の医師数が不足している状況では、人気のある診療科が必ずしも医師が余っているとは限らず、また、一つの診療科を救うと、モグラたたきのように別の診療科が医師不足に陥る危険性もあるので、きめの細かい調整が必要と思われます。
また、返済不要な奨学金を出す制度も、昭和47年開学の自治医科大学がずっと実施してきましたし、現在医学部学生定員増に伴って返済不要奨学金を自治体が出す地域枠も整備されたところです。
また、以前から、僻地の自治体病院の医師の給与は、都会の病院の医師の給与よりも相当高く設定されています。その分、自治体の財政を圧迫しているわけですが。この財源を何らかの形でさらに確保していただけるのであれば、大前氏のご提案のように、僻地の医師確保には追い風になると思います。この財源の確保についても厚労省が医学部を管轄するかどうかとは無関係のファクターです。
結局、厚労省が医学部を管轄したとしても、今の情勢では診療科の定員制の導入は難しいのではないでしょうか?また、海外では、厚労省が医学部を管轄していない国でも診療科や専門医の定員制が導入されています。診療科の定員制度やインセンティブ制度を作ることは、医学部を厚労省の管轄にする・しないとは別の次元の話のように思えます。
5年ほど前にオーストラリアの大学病院を視察したのですが、オーストラリアでも僻地への医師供給にたいへん苦労していました。医学部入学の徹底した地域枠とともに、専門医資格の条件として地域での一時的な診療経験を義務付けていました。
歯科医師くらい医師数を増やせば、市場原理だけで偏在問題も解決するかもしれませんが、医師数をある程度増やすだけでは医師偏在の問題は解決せず、私も何らかのマイルドな規制的手法と経済的手法の併用が必要であると考えています。
私の勝手な意見としては、具体的には二木氏のおっしゃるように、全科共通基準の専門医制度の確立とその必要数の制定、および、オーストラリア方式で、地域での一時的な診療経験を経済的インセンティブを与えるとともに専門医資格認定要件とするくらいなら、日本の現状でも許容範囲ではないかと考えています。これは、すぐには実現できないかもしれませんが、状況が整えば厚労省が医学部を管轄するかどうかとは関係なく実現可能だと思います。
ただ、大前氏とは若干違う趣旨で、私は大学病院の管轄には、文科省だけではなく厚労省も加わるべきであると思っています。私は、三重県選出の川崎二郎衆議院議員が厚労大臣であった時に、いろいろなお願いをしたのですが、その中の一つに、大学病院は文科省と厚労省を超越した部署が管轄するべきである、もしくは密接に連携をして管轄するべきであると進言したことがあります。
私の意見を聞き入れていただいたのかどうかは、まったくわからないのですが、進言して間もなく、2006年から文科省高等教育局医学教育課の課長(現在は企画官)は、厚労省から派遣された医系官僚になっています。文科省と厚労省の交流人事には、役所の現場ではいろいろとやりにくい点もあろうかと思いますが、私は、更にいっそう交流人事を深めて欲しいと思っています。
すなわち、現在では、医学部および附属病院は、制度的には文科省の管轄ですが、文科省と厚労省の両省がいっしょに管理をしていると申し上げていいでしょう。
またまた、超長いブログになってしまいましたが、今回のブログをまとめますと、医師偏在の対策として医師数増とともに規制的手法と経済的インセンティブの併用が必要であるという基本的な方向性では、大前氏の意見と同じですが、日本の医療供給体制の現状に合うような現実的な対応が必要であること、そして、まだ不十分かもしれませんが、いくつかの対策はすでになされていること、そして、その実現は厚労省が医学部を管轄するかしないかには関係がないと思われることをお話しました。
また、医学部の管轄を文科省から厚労省に移すことは現実的な対応ではないと思いますが、厚労省も大学病院に加わるべきであるということについては、大前氏の意見と共通した部分があります。現実的には、文科省医学教育課と厚労省の交換人事がすでに行われており、この交流はさらに強固なものにするべきであると考えます。
次回につづく