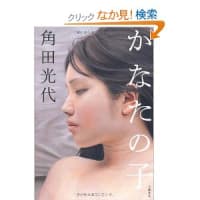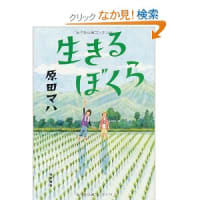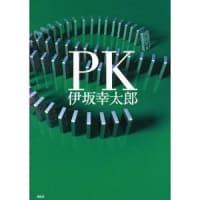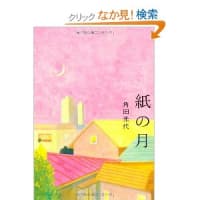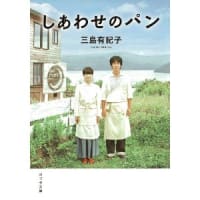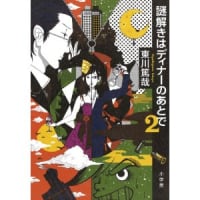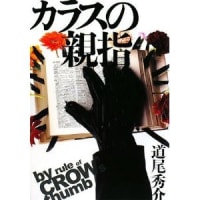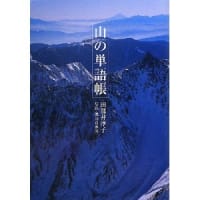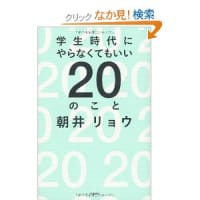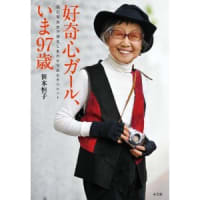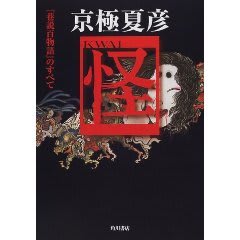
その目玉は、『巷説百物語』の映像化作品で、京極自身が手がけた「七人みさき」の脚本が完全収録されている点。『巷説百物語』シリーズは、2000年に「京極夏彦 怪」としてドラマ化され、放映後、第1話「七人みさき」は劇場でも公開されている。映像化にあたっては原作と異なるオリジナルの脚本が書き下ろされ、京極の言葉を借りれば「原作の設定を生かしつつも、まったく違うリフレッシュした又市が誕生した」という。「飛縁魔」「船幽霊」「死神」の、「七人みさき」3部作が収録されている『続巷説百物語』との異同を楽しむのもおもしろい。
夏だから、怪談。オカルト、ホラーなど言葉だけで意味が不明ですが。日本における怪談話。は民俗学的にも興味深し。
~妖怪譚の影には人間の愛憎劇が見え隠れし、複雑に絡み合った人間関係から怪異は生じる。表向きに不思議な妖怪譚は、裏には猥雑で歪んだ人間関係がある。歪みから発生した悲劇に泣く者、笑う者、そして死ぬ者。裏の出来事は、裏の世界の者たちの仕事。
「絵本百物語」は、江戸時代に流行った百物語の1つだが絵師竹原春泉の描いた妖怪に桃山人なる俳者が文章を記したスタイル。時代背景は、水野忠邦の天保の改革さなか。一般庶民の表現の自由と、言論の自由を奪う強行政治であり。著者の桃山人は、直接には語れない時代の批判を、妖怪という風刺を使って表現したという。妖怪画集と見せかけて、実は人間風刺だ。妖怪、幽霊は日常の視点では容易に見えてこない、人間の内面、その秘められた情念や思いを外に映し出す鏡。江戸時代では民間信仰にあっては自然に対する怖れや冒瀆心、好奇心などが定見下自然とのコミュニケーションの説話化であるし、年にあっては遊興の1つとしての怪談話・百物語、あるいは滑稽な人間風刺の1つとしての「お化け」
その日常ならざる者たち妖怪解説が興味深い
越後高田に伝わる「小豆洗」、甲斐国夢山の「白蔵王」、三悪人の「舞首」、淡路島の狸「芝右衛門狸」、加賀国の「塩の長司」、柳の木に出る「柳女」、京都右京区の「帷子辻」、穴熊「野鉄砲」、我慢強情の別名、無分別者「狐者異(こわい)」、「飛縁魔縁障女」、「死神」、海難者の亡魂が化けた「船幽霊」、四国の海岸地方の特に高知の死霊「七人みさき」、愛媛県松山市の化け狸「隠神狸」、徳島県徳島市津田西町穴観音の六右衛門狸と小松市日開野の「金長狸」の対決「阿波狸合戦」、漁業、海運商業を守護し福利をもたらす神霊「恵比寿」、「六部殺し」、「福神」、「阿多福」、「福助」
禅では現象世界のモノすべては無常(ありとあらゆるモノは移り変わり、変化変遷し、永遠不変なモノはない。人の肉体も人生も同じく変化しやがて消滅するものであるから、人がある状態や一部に固執、執着することはむなしい行為)と説く。信仰深い嵯峨天皇の皇后・橘嘉智子は美しい屍を帷子辻に野ざらしにし、自らの身をもって、無常の教えを実践した逸話は、挿絵と合わせてすさまじい。
「死神」とは悪念を持ったまま死んだ者の気が、同じような、悪念の持ち主に呼応して、魅入られてしまうこと。「死神が憑く」とは、死神が体に取り憑き、死にたい気持ちになることあるいはまもなく死ぬ運命にあること。死神に死ぬことを誘惑されること。
仏教後で「我慢」とは、世界の中心は自分だと考え、自分の我をよりどころにして心が驕り高ぶっていることを意味し、慢心(自分だけ気分がよければよいという心)。「狐者異」は、生きているうちは法(世間のモラル、仏教が説く徳行)を無視し、死んでからも忘念執着(自分勝手な思いこみ)を引きずって、無量の形(不平不満の恨み辛みがはかりしれない一念となった鬼の姿)で仏法世法の徳の妨げをなす。
真に人の心をうつしだす妖怪の個性豊かな面々や、それを生み出した、人間の想像力は、はかりしれません。