監督 コーエン兄弟 出演 ブラッド・ピット、ジョージ・クルーニー、ジョン・マルコヴィッチ、フランシス・マクドーマンド、ティルダ・スウィントン
あれっ、ブラッド・ピットがコーエン兄弟の映画に? 大丈夫かなあ。と、不安を抱えてみていると、最初に殺される。あ、これで安心して見ていられる--と、ふと思ってしまう。ブラッド・ピットのファンには申し訳ないが、そういう映画である。ストーリーはあるにはあるが、どうでもいい。「勘違い」が次々に重なり、「事件」が進んで行くのだが、その「勘違い」の重なり合い具合がおかしい。
ブラッド・ピットが最初に死んで安心した--と書いたが、まあ、それは書き出しの「方便」。どう書き出していいかわからないので、ついつい書いてしまったこと。
実は、ブラッド・ピットがなかなかいい。
何の勝算(?)もなくて、ただ、これはおもしろそうと思って、偶然手にいれたCIAの職員が記録したデータをもとに恐喝をこころみる役なのだが、世の中のことを何もわかっていないという感じが、目にとてもよくでている。
他人を見るときの視線が、他人の「思惑」のなかまで入っていかない。このひとはこういう行動をしているけれど、ほんとうは何を考えているのだろう--というようなことはまったく考えない。感じない。相手の「表面」に触れるだけなのだ。
カメラは、その視線、視線の力をとてもよく伝えている。
ブラッド・ピットにかぎらず、この映画では、みな「視線」で演技する。それをカメラは的確にとらえる。ある意味では「視線」の映画なのである。
たとえばジョージ・クルーニーの大きな目は、他人をぐいと自分の視界のなかに引き入れる。フランシス・マクドーマンド相手に、大人のおもちゃ(?)の椅子を紹介して、「すごいだろう、手作りなんだぞ」と自慢する時の目は傑作である。目のなかに入ってくる人間(女)を拒まない、という「枠なし(?)」の目である。その一方で、「枠」が広すぎて、目に入ってきたものをも、網目から取りこぼすように、見逃してしまう。妻が浮気していることに気がつかないし、間違って殺してしまったブラッド・ピットのことをジョン・マルコヴィッチと思いつづけてもいる。不都合なこと(?)は目の枠からこぼしてしまう。適度な大きさの目を維持することが、ジョージ・クルーニーにはできないのである。
そのジョージ・クルーニーの不倫相手、ティルダ・スウィントンはジョージ・クルーニーと正反対の目付きをする。相手をみつめながらも、相手が自分のなかへ入ってくることに対しては警戒する。常に相手の本心をさぐる。ジョージ・クルーニーと不倫を重ねながら、この男はほんとうは何を考えているのか、じーっとみつめるのだが、そのとき、ジョージ・クルーニーの視線がティルダ・スウィントンの内部へ入ってくることは、冷たく拒絶している。目は心の窓というが、ティルダ・スウィントンは自分の窓は閉ざして、相手の窓は覗き見るのである。レストランで食事をしたあと、ジョージ・クルーニーと別れるときのシーンや、弁護士に離婚の相談をするシーンの、弁護士のことばを聴きながら、頭の中でそのいみするところを反芻する目付きにも、それがとてもよくでている。
目のドラマ(?)のクライマックスは、公園でジョージ・クルーニーのうろたえるシーン。ジョージー・クルーニーは、自分が監視されている(追われている)と勘違いする。ここでも、ジョージ・クールニーの「枠なし」というか「底無し」に大きな目は、見るものすべてを「自分を監視している・追っている」と受け止めてしまう。
このときの、ジョージ・クルーニーの視線、それとぶつかる「監視舎」の、カメラのすばやい切り替えが、この映画は「視線」の映画だということをはっきり浮かび上がらせる。
そして、この裏返しが、CIAの幹部たち。彼らの視線。彼らは人間を直接見ない。事件を直接見ない。文字(リポート)にして、そのことばの動きを見る。人間をことばにして見てしまう。直接、自分の目で見ないがゆえに、そこに起きたことをすべて「見なかったこと」にしてしまって平気である。つまり、「事件」を葬り去って、まったく、心を痛めることがない。
自分の目で見る人間は心を痛めるが、自分の目で見なければ、心なんか痛まない。
などということを言ってしまうと、なんだかこの映画は哲学的・倫理的なものに落ちてしまいそうだけれど。まあ、しかし、そう思ってしまった。
あれっ、ブラッド・ピットがコーエン兄弟の映画に? 大丈夫かなあ。と、不安を抱えてみていると、最初に殺される。あ、これで安心して見ていられる--と、ふと思ってしまう。ブラッド・ピットのファンには申し訳ないが、そういう映画である。ストーリーはあるにはあるが、どうでもいい。「勘違い」が次々に重なり、「事件」が進んで行くのだが、その「勘違い」の重なり合い具合がおかしい。
ブラッド・ピットが最初に死んで安心した--と書いたが、まあ、それは書き出しの「方便」。どう書き出していいかわからないので、ついつい書いてしまったこと。
実は、ブラッド・ピットがなかなかいい。
何の勝算(?)もなくて、ただ、これはおもしろそうと思って、偶然手にいれたCIAの職員が記録したデータをもとに恐喝をこころみる役なのだが、世の中のことを何もわかっていないという感じが、目にとてもよくでている。
他人を見るときの視線が、他人の「思惑」のなかまで入っていかない。このひとはこういう行動をしているけれど、ほんとうは何を考えているのだろう--というようなことはまったく考えない。感じない。相手の「表面」に触れるだけなのだ。
カメラは、その視線、視線の力をとてもよく伝えている。
ブラッド・ピットにかぎらず、この映画では、みな「視線」で演技する。それをカメラは的確にとらえる。ある意味では「視線」の映画なのである。
たとえばジョージ・クルーニーの大きな目は、他人をぐいと自分の視界のなかに引き入れる。フランシス・マクドーマンド相手に、大人のおもちゃ(?)の椅子を紹介して、「すごいだろう、手作りなんだぞ」と自慢する時の目は傑作である。目のなかに入ってくる人間(女)を拒まない、という「枠なし(?)」の目である。その一方で、「枠」が広すぎて、目に入ってきたものをも、網目から取りこぼすように、見逃してしまう。妻が浮気していることに気がつかないし、間違って殺してしまったブラッド・ピットのことをジョン・マルコヴィッチと思いつづけてもいる。不都合なこと(?)は目の枠からこぼしてしまう。適度な大きさの目を維持することが、ジョージ・クルーニーにはできないのである。
そのジョージ・クルーニーの不倫相手、ティルダ・スウィントンはジョージ・クルーニーと正反対の目付きをする。相手をみつめながらも、相手が自分のなかへ入ってくることに対しては警戒する。常に相手の本心をさぐる。ジョージ・クルーニーと不倫を重ねながら、この男はほんとうは何を考えているのか、じーっとみつめるのだが、そのとき、ジョージ・クルーニーの視線がティルダ・スウィントンの内部へ入ってくることは、冷たく拒絶している。目は心の窓というが、ティルダ・スウィントンは自分の窓は閉ざして、相手の窓は覗き見るのである。レストランで食事をしたあと、ジョージ・クルーニーと別れるときのシーンや、弁護士に離婚の相談をするシーンの、弁護士のことばを聴きながら、頭の中でそのいみするところを反芻する目付きにも、それがとてもよくでている。
目のドラマ(?)のクライマックスは、公園でジョージ・クルーニーのうろたえるシーン。ジョージー・クルーニーは、自分が監視されている(追われている)と勘違いする。ここでも、ジョージ・クールニーの「枠なし」というか「底無し」に大きな目は、見るものすべてを「自分を監視している・追っている」と受け止めてしまう。
このときの、ジョージ・クルーニーの視線、それとぶつかる「監視舎」の、カメラのすばやい切り替えが、この映画は「視線」の映画だということをはっきり浮かび上がらせる。
そして、この裏返しが、CIAの幹部たち。彼らの視線。彼らは人間を直接見ない。事件を直接見ない。文字(リポート)にして、そのことばの動きを見る。人間をことばにして見てしまう。直接、自分の目で見ないがゆえに、そこに起きたことをすべて「見なかったこと」にしてしまって平気である。つまり、「事件」を葬り去って、まったく、心を痛めることがない。
自分の目で見る人間は心を痛めるが、自分の目で見なければ、心なんか痛まない。
などということを言ってしまうと、なんだかこの映画は哲学的・倫理的なものに落ちてしまいそうだけれど。まあ、しかし、そう思ってしまった。
 | ファーゴ [DVD]20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパンこのアイテムの詳細を見る |
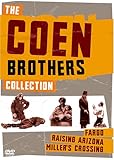 | コーエン・ブラザーズ コレクション [DVD]20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパンこのアイテムの詳細を見る |
















