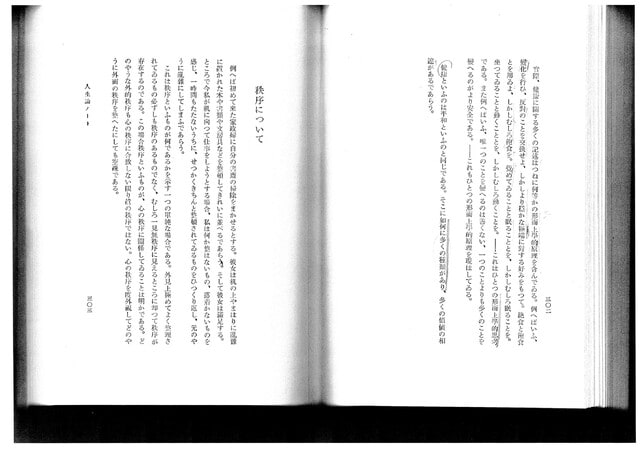最果タヒ『不死身のつもりの流れ星』(PARCO出版、2023年02月01日発行)
最果タヒ『不死身のつもりの流れ星』を半分くらいまで読み進んだ。「ぼく」「きみ」あるいは「あなた」、「愛」(恋)ということばが何度も出てくるように思う。「愛」のかわりに、「悲しい」「寂しい」「美しい」かもしれない。数えたわけではない。
ふと思ったのだが、たとえば「愛」はどこにあるのか。「ぼく」のなかにあるのか(「ぼく」から生まれてくるのか)、「きみ」のなかにあるのか(「きみ」から生まれてくるのか。
きっとちがうだろう。
それは「ぼく」と「きみ」のあいだにあって、それがあいだにあるときだけ、「ぼく」が「ぼく」であり「きみ」がきみ」である、というものなのだろう。言い直すと、いま書いたようなものは、すべて、ほんとうは存在しない。
「あいだ」すら、存在しない。
でも、それが、ときどき「生まれてくる」。それは偶然なのか、必然なのか、わからないが、そういう瞬間があるのだ。
そして、その瞬間に、こういうことが起きる。
ぼくはあなたのせいでぼくは誰とも混ざり合うことのない固有の存在なのだと思い知り、
(一等星の詩)
「ぼく」は「あなた」がいるから、ここにいる。「ぼく」は「あなた」によって産み出された存在であると言える。
で、このときの。
「混ざり合うことのない」ということばが、私にはとてもおもしろく思える。「混ざり合うことのない」ものは、「混ざり合ったものがない」ものであり、それは別なことばで言えば「透明」。しかし、透明なものは「見えない」。つまり存在しないように感じられる。その「見えない、透明」なものが「固有の存在」、そこにあるものとして見える。「見えない」のに、ある。
「混ざり合うことのない」ものは、どうなるのだろうか。「愛」とは「混ざり合う」ものだろう。
ここには、どうすることもできない「矛盾」がある。
そして、もうひとつの大切なことばが、この行のなかにある。「思い知る」という動詞。すべてはことばのなかで動く。「現実世界(物理的世界)」には「矛盾」はない。「矛盾」は、ことばのなかだけに存在する。もし世界に矛盾があるのなら、世界は存在しない。動いていかない。世界が動いている限り、世界に矛盾はない。ことばが世界に追いついていかないとき、「ことば」のなかに「矛盾」があらわれるだけである。
きみのさみしさはいつも、だれかから借りてきたものだったね、だからさみしくても、美しいものを見ると、美しいとおもえた、 (periodo)
「きみ」は、「きみ」の感情(さみしさ、美しいと思う気持ち)は、固有のものではない。だから、次々にかわっていく。これを先の詩の「ぼく」にあてはめることができるのではないか。
「ぼく」は「あなた」の借り物。「混ざり合うことのない」つまり、混ざりけのない」透明な「ぼく」は、「あなた」の「愛(と、仮に書いておく)」によって、「ぼく」という色(と、仮に書いておく)になるが、それは「借り物」だから、「愛」ではなくて「憎しみ」を見さみしさ」「うつくしさ」がると、もう「愛」ではいられなくなる。別れてしまう。
そのとき「ぼく」と「あなた」のあいだ(間)は広がるのではなく、なくなってしまう。
「矛盾」でしか語ることのできないもの、「混ざり合うことのない」ものが、そのとき、ことばのなかを通過していく。そして、それは「輝き」であり、目に見えない「光」だ。
ぼくとあなたが
消えてしまった街では、
雪の代わりに夏が降る。
溶けていくのはいつも世界の方で、
いつか夏だけが降り積もって、あ、まぶしい、 (雪の夏)
この「あ、まぶしい」が、そのとき、感じられる。まぶしさのなかで、何も見えなくなる。何もかもが消える。そして、消える瞬間に、存在した「ぼく」が「きみ」が、そして「愛」や「さみしさ」や「美しさ」が見える。そういう「矛盾」。
それは、どう名付けてもいいものであるからこそ、「ぼく」「きみ」、「愛」「さみしさ」「美しさ」ということばにならなければならない。「矛盾」は、ことばを必要としている。「矛盾」は「ことば」よって、発見されたがっている。
**********************************************************************
★「詩はどこにあるか」オンライン講座★
メール、skypeを使っての「現代詩オンライン講座」です。
メール(宛て先=yachisyuso@gmail.com)で作品を送ってください。
詩への感想、推敲のヒントをメール、ネット会議でお伝えします。
★メール講座★
随時受け付け。
週1篇、月4篇以内。
料金は1篇(40字×20行以内、1000円)
(20行を超える場合は、40行まで2000円、60行まで3000円、20行ごとに1000円追加)
1週間以内に、講評を返信します。
講評後の、質問などのやりとりは、1回につき500円。
★ネット会議講座(skypeかgooglemeet使用)★
随時受け付け。ただし、予約制。
週1篇40行以内、月4篇以内。
1回30分、1000円。
メール送信の際、対話希望日、希望時間をお書きください。折り返し、対話可能日をお知らせします。
費用は月末に 1か月分を指定口座(返信の際、お知らせします)に振り込んでください。
作品は、A判サイズのワード文書でお送りください。
少なくとも月1篇は送信してください。
お申し込み・問い合わせは、
yachisyuso@gmail.com
また朝日カルチャーセンター福岡でも、講座を開いています。
毎月第1、第3月曜日13時-14時30分。
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1
電話 092-431-7751 / FAX 092-412-8571
*
オンデマンドで以下の本を発売中です。
(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)
嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512
(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)
読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009
(3)評論『高橋睦郎「つい昨日のこと」を読む』314ページ。2500円(送料別)
2018年の話題の詩集の全編を批評しています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804
(4)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)
『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455
(5)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)
2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977
問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com