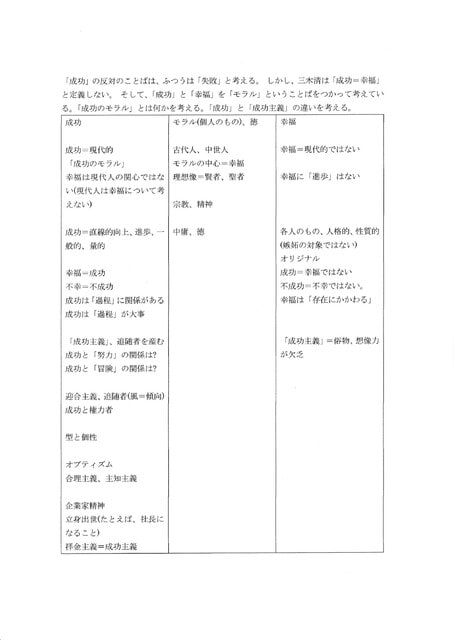藤山増昭『岸辺のパンセ』(編集工房ノア、2022年10月11日発行)
藤山増昭『岸辺のパンセ』の表題作。
生を乱す死と
死に繕われる生の岸辺に
一茎の葦の 羨しき発光
「一茎の葦」がパスカル「パンセ」を思い起こさせる。そして、藤山は「生と死」について考えている。そのことが直感できる書き出しである。この直感は、私の背を立ち上がらせる。背筋をのばさないと、読むことができない。私は「死」については何も知らない。だから、考えないことにしている。考えても仕方がないと思っている。これは、あくまで私の考えであり、藤山はそうは考えない。その考え方の違いに直面して、私の背はすっと伸びたのである。このひとは考え方が違うから、読んでみてもしようがない、という気持ちにならない。そうさせない「響き」がことばのなかにあった、ということだ。
羨しき発光
「発光」。藤山は「生と死の出会い」のようなものに、光を見ている。それはそこに初めからある「光」ではなく、「発した光」、瞬間的に生まれてきた光。そして、その「発光」には「羨しき」ということばが重ねられている。「羨しき」は「ともしき」とルビがある。私は、こういう読み方を知らないし、このことばをつかったこともない。私の知らないことを、藤山は私の知らないことばで語り始めている。しかし、それが全部わからないのではなく「発光」という私の知っている(と思っている)ことばといっしょに動いている。
私は本当に何かを知っているのか。知らずにいるのに、平気で、知ったかぶりを書いているのか。
それが、これから問われるのだ。その問いの前で、私の背は伸びた。
流れ下る 冷えた石の川床
削がれる意識を入れた洞窟の闇
今も残像する悍しき夢幻の淵
「発光」とは逆に、ここでは「闇」に代表される「光」の対極のものが書かれている。何も見えないわけではないが、見ていて「明るさ」を感じる世界ではない。この「あいまいな暗さ」を、藤村は、こう言い直す。
存在に付き纏う不可知と未在未生のかげ
堆積し続ける命の塔は ゆらぎ傾き
系統樹の小枝の先端がふるえている
私が「あいまいな暗さ」と読んだものは「かげ」である。(「かげ」には傍点が振ってある。)「かげ」は「実体(実在)」ではないもの、「実在するもの」に光があたったときに、その影響で生まれてくるものがあるが、ここでの「かげ」はそういう明瞭なものではない。ぼんやりとした「闇」の濃淡のようなものだ。この「あいまいな暗さ」のために「命」がゆらぎ傾き、ふるえている。これは「発光」というよりも、むしろ消えていく光、消滅する光の最後の姿に見える。
だが ふと 大空からのあおき反響
それは重々無尽の宇宙からの波動
劫初からの 澄みわたるいのちのこえ
「こえ」にも傍点が振ってあり「かげ」と対応していることがわかる。「かげ(闇の濃淡、ゆらぎ)」の対極にあるのは「光」ではなく「こえ」である。「こえ」は「いのちのこえ」と書かれているから、「いのち」と不可分のものと藤山が考えていることがわかる。
「光」と「声」に共通するのは、それが「波(波動)」であるということだろうか。
「こえ」はまた「反響」とも関係している。呼応している。「響き」、それも単純な響きではなく「反響」。跳ね返ったもの。何が跳ね返ったものなのか。たぶん、藤山の「意識」、あるいは「声にならない声」を発したとき、それに答えるように「こえ」が跳ね返ってきた。
その「反響」に「あおき」ということばが重なっている。「青き」だろう。これが藤山の言う「光」(発光)だろう。それは「白」ではなく、「あお」、そして「澄みわたる/あお」ということになる。しかも、それは「視覚」に訴えてくるだけではなく、「聴覚」に「こえ」として、つまり「ことば」としてやってくる。
「宇宙は私を包み 一つの点のように
のみこむ。考えることによって
私が宇宙をつかむ。」
注釈によれば、これはパスカルの「パンセ」からの引用である。生と死の衝突の瞬間に、藤山は「発光」を見た。それは「ことば/こえ」として藤山のとらえた。しかし、それは生と死が藤山を「のみこむ」であると同時に、藤山が生と死を「つかむ」ということだ。
瞬間的に、藤山はパスカルのことばにのみこまれ、包まれている。しかし、それは藤山のパスカルを理解する方法なのだ。「のみこまれ」た瞬間に、それを「つかむ」。パスカルが藤山をのみこむとき、藤山はパスカルをつかむ。
切り離せない。
この、私が「切り離せない」と呼ぶものを、藤山は、最終連で、こう言い直している。
感応のなかにも
外なる空と 内なる空とを
つかみ つなげるのだろうか?
「つなげる」。それは「接触」ではなく「融合」だろう。
藤山のことばは、少しずつ「意味」(定義)をかえながら、新しいことばになり、その変化のなかで、変化することでしか描けない「世界」をとらえている。その運動に、藤山が真摯に向き合っていることがつたわってくる。
この真摯さのために、私の背が、すっと伸びたのだと思う。
ゆっくりと読みたい詩集だ。ゆっくりと読まなければならない詩集だ。これは、自戒として書いておく。私は早く読みすぎる。
だから。
一息ついて、私は少し追加する。
「宇宙は私を包み 一つの点のように
のみこむ。考えることによって
私が宇宙をつかむ。」
「宇宙と私」「パスカルと藤山」が「一つ」に融合するとき、そこに「考える」ということばが動いている。「考える」のは「ことば(こえ)」をつかって考えるのである。藤山は生と死の出会いについて、考えた。ことばを動かした。それが、この詩集ということになる。この詩集を読むためには、私は私なりに、私なりのことばを動かさなければならない。考えなければならない。この詩集は、考える詩集である。
**********************************************************************
★「詩はどこにあるか」オンライン講座★
メール、skypeを使っての「現代詩オンライン講座」です。
メール(宛て先=yachisyuso@gmail.com)で作品を送ってください。
詩への感想、推敲のヒントをメール、ネット会議でお伝えします。
★メール講座★
随時受け付け。
週1篇、月4篇以内。
料金は1篇(40字×20行以内、1000円)
(20行を超える場合は、40行まで2000円、60行まで3000円、20行ごとに1000円追加)
1週間以内に、講評を返信します。
講評後の、質問などのやりとりは、1回につき500円。
★ネット会議講座(skypeかgooglemeet使用)★
随時受け付け。ただし、予約制。
週1篇40行以内、月4篇以内。
1回30分、1000円。
メール送信の際、対話希望日、希望時間をお書きください。折り返し、対話可能日をお知らせします。
費用は月末に 1か月分を指定口座(返信の際、お知らせします)に振り込んでください。
作品は、A判サイズのワード文書でお送りください。
少なくとも月1篇は送信してください。
お申し込み・問い合わせは、
yachisyuso@gmail.com
また朝日カルチャーセンター福岡でも、講座を開いています。
毎月第1、第3月曜日13時-14時30分。
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1
電話 092-431-7751 / FAX 092-412-8571
*
オンデマンドで以下の本を発売中です。
(1)詩集『誤読』100ページ。1500円(送料別)
嵯峨信之の詩集『時刻表』を批評するという形式で詩を書いています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072512
(2)評論『中井久夫訳「カヴァフィス全詩集」を読む』396ページ。2500円(送料別)
読売文学賞(翻訳)受賞の中井の訳の魅力を、全編にわたって紹介。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073009
(3)評論『高橋睦郎「つい昨日のこと」を読む』314ページ。2500円(送料別)
2018年の話題の詩集の全編を批評しています。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168074804
(4)評論『ことばと沈黙、沈黙と音楽』190ページ。2000円(送料別)
『聴くと聞こえる』についての批評をまとめたものです。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168073455
(5)評論『天皇の悲鳴』72ページ。1000円(送料別)
2016年の「象徴としての務め」メッセージにこめられた天皇の真意と、安倍政権の攻防を描く。
https://www.seichoku.com/user_data/booksale.php?id=168072977
問い合わせ先 yachisyuso@gmail.com