嘉永6年(1853年)6月3日、フィルモア・ペリー率いるアメリカ艦隊が、江戸湾入口の浦賀の沖合にやって来ました。いわゆる黒船来航です。蒸気船2隻、大型帆船2隻を引き連れての突然の来航は、江戸幕府に大きな衝撃を与えました。
6月9日、ペリーは艦隊を艦砲射撃距離内まで接近させます。その時海上警備の船を出していたのは、会津藩と忍藩でした。会津藩船130隻、忍藩船50隻が、ペリー艦隊に併走していたのです。
日本近海には18世紀後半頃から、頻繁に外国船が現れるようになります。海防の必要を感じた幕府は、各藩に海防の番役を命じます。中でも会津藩は、樺太の警備に始まり、ペリーの時の江戸湾近辺の警備に至るまで、このお役を仰せつかることが多かったようです。そのような経緯で、会津藩は外国から迫る脅威を肌に感じておりました。決して田舎の世間知らずの藩だったわけではありません。

〈wikipediaより転載〉
アメリカ大統領フィルモアからの親書を、浦賀奉行所与力中島三郎助に渡したペリーは、翌年再び訪れることを告げ、引き上げました。
松平容保が会津藩9代目藩主となったのは、この前年嘉永5年(1852年)のことです。
ペリー艦隊が引き上げてよりわずか10日後、第12代将軍徳川家慶が病死します。13代目を継いだ家定は病弱で、この国難を乗り切るにはいささか器が足りない。時の老中・阿部正弘はそれまでの風習を破り、広く諸大名や朝廷にまで意見を求め、挙国一致で国難を乗り切ろうとします。これが契機となって、薩摩藩などの有力外様大名が、幕政に参画するようになっていきます。
翌年、約束通り再びペリーがやって来ました。幕府は条約を結ぶしかないと判断し、水戸藩主・徳川斉昭の強力な反対意見を押しのけ、日米和親条約を締結します。ここに事実上、鎖国は終了したのです。
ちなみにこの時、仙台藩の藩校養賢堂学頭・大槻磐渓は開国論を幕閣に進言しています。仙台藩も決して世界を知らなかったわけではないのです。
日米和親条約は、アメリカ船が立ち寄った際に水や食料、薪などを供給するとか、漂着した船員を保護するといった内容で、具体的な通商等の取り決め事はありませんでした。要するに仲良くしましょう、ということで、時の孝明天皇はこれが開国に繋がる条約だとは気が付かなかったらしいですね。仲良くするのは良いことだとして、条約締結に賛成したのだそうです。
安政3年(1856年)アメリカ総領事タウンゼント・ハリスが下田に着任、翌年には江戸に赴き、大統領の親書を幕府に提出、通商条約の調印を求めます。幕府の老中は堀田正睦、堀田はバリバリの開国派でしたから、この親書を持って京に上り、朝廷の勅許を得ようとします。前回の和親条約と同様に、すんなりと受け入れてくれるだろうと、高を括っていたかもしれません。ところが孝明天皇は大の外国人嫌い。神国たる日ノ本に、穢れたる異人を入れるわけにはいかないと、条約に大反対します。堀田はなすすべもなく江戸に戻ります。
このとき、大老に就任したのが、彦根藩主・井伊直弼でした。
大老は、非常時のみ置かれる臨時職で、権限が大きい。井伊は条約の締結は急務として、天皇の勅許を得ないまま、条約の承認に踏み切ります。これを不敬だとして怒ったのが、水戸の徳川斉昭や、斉昭の息のかかった公家達です。これに対し井伊は、大老の大権で水戸斉昭を蟄居謹慎させ、斉昭に便乗した水戸藩関係者や公家をはじめ、多くの反幕的な人々を処罰します。そのとばっちりを受ける形で、吉田松陰、橋本佐内なども捕縛され、処刑されてしまう。世に言う、安政の大獄です。
井伊にしてみれば、この緊急事態を乗り切り、日本を守り、幕府を守るにはこれしかないと思ったのでしょう。しかしやり方が強引すぎました。
万延元年(1860年)井伊大老は江戸城桜田門外にて、水戸藩を脱藩した浪士達によって暗殺されます。世に言う桜田門外の変です。
幕閣の最高権威者である大老が、一介の浪士達に斬殺されるという前代未聞の出来事は、徳川幕府の権威がいよいよ地に墜ちたことを示すものとなりました。
それにしても、徳川斉昭という人は何を考えていたのでしょう?本来ならば、幕府を補佐する御三家という立場から、幕府と朝廷の中を取り持つように努力すべきなのに、身内(徳川宗家)の足を引っ張るようなことをして、結果的に反幕勢力を台頭させるきっかけをつくってしまった。おそらくは水戸学の立場から、尊皇攘夷を徹底させようとしただけなのかもしれませんが、水戸学には天皇と幕府との関係性や、幕府と水戸藩との関係性等を明確に規定した学説がなかったようです。その点会津藩のような明確な理論付けがなされていなかったのです。結果、親藩しかも御三家でありながら、幕府潰しの片棒を担ぐようなことを起こしてしまった。なんとも皮肉なものではあります。
桜田門外の変で藩主を殺された彦根藩側は当然激怒します。水戸藩邸に軍勢を差し向けようかという勢いでした。これを仲栽したのが、会津藩9代藩主・松平容保でした。容保は両藩に使者を使わして仲裁に努め、ことを治めることに成功します。この功績によって容保は、幕閣内で一目置かれる存在となって行きます。これが後々、京都守護職就任要請へと繋がっていくわけです。
(続く)
参考文献
『会津武士道』
中村彰彦著
PHP文庫
『それぞれの戊辰戦争』
佐藤竜一著
現代書館
『会津と長州、幕末維新の光と闇』
一坂太郎・星亮一
講談社
6月9日、ペリーは艦隊を艦砲射撃距離内まで接近させます。その時海上警備の船を出していたのは、会津藩と忍藩でした。会津藩船130隻、忍藩船50隻が、ペリー艦隊に併走していたのです。
日本近海には18世紀後半頃から、頻繁に外国船が現れるようになります。海防の必要を感じた幕府は、各藩に海防の番役を命じます。中でも会津藩は、樺太の警備に始まり、ペリーの時の江戸湾近辺の警備に至るまで、このお役を仰せつかることが多かったようです。そのような経緯で、会津藩は外国から迫る脅威を肌に感じておりました。決して田舎の世間知らずの藩だったわけではありません。

〈wikipediaより転載〉
アメリカ大統領フィルモアからの親書を、浦賀奉行所与力中島三郎助に渡したペリーは、翌年再び訪れることを告げ、引き上げました。
松平容保が会津藩9代目藩主となったのは、この前年嘉永5年(1852年)のことです。
ペリー艦隊が引き上げてよりわずか10日後、第12代将軍徳川家慶が病死します。13代目を継いだ家定は病弱で、この国難を乗り切るにはいささか器が足りない。時の老中・阿部正弘はそれまでの風習を破り、広く諸大名や朝廷にまで意見を求め、挙国一致で国難を乗り切ろうとします。これが契機となって、薩摩藩などの有力外様大名が、幕政に参画するようになっていきます。
翌年、約束通り再びペリーがやって来ました。幕府は条約を結ぶしかないと判断し、水戸藩主・徳川斉昭の強力な反対意見を押しのけ、日米和親条約を締結します。ここに事実上、鎖国は終了したのです。
ちなみにこの時、仙台藩の藩校養賢堂学頭・大槻磐渓は開国論を幕閣に進言しています。仙台藩も決して世界を知らなかったわけではないのです。
日米和親条約は、アメリカ船が立ち寄った際に水や食料、薪などを供給するとか、漂着した船員を保護するといった内容で、具体的な通商等の取り決め事はありませんでした。要するに仲良くしましょう、ということで、時の孝明天皇はこれが開国に繋がる条約だとは気が付かなかったらしいですね。仲良くするのは良いことだとして、条約締結に賛成したのだそうです。
安政3年(1856年)アメリカ総領事タウンゼント・ハリスが下田に着任、翌年には江戸に赴き、大統領の親書を幕府に提出、通商条約の調印を求めます。幕府の老中は堀田正睦、堀田はバリバリの開国派でしたから、この親書を持って京に上り、朝廷の勅許を得ようとします。前回の和親条約と同様に、すんなりと受け入れてくれるだろうと、高を括っていたかもしれません。ところが孝明天皇は大の外国人嫌い。神国たる日ノ本に、穢れたる異人を入れるわけにはいかないと、条約に大反対します。堀田はなすすべもなく江戸に戻ります。
このとき、大老に就任したのが、彦根藩主・井伊直弼でした。
大老は、非常時のみ置かれる臨時職で、権限が大きい。井伊は条約の締結は急務として、天皇の勅許を得ないまま、条約の承認に踏み切ります。これを不敬だとして怒ったのが、水戸の徳川斉昭や、斉昭の息のかかった公家達です。これに対し井伊は、大老の大権で水戸斉昭を蟄居謹慎させ、斉昭に便乗した水戸藩関係者や公家をはじめ、多くの反幕的な人々を処罰します。そのとばっちりを受ける形で、吉田松陰、橋本佐内なども捕縛され、処刑されてしまう。世に言う、安政の大獄です。
井伊にしてみれば、この緊急事態を乗り切り、日本を守り、幕府を守るにはこれしかないと思ったのでしょう。しかしやり方が強引すぎました。
万延元年(1860年)井伊大老は江戸城桜田門外にて、水戸藩を脱藩した浪士達によって暗殺されます。世に言う桜田門外の変です。
幕閣の最高権威者である大老が、一介の浪士達に斬殺されるという前代未聞の出来事は、徳川幕府の権威がいよいよ地に墜ちたことを示すものとなりました。
それにしても、徳川斉昭という人は何を考えていたのでしょう?本来ならば、幕府を補佐する御三家という立場から、幕府と朝廷の中を取り持つように努力すべきなのに、身内(徳川宗家)の足を引っ張るようなことをして、結果的に反幕勢力を台頭させるきっかけをつくってしまった。おそらくは水戸学の立場から、尊皇攘夷を徹底させようとしただけなのかもしれませんが、水戸学には天皇と幕府との関係性や、幕府と水戸藩との関係性等を明確に規定した学説がなかったようです。その点会津藩のような明確な理論付けがなされていなかったのです。結果、親藩しかも御三家でありながら、幕府潰しの片棒を担ぐようなことを起こしてしまった。なんとも皮肉なものではあります。
桜田門外の変で藩主を殺された彦根藩側は当然激怒します。水戸藩邸に軍勢を差し向けようかという勢いでした。これを仲栽したのが、会津藩9代藩主・松平容保でした。容保は両藩に使者を使わして仲裁に努め、ことを治めることに成功します。この功績によって容保は、幕閣内で一目置かれる存在となって行きます。これが後々、京都守護職就任要請へと繋がっていくわけです。
(続く)
参考文献
『会津武士道』
中村彰彦著
PHP文庫
『それぞれの戊辰戦争』
佐藤竜一著
現代書館
『会津と長州、幕末維新の光と闇』
一坂太郎・星亮一
講談社












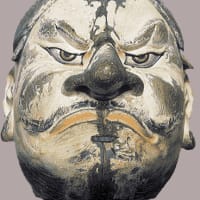







この時に将軍家定公の後継ぎに七男坊慶喜君を推して揉めているし、奥様が公家だった経緯から孝明天皇から幕府をすっ飛ばして水戸へ直接勅許が来たり…。
西郷はんがまだ吉之介を名乗ってた時に確か水戸に来て薩摩藩の意向を伝えていた逸話もあるから、人脈根回しといい将軍に成りかわって政治をしたかったのか?と想像します。
この当時の水戸学、完全な私見ですが私にとっては日本赤軍のように極端な勤皇に感じます。
新撰組から御陵衛士なるものを作った伊東甲子太郎も水戸学を学んだ茨城の人間です。(も~近藤さんの邪魔しやがって、プンプン!)
まぁ、それで黙して士道を貫いた容保公がとても懐が深い人物だと想像してしまうのですが。
長々と失礼しました~。右から左に聞き流して下さい~。
元々は徳川幕府の正当性を証明する手段として、朱子学を採用し、その朱子学を基に発展していったのが水戸学だったのですが、幕府を守るはずの理論が、いつの間にか討幕の理論づけに貢献してしまっている。水戸学はこうした自己矛盾を抱えた学問だったのですが、徳川斉昭はどこまでわかっていたのか…。
その点会津藩は、幕府への忠節と尊王とが矛盾なく結びついていました。特に容保公はそうした会津士道をどこまでも真っ直ぐに貫こうとしました。その清廉さは感動的ですらありますが、政治というものは、それだけでは上手くいかない。その清廉さ故に、会津藩は悲劇を被ってしまうことになるのです…。
毒論ですが(汗)朱子学は赤い魔物の学問だと思っています。儒教が律するものでありながら、朱子学は李王朝の流れを汲む、俺が一番正しいんだ、刃向かうものは粛正するぞ、みたいな空気に包まれていると思います。
水戸で生じた勤皇天狗党も「あなたがたは何をしているか分かっているのか?」と尋ねたら、
「私が一番正しいですが、何か?」と答えてきそうな自我の尊大さを正しさにすり替えていそうです。
光圀さんも朱子学がこんな末路に辿ると思わなかったでしょう。
ただ少しフォローをするならば、親父の野心のおかげか徳川慶喜も日本人が日本人同士で争うことに虚しさを感じていたかもしれないし(天狗党も彼は粛正してますよね?)吉田松陰のお弟子さんの桂小五郎などは「逃げの小五郎」と称されただけあって、命を捨てずに戦う現代人に近い背景を生み出しているのかも…など想いをはせてみたりしてました。
あ~また長文失礼します(>_<)
私の理想はサザエさんのフネさんなのにまた人の庭でおしゃべりし過ぎてしまいました。
いつも勝手に書いてゴメンナサイ~。