設楽原歴史資料館のフェイスブックを見ていて、今年もこの季節がやってきたことを知る。
火縄銃撃ちまくりの季節。
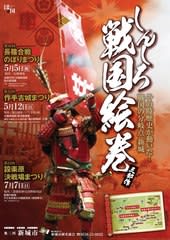
5月5日 長篠合戦のぼりまつり(鳳来:長篠城址)
5月12日 作手亀山古城まつり(作手:亀山城跡)
7月7日 設楽原決戦場まつり(新城:設楽原決戦場跡)
長篠合戦の発端から設楽原の決戦までの、それぞれの現場となった場所で祭が行われます。
折角長篠の戦関連について訪れるのであれば、上記の日を狙ってはいかがでしょうか?
ちなみに、長篠の戦いは5月21日(旧暦)。
5月にちなんだのが長篠合戦のぼりまつりと作手亀山古城まつり。
旧暦5月、新暦7月にちなんだのが設楽原決戦場まつり。
長篠の戦いで籠城していた現場が長篠城址。
長篠城の後詰として登場した織田・徳川軍と包囲していた武田軍が激突したのが設楽原決戦場。
鉄砲が三千丁なのか1千丁ばかりなのか?
武田の騎馬隊はいたのかいないのか?
様々な議論を呼んで、歴史好きのハートをわしづかみにしているのが長篠・設楽原の戦いです。
では、作手亀山城と長篠・設楽原の戦いの関係は?
歴史好きの方ならお解かり頂けると思いますが、一般の方だとイマイチご存知ないことが多い。
長篠城に籠城していたのは奥平貞昌(後の信昌)。
この奥平家の居城が作手亀山城なのです。
「なんだ、そんだけかい。」
と、思われた方々。
そんだけではありません。
奥平家は奥三河では当時最大勢力といってよく、この家の帰趨が奥三河地域の支配権と密接に絡んでいます。
長篠前夜は徳川家についていたものの、武田の侵略を受けやむなく武田方に。
しかし、信玄死去による武田家中の動揺とその隙を狙った織田・徳川方の猛烈な調略によって奥平家は武田から徳川に寝返ります。
その際、亀山城や古宮城といった作手城館群を舞台に、武田と奥平の間で緊迫したやりとりが行われます。見事に武田の監視の目を潜り抜けた奥平家は亀山城から大脱走し、武田軍を宮崎(岡崎市)で迎え撃ちます。徳川の援軍もやってきて武田軍を撃退。奥平家は徳川に臣従します。
武田勝頼にすれば「自分を軽く見て裏切った」奥平家が、これまた信玄時代にとったものの代替わりの際に奪い返された長篠城の城番として配置されたわけです。
「憎たらしいわぁ~。」
と、思って、つい入れ込んで拘ってしまい、織田信長の出陣を招いてしまった・・・、か、どうかはわかりませんが、長篠城に籠もった奥平貞昌にすれば、降伏しても殺されることが目に見えているだけに降伏できない。通常、籠城戦は1ヶ月程度持ちこたえれば名誉と考えて降伏することが多かったそうですが、この場合は特殊事情により降伏できない。
そのため、武田勝頼を結果的に足止めする形になり、設楽原決戦を招く結果となった訳です。
作手亀山は長篠前夜、と、言えるわけです。
こうした経緯を踏まえ、旧新城市・鳳来町・作手村が合併して新・新城市が誕生し、折角一緒になったのだから、と、連携してアピールすることを観光協会が始められたのが「しんしろ戦国絵巻」なのです。
実に意義深い。。。(感涙)
そういえば、長篠付近に住んでいて驚愕したのが、この地域の火薬消費量。
火縄銃の演武はしょっちゅうあるわ、手筒花火はガンガン打ち上げるわ、これだけ火薬を消費している地域って珍しいのではないかと思う。

名古屋では火縄銃撃つ、というと、人がわんさか集まってくるのですが、長篠近辺では当たり前すぎて普通。
始めは、このギャップに驚きました。
この火薬消費量と長篠合戦自体も結びつくといえば結びつきます。
長篠合戦で織田徳川連合軍が勝つ⇒織田信長本能寺で滅ぶ⇒諸々あって徳川幕府になる⇒徳川幕府のお膝元である三河地域は武器である火縄銃から派生する花火など火薬の消費について他の地域より規制が緩やか⇒手筒花火などの伝統文化が花開く。
と、いう図式です。
そんな様々な事情を踏まえた上で、実際に合戦の現場で火縄銃演武や合戦武者行列などをご覧いただけば、相当に迫力を感じていただけるのではないかと思います。
ぜひ。
火縄銃撃ちまくりの季節。
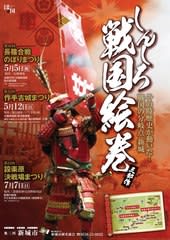
5月5日 長篠合戦のぼりまつり(鳳来:長篠城址)
5月12日 作手亀山古城まつり(作手:亀山城跡)
7月7日 設楽原決戦場まつり(新城:設楽原決戦場跡)
長篠合戦の発端から設楽原の決戦までの、それぞれの現場となった場所で祭が行われます。
折角長篠の戦関連について訪れるのであれば、上記の日を狙ってはいかがでしょうか?
ちなみに、長篠の戦いは5月21日(旧暦)。
5月にちなんだのが長篠合戦のぼりまつりと作手亀山古城まつり。
旧暦5月、新暦7月にちなんだのが設楽原決戦場まつり。
長篠の戦いで籠城していた現場が長篠城址。
長篠城の後詰として登場した織田・徳川軍と包囲していた武田軍が激突したのが設楽原決戦場。
鉄砲が三千丁なのか1千丁ばかりなのか?
武田の騎馬隊はいたのかいないのか?
様々な議論を呼んで、歴史好きのハートをわしづかみにしているのが長篠・設楽原の戦いです。
では、作手亀山城と長篠・設楽原の戦いの関係は?
歴史好きの方ならお解かり頂けると思いますが、一般の方だとイマイチご存知ないことが多い。
長篠城に籠城していたのは奥平貞昌(後の信昌)。
この奥平家の居城が作手亀山城なのです。
「なんだ、そんだけかい。」
と、思われた方々。
そんだけではありません。
奥平家は奥三河では当時最大勢力といってよく、この家の帰趨が奥三河地域の支配権と密接に絡んでいます。
長篠前夜は徳川家についていたものの、武田の侵略を受けやむなく武田方に。
しかし、信玄死去による武田家中の動揺とその隙を狙った織田・徳川方の猛烈な調略によって奥平家は武田から徳川に寝返ります。
その際、亀山城や古宮城といった作手城館群を舞台に、武田と奥平の間で緊迫したやりとりが行われます。見事に武田の監視の目を潜り抜けた奥平家は亀山城から大脱走し、武田軍を宮崎(岡崎市)で迎え撃ちます。徳川の援軍もやってきて武田軍を撃退。奥平家は徳川に臣従します。
武田勝頼にすれば「自分を軽く見て裏切った」奥平家が、これまた信玄時代にとったものの代替わりの際に奪い返された長篠城の城番として配置されたわけです。
「憎たらしいわぁ~。」
と、思って、つい入れ込んで拘ってしまい、織田信長の出陣を招いてしまった・・・、か、どうかはわかりませんが、長篠城に籠もった奥平貞昌にすれば、降伏しても殺されることが目に見えているだけに降伏できない。通常、籠城戦は1ヶ月程度持ちこたえれば名誉と考えて降伏することが多かったそうですが、この場合は特殊事情により降伏できない。
そのため、武田勝頼を結果的に足止めする形になり、設楽原決戦を招く結果となった訳です。
作手亀山は長篠前夜、と、言えるわけです。
こうした経緯を踏まえ、旧新城市・鳳来町・作手村が合併して新・新城市が誕生し、折角一緒になったのだから、と、連携してアピールすることを観光協会が始められたのが「しんしろ戦国絵巻」なのです。
実に意義深い。。。(感涙)
そういえば、長篠付近に住んでいて驚愕したのが、この地域の火薬消費量。
火縄銃の演武はしょっちゅうあるわ、手筒花火はガンガン打ち上げるわ、これだけ火薬を消費している地域って珍しいのではないかと思う。

名古屋では火縄銃撃つ、というと、人がわんさか集まってくるのですが、長篠近辺では当たり前すぎて普通。
始めは、このギャップに驚きました。
この火薬消費量と長篠合戦自体も結びつくといえば結びつきます。
長篠合戦で織田徳川連合軍が勝つ⇒織田信長本能寺で滅ぶ⇒諸々あって徳川幕府になる⇒徳川幕府のお膝元である三河地域は武器である火縄銃から派生する花火など火薬の消費について他の地域より規制が緩やか⇒手筒花火などの伝統文化が花開く。
と、いう図式です。
そんな様々な事情を踏まえた上で、実際に合戦の現場で火縄銃演武や合戦武者行列などをご覧いただけば、相当に迫力を感じていただけるのではないかと思います。
ぜひ。









