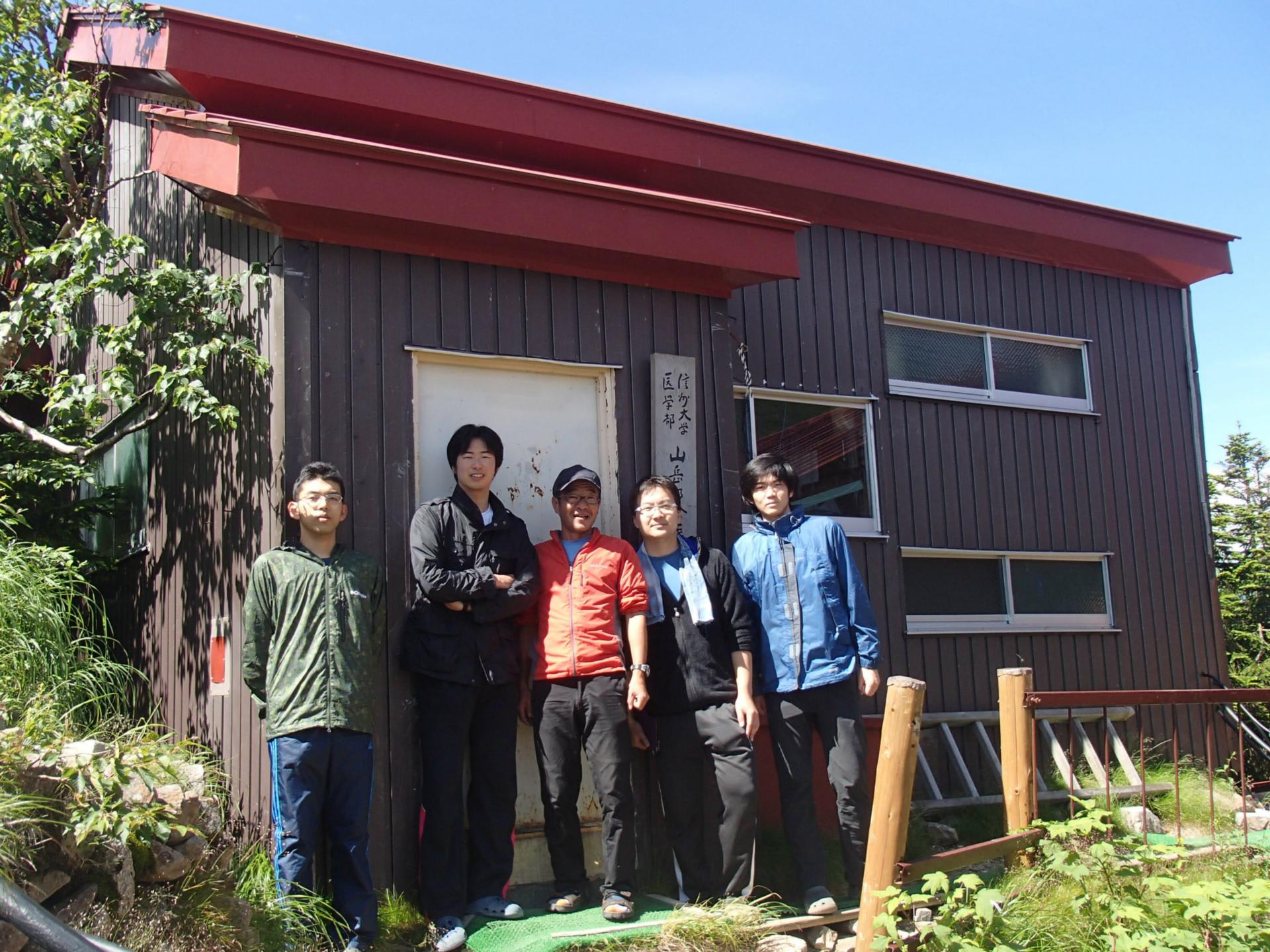2014年9月4日(木)
天候:曇り
週末は仕事で休みが取れない。よって平日に土日は賑わうところへ行くことにした。
誰も休み合わないだろうな~と思ったら、昨年沢デビューを果たしたS君が同行してくれることとなる。
3時にうちで待ち合わせ、一路西沢渓谷へ。
ガスっているが、雨は落ちていない。しかも駐車場は、3台あるだけ。
ここは首都圏から近いため、土日は本当に混む。。。
まずは、西沢渓谷との分岐へ向け、散策路を行く。30分くらいで、西沢と東沢の二俣だ。

吊り橋
これを渡ると、一休み出来るベンチがある。

西沢渓谷入口
西沢渓谷は歩いたことないが、道も良くいいみたいだ。
ここからベンチの横を右へ。河原へ下りてすぐに鶏冠谷の出合。
数年前にここの左俣へ行った。帰りの鶏冠尾根もなかなか面白いものであったが、ロープ必要です。
不用意には入らない方がいいであろう。

鶏冠谷出合
ここで沢装備へ変換。ゴーロの河原を渡渉して行く。
右側には昔の登山道の名残の道がある。適当なところでこの道に上がる。
道が一旦下って河原へ行くと、ホラノ貝の滝。

ゴルジュの入口
滝はよく見えないが、ここのようだ。

立派な看板

旧登山道から見たところ
なかなかのゴルジュである。泳ぎなどの練成するにはいいかも。
ここを過ぎていくと、山の神到着。50分くらいか。

山の神
ここで一本入れて、河原へ下りる。ここからは旧登山道でなく河原を行く。

右から一本合わせてその次に左手に現れたのは、乙女の滝

乙女の滝

これまた立派な看板
ここはアイスのゲレンデにもなっている。
その次にお出ましは、黒部上廊下を思わせる岩壁。ちょっと小さいが。。。

その先にどーんとナメの滝が落ちてくる。

東のナメ沢

東のナメ沢出合
ミニ西ゼンと言ったところだ。
その次に左に小さいナメ滝があってその先の沢が右折するところで西のナメ沢のお出ましである。

西のナメ沢
こちらの方が幅広い。太いワイヤーが垂れていたのは、昔の登山道の名残の橋の残骸か。
ここで休んで、しばし河原を行くとよーやく釜ノ沢出合である。ここまで3時間ちょっとかかった。
骨の折れることである。ここまでもいくつもの焚き火の跡などあり、泊まりの優良物件は多数である。

釜ノ沢出合

ご親切な看板
これのお陰で迷うことはない。この看板の横に出ていた湧き水はうまかった。
さてここからが本日のメインイベント。
出合からすぐに、魚止めの滝である。

魚止めの滝(10m)
ここは、花崗岩スラブ(ナメ)特有のクラックなどを使って、左の壁から登るが、一手、私でギリのホールド。
女子などがいればお助けが必要か。

魚止めの滝上から
この滝上が右折している。その先が噂の千畳のナメか。

千畳のナメ
200m位だが、幅は広く広葉樹がいい感じだ。
ヒタヒタと行く。すぐ終わってしまうが。これからするとやはり私がいつも行く沢上谷のナメの方が
まだ少し長くてヒタヒタを楽しめる。
今まで行ったナメのヒタヒタは、やはりクワウンナイ川には適わない。ここは長めのコケがカーペットみたいで
ヒタヒタと言うよりフカフカのナメ歩きという感じであった。
さて、その先もナメ滝を二つ。

ナメ滝(8m)
ここは水流の左を簡単に行ける。その先もナメの小滝が何段かある。ものの本によっては、3段何mなどとなっている。
その次は、遡行図などでは曲り滝となっているが、現地看板は、野猿の滝とあった。

野猿の滝

看板
これは右から巻く。ピンクのテープなど至る所にあり迷うことはない。
巻き道も、昔道のためか人も多く入るので、しっかりしたものである。
そして、イベント最後の大物のお出ましである。

両門の滝
今回はこれが見たかった。ここで東俣と西俣に分かれる。
水量もそこそこあり、いい感じ~
ここで休んで、先を急ぐ。巻きはしっかりしている。

ヤゲンの滝(15m)
両門の滝上でこの滝に出合う。右から巻き。
その上に5mくらいの滝がある。これは左登ったっけ?

5m滝
その上は、しばらく河原が続く広河原。ビバーク敵地である。優良物件多数。

すぐのところは、薪もないくらい綺麗になっていた。よっぽど多くの人が泊まるのであろう。
通常は、ここで1泊というところだ。
広河原は、ゴーロ行くと時間かかるので右の優良物件多数の森の中を行く。
旧登山道であろうと思う。

しかしこれが長かった。。。途中ガスってきたり晴れたりと天気は忙しそうであったが、
我々は、黙々と距離を稼ぐ。普通の登山道みたいでサクサク行けるが、単調すぎる。

ミヤマトリカブト
一回休みとってから行くと飽き飽きした頃、倒木で荒れた河原に出る。
その先ようやく滝の登場だ。やっと沢登りらしくなった。

2段20m
これはあっさり登れる。

2段目
2段目登ると陽が差してきた。

その先の荒れた二俣がミズシ沢との分岐。これを右へ行く。

ミズシ沢出合
ここ、ミズシ沢の方が本流っぽいので間違えやすいかもしれない。
小滝をいくつか越えて高度を稼ぐと、ナメ滝が出合っている。ここが木賊沢出合だ。
木賊沢の右を上がって行き、途中渡って小尾根を越して左のナメに行く。

木賊沢を上がる

上の緑の所を渡り左の沢へ
左のナメを上がって行く。

またちょっとガスってきた。その上に崩落が左から来ている。ここまで来ると上に甲武信小屋のポンプ小屋が見える。
崩落地から一登りで、ポンプ小屋。

ワラジの塚?があった。

ここの水は冷たくてうまい。ここで沢装備を解いて、アプローチシューズで小屋へ一登り。

甲武信小屋

小屋前ベンチ
いい雰囲気の小屋である。いつか泊まってみたい。このベンチは初めて見た。最近出来たものか。
ここに荷物をデポって、山頂へ。ここで14時。8時間で登ったことになる。
山頂に着く頃、雲が割れてきた。

山頂

富士山
晴れていればもっと綺麗に見えるが。。。
記念撮影してから小屋へ戻る。

1430に小屋発。この先の木賊山への登りは痺れた~効き目満点。
やっとこさ木賊山へという感じである。

木賊山山頂
この山の少し先から戸渡尾根を下る。この下りも長いよ~。。。
途中、近丸新道を行き、暗くなる前に駐車場着。
11時間45分行動であった。痺れた!
奥秩父の名渓と旧登山道(古道)を行けたのは良かったが、名渓は両門の滝までだなと。
人が言うほどのことはなかった様に思うが、一度入ってみなければの沢であった。
超~久々の沢旅であったが、最近の歩きばかりの鈍った体にはいい刺激となった。
今月は極力、沢へ行きたいと思う今日この頃である。
天候:曇り
週末は仕事で休みが取れない。よって平日に土日は賑わうところへ行くことにした。
誰も休み合わないだろうな~と思ったら、昨年沢デビューを果たしたS君が同行してくれることとなる。
3時にうちで待ち合わせ、一路西沢渓谷へ。
ガスっているが、雨は落ちていない。しかも駐車場は、3台あるだけ。
ここは首都圏から近いため、土日は本当に混む。。。
まずは、西沢渓谷との分岐へ向け、散策路を行く。30分くらいで、西沢と東沢の二俣だ。

吊り橋
これを渡ると、一休み出来るベンチがある。

西沢渓谷入口
西沢渓谷は歩いたことないが、道も良くいいみたいだ。
ここからベンチの横を右へ。河原へ下りてすぐに鶏冠谷の出合。
数年前にここの左俣へ行った。帰りの鶏冠尾根もなかなか面白いものであったが、ロープ必要です。
不用意には入らない方がいいであろう。

鶏冠谷出合
ここで沢装備へ変換。ゴーロの河原を渡渉して行く。
右側には昔の登山道の名残の道がある。適当なところでこの道に上がる。
道が一旦下って河原へ行くと、ホラノ貝の滝。

ゴルジュの入口
滝はよく見えないが、ここのようだ。

立派な看板

旧登山道から見たところ
なかなかのゴルジュである。泳ぎなどの練成するにはいいかも。
ここを過ぎていくと、山の神到着。50分くらいか。

山の神
ここで一本入れて、河原へ下りる。ここからは旧登山道でなく河原を行く。

右から一本合わせてその次に左手に現れたのは、乙女の滝

乙女の滝

これまた立派な看板
ここはアイスのゲレンデにもなっている。
その次にお出ましは、黒部上廊下を思わせる岩壁。ちょっと小さいが。。。

その先にどーんとナメの滝が落ちてくる。

東のナメ沢

東のナメ沢出合
ミニ西ゼンと言ったところだ。
その次に左に小さいナメ滝があってその先の沢が右折するところで西のナメ沢のお出ましである。

西のナメ沢
こちらの方が幅広い。太いワイヤーが垂れていたのは、昔の登山道の名残の橋の残骸か。
ここで休んで、しばし河原を行くとよーやく釜ノ沢出合である。ここまで3時間ちょっとかかった。
骨の折れることである。ここまでもいくつもの焚き火の跡などあり、泊まりの優良物件は多数である。

釜ノ沢出合

ご親切な看板
これのお陰で迷うことはない。この看板の横に出ていた湧き水はうまかった。
さてここからが本日のメインイベント。
出合からすぐに、魚止めの滝である。

魚止めの滝(10m)
ここは、花崗岩スラブ(ナメ)特有のクラックなどを使って、左の壁から登るが、一手、私でギリのホールド。
女子などがいればお助けが必要か。

魚止めの滝上から
この滝上が右折している。その先が噂の千畳のナメか。

千畳のナメ
200m位だが、幅は広く広葉樹がいい感じだ。
ヒタヒタと行く。すぐ終わってしまうが。これからするとやはり私がいつも行く沢上谷のナメの方が
まだ少し長くてヒタヒタを楽しめる。
今まで行ったナメのヒタヒタは、やはりクワウンナイ川には適わない。ここは長めのコケがカーペットみたいで
ヒタヒタと言うよりフカフカのナメ歩きという感じであった。
さて、その先もナメ滝を二つ。

ナメ滝(8m)
ここは水流の左を簡単に行ける。その先もナメの小滝が何段かある。ものの本によっては、3段何mなどとなっている。
その次は、遡行図などでは曲り滝となっているが、現地看板は、野猿の滝とあった。

野猿の滝

看板
これは右から巻く。ピンクのテープなど至る所にあり迷うことはない。
巻き道も、昔道のためか人も多く入るので、しっかりしたものである。
そして、イベント最後の大物のお出ましである。

両門の滝
今回はこれが見たかった。ここで東俣と西俣に分かれる。
水量もそこそこあり、いい感じ~
ここで休んで、先を急ぐ。巻きはしっかりしている。

ヤゲンの滝(15m)
両門の滝上でこの滝に出合う。右から巻き。
その上に5mくらいの滝がある。これは左登ったっけ?

5m滝
その上は、しばらく河原が続く広河原。ビバーク敵地である。優良物件多数。

すぐのところは、薪もないくらい綺麗になっていた。よっぽど多くの人が泊まるのであろう。
通常は、ここで1泊というところだ。
広河原は、ゴーロ行くと時間かかるので右の優良物件多数の森の中を行く。
旧登山道であろうと思う。

しかしこれが長かった。。。途中ガスってきたり晴れたりと天気は忙しそうであったが、
我々は、黙々と距離を稼ぐ。普通の登山道みたいでサクサク行けるが、単調すぎる。

ミヤマトリカブト
一回休みとってから行くと飽き飽きした頃、倒木で荒れた河原に出る。
その先ようやく滝の登場だ。やっと沢登りらしくなった。

2段20m
これはあっさり登れる。

2段目
2段目登ると陽が差してきた。

その先の荒れた二俣がミズシ沢との分岐。これを右へ行く。

ミズシ沢出合
ここ、ミズシ沢の方が本流っぽいので間違えやすいかもしれない。
小滝をいくつか越えて高度を稼ぐと、ナメ滝が出合っている。ここが木賊沢出合だ。
木賊沢の右を上がって行き、途中渡って小尾根を越して左のナメに行く。

木賊沢を上がる

上の緑の所を渡り左の沢へ
左のナメを上がって行く。

またちょっとガスってきた。その上に崩落が左から来ている。ここまで来ると上に甲武信小屋のポンプ小屋が見える。
崩落地から一登りで、ポンプ小屋。

ワラジの塚?があった。

ここの水は冷たくてうまい。ここで沢装備を解いて、アプローチシューズで小屋へ一登り。

甲武信小屋

小屋前ベンチ
いい雰囲気の小屋である。いつか泊まってみたい。このベンチは初めて見た。最近出来たものか。
ここに荷物をデポって、山頂へ。ここで14時。8時間で登ったことになる。
山頂に着く頃、雲が割れてきた。

山頂

富士山
晴れていればもっと綺麗に見えるが。。。
記念撮影してから小屋へ戻る。

1430に小屋発。この先の木賊山への登りは痺れた~効き目満点。
やっとこさ木賊山へという感じである。

木賊山山頂
この山の少し先から戸渡尾根を下る。この下りも長いよ~。。。
途中、近丸新道を行き、暗くなる前に駐車場着。
11時間45分行動であった。痺れた!
奥秩父の名渓と旧登山道(古道)を行けたのは良かったが、名渓は両門の滝までだなと。
人が言うほどのことはなかった様に思うが、一度入ってみなければの沢であった。
超~久々の沢旅であったが、最近の歩きばかりの鈍った体にはいい刺激となった。
今月は極力、沢へ行きたいと思う今日この頃である。