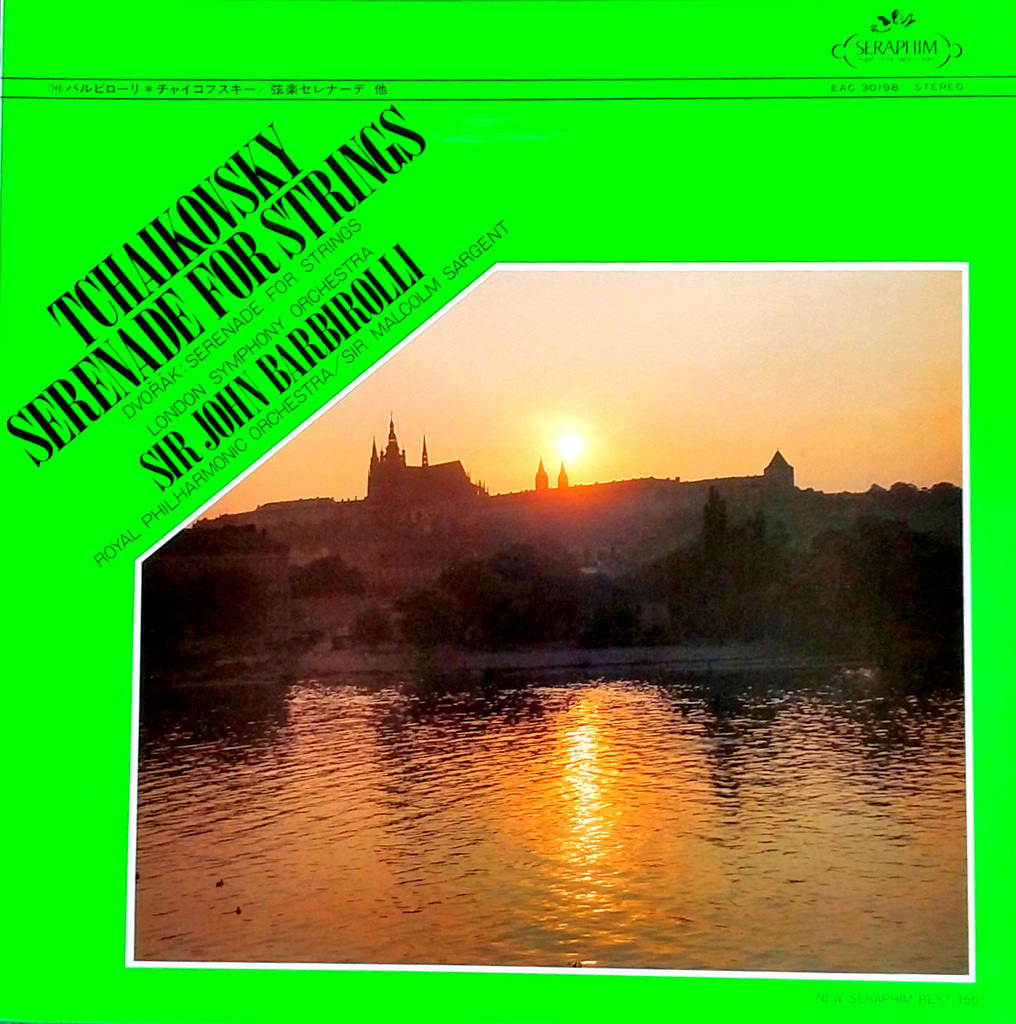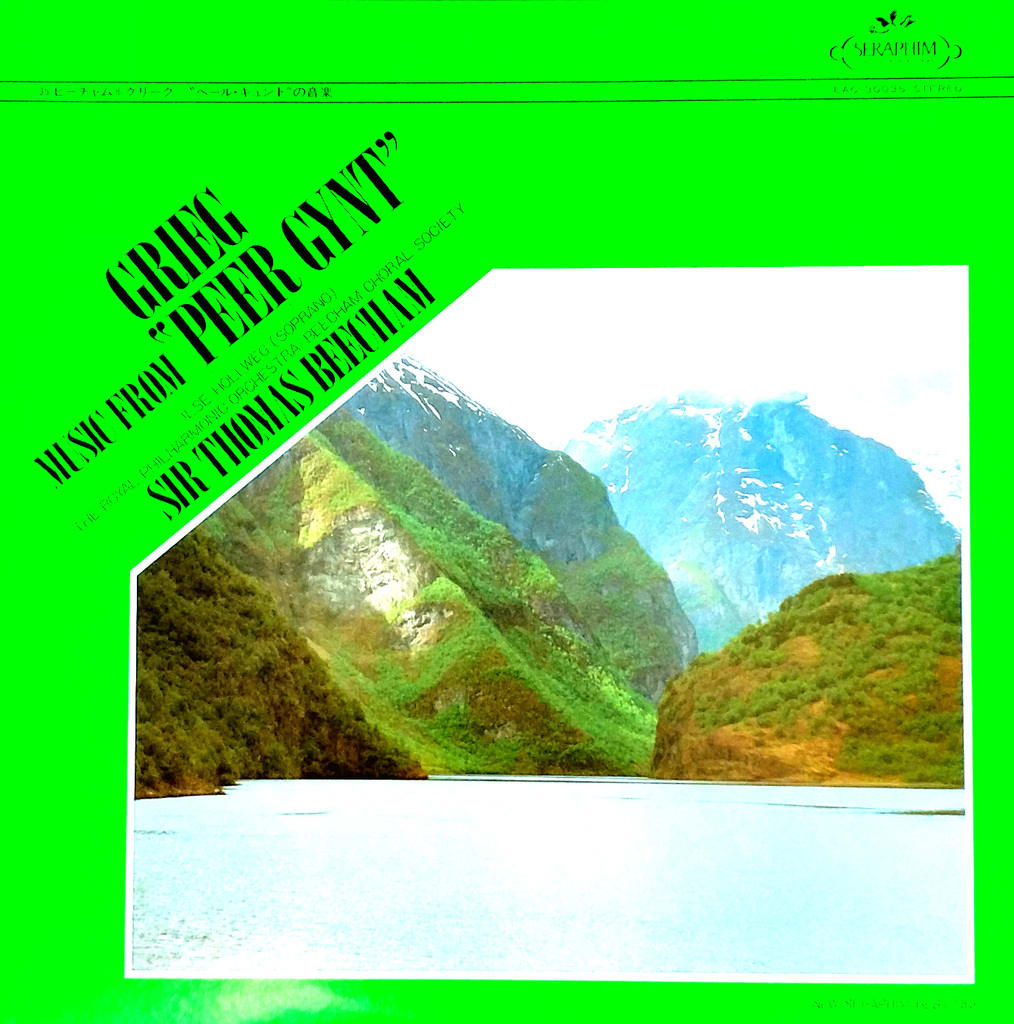
グリーク:劇音楽「ペール・ギュント」
結婚行進曲
イングリッドの嘆き
山の魔王の殿堂にて
朝
オーゼの死
アラビアの踊り<第1番>
ソルベイグの歌
アニトラの踊り
ペール・ギュントの帰郷<嵐の情景>
子守歌
指揮:トーマス・ビーチャム
管弦楽:ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
ソプラノ:イルゼ・ホルヴェイグ
合唱:ビーチャム合唱協会
LP:東芝EMI(SERAPHIM) EAC‐30035
1874年、グリークはかねてから尊敬していたノルウェイの文豪イプセンから、自作の劇「ペール・ギュント」上演のための附随音楽の作曲を依頼された。当初、気の進まなかったグリークであったが、故郷であるベルゲンに帰り、作曲に没頭することになる。翌1875年の夏に、前奏曲、舞曲、独唱曲、合唱曲など全部で23曲からなるこの曲は完成した。1876年には初演され、そして劇も附随音楽も共に成功をおさめることができたのである。これに気を良くしたグリークは、この劇音楽の中から4曲を選び、管弦楽第1組曲(朝、オーゼの死、アニトラの踊り、山の魔王の殿堂にて)をつくり、さらに管弦楽第2組曲(イングリッドの嘆き、アラビアの踊り、ペール・ギュントの帰郷)もつくった。このLPレコードでは、普通演奏される第1組曲、第2組曲ではなく、劇附随音楽として独唱や合唱を交えた原曲の形で10曲が選ばれ、演奏されている。しかし、演奏される順序は劇と同一ではなく、指揮のトーマス・ビーチャムの考えによる、緩急ところを得た配列になっている。トーマス・ビーチャム(1879年―1961年)は、イギリスの名指揮者で、シベリウスやグリークを振らせたら右に出る者はいないとまで言われた人。このLPレコードでもその本領を遺憾なく発揮している。きりりと締まったその演奏は、思わず目の前で劇が上演されているような錯覚すら覚えるほど迫力満点。ダイナミックさに加え、揺れ動く陰影を持ったロマンの香りを漂わせる指揮ぶりは、さすが伝説の指揮者と納得させられる。ソプラノのイルゼ・ホルヴェイグの歌声もグリークの曲に誠に相応しく、この録音を一層盛り上げている。録音の状態がすこぶる良く、LPレコードの美しい音色に暫し聴き惚れるほど。トーマス・ビーチャムは、イギリス出身の指揮者。学校での音楽の専門的教育は受けなかったが、アマチュア・オーケストラの指揮者などを経て、1899年にハンス・リヒターの代役でハレ管弦楽団を指揮し、プロの指揮者としてデビューを飾った。1915年イギリス・オペラ・カンパニーを創設し、しばらくはオペラ指揮者として活動したが、1932年ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を創設。また同年にロイヤル・オペラ・ハウスの音楽監督に就任し、オペラを上演。1946年新たにロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団を創設、生涯にわたり英国音楽界に多大なる貢献をした。(LPC)