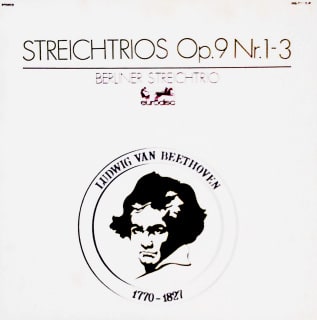
ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番 ト長調Op.9‐1
第3番 ニ長調Op.9‐2
第4番 ハ短調Op.9‐3
弦楽三重奏:ベルリン弦楽四重奏団員
カール・ズスケ(ヴァイオリン)
カール=ハインツドムス(ヴィオラ)
マティアス・プフェンダー(チェロ)
LP:日本コロムビア(eurodisc) OQ‐7112‐K
発売:1976年4月
ベートーヴェンは、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロによる作品として、弦楽三重奏曲4曲とセレナーデ1曲の合計5曲を遺している。これらはいずれもベートーヴェンの20歳代の初期の作品に当る。これらの中で、1798年に完成したOp.9の3曲は、初期の作品とはいえ、モーツァルトの世界から抜け出し、いよいよベートーヴェンらしい顔を覗かし始めた頃の作品である。この3曲の弦楽三重奏曲は、中期から後期にかけてベートーヴェンが作曲した傑作の森の陰に隠れ、あまり話題に上ることもなく、また、演奏の機会も決して多くはない。しかし、改めてこの3曲を聴いてみると、後年花開くベートーヴェンの才能の最初の萌芽が聴き取れ、実に興味深い作品であることに気づく。ベートーヴェンは、以後弦楽三重奏曲は書かず、もっぱら弦楽四重奏曲に傾倒する。これは、ベートーヴェンが、より深い音色を弦楽器の求めた結果であることが推測される。弦楽三重奏曲第2番ト長調Op.9‐1は、隅々まで眼の行き届いたがっちりとした構成力が印象に残る初期の力作。同第3番ニ長調Op.9‐2は、詩的な雰囲気を漂わせ、哀愁味も持ったロマン的な作品。そして、同第4番ハ短調Op.9‐3は、初期の器楽作品の中でも傑作と目される曲で、緊張感が全体を包み込み、曲の盛り上げ方も非凡なものが感じ取れる。これら3曲を、このLPレコードで演奏しているのは、ベルリン弦楽四重奏団員のヴァイオリン:カール・ズスケ、ヴィオラ:カール=ハインツドムス、チェロ:マティアス・プフェンダーの3人である。ベルリン弦楽四重奏団とは、1965年に、ゲヴァントハウス管弦楽団のコンサートマスターを経て、ベルリン国立管弦楽団の第1コンサートマスターを務めていたカール・ズスケ(1934年生まれ)を中心に結成された旧東ドイツ屈指のカルテットのこと。当初は、ズスケ弦楽四重奏団と称していたが1970年に改称し、以後ベルリン弦楽四重奏団として活躍することになる。1973年には来日も果たしている。カール・ズスケは、モーツァルトのヴァイオリンソナタなどの名録音も遺しているが、音色に透明感があり、常にきっちとした構成美で演奏し、日本でも多くのファンを持っていた。このLPレコーでの演奏は、卓越した演奏技術に貫かれた安定感のある演奏内容となっており、それに加えて、音色が美しく、爽やかな印象を醸し出し、実に魅力的な演奏だ。それにしても今後、ベートーヴェン初期の、これら3曲の魅力的な弦楽三重奏曲の演奏機会が増えることを願うばかりだ。(LPC)













