森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
花・髪切と思考の
浮游空間
カレンダー
| 2025年9月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
|
||||||||
goo ブログ
最新の投稿
| 8月6日(土)のつぶやき |
| 8月5日(金)のつぶやき |
| 6月4日(土)のつぶやき |
| 4月10日(日)のつぶやき |
| 2月10日(水)のつぶやき |
| 11月12日(木)のつぶやき |
| 10月26日(月)のつぶやき |
| 10月25日(日)のつぶやき |
| 10月18日(日)のつぶやき |
| 10月17日(土)のつぶやき |
カテゴリ
| tweet(762) |
| 太田光(7) |
| 加藤周一のこと(15) |
| 社会とメディア(210) |
| ◆橋下なるもの(77) |
| ◆消費税/税の使い途(71) |
| 二大政党と政党再編(31) |
| 日米関係と平和(169) |
| ◆世相を拾う(70) |
| 片言集または花(67) |
| 本棚(53) |
| 鳩山・菅時代(110) |
| 麻生・福田・安倍時代(725) |
| 福岡五輪幻想(45) |
| 医療(36) |
| スポーツ(10) |
| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |
最新のコメント
| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |
| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |
| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |
| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |
| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |
| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |
最新のトラックバック
ブックマーク
| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |
| ■ machineryの日々 |
| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |
| ■ すくらむ |
| ■ 代替案 |
| ■ 非国民通信 |
| ■ coleoの日記;浮游空間 |
| ■ bookmarks@coleo |
| ■ 浮游空間日記 |
過去の記事
検索
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |
ウィキペディア頼み
ある記事に驚いた。
アメリカのある名門大学で、百科事典「ウィキペディア」を学生がテストやリポートで引用することを認めない措置を1月に決めたという記事だ。
日本史を教えるニール・ウオーターズ教授(61)は昨年12月の学期末テストで、二十数人のクラスで数人が島原の乱について「イエズス会が反乱勢力を支援した」と記述したことに気づいた。「イエズス会が九州でおおっぴらに活動できる状態になかった」と不思議に思って間違いのもとをたどったところ、ウィキペディアの「島原の乱」の項目に行き着いた。 (朝日新聞2・23電子版)
こんな経過があって、同大史学部では1月、「学生は自らの提供する情報の正確さに責任をもつべきで、ウィキペディアや同様の情報源を誤りの言い逃れにできない」として引用禁止を通知したという。
もともと百科全書は、知識の結集を図るのだから、多様な潮流をふくむ。まさに共同作業なのだから、そこに記述の統一性、正確さは保証されないだろう。ここを、学生達は認識すべきだった。
むしろ私が驚いたのは、大学の措置である。引用禁止はお世辞にも妥当とは思えない。引用は自説を説明し担保するためにある。そうすると、記事にあるように「自らの提供する情報の正確さに責任」がともなうのだから、その限りで参照文献が何であるかを問わないだろう。
ウィキペディアと他の百科事典の区別をつけようとは私は思わない。そして、ウィキペディアからの引用が学術研究にとって適切なのかどうか、その判断は引用者に委ねられている。そこで洋の東西を分けずリテラシーが問われている。
話はかわり思い出すのは、百科全書といえば、ディドロに連なる「百科全書派」だ。この「百科全書派」の方法論に学び続いたのだろうか、よく知られるように林達夫や加藤周一らが日本での百科事典編集にあたった。以下、引用。
フランス啓蒙思想の頂点に位置する『L'Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, par une societe de gens de lettres(百科全書、あるいは科学・芸術・技術の理論的辞典)』は、1751年から1772年にかけて、また1776年から1780年にかけて編集された大規模な百科事典であり、編集に携わったドゥニ・ディドロやジャン・ル・ロン・ダランベールをはじめとして、ヴォルテールやジャン=ジャック・ルソーなど、18世紀中頃の進歩的知識人を総動員して刊行された。
引用は、Wikipediaによった。かくいう私も毎度、ウィキペディアにお世話になっているのだが。
■blogランキング・応援のクリックが励みになります。⇒
「格差はどんな時代にもある」
不祥事がつづく安倍内閣への世間の風あたりが強い。当の首相と自民党中枢は黙って見過ごすことが、さすがにできないのだろう。ついに中川秀直幹事長がおよそ前時代的ともいえる態度でゆるんだタガを締めなおした。みようによっては恫喝だ。そして、見兼ねた前首相・小泉純一郎が激をとばしたという。曰く、
何をやっても批判される。いちいち気にするな。
前首相はつぎのようにもいっている。
『格差はどんな時代にもある』と、なぜはっきりと言わないんだ。自分は予算委員会で言い続けてきた。君たちは日本が近隣諸国より格差があると思うか ==朝日新聞2・21web版==
私が気になったのはこちらの発言だ。
「格差はどんな時代にもある」。これは格差がいつ、どこでもある、ということと同義だろう。たしかに、一般的な格差ならどこにでもあるだろう。問題になっているのは、くりかえすけれど、絶対的格差だ。たとえば、いま、ここにあるワーキングプア層の存在である。
「ワーキングプアとは何をもってプアというのでしょう」という、まるで地球の外から来たかのようなコメントを残してくれた人もいたが、2度放映したNHKばかりではなく、多くのメディア、数々の書籍でもとりあげられているのだから、それを見聞きし、読む、どんな立場の人であろうと、自らの周りにワーキングプアとよばれる人びとがいるのだ。ワーキングプアという概念も熟したのだ。
話を元にもどせば、小泉前首相の発言は、いま、ここにある絶対的格差を認めようとしない立場の表白だといえる。そんなものはどこにでもころがっている事象なのだし、関心を寄せる対象でもないのだから。ここはしかし、彼自身にふりかえってもらう必要がある。「格差があって何が悪い」という発言を自ら否定せざるをえなかったことを。
傍観者なら、性懲りもなく前首相が上のように強弁するのも、そして何をもってプアというのかという認識もまた、まさに喜劇とよぶだろうが、これほどの想像力の貧困が現にあることは日本にとって悲劇だといわざるをえない。これが新自由主義の核心か。

100万人リストラというアクセル
格差と貧困の現れにメディアも注目し報道するようになって、国民の関心も高まりました。昨日ふれたように、貧困と格差の拡大のなかで日本社会が大きく変容していることにともなって、いつなんどき自分も社会から排除されるのかという不安がつきまとうこともその一因かもしれません。 貧困と格差が拡大していった背景は正規雇用の減少と無関係ではもちろんありません。
貧困と格差が拡大していった背景は正規雇用の減少と無関係ではもちろんありません。
データ(上図、クリックすると拡大します)をみると、正規雇用労働者が大きく減るのは1999年からです。1998年に3790万人の労働者は2005年3330万人と450万人ほど減っています。若年の労働者は1995年から減り始め、絶対数は580万人から280万人程度に減ってしまいました。
とくに以下の点に注目する必要があります。私は以前に「ワーキングプアと100万人の大リストラ」というエントリーを公開しましたが、あらためてふれたいと思います。ここで示したのは、2001年から1年間で100万人の大リストラがおこなわれていたという事実です。これが画期となっているということです。
だが、この大リストラに、労働組合もその本来の力を発揮できませんでした。従来の長期雇用体制がここで一気に崩れたのです。企業は、日本型雇用とよばれる「くびき」から解き放されるという劇的変化をとげたのでした。その結果、7年間で460万人も減少した正規雇用労働者。他方で非正規雇用労働者が400万人もふえるという「巨大な置き換え」が進行しました。1万人のリストラはアクセルとなって大きく雇用環境は変化しました。
たとえば、大学等を卒業した若者が「終身雇用」を前提として正規雇用として採用されていたそれまでの状況を一変させました。 青年労働者の正規雇用の激減と非正規雇用・失業の急増はその結果です。下図をご覧いただけば明らかなように、若者の世代では所得の格差が著しく拡大しているのがうかがえます。他の年代層に比べると所得格差は小さかったのですが、右肩あがりに数値が大きくなっています。だから、若者の非正規と失業が増えると、たとえば結婚している比率にみられる若者の深刻な貧困にも結びつくのです(格差社会-「努力すれば報われる社会」のうさん臭さ)。
青年労働者の正規雇用の激減と非正規雇用・失業の急増はその結果です。下図をご覧いただけば明らかなように、若者の世代では所得の格差が著しく拡大しているのがうかがえます。他の年代層に比べると所得格差は小さかったのですが、右肩あがりに数値が大きくなっています。だから、若者の非正規と失業が増えると、たとえば結婚している比率にみられる若者の深刻な貧困にも結びつくのです(格差社会-「努力すれば報われる社会」のうさん臭さ)。
その上にいま、構造改革は、本来、所得の集中を修正する再分配をむしろ弱めているのが実情です。社会保障や教育もリストラし、そして税制では低所得者に困難をいっそう押しつける改悪がおこなわれたのです。その意味で、国民は2つの困難に直面しているといえます。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
注;上図は、後藤道夫都留文科大学教授。下図は「社会実情データ図録」から(http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/4665.html)。
「再チャレンジ」策はだれを「救う」のか
「努力すれば報われる」という言説にふれて、多くの人が努力しても報われない環境にある。そして中・低(所得)層のこうした困難にもかかわらず、いっそうの負担を押しつけながら、上層を優遇しようとすることは、社会構造の再編の表れ、と私は続けました(格差・貧困と財界のエゴイズム)。
こうして財界・支配層の権益を確保し競争にうちかっていくのです。この点を少しみてみたいと思います。
貧困と格差の拡大のなかで日本社会は大きく変容してきました。たとえば若者の社会への帰属意識-家族、学校、会社など-の低下や犯罪の増加などがたびたび指摘されています。これは、従来の社会の秩序のあり方が大きく問われていることの反映でしょう。だから、税制、社会保障など一連の制度改定にもみられるような社会統合への動きは、保守支配層のこうした変容にたいする危機感の表れといえるかもしれません。一方で、国民の関心もこれにともない高まっています。
格差社会への、これほどの国民の強い関心は社会の変容のためだともいえるでしょう。
支配層の貧困・格差問題への対応のうち、「再チャレンジ」支援策は、以上の文脈で考えると安倍内閣の「目玉施策」なのでしょう。その方向はすでに「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」のなかで示されていました。例の「骨太の方針」です。
この方針は、以後10年の日本が挑戦すべき課題の1つに以下(注)をあげました。そこでは露骨に「中流層」-額面どおりなのか疑わしい、上流ではないのか-への支援がうたわれています。
引用した文章の前段にある「不均衡への克服」が象徴的に示すように、これは、支配層の貧困・格差問題への対応(の方向)を示しています。解決法は、「経済成長の果実」を活用することを基本と明記しています。その「果実」は構造改革のいっそうの推進を想定してのものにほかなりません。また、その過程で生じる「副作用」を否定していません。それには、「真の社会的弱者に絞り込んだ自立支援型のセーフティネットをきめ細かく構築」すべきだと指摘しています。
けれど、そもそも彼らは自立できないから「真の社会的弱者」というのではないでしょうか。だから、安倍首相は、『再チャレンジ』はセーフティネットではない、といったのです。
実際の「再チャレンジ」支援策で列記されているのは、自立が可能な条件下にある人びとが中心とされているようです。
「骨太の方針」がいうように、経済のみならず社会や政治の安定の基礎となる「健全で意欲ある中流層」への支援にこそ照準があてられています。
ここに社会統合への動きと核心めいたものをみるのです。

注;
国民生活に目を転じると、若年層を中心に教育や就業の状況にばらつきが大きくなるおそれ、雇用環境の激変等を背景とする将来に対する不安感の高まり、児童生徒や若者の凶悪犯罪による社会的な不安、都市と地方間での不均衡等の問題が生じている。この新たな不均衡の克服が我が国の第三の「挑戦」として求められる。
機会の平等や社会的セーフティネットなどの課題に対しては、健全で意欲ある中流層の維持こそが経済のみならず社会や政治の安定の基礎となるとの認識に立って、政府は最大限の努力で丁寧かつ誠実に対応していかなければならない。
問題の解決は「経済成長の果実」を活用することを基本とし、そのための構造改革を重点的に進めつつ、一方で、その副作用に対しては、真の社会的弱者に絞り込んだ自立支援型のセーフティネットをきめ細かく構築すべきである。経済成長と安全・安心の社会を両立させる21世紀型の「穏やかで豊かな日本社会」を拡大均衡の中で作っていかなければならない。
「格差があって何が悪い」という議論
小泉首相(当時)が「格差は広がっていない」とのべ、マスメディアが社会的な格差問題を取り上げはじめたのは05年末くらいからでした。そしてその後、小泉首相が「格差があって何が悪い」と居直ったのはよく知られています。
内閣府の説明によれば世帯の所得分布をしめすジニ係数はたしかに上昇しているが、それは、高齢者の比率が高まってきているからということと、世帯の規模が縮小していることから説明できるということを、同首相はその理由にしたものでした。
いったい高齢者の比率がふえたことによる格差の拡大は格差拡大ではないという説明がとおるのかどうか。常識的には理屈にあわない小泉氏の強弁としかいわざるをえないでしょう。政府の資料によって、ジニ係数が示す格差が拡大しているのですから、政府が考えてよいのは、所得税の累進率を少なくとも以前の80年代に戻すこととか、社会保障の給付部分で所得再分配を考慮してしかるべき、格差拡大を是正するためにこう考えるのではないでしょうか。
個々人の所得の分布が仮にかわらないと仮定して、直接税や社会保険料、さらに医療・介護や教育などを利用する際の自己負担がふえれば、とくに低所得者への打撃が大きくなるのは容易に理解されることです。
このようにふりかえってみると、小泉首相は、構造改革で格差を広げ、さらにさまざまな制度改悪によって自己負担をふやしたという意味で二重にまちがっていたということになるでしょう。
この小泉首相と同じように格差があって何が悪いと考えている人は意外に多いようです。昨日、一昨日のエントリー「格差・貧困と財界のエゴイズム」「格差社会-『努力すれば報われる社会』のうさん臭さ」にたいして意見をいただきました。その意見も「報われない人」がいることをいわば当然視するものの一つでした。しかし、これはつきつめていうと、横たわっている問題そのものから目をそらすものではないでしょうか。
いま切実な問題としてクローズアップされているのは、生活保護並みの生活すら送れない人、いわゆるワーキングプア層の拡大です。別の言葉でいえば、常識的な社会生活を送るのかどうかという「絶対的格差」の問題に日本はいま直面しているということです。ここに目をむける必要があると思うのです。本来、絶対的格差はあってはならない。憲法ではもともと、最低限の健康で文化的な生活を送る権利を保障しているのですから。
その上で、いわゆる相対的格差が生ずるというのなら理解されやすいのでしょうが。(相対的格差;富裕層と貧困層の所得格差など)
それでも、その相対的格差が、絶対的格差を同時に引き起こしていることにも目をむけることが必要だと私は思います(この点は、「格差・貧困と財界のエゴイズム」)。たとえば、規制緩和の結果、不安定雇用・低収入の労働者がふえ、一方では、正規から非正規への置き換えをやった企業の収益はふえたのです。絶対的格差はこの経過で拡大し、そのことで富裕層が広がったといえるでしょう。結局、構造改革は絶対的格差を拡大したのです。
「再チャレンジ」支援策は、自立支援を基本に置いたものですから、自立できそうにないほんとうの社会的弱者を視野に入れたものではないという意味で、絶対的格差を解消することにはならない。だから、安倍首相がのべたという「『再チャレンジ』はセーフティネットではない」という言葉はその限りで正しいといわなければなりません。
いかにしたら絶対的格差の解消にむかうのか、そのための議論が国会でも大いにされてしかるべきです。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
格差・貧困と財界のエゴイズム
努力すれば報われるという言説のいかがわしさ。これは、「報われた者」が権益を守り抜こうとするとき、その言動に鮮明に表れるようです。昨日のエントリーで、日本がはたして「努力すれば報われる」社会なのかについてふれ、現実には多くの人が努力しても報われない環境にあることをいくつか例をあげてみてみました。単に報われないばかりか、今日の日本の状況は、生きることさえ困難になり、将来の不安は極度に高まらざるをえないような時点にあることは否定しようのないものになっています。
端的にいえば、上でのべた現実にたいして、それを改善したり是正しようとする方向にむかうのではなく、個人の努力が足りないといって、自助努力と自己責任を迫ってきたのが新自由主義でした。別の面からこれをみるなら、財界・支配層が、中・低(所得)層の困難にもかかわらず、そこにまるで傷に塩をすり込むかのようにいっそうの負担を押しつけ、上層を優遇しようとすることは、財界・支配層の権益を確保し競争にうちかっていくための、社会構造の再編の表れといっても過言ではありません。あるいは階級構造の再編といってよいかもしれません。
あらためていいたいのは、「努力すれば報われる」という言葉のうらには、上層の「努力」による成果は、現実には「報われない人」びとの努力によって支えられ、もたらされたものであることです。たとえば、国際的には比較するのも恥ずかしくなるような最低賃金で働く労働者はその象徴的なものかもしれません。
高い収益、そして利潤と蓄積、これこそ支配層の追求する対象なのでしょうが、その代表格として経団連があることは論をまちません。つい最近、その経団連の御手洗富士夫会長が労働者派遣法にかみつきました。派遣社員を3年で正社員にする制限を見直せ、これが御手洗氏の主張です。彼は、3年たったら正社員にすると、たちまち日本のコストは硬直的になってしまう 、とのべたのです。これこそ、支配層の身勝手さを示す典型ではないでしょうか。
柳沢厚生労働大臣はさすがに、衆院予算委(16日)で、「派遣を製造業に広げたさいの、私どもの期間制限をした趣旨とは反している発言になる」と同氏の発言を批判せざるをえませんでした。
あくなき利潤の追求-ここに大企業・財界の論理が働いています。その結果、大企業は過去最高益をつづけています。たとえば、トヨタ自動車は、23兆円(売り上げ)、2兆円(営業利益)という06年度の見通しを明らかにしました。また、資本金10億円以上の大企業では、一人あたりの役員報酬が2800万円(05年度)といわれています。01年度は1400万円ですから4年間で倍加しています。
昨日みた年々、非正規がふえ、結婚もできない青年労働者がいる中・低層の実態とまさに対照的です。ここに、大企業・財界の横暴勝手、エゴイズムの一端をみる思いがします。

格差社会-「努力すれば報われる社会」のうさん臭さ
努力すれば報われる社会を、とはもっともらしい。そうであってほしいと誰もが思う。
安倍内閣もそう喧伝することしきりだが、もともとは、1999年の経済戦略会議答申にさかのぼらなければならない(「日本経済再生への戦略」)。そこでは、つぎのようにのべている。
日本経済の活力再生には、経済的・財政的に疲弊している地方の自立を促す制度改革が必要なほか、努力した者が報われる公正な税制改革や創造的な人材を育成する教育改革など個々人の意欲と創意工夫を十二分に引き出す新しいシステムの構築が不可欠である。
と、「頑張っても頑張らなくても結果がかわらない社会」に決別し、切磋琢磨し、競争することで成果に応じた正当な評価を受ける社会をこの答申はもちあげたのである。
 以来、努力すれば報われるという言葉は、私たちが直面する実態から遊離して一人歩きしてしまった。そして、安倍首相のいう再チャレンジが可能な国づくりというのもこの延長に位置づけることができる。
以来、努力すれば報われるという言葉は、私たちが直面する実態から遊離して一人歩きしてしまった。そして、安倍首相のいう再チャレンジが可能な国づくりというのもこの延長に位置づけることができる。
努力すれば報われるというレトリックは、逆に、努力しなければ、報われ(ることは望んではなら)ないということと同じだ。むろん努力して報われる人もいるだろう。だが、現実につきつけられるのは、努力しても(働いても)報われない人が多数存在するということだ。
非正規雇用労働者の推移はそのことをはっきりと裏付けている。本川裕氏の「社会実情データ図録」から引用させていただくと、非正規雇用労働者の増加傾向は明白だ。どの年齢層も右肩上がりなのである(右上図)
。また、「正社員と非正社員の結婚している比率」は明らかに傾向が異なる。もちろん非正社員の比率がより低い。 (右下図) これらのデータは、非正規雇用がまさに政策的に増加させられた結果を示している。そして、非正規の結婚していない比率の相対的な高さは、彼・彼女らの賃金の低さを表現していることにほかならない。結婚できないのである。なによりも非正規雇用労働者は望むべくして非正規にとどまっているわけではない。自らの処遇を自ら決定などできない。かつての日本型雇用がくずれ、非正規など不安定雇用形態の労働市場の比重が急増した結果だ。
これらのデータは、非正規雇用がまさに政策的に増加させられた結果を示している。そして、非正規の結婚していない比率の相対的な高さは、彼・彼女らの賃金の低さを表現していることにほかならない。結婚できないのである。なによりも非正規雇用労働者は望むべくして非正規にとどまっているわけではない。自らの処遇を自ら決定などできない。かつての日本型雇用がくずれ、非正規など不安定雇用形態の労働市場の比重が急増した結果だ。
こうしてみると、さきの議論は、あたかも努力している人は収入の高い人のことを指し、低い収入なのは努力していないからだといっているようでもある。
耳障りよく、努力すれば報われる社会をと打ち出される際には、まず労働コストの削減が所与の条件としてあることを承知しておく必要がある。だから、こうした事実を前にしてもなお、再チャレンジ、再チャレンジとやかましく騒ぎ立てる内閣は、そもそも疑ってかからないといけない、いかがわしい内閣ということだ。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
日本の子どもは「孤独」、誰がこうしたのか
 ユニセフ・イノチェンティ研究所は14日、経済先進国(全て0ECD加盟国)の子どもや若者を取り巻く状況に関する研究報告書(Report Card 7)を発表しました。 読売新聞はこれをつぎのように伝えました。
ユニセフ・イノチェンティ研究所は14日、経済先進国(全て0ECD加盟国)の子どもや若者を取り巻く状況に関する研究報告書(Report Card 7)を発表しました。 読売新聞はこれをつぎのように伝えました。国連児童基金(ユニセフ)は14日、先進国に住む子どもたちの「幸福度」に関する調査報告を発表した。それによると、子どもの意識をまとめた項目で、「孤独を感じる」と答えた日本の15歳の割合は、経済協力開発機構(OECD)加盟25か国29・8%と、ずば抜けて高かった。日本に続くのはアイスランド(10・3%)とポーランド(8・4%)だった。
また、「向上心」の指標として掲げた、「30歳になった時、どんな仕事についていると思いますか」との質問に対しては、「非熟練労働への従事」と答えた日本の15歳の割合は、25か国中最高の50・3%に達した。
 また日本は、親が働いていない家庭の割合が、先進国中で最も少ない0・4%。ところが、平均収入の5割を下回る家庭に暮らす「貧困児童」の割合は、14・3%にのぼり、最悪の米国(21・7%)から数えてワースト9位となり、子どもを持つ「ワーキングプア」の家庭が相当数に達していることが分かった(下図=引用者)。
また日本は、親が働いていない家庭の割合が、先進国中で最も少ない0・4%。ところが、平均収入の5割を下回る家庭に暮らす「貧困児童」の割合は、14・3%にのぼり、最悪の米国(21・7%)から数えてワースト9位となり、子どもを持つ「ワーキングプア」の家庭が相当数に達していることが分かった(下図=引用者)。== 以上、読売新聞2・14 ==
どの指標も、子どもの成長にとって日本の環境が好ましいものではないことを示唆しています。とくに、読売新聞も指摘する低所得層の子どもたち(読売記事では「貧困児童」)が相当数にのぼっており、今の格差社会とよばれる日本を映し出しています。
その影は、「孤独を感じる」と応えた子どもが加盟25カ国中ですば抜けて高かったこと、将来を楽観的にみるのではなく、「非熟練労働への従事」と答えた子どもたちが50%を超えるという最高値を示したことに、落とされている気がしてなりません。むしろ皮肉にも子どもたちは冷静にみているといえるのかもしれません。これはいま、ここに生き、勝ち組をあおる風潮の中でそれにむかって血道をあげる、あるいはあげざるをえない大人たちをあざ笑う結果であるようにも思います。
まさにこれは今日の日本への警鐘だと私はとらえます。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒

ゴンベイさんからは、コメントでこの記事を紹介いただきました。ありがとうございました。
格差社会の一面 -医療費支払いで不安、低所得層
ワーキングプア層が400万を超えたともいわれる今日、この層の人たちの健康が守られるのかどうか、気がかりなところです。
日本医療政策機構が実施した調査が発表され、低所得者が病気にかかった時に医療費が支払えないという不安を感じていることが明らかになりました。
医療費支払いに不安、低所得層の8割超 NPO調査(朝日新聞2・16)  報道によると、将来、医療費を払えない不安を抱える人は、高所得層の36%に対し、中間層で74%、低所得層では84%にのぼったといいます。この調査では低所得者層を年間世帯収入300万円未満などと定めています。世帯構成などが報道では明らかにされていないという弱点がありますが、この層はワーキングプア層とみなしてよいと思われます。この低所得層は、実に5世帯のうち4世帯は支払いに不安を抱えているという結果です。
報道によると、将来、医療費を払えない不安を抱える人は、高所得層の36%に対し、中間層で74%、低所得層では84%にのぼったといいます。この調査では低所得者層を年間世帯収入300万円未満などと定めています。世帯構成などが報道では明らかにされていないという弱点がありますが、この層はワーキングプア層とみなしてよいと思われます。この低所得層は、実に5世帯のうち4世帯は支払いに不安を抱えているという結果です。
同機構は「所得によって医療に対する意識に大きな格差があることがわかった。医療政策を考えるうえで重要な要素になる」と分析しているといいます。
そこで考えるのは、「意識に大きな格差がある」という現実です。
「長瀬指数」というものがあります。患者負担の割合とこれに対する医療費の関係を明らかにした算定式で、旧内務省で使われていたとされます。この式によれば患者負担無しの場合を1とすると、医療費負担が1割で0.848、2割で0.712となり、3割では0.592と、医療費を4割以上削減できることが予測できるわけです。つまり今の厚労省の医療費削減の方程式ともいえるものです。
数式で表すと以下のとおりです。
y=1-1.6x+0.8x2(xの二乗)
だから長瀬指数によれば、2割負担だと医療需要の7割、3割負担で6割しか確保されないということになるのです。厚労省が戦前の内務省時代からもちいていた数式で、こんな結果がでる。厚労省はを国の負担を抑える際、これによって予測してきた。逆にいえば、国民の側からすると3割負担では、患者側に抑制がはたらき、本来の社会保険など公的医療保険が空洞化する実態が、これによっても分かるということです。いまでも厚労省はこの「長瀬式」をもちていいます。もっとも厚労省は3割負担が「限界」といっていますが、保険診療と自費診療をドッキングさせた特定療養費制度がすでに導入されていることを考えると、事実上、3割を制度的には超えているとみなければなりません。
そこで、日本医療政策機構の調査に話を戻すと、ワーキングプア層に等しいと思われる低所得層が不安を感じるのもうなづけます。もともと医療費はこの調査の低所得層にも、中所得層にも、高所得層にも同一診療内容であれば同額のはずです。仮に医療費負担が1万円だとすると、この1万円の年収に占める割合は当然、異なります。低所得層では300分の1以上ですから、他の階層以上に占める割合は高く、低所得層により受診抑制がはたらくのは当然でしょう。そうなると健康にも影響が及ぶことは容易に想像されます。
社会保障は本来、所得再分配機能をもっているといわれています。要するに社会保障は、主として保険料を財源とした「健康な人」から「病気の人」への所得再分配や「所得の多い人」から「所得の少ない人」への所得再分配が働かなければならないのです。
しかし、とくに小泉構造改革以降、再分配抑制がとられてきました。その結果、自己負担が1割、2割、3割とふえると、どのように影響するのか、今回の意識調査は示すものでしょう。所得の多寡が受診に影響を与え、別のエントリーで言及した健康の格差につながっていく。調査はわれわれにこれを教えているといえます。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
ビッグマック問答・続編 -日本の豊かさ、貧しさ
再び丁寧なコメントを頂戴した。再びといったが、今度は前回とちがったHNになっている。
同一の人からのものだという前提にたっていえば、前回からの論点の発展はないと私は考えるので、一昨日からのコメントにたいする私の対応、「ビッグマック問答」もこれで終わりにしたい。
以下、いただいたコメントとそれにたいする<これお・ぷてら>のコメントは以下のとおり。
=====================================
さっそくのお返事をありがとうございます。そのうえ、小生のつたない投稿ごときをエントリーにまで取り上げていただけるとは何たる光栄。ところで、おふれいただいたついでに、もう少し話をお聞き願えないでしょうか。自分紹介が遅れましたが、私は間違いなく「8割」の方に属する人間で、しがない労働者でございます。このご時世、私の職場にも、ご他聞にもれず賃金改定の嵐が吹き荒れ、何かと苦労は絶えません。格差もあるのでしょう。しかし自分を「貧困」だと考えたことだけは一度もございません。ひたすら額に汗し、腹ペコになってパクつく弁当の一口に、このうえない幸せを感じられる毎日を送る次第でございます。もちろん、この国が良くなって欲しいという願いは、これお・ぷてら様と何ら変わりはありません。ですが、私には、格差社会・貧困化というコトバにだけは、どうしても納得がまいらない部分があるのです。そこでいくつか質問がございますので、もしまたお返事をいただけたら幸いです。
ではまず、日経のこの記事(2006/12/06)を解説いただけないでしょうか。
「世界の「富」、人口の2%が半分以上所有 」
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061205AT1C0500205122006.html
これは国連の調査機関が発表した結果だそうですが、記事によれば、「日本は世界平均や米国などと比べて格差が小さかった。」ということです。はたまたこのデータをもとに、こちらの方が行った計算によれば、「日本人のほぼ全員が世界の富の85%を保有する人口の上位10%に属している」のだとか。
http://blog.mag2.com/m/log/0000062475/108003002.html
パレートの法則が正しいとすれば、世界のなかでも豊かと云える日本人が、8対2にわかれて取り分の争いをしているわけですね。
格差といえば、所得格差の度合いを示す「ジニ係数」はご存じのことと思います。ではこちら。2005年、世界銀行が公表したこのデータをどうご覧なさいますでしょうか。
http://devdata.worldbank.org/wdi2005/Table2_7.htm
これによれば日本の格差の度合いは、なんと、下から2番めではありませんか。
この二件について、なにとぞご指導のほどをいただけたら幸いに存じる次第です。ありがとうございました。
=====================================
 以下は、いただいたコメントにたいする<これお・ぷてらのコメント>。
以下は、いただいたコメントにたいする<これお・ぷてらのコメント>。
最初に申し上げておきますが、私の記事に関するコメントやご質問にたいしては、可能なかぎりお答えしたいと願っています。ただ、当方もまた、限られた時間ゆえ、限度がもとよりあります。ご了承ください。
そこで、昨日のエントリーで明らかなように私が関心をもつのは、世界にたいするあなたのまなざしがなぜ日本にたいしては屈折するのか、ということです。繰り返し世界にたいして開かれているだろうあなたのまなざしは、こと日本の現実を前にすると、まるで消失してしまっているかのようです。
この点を除けば、今回あらためて提示していただいたそれぞれの記事にいかように「解説」しようと、少しも議論の発展はみられないと感じます。もちろん、私は自分の感想をのべるのみで、解説する立場にないことはいうまでもありません。
あえていえば、私の一連のエントリーでとりあげているのは「2割の人が全体の8割の所得を占めることに端的に示されるような、極端な偏りを含んでいる」日本の現実に関してです。その日本と世界の国々の間の比較は、別の問題として取り扱わなければならないでしょう。日本の現実に着目するのは、いまの統治機構が国家という形をとって現れている以上、あなたが仰るように「この国が良くなって欲しいという願い」を成就させるためには、とりあえずこの国を考えないといけないからにすぎません。
以下、感想をのべておきます。①、②、③は提示いただいた参照資料を順に符番したものです。
①「世界の『富』、人口の2%が半分以上所有」 単に日米への「富」の集中を伝えているだけでしょう。もっといえば日米の、それも一部に集中しているということでしょう。
②「世界の富、人口の2%、半分以上所有―国連調査」
「一人あたりの富の平均が、日本の場合はおよそ2,000万円と世界一位の数字となっています」と記事では紹介されていますが、富の平均値であって、日本のなかのばらつきは当然、表現していませんね。
③所得などの不平等度を表すローレンツ曲線ですよね。「構成員どうしの所得の差を全体としてみる」という前提をはっきりさせておけばよいのでは。
あなたが示されている表では、日本の「Lowest 20%」はどのようになっているのでしょう(上図の赤い囲み部分)。他の国と比較してみても、はっきり分かるくらい高いですね。下位20%に入る層が日本は多いのです。私にいわせれば、ここが問題です。同時に、他国との比較の上で相対的な「日本の豊かさ」に言及しながら、以上の点に一言も言及されないのは理解しがたいことなのです。

図は、コメントをいただいた方が参照されているものを引用させていただいた。
【参考エントリー】
ビッグマックからみる日本の豊かさ、貧しさ
ビッグマックからみる日本の豊かさ、貧しさ
昨日の記事に関してコメントをいただいた。コメントは、文面から察すると、以下のとおり格差と貧困が広がっていることにたいして懐疑的なものだと受け取ることができる。その意見は、日本の「豊かな一面」をとりあげて、「貧しさ」を打ち消そうとしている点で典型的だと思う。
コメント欄で尽くせなかったこともあるので、あらためてエントリーして、ふれておきたい。
いただいたコメントは以下3つ(原文のまま)。
=====================================
日本の貧困率2位に対する疑問
ついせんだって、ビッグマック一個がどのくらいの労働で食べられるかという調査では、日本(東京)が世界で一番豊かだという結果が出ていました。
以下引用)東京では10分間働けばマクドナルドの「ビッグマック」が買える――。スイスの大手金融UBSグループが、世界各国でビッグマック1個を買うのに必要な労働時間を調べた06年の調査で東京が最短となり、最も豊かという結果が出た。最長のコロンビアの首都ボゴタは97分間で、東京の10倍近い。(引用終わり)
またこの朝日の記事によれば、人間の「豊かさ」指数で、日本は高福祉の北欧諸国にまざり、堂々の七位に入っています。
http://b.hatena.ne.jp/entry/3204660
貧困率や最低賃金2位というわりに、豊かさ1位(7位)。いったいこれはどういうことなのでしょうか。
補足
失敬。ビッグマックの元記事のURLが抜けていました。http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.asahi.com/business/update/0810/139.html
日本は貧困なのか豊かなのかどちらなのでしょうか。データも取り方次第で、いくらでもトリックが可能なのではありますまいか。
質問
ちょっと待っていただきたい。日本が高齢化社会であることや、フリーター人口が多いということは、とりもなおさずそれだけこの国が豊かだということのメルクマールではありますまいか。格差社会、貧困化が叫ばれるわりに、日本に難民や餓死者、浮浪児があふれているという話は聞いたことがない。これは高校に例えたら、灘高のなかで自分は劣等性だと嘆いているというのに等しい状況なのではないでしょうか。世界一の豊かさのなかで叫ぶ格差。飼い犬までメタボリックに悩むこの国の状況をアフリカの貧しい人々が見たらどんなに悲しい気持ちになるのかと思うと、私は恥ずかしいです。
=====================================
以上の3つのコメントにたいして、次のコメントを残した。
これお・ぷてらのコメント
ご紹介いただいた朝日の記事は、「ビッグマック一個がどのくらいの労働で食べられるかという調査」ですから、比較する際には、物価(サービス含む)と賃金がその尺度になるでしょう。賃金は平均的な数値がもちいられていると思います。
また、「豊かさ」指数とは人間開発指標でしょうから、平均寿命、教育水準(成人識字率と就学率)、国民所得を用いて算出しているものですね。
一方で、貧困についてはOECDが公表しています。その指標は周知の通り相対的貧困率といわれるものです。中央値の50%未満の等価可処分所得を有する人々の割合、というものです。OECDはそれが拡大していることを指摘しました。
>日本は貧困なのか豊かなのかどちらなのでしょうか。データも取り方次第で、いくらでもトリックが可能なのではありますまいか。
ですから、貧困なのか豊かなのかどちら、「トリックが可能」というより、何にもとづいて何を表しているかの問題でしょう。エントリーで問題にしているのは、貧困と格差ですから、わかりやすくいえば、国民の2割が8割の所得を有している日本の現状をふれているわけです。
アフリカの貧しい人々にたいする○○さんのまなざしは、日本の8割とはいわないまでも、その底辺にいる人びとにも、おそらく投げかけられていると思いますし、理屈の上でもそうでないといけません。その方がたは、たぶん灘高生にはもとよりなりえず、「メタボリックに悩む」犬をもつこともできないだろうと、私は思います。
別の表現をすれば、このエントリーはそのまなざしについてのべているといえるでしょう。
まったくの余談ですが、参照されている記事のなかの日本マクドナルドが、アルバイトにたいして賃金未払いであったことが以前、報じられました。利潤追求がいかにしておこなわれているかを示すという意味で、これもまた「日本の豊かさ」の一面なのでしょうね。
(以上、これお・ぷてらのコメント)
このように、私が昨日のエントリーや格差社会支える「最低賃金制」でのべているのは、貧困と格差にかかわるものだ。
いくつかの調査にもとづき、日本の「豊かさ」を提示されているのだが、私が明らかにしようと思うのは貧困と格差の存在であって、最低賃金の低さだ。列記されている「豊かさ」は、分かりやすくいえば日本の総体を映し出しているものだろう。それは、2割の人が全体の8割の所得を占めることに端的に示されるような、極端な偏りを含んでいるものだ。あえていえば、そこに関心を払う必要があると考えている。
引用に関連する商品をつくるマクドナルドが賃金未払いで、未払い分の支払い命令が出た。まるで笑い話のようだが、そうしてまでも利潤を追求する姿をそのまま笑っておくだけではすまない現実がある。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
貧困と格差をどう解決していくのか -国会論戦から①
20世紀と21世紀の移り目に、貧困と格差が顕在化し、それが深刻化するという変化に日本はみまわれることになった。格差社会という言葉はすでに定着した感じだが、なかには格差の事実を認めようとしない者もいる。また、格差社会についてのべてはいるが、貧困と格差を生んできた構造改革路線に抵抗し、解決の有効な手立てを明らかにしているかといえば、すべてがそうとはいえないようだ。
今国会で、貧困と格差をめぐって審議がはじまった。その中で、気になった答弁がある。柳沢厚労相はつぎのようにのべた。論戦は非正社員をめぐってである。
実際には正社員とは全く職務が異なる方々が、パートの中の90%近くいることを理解してほしい。(朝日新聞2・13)
さらに同氏は菅直人氏(民主)の質問にたいして、パート労働法改正案について、正社員との賃金などでの差別禁止の対象となるのは「(パート)全体の4~5%」と説明した。
おかしいのではないかと思って、厚生労働省ホームページがリンクをはっている21世紀職業財団がおこなった調査「パートタイム労働者実態調査結果概要(平成17年9月)」をみてみた。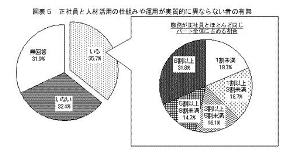 右のグラフをみてほしい(クリックすると拡大します)。注意をしないといけないのは事業所調査であることだ。このグラフが示すのは、「正社員と人材活用の仕組みや運用が実質的に異ならない」非正社員の有無と、その非正社員のパート全体に占める割合(を事業所にたずねたもの)である。だから、柳沢氏の答弁がほんとうならば、4~5%といっているのだから、右のグラフから推測すると、割合10%未満の事業所に労働者数は集中しているということになるだろう。ようするに大規模事業所では差別禁止の対象は少ないということを示すのだろう。
右のグラフをみてほしい(クリックすると拡大します)。注意をしないといけないのは事業所調査であることだ。このグラフが示すのは、「正社員と人材活用の仕組みや運用が実質的に異ならない」非正社員の有無と、その非正社員のパート全体に占める割合(を事業所にたずねたもの)である。だから、柳沢氏の答弁がほんとうならば、4~5%といっているのだから、右のグラフから推測すると、割合10%未満の事業所に労働者数は集中しているということになるだろう。ようするに大規模事業所では差別禁止の対象は少ないということを示すのだろう。
だが一方で明らかになるのは、事業所をベースにした場合、多くの事業所に「パート労働法改正案」の対象者がいるという実態である。労働行政が指導すべきなのは、この実態ではないか。同氏の答弁には、なにやらカラクリめいたものを感じるのだ。
私が気になったのはこの答弁なのだが、その上で、菅氏の質問以上に重要な提案が必要だと考えている。たしかに正社員と非正社員の格差は解消しないといけないが、問題は、その正社員・非正社員の実態そのものが貧弱なことである。それは端的にいえば、日本の最低賃金制度の水準に表れている。ここを追及し、改善することこそが今の局面の課題だと私は思う。ワーキングプアを生み出す程度の、低い最低賃金が存在することを問わねばならないのではないか。少なくとも単身労働者が社会保険と税金を払い、働くために必要な経費を見込んだうえで生活保護水準の生活が最低でも可能となるような賃金水準を確保しなければならないだろう。そうでなければ、正社員と非正社員の格差が仮になくなったとしても、根本的な解決に向かったとはお世辞にもいえない気がしてならない。むろん多少は前進であることにちがいはないのだが。極論すれば、この理解は正社員と非正社員の格差をとらえているのだが、貧困の根本のところに目がむいているとはいえない。
話を元に戻すと、このやりとりにみられるように労働者を囲む環境は決して穏やかでない。ホワイトカラーエグゼンプションはとりあえず政府が国会提出をとりやめた格好にいまあるが、労働者にとって「ビッグバン」とよばれるように労働環境を一変するようなしかけが今後、画策されようとしている。
だからこそ、最低賃金制の改善は安定した社会保障をめざしていいく上でも課題ではないだろうか。賃金の最低水準が生活保護水準より低ければ、いきおい最低生活の保障を求める圧力は生活保護という制度にむかうだろう。この間の経過で明らかなとおり、そうなると今度は生活保護を抑え込む方向に力が働いてきた。そんな悪循環をあらためる上でも、最低賃金制度の改善は不可欠ではないだろうか。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
注;パート労働法改正案
労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)は1月22日、さる1月16日に厚生労働省から諮問されていた「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」(パートタイム労働法改正案要綱)について、諮問案をおおむね妥当と認める答申をとりまとめ、柳澤厚労相に提出した。
同改正法案要綱では、パートタイマーに対する労働対策として、(1)パートタイマーを雇入れたときには、退職手当その他厚生労働省令で定める賃金に関する事項を文書交付により明示する、(2)職務内容が通常の労働者と同一のパートタイマー(期間の定めのない労働契約の者に限る)であって、通常の労働者と同様の職務変更が見込まれる者に対しては、パートであることを理由として待遇に差別的取扱いをしてはならない、(3)通常の労働者に実施する教育訓練であって、従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務が同一のパートタイマーにも実施しなければならない-などの事項を法規定することとしている。
答申を得た同省では、これに基づいて法律案を作成し、今通常国会に提出することとしている。
http://www.chosakai.co.jp/news/n07-01-25-2.html
「ぶら下がり取材」とメディア
元写真記者による記事盗用問題を受け、朝日新聞社は、昨年1月からテレビCMや駅広告などで展開してきた「ジャーナリスト宣言。」と題した広告キャンペーンを自粛した。同社によると、社員の不祥事による広告自粛は初めてだという。
このキャンペーンは、05年に取材内容の漏えいなど社員の不祥事が相次いだことから、「ジャーナリズムの原点に立ち、真実を追求する姿勢をなおいっそう強めていく」(広報部)としてスタート。テレビやラジオのほか、駅のホームなどで広告活動を展開していた。
同社広報部は「報道機関として広告自粛が妥当と考えた」と話している。(毎日新聞2・9)
このきっかけとなったのは、朝日新聞本社カメラマンによる記事盗用問題。盗用は、読売新聞富山版に昨年1月21日付で掲載された記事を下敷きにしたものでした。
今回の「朝日」の措置は、「ジャーナリズムの原点に立ち、真実を追求する姿勢をなおいっそう強めていく」といういわば再出発の誓いが、もろくも崩れ去ったからです。ここに至って「宣言し続ける」のはもはや欺瞞にしか映らないという判断でしょう。
たびたび起こるこんな事件が国民の信頼を裏切ってきたことはいうまでもありません。
ところが、上記宣言にまつまでもなく真実を国民に伝えるべきマスメディアの取材力が低下しているといわれています。例にとるのはぶら下がり取材です。
以前の話になりますが、安倍首相になって早々、首相のぶら下がり取材を小泉時代に1日2回だったものを1回にするしないで官邸と内閣記者会との間でやりとりになりました。ご存知の方も多いでしょう。
聞くところによれば、このぶら下がり取材は、各社の新人記者が慣例で担当するといいます。要するに総理番は、政治部においては一年生記者の仕事なわけです。相手が総理だから「特落ち」(特ダネの反対)がないというのでしょうか、政治部に配属された若い記者が総理を担当する慣例になっているといいます。
すると、容易に想像できるように、総理のいう一言一言が、反論もされずに記事になっていきます。これをうまく活用したのが小泉前総理でしょう。極論すれば、小泉前首相に新人記者は軽くあしらわれ続けたことになります。
取材力の低下の一因は、たとえばこんな取材のあり方にもあるでしょう。
だが、こんな取材のあり方はどこからくるのでしょうか。記事を書く記者に寄り添って考えると、記者の労働環境がどうなっているのかにも注目せざるをえません。
一連の「不祥事」の背景には経営の成果、事業成績を追い求めることに汲々とする姿勢があるのでしょう。 新聞協会資料によれば、広告収入が年々落ちていることが分かります(図をクッリクすれば拡大されます)。つまり、広告媒体としての新聞の価値が低下しているということです。こんなところから業界の危機感は強いと思われます。逆にいえば、この点で政治の介入の余地が残されていることになるでしょう。
新聞協会資料によれば、広告収入が年々落ちていることが分かります(図をクッリクすれば拡大されます)。つまり、広告媒体としての新聞の価値が低下しているということです。こんなところから業界の危機感は強いと思われます。逆にいえば、この点で政治の介入の余地が残されていることになるでしょう。
実際、新聞広告の半分は電通がにぎり、テレビのコマーシャルも電通のシェアは高いといわれています。だから、経営にひびく問題を迂回していくという姿勢になるというわけです。権力の監視どころではないはずです。
そのもとで、賃金にも成果主義賃金が持ち込まれています。また、経営の効率化を図るために、人員削減という「合理化」にさらされています。いきおい労働条件が悪化し、その中に記者も置かれているのです。知り合いの記者に聞けば、成果主義のなかでは、記者同士の議論の時間さえ限られていて、自分の成果をあげるという目先に関心が集中するといいます。これが記者をとりまく現実でしょう。
だが、こんな矢先につぎの記事が目を引きました。
北海道新聞社員が地下鉄止める 「会社員」として報道(朝日新聞2・9)
マスメディアに求められると私が考えるのは、しっかりと国民の立場にたって報道することです。そこにたって国民に判断材料を提供することが本来の仕事ではないでしょうか。
マスメディアはどこに身をおくのか、自らはっきりさせると同時に、国民に実際の記事・報道でそれを示す必要があります。
そうしなければ、たとえば朝日新聞の今回の問題を本質的に解決したことにはならないでしょう。

日本からみた幼稚園児殺害事件
初公判がはじまった滋賀・幼稚園児殺害事件について昨日、加害中国人女性の側からみた。この事件を、中国人女性とは異なる日本側からもみなくては、どこか欠落するような気がしてならない。
生まれ育った土地を離れて、大都会で生活しはじめたときに、いいようもない不安に襲われたことがある。たとえば、それまで遭遇したことのなかった人ごみとその流れはもちろん、地下街を歩く人の速さにさえ圧倒され驚いた。数十年も前のことだから、今とちがって情報の伝播する速度は格段に遅く、それだけに地方と都市の社会的・経済的な格差は保持されていて、地方と都市の差異は、現在とは比較にならないほど大きかったはずである。その差異に戸惑ったのだ。自らの経験の領域を超えたこうした経験は、ただ将来にむかった不安であるばかりでなく、現在=その時における、ある種の気恥ずかしさを強いるものだったのだ。
いまここで、自己と他者を共通に囲う普遍性があるとしよう。それは、お互いが「何かであること」を根本から否定し、ないものにする、つまりアイデンティティの変容によってのみ保証されるものであろう。
この園児殺害事件をこの視点からみてみると、たとえばコミュニケーションは、中国語によるか、日本語によるか、または第三の言語によるか、そのいずれかによって可能だ。この事件では、中国語か日本語のいずれか、さらにいえば日本社会のなかの現実であることから予測されるように、日本語によるコミュニケーションの成立が可能性としては大きいはずである。したがって、事件の背景に、この中国人女性にとっては「中国人であること」、つまり中国語の使用をやめるのが不可能だという問題が横たわっていたと解釈できる。逆に日常での中国語によるコミュニケーションは希薄だったと容易に推測される。
犯行によって彼女はその特異性を乗り越えようとしたのだが、この特異性が日本社会のなかでのコミュニケーションという循環の中にある以上、循環を切断したところそれを否定し去ることはできなかったのだ。
つぎの言葉がある。
責任を可能なものとしている契機と、赦しを可能なものにしている条件は、同じ逆説である。だから責任が可能なのは、われわれが、「絶対に赦しえない」という認識を保ったまま、それを赦すことができる場合である。赦しが因果関係を乗り越えるその同じやり方だけが、責任という感覚をも生み出すことができるからだ。犯罪者を心神喪失と見なして、責任概念の守備範囲から放逐するのでもなければ、責任能力を認定した上で断罪するのとも異なる、第三の道がここにはないだろうか。大澤真幸「試練にたたされる『責任』概念」(『朝日新聞』、2001・6・23)
この文脈で、滋賀・幼稚園児殺害事件を考えることはできないだろうか。
もとより、赦すことができ、また責めることができるのは、犠牲者と、あえていえば遺族や親友のみである。残された遺族の深い心の傷は察して余りある。
こう考えるならば、日本社会における外国人の受容の現状とその条件にも、私は目を向けざるをえないのである。これは、「何かであること」を根本から否定し、無いものにする(無化する)、つまりわれわれ日本人の側には、はたしてアイデンティティの変容の条件があるのか否かを問うことでもあるのだ。
自らに直接原因がないこの事件の責任をわれわれが受け止めるとすれば、それはまさにこのことだろう。

中国人女性側からみた幼稚園児殺害事件
朝日新聞(2・2)が滋賀県でおきた幼稚園児殺害事件の初公判のもようを伝えた。事件当時のメモをたよりにふりかえってみて、つぎのような感想をもった。
この幼稚園児殺害事件は、中国人である一人の母親の犯罪である。彼女は来日して7年(事件当時)だという。7年間の彼女を取り巻く世界は、それまでに彼女がみてきた世界と比べてみると、特異なものとして映ったにちがいない。両者は重なり合うことなく、中国と日本という空間的な、そしてそれぞれの社会の時間的な差異を投影して、交差するばかりであったろう。その上に、彼女が発し操るべき言語の壁、少なくとも彼女にそうみえた壁は大きかったはずであり、それこそが日本社会における自己の特異性=「周縁性」を彼女に強要するものであったにちがいない。
犠牲になったのは、彼女がわが子を幼稚園まで送る車に同乗した園児2人だ。犯行の動機を、彼女は、わが子と他の園児たちとのコミュニケーションがうまくいかなかったとのべているという。だが、この中国人女性の言葉にそのまま首肯するのではなく、その動機を、背面から迫っていかなければ、われわれは事件の全容をつかむ入口にも立てないだろう。
コミュニケーションがうまくとれなかったのは彼女にとってのわが子だけでなく、彼女自身でもあった。この女性は、他の園児とのコミュニケーションがうまくとれないわが子と他の園児との関係性を、おそらく自らに置き換えたのだ。つまり、犯罪を犯した母親は、自己の他者であるわが子にとっての他者=園児(事件の場合、2人)に自らを投影させ、鏡像である園児の「否定」、つまり自らの否定を犯行によって実行したのだった。そのことによって、彼女は日本への同化をはかろうとしたのではないか。否定されなければならなかったのは自己であった。
いいかえれば園児は自己であったのだ。正確にいえば、中国から日本という異国に移り住んだ自己の「周縁性」を、わが子の他者である2人の園児に彼女はみたのだった。だから、自らの他者であるわが子の他者、犯行の対象は、わが子がうまくコミュニケーションがとれないと彼女が認識する園児であれば、特定の人物ではなく何者でもよかったのである。そのわが子の他者=園児を鏡像として、彼女は自らを否定しようとしたのだ。
この中国人女性にとって、日本社会そのものが自らの経験の領域を超えた経験にほかならず、そのなかでは、彼女は受動的にならざるをえなかったはずだ。言葉を発するということを起点にしたコミュニケーションのなかでは、中国人である彼女は能動的にふるまうことはついにできなかった。換言すれば、コミュニケーションの道具であるべき言語、この場合の日本語を駆使しえないという消極性のいきつくところ、要するに自らを否定せざるをえないと、この女性は感じとったのだろう。
それゆえ、彼女の能動性は、言葉を発語するところからはじまるコミュニケーションという循環する関係のなかではなく、園児の殺人という犯行において実現されたのだと考えないといけないのだろう。彼女の能動性は残酷な殺人という行為で表れ、コミュニケーションという循環の切断でもあったのだ。そのことで彼女は自らを否定し日本人に同化すると考えたのだ。
■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒ 
注;幼稚園児殺害事件
滋賀県長浜市で昨年2月、同市立神照(かみてる)幼稚園に通う武友若奈ちゃん(当時5)と佐野迅ちゃん(同)を殺害したとして、殺人などの罪に問われた中国籍の鄭永善(てい・えいぜん)被告(35)の初公判が2日、大津地裁(長井秀典裁判長)で開かれた。鄭被告は罪状認否で「刺したけれど、砂人形なので死ぬことはない。血も出ていない。殺人ではない」と述べ、殺人罪についての起訴事実を否認した。弁護側は「精神疾患の強い影響下で、心神喪失か心神耗弱状態だった」と主張した。
裁判では、鄭被告の責任能力の有無が最大の争点。公判と並行して鄭被告の精神鑑定が進められる。判決は10月16日に言い渡される見通し。
検察側の冒頭陳述によると、中国出身の鄭被告は05年4月、長女(6)がグループ通園をする園児らにとけ込めないと考えた。
同年12月に、長女が嘔吐(おうと)したのを見てほかの園児が水筒に異物を入れたのではと不安になり、犯行直前の06年2月10日、長女が再び嘔吐したことから「いじめられている」と一方的に思い込んで憎悪を募らせ、殺害を決意したとした。 == 朝日新聞2・2から引用 ==
| « 前ページ | 次ページ » |

















