河村たかしという男は本当に、軽いというか、まあ「政治屋」である。南京大虐殺はなかった?
私も「大虐殺」と呼ぶべきものはなかったと思う。
そもそも、30万だとか、20万だとか到底あり得ない数字はともかくも、数万人が殺されたとして、あるいは死んだとして、その数だけをもってして「大虐殺」と名付けるべきなのか。
しかも、数万人の死因が日本軍による虐殺だという証拠はどこにもない。確かに、略奪だとレイプだのの証言はあるが、その証言が死んだ人数分ありわけでもなければ、一部の証言は事件の全貌を語り得るなどと思うのであれば、その人間は「単純」を通り越して「アホ」だとしか言いようがない。幕府山事件のように、戦時国際法上、グレーなものもあり、これを「大虐殺」に加えるべきかいなかも論争点になりえる。そもそも、戦時国際法上云々というのは、連合軍の日本占領政策の合法性も含め、おおよそグレーなものなのであり、そのそもそもの原因は戦時国際法それ自体にあるのである。
もし南京の例を、そこで日本軍のみの手により(つまり占領以前の国府軍の住民、友軍将兵への暴虐はあえて含まず)数万人が殺されたケースに「南京大虐殺」の固有名詞を関するなら、南京事件ほどグレーな部分のないほど明々白々たる戦時国際法違反である東京大空襲(当初から一般市民がターゲットであったことは今や米国自身の公開資料が明らかにしている)や広島・長崎への原爆投下にも「東京大虐殺」、「広島・長崎大虐殺」と名付けようではないか? ソ連軍による満蒙での暴虐行為やシベリアでのポツダム宣言違反の行為にも固有名詞を与えようではないか。ちなみに、ポ宣言違反したのは、厳密にはソ連だけではない。中華民国も大陸、台湾で同様の違反をしている。これは彼ら自身の公文書が「ゲロ」している。
数万人死んだというのであれば、まずはそのうち戦闘行為の結果なのか否か、そのうちのどれほどが戦闘員/非戦闘員だったのか、戦時国際法に照らして日本軍の不法行為の所産か否か、を資料をもって明らかにされるべきである。
そうした検証行為が不十分な現状において、「大虐殺はあった」と断定するのは、無責任極まりない行為だ。
ちなみに、慰安婦問題同様、しばしば「生き残り」の証言がもちだされるが、証言を無条件に事実として真実として認定する能天気がいまだこの世に存在することが私には信じられない。しかも、相手は、あの政治体制下に生きる人々である。前国家主席までもが、その父親が日本軍の手先であり、自身も日本占領下の南京で学生生活を送り日本語を専攻していた人物であったことを、自国民には対しては糊塗し、そのことを公言することを許さない体制の下での「「証言」であることを忘れてはなるまい。
谷川氏も具体的にいかなる理由で数万人と自信をもって断定するのか明らかにすべきだ。なぜならば、河村市長に対する批判も自分自身の「断定」が前提になっているからである。
一方、河村氏もアホだ。そうした発言を軽々しくして一体政治的に何のメリットになるというのか。それに父親の個人的経験のみをもって「大虐殺」を否定するのは児戯に等しい。日本軍の支配下にある都市で日本軍への敵意をむき出しにしていかに生きて行けようか。その点を考えもせず、だから大虐殺はなかったとは・・。
まあ、谷川氏も河村氏も、野良犬の喧嘩みたいなものだと思えば気にすることもないのだが、大の大人の発言としてはどちらも情けないものがある。前者はジャーナリスト、後者は政治家。まさにトホホである。
追記 ちなみに谷川氏はポルポトの虐殺に言及しているが、実は、これについてもその実態についてはやはり現時点で断定するのは問題かもしれない。虐殺と呼ぶべきか否かはさておき、ポ政権が大量の死亡者を出したことは間違いないのかもしれないが、その正確な実態については、ベトナムや米国の思惑というものが、どうも真相究明を難しくしているという指摘もなくはなく、やはりもう少し時間をかけて検証されるべき問題なのかもしれない。
私も「大虐殺」と呼ぶべきものはなかったと思う。
そもそも、30万だとか、20万だとか到底あり得ない数字はともかくも、数万人が殺されたとして、あるいは死んだとして、その数だけをもってして「大虐殺」と名付けるべきなのか。
しかも、数万人の死因が日本軍による虐殺だという証拠はどこにもない。確かに、略奪だとレイプだのの証言はあるが、その証言が死んだ人数分ありわけでもなければ、一部の証言は事件の全貌を語り得るなどと思うのであれば、その人間は「単純」を通り越して「アホ」だとしか言いようがない。幕府山事件のように、戦時国際法上、グレーなものもあり、これを「大虐殺」に加えるべきかいなかも論争点になりえる。そもそも、戦時国際法上云々というのは、連合軍の日本占領政策の合法性も含め、おおよそグレーなものなのであり、そのそもそもの原因は戦時国際法それ自体にあるのである。
もし南京の例を、そこで日本軍のみの手により(つまり占領以前の国府軍の住民、友軍将兵への暴虐はあえて含まず)数万人が殺されたケースに「南京大虐殺」の固有名詞を関するなら、南京事件ほどグレーな部分のないほど明々白々たる戦時国際法違反である東京大空襲(当初から一般市民がターゲットであったことは今や米国自身の公開資料が明らかにしている)や広島・長崎への原爆投下にも「東京大虐殺」、「広島・長崎大虐殺」と名付けようではないか? ソ連軍による満蒙での暴虐行為やシベリアでのポツダム宣言違反の行為にも固有名詞を与えようではないか。ちなみに、ポ宣言違反したのは、厳密にはソ連だけではない。中華民国も大陸、台湾で同様の違反をしている。これは彼ら自身の公文書が「ゲロ」している。
数万人死んだというのであれば、まずはそのうち戦闘行為の結果なのか否か、そのうちのどれほどが戦闘員/非戦闘員だったのか、戦時国際法に照らして日本軍の不法行為の所産か否か、を資料をもって明らかにされるべきである。
そうした検証行為が不十分な現状において、「大虐殺はあった」と断定するのは、無責任極まりない行為だ。
ちなみに、慰安婦問題同様、しばしば「生き残り」の証言がもちだされるが、証言を無条件に事実として真実として認定する能天気がいまだこの世に存在することが私には信じられない。しかも、相手は、あの政治体制下に生きる人々である。前国家主席までもが、その父親が日本軍の手先であり、自身も日本占領下の南京で学生生活を送り日本語を専攻していた人物であったことを、自国民には対しては糊塗し、そのことを公言することを許さない体制の下での「「証言」であることを忘れてはなるまい。
谷川氏も具体的にいかなる理由で数万人と自信をもって断定するのか明らかにすべきだ。なぜならば、河村市長に対する批判も自分自身の「断定」が前提になっているからである。
一方、河村氏もアホだ。そうした発言を軽々しくして一体政治的に何のメリットになるというのか。それに父親の個人的経験のみをもって「大虐殺」を否定するのは児戯に等しい。日本軍の支配下にある都市で日本軍への敵意をむき出しにしていかに生きて行けようか。その点を考えもせず、だから大虐殺はなかったとは・・。
まあ、谷川氏も河村氏も、野良犬の喧嘩みたいなものだと思えば気にすることもないのだが、大の大人の発言としてはどちらも情けないものがある。前者はジャーナリスト、後者は政治家。まさにトホホである。
追記 ちなみに谷川氏はポルポトの虐殺に言及しているが、実は、これについてもその実態についてはやはり現時点で断定するのは問題かもしれない。虐殺と呼ぶべきか否かはさておき、ポ政権が大量の死亡者を出したことは間違いないのかもしれないが、その正確な実態については、ベトナムや米国の思惑というものが、どうも真相究明を難しくしているという指摘もなくはなく、やはりもう少し時間をかけて検証されるべき問題なのかもしれない。











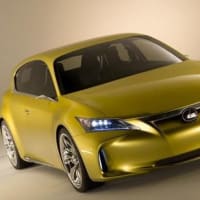











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます