
市民レポーターの浅野です。
SSH校というのは、スーパーサイエンスハイスクールのことで、
文部科学省の指定を受けて、大学や研究機関、企業などの協力を得ながら、
科学する心を高校生に根付かせ、世界に通用する生徒を育て上げようという活動です。
今月は、前回の続編をお送りします。
前回では、甲府南高校が取り組むSSH活動の経緯や現状について
SSH担当の雨宮先生のインタビューを中心にお送りしました。
今回では、前回に引き続いて雨宮先生のインタビューと、
6月23日、24日に行われた「緑陽祭」でのSSH活動の様子をレポートします。
☆雨宮先生のお話の続きです。☆
1.本校に入学される生徒さんはSSH活動を期待して入学されますか?
『本校のSSH活動は地元では大変有名になっていますので、
はじめからSSH活動を意識して入学してこられます。』
 1年から2年になるとき、文系・理系の選択をするのだそうですが、
1年から2年になるとき、文系・理系の選択をするのだそうですが、
今では理系希望者が大変増えているという事で、
SSH活動に対する生徒さん達の評価も高いようです。
2.課題研究の進め方について教えて下さい。
『まずテーマの選び方ですが、生徒自身の発想や、先輩方の継続、
文献や冊子類からのアイデアなどいろいろですが、
学校が主催する著名な先生方の講演会もテーマ選びに参考になります。
テーマが決まったら、研究の進め方や成果の発表の仕方など、
先生の指導を受けながら生徒さん達が立案していきます。』
****************************************
報告書の中の1ページ。
このページには何が書いてあるのかな?
「きのこに学ぶ木の食べ方」
え??、木の食べ方??
京都大学西村先生のご講演です。
****************************************
 ここで、ついていけない生徒さんはいませんかと質問したところ、
ここで、ついていけない生徒さんはいませんかと質問したところ、
実際の課題研究に対しては複数の先生が指導を担当しますし、
個人的な活動ではなくて、グループを組んで活動するので、
個人的な落伍現象はないとのことでした。
先生方の継続的な指導が大切だということですね。
イヤ~、先生方のご苦労が忍ばれます
成果の発表は、「英語で発表する」ことが目標だそうです
これはSSH校の重要な柱である「国際的に通用する人材づくり」に必須な内容で、
本校では「サイエンスイングリッシュ」という活動で展開しているとのことでした。
3.最後に甲府市との関わりについてお聞かせください。
『学校周辺の歴史・地理的な調査を行って、当時の地勢模型を作ったり、
リニア新幹線の新駅に望まれる開発形態を研究したり、
身近な研究テーマを通して科学的な考え方を体験しています。』
 インタビューを通して先生方のご苦労の一端を聞き出そうとしたのですが・・・
インタビューを通して先生方のご苦労の一端を聞き出そうとしたのですが・・・
「確かに大変です!」と一言。
その後は笑顔に隠してしまわれます。
その表情の中に、この活動に懸けた雨宮先生の自信と熱意が感じ取れました
☆先日、本校で「緑陽祭」が行われました。☆
若いエネルギーに満ち溢れた学園祭でしたが、
その中で、SSH活動を推進している4つの学部が共同で「合同ワークショップ」を展開していました。
「物理・宇宙部」「物質化学部」「生命科学部」「数理情報部」の4部が主催して、
来校者の小学生、中学生の皆さんに、科学を実際に体験してもらおうという企画です。
****************************************
ワークショップの入口です。
ジミな入口ですが、 なんとなく
「入ってみようか!」とそそる入口です。
****************************************
「歩くやじろべえ」って想像できます
普通やじろべえといえば、支点を中心にして左右のバランスをとる動きですよね。
それが歩き出す
う~ん 小学生は大喜び、付添いの大人はびっくり
小学生は大喜び、付添いの大人はびっくり

ワークショップのほんの一例です。
科学って面白いですね
ワークショップや、サイエンスショー(校庭で行われた科学実演)での様子を写真でご紹介します。
↓↓↓ 体験の皆さんは興味津々で、楽しいひと時を過ごしていただきました。
SSH学習の生徒さんたちの真剣な姿もありました。



 (以上4葉の写真提供:甲府南高校)
(以上4葉の写真提供:甲府南高校)
****************************************
今日(23日)の体験は終了しました。
手応えは十分です。
でも本命は明日(24日)!!
さっそく明日(24日)の体験教室の準備に
余念がないスタッフの生徒さん達です。
****************************************
この企画は今年初めて行われたそうです。
『体験して初めて科学の楽しみを知った来校者が沢山いて、
今年の企画に手ごたえを感じました』、
と嬉しそうに語るスタッフの生徒さんの話が印象的でした
『教科書の世界からほんの少し飛び出しただけで、
新たな楽しみがあるのでそれを体験してほしいと思いました』
との発言に、ワークショップを行う側もしっかりと学んでいると感じました。
この企画を影で支えた先生方のご苦労に感謝感謝・・・ですね
そのスタッフさんは3年生なので、これからはSSH活動よりも、受験体制に入るとのことでしたが、
将来科学系の仕事に就ければうれしいと抱負を話してくれました。
学園祭ですから、SSH活動の今までの研究成果もしっかりと掲示されていました。
↓↓↓ 立派な研究発表です。
いろいろな賞を受賞していることも知ることができました。



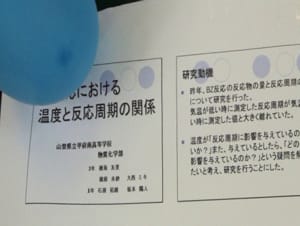
前回と今回を通して、甲府南高校のSSH活動の一端をご紹介しました。
国内のいろいろな発表大会で大きな成果を収めているお話もお聞きしましたが、
とてもここでは書ききれません。
ぜひ本校のHPを訪ねてみてください。
























 な湖上園。
な湖上園。


































 055-251-8161
055-251-8161 ということで、気温も高かったのですが
ということで、気温も高かったのですが



























