第二のモノサシ どういう歴史をもっているか
党をつくって88年間、なぜ一度も名前を変えずに活動できたか
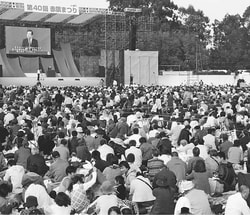 (写真)赤旗まつりの中央舞台でおこなわれた志位和夫委員長の記念演説 |
第二のモノサシは、どういう歴史をもっているか、ということであります。政党がどんな歴史をもっているかも、その値打ちをはかる大切なモノサシです。
日本共産党は、88年前(1922年)に党をつくって以来、「日本共産党」という一つの名前で通しています。日本共産党は、過去の日本軍国主義による侵略戦争や植民地支配に命がけで反対を貫いた唯一の政党です。だから戦後も、同じ名前で堂々と活動しています。なぜ名前を変えないのかという質問がありますが、なぜ一度も名前を変えずに活動できたか、ここが大事です(拍手)。ここをよく見てほしいと思うのです。
ほかの政党に歴史がないわけではありません。公明党は別にして、ほかのすべての党は源流を戦前の日本の政治のなかにもっています。しかし、保守政党も、「社会主義」を名乗った政党も、日本共産党以外のすべての政党は党を解消し、大政翼賛会に合流して、侵略戦争を推進しました。戦後、昔の名前では国民に顔向けができなくなり、すべての党が名前を変えたのであります。
私たちの党の歴史は過去の問題ではありません。いまに生きる生命力をもっています。今年に入って、それを実感した出来事を二つ紹介したいと思います。
「韓国併合」100年――併合条約を「不法・不当」ときっぱりいえる党
今年は、「韓国併合」100年です。私は、8月15日におこなわれた韓国民団主催の光復節中央記念式で初めてあいさつする機会がありました。そこで、「『韓国併合』100年と日本共産党の立場」について、つぎのように表明しました。
「『韓国併合』は、日本軍による繰り返しの侵略、王妃の殺害、国王・政府要人への脅迫、民衆の抵抗の軍事的圧殺によって実現されたものであり、『韓国併合条約』は、日本が韓国に対して、軍事的強圧によって一方的におしつけた不法・不当な条約です」
そうのべた瞬間、会場の全体から大きな拍手が起こりました。(拍手)
実は、「韓国併合」条約は「不法・不当な条約」ということを、日本政府はいまだにいえないのです。この条約は「すでに無効」としかいえないのです。1965年の日韓条約で、国交正常化をおこなったさい、植民地支配への反省をしなかったからであります。
「韓国併合」条約を「不法・不当な条約」ときっぱりいえるのは、党創立当初から朝鮮、台湾など植民地解放を主張しつづけてきた日本共産党ならではのものだと(拍手)、私は、あいさつをしながら、先輩たちの不屈のたたかいに大きな誇りを感じました。(拍手)
歴史に時効はありません。日本の政治は、この問題をいずれのりこえてこそ、韓国・朝鮮の人々とのほんとうに心通う友好がつくれると思います。
一つご報告したいことがあります。10月に入って、日韓議員連盟に日本共産党も加入してほしいという連絡がありまして、党議員全員が加入する手続きをとりました(拍手)。私が4年前に初めて訪韓したさいに、韓国の政界の側からは、「なぜ(日韓議員連盟から)日本共産党を除外しているのか。参加を認めるべきだ」という声がずいぶんあがりました。懸案の課題でしたが、ここでも大切な一歩前進があり、議員連盟の一員としても韓国と普通におつきあいができる関係になったことを報告しておきたいと思います。(拍手)
尖閣問題――侵略戦争に反対をつらぬいた党ならではの先駆的な見解
もう一つは、尖閣問題です。日本共産党は、すでに1972年に見解を発表し、尖閣諸島の日本領有は歴史的にも国際法上も明確な根拠があると表明してきましたが、10月4日に、さらにつっこんだ見解を発表いたしました。
新たに踏み込んだ中心点は、「日本は、日清戦争に乗じて尖閣を不当に奪った」という中国側の主張にたいして、日清戦争の講和を取り決めた下関条約と、それに関連するすべての交渉記録を詳細に分析し、「日本による尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾・澎湖(ほうこ)列島の割譲という侵略主義、領土拡張主義とは性格がまったく異なる、正当な行為であった」ときっぱり表明したことにあります。(拍手)
この見解は広い反響を呼んでいます。ある防衛省関係者は、「最も重要なのは、日本の領有の正当性を粘り強く国際社会に訴えていくことだ。共産党の見解に敬意を表する」とのべました。ある外交官のOBは、「政府以上のものだ」と評価してくれました。あるアジアの駐日公使は、「中国にこれだけのことをいったのは見事だ」と感想を語りました。読売新聞はコラムで「尖閣アピール“1番は共産党”」と報じました(拍手)。衆院での代表質問で、この問題での党の立場を表明しますと、議場から大きな拍手がステレオでおこりました(笑い、拍手)。翌日には外務省のホームページにも(尖閣問題の)詳しい解説がのりました。その多くの論点は、わが党の見解とそっくりのものでありますが、もちろん、特許権の侵害だなどとけちなことをいうつもりはありません。(笑い、拍手)
どうしてこういう見解をだせたか。私たちが、過去の日本の侵略戦争や植民地支配に最も厳しく反対してきた政党だからであります(「そのとおり」の声、拍手)。だから日清戦争で侵略で不当に奪ったのは台湾と澎湖列島であり、尖閣諸島はそれとは別の正当な領有だったと、きちんと論をたてられるのであります。
歴代政府の弱点――侵略戦争への反省がないと、正当な領有権の主張もできない
歴代日本政府のどこが問題か。歴代政府は、本腰を入れて、尖閣諸島の領有の正当性を中国政府や国際社会に訴える政治的・外交的対応をやってきませんでした。
1972年の日中国交回復の時にも、78年の日中平和友好条約の時にも、92年に中国が「領海法」で尖閣を中国領に含めた時にも、本腰を入れた領有権の主張をしていません。民主党に政権が代わっても、ここが弱いのです。
どうしてそういう弱点が生まれているのか。根本には、侵略戦争への反省がないまま日中国交回復をおこなったという問題があります。1972年9月の田中角栄首相と周恩来首相との国交回復交渉の記録が公開されています。それを見ても、侵略戦争への反省はないのです。「迷惑をかけた」という程度のものなのです。尖閣諸島については、田中首相が「尖閣についてどう思いますか」と尋ね、周恩来首相は「話したくない」と答えている。これだけのやりとりしかないのです。領有権の主張はまったくおこなわれていません。侵略戦争の反省がないから後ろめたいんですね。だから領有の正当性を主張できず、卑屈な対応になっていく。だいたい、反省がないと、侵略で奪った領土と、正当に領有した領土との白黒の区別もつかなくなってしまいます。
いまの私たちのたたかいも必ず未来に生きて働くという展望をもって
過去の誤りに正面から向き合い、誤りを真摯(しんし)に認めてこそ、アジア諸国との本当の友情を得ることができる。また、尖閣問題のように、日本の正当な権利を堂々と主張し、真の意味で国益を守る仕事をすることができる。私は、このことを訴えたいと思います。(拍手)
暗黒の時代に、命がけで反戦平和の旗を掲げた私たちの先輩たちは、そのたたかいがはるか先の21世紀の時代に、こういう形で生きて働くとは想像もしなかったことでしょう。しかし、正義と道理に立つものは必ず未来に生きて働く。これが私たちの確信であります。(拍手)
みなさん。いまの私たちのたたかいも、必ず未来に生きて働くという展望をもち、誇りをもって、ともに奮闘しようではありませんか。(大きな拍手)















