
 姪っ子メグ なんか、分厚い文庫本を読んでたわねぇ。なに?
姪っ子メグ なんか、分厚い文庫本を読んでたわねぇ。なに? キミオン叔父 ああ、平凡社ライブラリー『逝きし世の面影』(渡辺京二@1900円)。
キミオン叔父 ああ、平凡社ライブラリー『逝きし世の面影』(渡辺京二@1900円)。 ヒエー、文庫で1900円もするの?
ヒエー、文庫で1900円もするの? 最近、高額文庫本って結構、多いのさ。埴谷雄高の『死霊』なんかも、文庫版で登場したからね。これは1500円を切っていたと思ったけど。
最近、高額文庫本って結構、多いのさ。埴谷雄高の『死霊』なんかも、文庫版で登場したからね。これは1500円を切っていたと思ったけど。 で、渡辺京二さんって?
で、渡辺京二さんって? ああ、僕らの世代では、とても関心を持たれた評論家でね。熊本に在住しながら、日本の歴史の中のコンミューンやその挫折を描いてきたんだ。『小さきものの死』『神風連とその時代』『日本コミューン主義の系譜』とか、夢中で読んだよ。
ああ、僕らの世代では、とても関心を持たれた評論家でね。熊本に在住しながら、日本の歴史の中のコンミューンやその挫折を描いてきたんだ。『小さきものの死』『神風連とその時代』『日本コミューン主義の系譜』とか、夢中で読んだよ。評伝では、北一輝とか宮崎滔天とか。で、このころは、江戸近世の再評価が』中心的な仕事になってる。まあ、九州出身の一連のどこか反骨性と土俗性を持った思想家の流れというか・・・。
 石牟禮みち子さんとか森崎和江さんとか、九州は女性も骨太よねぇ。
石牟禮みち子さんとか森崎和江さんとか、九州は女性も骨太よねぇ。 で、この本はさ、江戸末期に異邦人が日本に来ただろ、彼らの膨大な日本についての文献を渉猟してさ、彼らに当時の日本や日本人がどう写っていたのか、どう評価されていたのかを、丁寧にチェックしてるの。明治の初期までは、江戸の幕藩体制のなかで貧しくも逞しく生きてきた名もない庶民や職人や商人の、文明があったんだよ。で、異邦人たちは、そんな日本をまったく想像していなくて、みんな驚愕してるんだ。
で、この本はさ、江戸末期に異邦人が日本に来ただろ、彼らの膨大な日本についての文献を渉猟してさ、彼らに当時の日本や日本人がどう写っていたのか、どう評価されていたのかを、丁寧にチェックしてるの。明治の初期までは、江戸の幕藩体制のなかで貧しくも逞しく生きてきた名もない庶民や職人や商人の、文明があったんだよ。で、異邦人たちは、そんな日本をまったく想像していなくて、みんな驚愕してるんだ。 あたしたちが歴史の教科書で習っているのは、士農工商の厳しい身分制、封建制のなかで、庶民は貧しく圧制を受けていたというものだったわよね。まあ、江戸とか大阪とか大都市では、町人文化が花開いたこともあったけど・・・。で、開国して、明治維新になり、急速に欧米化が始まるわけよね。
あたしたちが歴史の教科書で習っているのは、士農工商の厳しい身分制、封建制のなかで、庶民は貧しく圧制を受けていたというものだったわよね。まあ、江戸とか大阪とか大都市では、町人文化が花開いたこともあったけど・・・。で、開国して、明治維新になり、急速に欧米化が始まるわけよね。 だよな。でもこの本を読んでるとさ、たしかに異邦人が目にした日本は、貧しくはあったけど、人々は清潔で快活でとても幸せそうにみえるって口をそろえて証言してるんだ。
だよな。でもこの本を読んでるとさ、たしかに異邦人が目にした日本は、貧しくはあったけど、人々は清潔で快活でとても幸せそうにみえるって口をそろえて証言してるんだ。例えばさ、チェンバレンという人の言葉に代表させればね、「古い日本は妖精の棲む小さくてかわいらしい不思議の国であった」と。で、日本人の陽気さ、簡素さ、礼節、親和性、自由といった概念で、感歎のオンパレード!世界でこんな国はない、と。果たして西洋文明が入る必要があるかどうか悩んでしまう、とまで何人かが言っている。
 なんか、こそばゆいみたいな。でもそれはあくまでも、古い日本であって、西欧化した日本じゃないわけよね。
なんか、こそばゆいみたいな。でもそれはあくまでも、古い日本であって、西欧化した日本じゃないわけよね。 そうなの。その面影が残ったのは、せいぜいのところ、明治の中期ぐらいまでなんだよね。で、もうそんな文明は無くなってしまったわけさ。
そうなの。その面影が残ったのは、せいぜいのところ、明治の中期ぐらいまでなんだよね。で、もうそんな文明は無くなってしまったわけさ。 もしかしたら、現在のあたしたちがタイムマシーンでこの時代に迷い込んだら、同じように「妖精の棲む不思議の国」って思っちゃうかもしれないわね。
もしかしたら、現在のあたしたちがタイムマシーンでこの時代に迷い込んだら、同じように「妖精の棲む不思議の国」って思っちゃうかもしれないわね。




 そうか、日本に写真が入ってきたのは、残っている記録で言えば、第1号がペルー提督の黒船できた専属写真師なんだね。で、彼らがはじめて見る日本を記録したり、交渉相手の肖像撮影をしたりしたんだ。
そうか、日本に写真が入ってきたのは、残っている記録で言えば、第1号がペルー提督の黒船できた専属写真師なんだね。で、彼らがはじめて見る日本を記録したり、交渉相手の肖像撮影をしたりしたんだ。 長崎の出島とかさ、そこからポルトガルとかオランダの数奇者が持ち込んだのかと思ってたわ。
長崎の出島とかさ、そこからポルトガルとかオランダの数奇者が持ち込んだのかと思ってたわ。 で、その写真師のわざに吃驚仰天した日本人の中から、写真術を習う人たちが何人も出てきたんだな。江戸の鵜飼玉川という御仁なんかは、結構早くに写真館を開設して、肖像写真なんかを撮ってる。
で、その写真師のわざに吃驚仰天した日本人の中から、写真術を習う人たちが何人も出てきたんだな。江戸の鵜飼玉川という御仁なんかは、結構早くに写真館を開設して、肖像写真なんかを撮ってる。 写真で生命が吸い取られてしまう・・・みたいに思った人もいたのかな。いやいや、日本人は、たぶんとても好奇心が強くて、しかも新しいもの好きなところもあるからなあ。
写真で生命が吸い取られてしまう・・・みたいに思った人もいたのかな。いやいや、日本人は、たぶんとても好奇心が強くて、しかも新しいもの好きなところもあるからなあ。 初期はアンゲロタイプというのかな。ガラス版に卵白をつけたみたいな奴でしょ、まだ当然、プリントはできないわけだし、露光時間も長かったんだろうな。
初期はアンゲロタイプというのかな。ガラス版に卵白をつけたみたいな奴でしょ、まだ当然、プリントはできないわけだし、露光時間も長かったんだろうな。 ほらほら、撮影時に、動いてしまわないように、頭の固定台みたいなのも用意されてるわ。あとは、しかたないけど、みんな緊張してるよね、ヘラヘラ笑ってる人はいない(笑)。でもだんだん、遊び人みたいな伊達者が出てきて、ちょっとポーズをつけて流し目をするようになるのよね。
ほらほら、撮影時に、動いてしまわないように、頭の固定台みたいなのも用意されてるわ。あとは、しかたないけど、みんな緊張してるよね、ヘラヘラ笑ってる人はいない(笑)。でもだんだん、遊び人みたいな伊達者が出てきて、ちょっとポーズをつけて流し目をするようになるのよね。 記録写真としても、建築物や公共工事なんかも撮られているね。ポートレイトなんかが登場するのは、もうちょっと後だな。渡辺京二さんの『逝きし世の面影』じゃないけどさ、まだまだ写真機は高額のものだったけど、庶民の記録写真があると、面白いだろうなあ。江戸末期から明治初期にかけての異邦人の記録は、ほとんどがスケッチだったんだけどね。
記録写真としても、建築物や公共工事なんかも撮られているね。ポートレイトなんかが登場するのは、もうちょっと後だな。渡辺京二さんの『逝きし世の面影』じゃないけどさ、まだまだ写真機は高額のものだったけど、庶民の記録写真があると、面白いだろうなあ。江戸末期から明治初期にかけての異邦人の記録は、ほとんどがスケッチだったんだけどね。 ねぇ、あの写真機はその頃のものだけど、日本製ですって。こんなに美しく精巧につくれるのは、世界でも日本だけだ、とびっくりされたらしい。細工師やからくり師や工芸意匠も卓越してたものね。
ねぇ、あの写真機はその頃のものだけど、日本製ですって。こんなに美しく精巧につくれるのは、世界でも日本だけだ、とびっくりされたらしい。細工師やからくり師や工芸意匠も卓越してたものね。 渡辺さんの本にも書かれていたけど、貧しい家でも、そこで使われている食器や薬缶や鍋やといった生活道具が、とてもセンスがよくて、異邦人は競って買い取って、本国に送ったみたい。そこから、浮世絵の世界とは異なった意味で、工芸意匠としてのジャポネスクがまたブームになっていくんだね。
渡辺さんの本にも書かれていたけど、貧しい家でも、そこで使われている食器や薬缶や鍋やといった生活道具が、とてもセンスがよくて、異邦人は競って買い取って、本国に送ったみたい。そこから、浮世絵の世界とは異なった意味で、工芸意匠としてのジャポネスクがまたブームになっていくんだね。 そうかそうか。おじさん、その本読み終わったら、貸してよね。
そうかそうか。おじさん、その本読み終わったら、貸してよね。










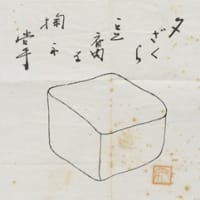


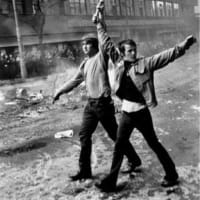



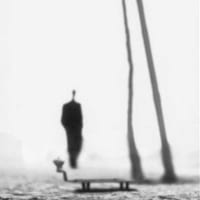

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます