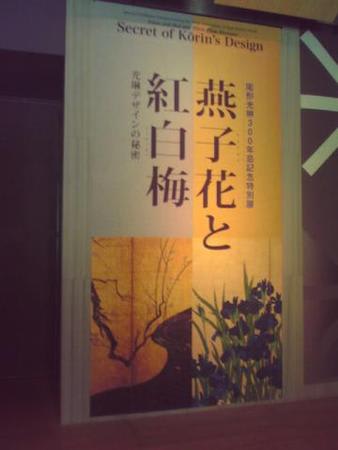今日はゴールデンウイーク最後の休日となりました。ダメ人間として何となく自堕落な連休を過ごしてしまいましたが、今日ばかりは美術観賞のハシゴをするというしっかりとした予定を立てて出かけることにしました。
先ず向かったのは表参道にある根津美術館です。ここでは今《燕子花と紅白梅》展が開かれています。今年は江戸時代中期に活躍した画師・尾形光琳の300年忌に当たるため、それを記念して、根津美術館所蔵の《燕子花(かきつばた)図屏風》と、静岡県熱海市にあるMOA美術館所蔵の《紅白梅図屏風》という光琳作の二つの国宝の屏風が、実に56年振りに一堂に会して公開されるという大変貴重な展覧会です。
《燕子花図屏風》は光琳円熟期の作で、伊勢物語の東下りの場面をモチーフに画かれたものと言われています。と言っても物語の登場人物等は一切画かれず、金地の画面には群青と緑青だけで簡潔に画かれた燕子花の花が咲き乱れているだけです。二双一対の屏風で、右隻は画面のほぼ中央を横切るように満開の燕子花が画かれ、左隻には画面の左上から右下に向かって斜めに燕子花が画かれ、右上の部分には余白が大胆に空けられています。
燕子花ではありませんが、オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホや、フランスの印象派絵画の巨匠クロード・モネをはじめとする画家達にもアイリスを描いた作品があります。モネのアイリスは静物画として周囲の調度品等も描かれていますが、ゴッホのアイリスは花瓶に活けられたアイリスの背景は、ただ鮮やかな黄色一色に塗られています。もしかしたらゴッホはパリ万国博覧会でこうした屏風画等を目にして、その大胆な構図に影響を受けたかも知れません。
因みにこの燕子花の花は、一説には型紙を用いて画かれているとも言われています。実際に見てみると同じパターンの花の固まりが何箇所かに見られ、それが画面に心地よい一定のリズム感をあたえています。
一方の《紅白梅図屏風》は光琳晩年の作とされています。金地の画面の二双一曲の屏風の右隻には勢いよく枝を天に向けて伸ばす紅梅の若木が、左隻にはゴツゴツと力強い幹から画面上に弧を描きながら地面スレスレに枝を伸ばした白梅の古木が、そしてその二本の梅の木の間にはSの字をいくつも並べたような『琳水(りんすい)』という独特の表現で水流を表した川が画かれています。
この屏風を生で観るのは今回が初めてでした。実際に観てみると、リアリティのある梅の木の幹や枝の表現に対して、まるでスタンプを押したかのように簡略化された梅の花との描き方の対比が実に特徴的でした。また屏風として立てることによって中央の琳水の川も両端の梅の木も想像以上の立体感になって、優美さだけでなく見る者に迫って来るような力強さも感じました。これは図録を見ただけでは分からないことでしたので、感動的な発見でした。
この二つの国宝が、いつまた同時公開されるか分かりませんので、この貴重な機会に是非足を運んで、天才画師光琳の息吹に触れてみて下さい。
先ず向かったのは表参道にある根津美術館です。ここでは今《燕子花と紅白梅》展が開かれています。今年は江戸時代中期に活躍した画師・尾形光琳の300年忌に当たるため、それを記念して、根津美術館所蔵の《燕子花(かきつばた)図屏風》と、静岡県熱海市にあるMOA美術館所蔵の《紅白梅図屏風》という光琳作の二つの国宝の屏風が、実に56年振りに一堂に会して公開されるという大変貴重な展覧会です。
《燕子花図屏風》は光琳円熟期の作で、伊勢物語の東下りの場面をモチーフに画かれたものと言われています。と言っても物語の登場人物等は一切画かれず、金地の画面には群青と緑青だけで簡潔に画かれた燕子花の花が咲き乱れているだけです。二双一対の屏風で、右隻は画面のほぼ中央を横切るように満開の燕子花が画かれ、左隻には画面の左上から右下に向かって斜めに燕子花が画かれ、右上の部分には余白が大胆に空けられています。
燕子花ではありませんが、オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホや、フランスの印象派絵画の巨匠クロード・モネをはじめとする画家達にもアイリスを描いた作品があります。モネのアイリスは静物画として周囲の調度品等も描かれていますが、ゴッホのアイリスは花瓶に活けられたアイリスの背景は、ただ鮮やかな黄色一色に塗られています。もしかしたらゴッホはパリ万国博覧会でこうした屏風画等を目にして、その大胆な構図に影響を受けたかも知れません。
因みにこの燕子花の花は、一説には型紙を用いて画かれているとも言われています。実際に見てみると同じパターンの花の固まりが何箇所かに見られ、それが画面に心地よい一定のリズム感をあたえています。
一方の《紅白梅図屏風》は光琳晩年の作とされています。金地の画面の二双一曲の屏風の右隻には勢いよく枝を天に向けて伸ばす紅梅の若木が、左隻にはゴツゴツと力強い幹から画面上に弧を描きながら地面スレスレに枝を伸ばした白梅の古木が、そしてその二本の梅の木の間にはSの字をいくつも並べたような『琳水(りんすい)』という独特の表現で水流を表した川が画かれています。
この屏風を生で観るのは今回が初めてでした。実際に観てみると、リアリティのある梅の木の幹や枝の表現に対して、まるでスタンプを押したかのように簡略化された梅の花との描き方の対比が実に特徴的でした。また屏風として立てることによって中央の琳水の川も両端の梅の木も想像以上の立体感になって、優美さだけでなく見る者に迫って来るような力強さも感じました。これは図録を見ただけでは分からないことでしたので、感動的な発見でした。
この二つの国宝が、いつまた同時公開されるか分かりませんので、この貴重な機会に是非足を運んで、天才画師光琳の息吹に触れてみて下さい。