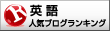「あこがれ」の父島入港と同じタイミングになりました。
PAPAYA号での、半日ツアーに参加していました。おが丸の出航に間に合うように
正午頃に戻る、ドルフィン・スイム、南島上陸見学、兄島海中公園(船長曰く
「竜宮城だと思った。)をまわれるコスト・パフォーマンスの高いツアーです。
http://cgi.members.interq.or.jp/blue/papaya/schedule/sche6.cgi
私は二年続けての参加でしたが、初めての船での硫黄等墓参訪島参加で父島も
初めての同行者が一緒でした。「南島も、兄島の海も見た方がいい。」と
半日ツアーに参加しました。
南島を見終わって、兄島に向かってPAPAYA号が北上している時でした。
同行者:「何か、見えませんか?棒みたいなのが。」
私 :「何か、棒みたいなのが、見えるみたいですね。」
同行者:「あれ、何ですかね?」
私 :「棒みたいなの、分かりませんね。何ですかね?」
同行者:「きっと、灯台みたいなのが沖にあるんですかね。そういうものですね。」
私 :「おそらく、灯台みたいなのでしょう。きっと。」
その時、心の中で 私 :「二見港沖合いに、灯台みたいなのなんか無いし、あんな、棒みたいな灯台みたいなものがあるはずがない。視力が悪くて、見えるか見えないかなので、あれが何かなんて、どうでもいいのだが。おそらく、海底油田調査掘削設備のようなものの、ごくごく小さな物。何か、調査でもしているモノだろう、、。どうでもいいが。」
そうこうするうちに、うっすらと遠くに一本の縦棒のように見えていたものが、
様子が変わってきて、横幅が出てきました。見える向きが変わったためです。
同行者:「違いますね。あれ。棒が一本ではないみたいです。」
私 :「見え方が変わったね。棒ではないみたいですね。」
PAPAYA号は、速いので、どんどん物体に近づき、対象が、ますますはkkりと見えるようになってきました。
同行者:「帆船のマスト。あれ船ですよ。」
私 :「マストみたいに見えますね。」
その時には、PAPAYA号船長から、「本日、入港する 帆船 あこがれが前方に見えています。」とアナウンスがありました。
写真は兄島から戻り湾内に入ったPAPAYA号から撮影した、到着直後の「あこがれ」
風をうまく制御して進む帆船の仕組みと、
小笠原丸船内ツアーの解説で聞いた、「スクリュー反転しません。」
という話とに、共通点を感じます。
風上に向かってでさえ前進できる風の制御の仕方と、
反転なしで細かい操船ができる小笠原丸。
「エンジョイ!島ライフ」の日記でも、「あこがれ」の入港から
大阪南港に帰るまでを
取り上げて報じてくれていました。
帆船、ヨット、ウィンドサーフィンなど、帆で風を扱う操船、スポーツに
は無縁ですが、私たちがいた日に、父島に来たということで、
親近感がわきました。
「あこがれ」という名前にも、ちょうど、私たちが故郷の島を訪問して
いたこととの因縁めいたものを感じました。
豊かだった島に、もう一度、住みたいという、戦前に住んでいた人。
祖父母や母が暮らした島を、もっともっと訪問したいと思う私たち。
激烈を極めた玉砕戦で命を落とした人たちの遺族の
何度も、近くで慰霊墓参をしたいという思い。
皆の硫黄島への あこがれ が、早く実を結べば良いなと思いながら、
きれいな帆船を、おが丸に乗り込む直前にも、眺めました。
PAPAYA号での、半日ツアーに参加していました。おが丸の出航に間に合うように
正午頃に戻る、ドルフィン・スイム、南島上陸見学、兄島海中公園(船長曰く
「竜宮城だと思った。)をまわれるコスト・パフォーマンスの高いツアーです。
http://cgi.members.interq.or.jp/blue/papaya/schedule/sche6.cgi
私は二年続けての参加でしたが、初めての船での硫黄等墓参訪島参加で父島も
初めての同行者が一緒でした。「南島も、兄島の海も見た方がいい。」と
半日ツアーに参加しました。
南島を見終わって、兄島に向かってPAPAYA号が北上している時でした。
同行者:「何か、見えませんか?棒みたいなのが。」
私 :「何か、棒みたいなのが、見えるみたいですね。」
同行者:「あれ、何ですかね?」
私 :「棒みたいなの、分かりませんね。何ですかね?」
同行者:「きっと、灯台みたいなのが沖にあるんですかね。そういうものですね。」
私 :「おそらく、灯台みたいなのでしょう。きっと。」
その時、心の中で 私 :「二見港沖合いに、灯台みたいなのなんか無いし、あんな、棒みたいな灯台みたいなものがあるはずがない。視力が悪くて、見えるか見えないかなので、あれが何かなんて、どうでもいいのだが。おそらく、海底油田調査掘削設備のようなものの、ごくごく小さな物。何か、調査でもしているモノだろう、、。どうでもいいが。」
そうこうするうちに、うっすらと遠くに一本の縦棒のように見えていたものが、
様子が変わってきて、横幅が出てきました。見える向きが変わったためです。
同行者:「違いますね。あれ。棒が一本ではないみたいです。」
私 :「見え方が変わったね。棒ではないみたいですね。」
PAPAYA号は、速いので、どんどん物体に近づき、対象が、ますますはkkりと見えるようになってきました。
同行者:「帆船のマスト。あれ船ですよ。」
私 :「マストみたいに見えますね。」
その時には、PAPAYA号船長から、「本日、入港する 帆船 あこがれが前方に見えています。」とアナウンスがありました。
写真は兄島から戻り湾内に入ったPAPAYA号から撮影した、到着直後の「あこがれ」
風をうまく制御して進む帆船の仕組みと、
小笠原丸船内ツアーの解説で聞いた、「スクリュー反転しません。」
という話とに、共通点を感じます。
風上に向かってでさえ前進できる風の制御の仕方と、
反転なしで細かい操船ができる小笠原丸。
「エンジョイ!島ライフ」の日記でも、「あこがれ」の入港から
大阪南港に帰るまでを
取り上げて報じてくれていました。
帆船、ヨット、ウィンドサーフィンなど、帆で風を扱う操船、スポーツに
は無縁ですが、私たちがいた日に、父島に来たということで、
親近感がわきました。
「あこがれ」という名前にも、ちょうど、私たちが故郷の島を訪問して
いたこととの因縁めいたものを感じました。
豊かだった島に、もう一度、住みたいという、戦前に住んでいた人。
祖父母や母が暮らした島を、もっともっと訪問したいと思う私たち。
激烈を極めた玉砕戦で命を落とした人たちの遺族の
何度も、近くで慰霊墓参をしたいという思い。
皆の硫黄島への あこがれ が、早く実を結べば良いなと思いながら、
きれいな帆船を、おが丸に乗り込む直前にも、眺めました。