発達障害、学習障害や、読み書きが苦手な子どもたちのための
英語と国語のクラスを開いています。
私は英語の教員なのですが
今回なぜ”国語”を始めたかというと、
これまで英語を指導してきて
「なぜできない?国語が足を引っ張っている?」
という印象をずっと持っていました。
そのうち、子どもたちが根っこに抱えている問題が、
母語である国語との関係で見えてきました。
わたしたち英語を教えている者は、つい、
文法の教え方、単語の覚え方、楽しい外国語の歌やチャンツ、ゲームなどに一生懸命になって、
「この子がなぜ英語が上達しないのか」という根元をあまり見ていない気がします。
気のせいかもしれません。
少なくとも私は、そういうことは「英語の指導法やアプローチでなんとかなる」と
思っていました。
ですが、少し前にブログで書いたように、学習者の母国語習得と、
外国語の習得には深い関係があります。
また、母国語で抱えている問題は同じように外国語習得の際にも現れてきます。
そして日本語を母語とする学習者には、
アルファベットという、音素的に複雑な文字体系を学ぶというチャレンジがあります。
そもそも、
なぜ子どもたちが「読めない書けない話せない」のか?
それを無視したまま、英語が伸びるのか?
根本的な問題は、全教科に同じように影響しているので
やはりどの教科を担当していても、
知っておかなくてはいけない知識と技術があると思っています。
「わかった!」「できた!」っていう子どもの喜びや満足な顔を
見せてもらえるほど嬉しいことはないですねえ・・・
それが明日の授業への原動力になってます!
さて話を戻します。
英語の文法の時間は、主語や目的語といった語の意味や
品詞などの知識が大きく文法理解を助けます。
その下敷きになるのは、やはり母語の構造の理解です。
日本語で「名詞を集めなさい」と言っても、集められない子が
どうやって英語の名詞の使い方がわかりますか。
動名詞や、分詞、関係詞が出てきたときも、
まず基本単位の品詞の理解がなければ、
長文の構造などはとてもとてもわからないと思いませんか。
文法だけではありません。
小学3年生で日本語のローマ字を入れるのであれば、
しっかりと日本語は子音と母音で成り立っているということや、
子音ひとつひとつの音についてもっとしっかり教えるべきです。
子音と母音を足すことで、日本語の音はできているという理解があるだけでも、
中学校に入って、フォニックスをもし習う機会があれば
読みがかなりスムーズになります。
読解も、読書が好きな子は、英語の読解も得意です。
もともと、国語の読み書きが苦手というだけで、本から離れてしまっていると
数年後には、理解力の差につながってしまいます。
上記にあげたようなことは、学習障害があるからといって
後回しにしていると、本来の知的レベルよりも学習がどんどん遅れてしまいます。
ですが、比較的第三者が手を貸しやすく、教えやすい部分でもあると思っています。
チャレンジ国語教室は、
英語教室でできないことをフォローしたいと思って開きました。
英語の時間に国語の文法はできませんから・・・。
まずは、母国語の文法意識を鍛え、書きにつなげるために
”ガウディア”という教材を使わせて頂くことにしました。
日能研と河合塾が開発した、考えて気づかせる工夫が一杯の教材です。
それも、個別、分野別に対応できるので、
集団でも個別指導に近い効果があると思っています。
そして、今回はみんな「書く」ことが極端に苦手なので、
予定していませんでしたが書字指導を入れていくことにしました。
書字指導って、やり方は何通りもあります(ネットでも色々探せば出てきます)。
子どもの得意な覚え方・学び方に合わせて、「これはどうかな?」と出してみます。
そしてしばらくやらせて、合っているかどうか、子どもに確認します。
合っているようだったら、それでOK。
「つまんない」とか「無理」という言葉が出てくれば、違うのを試させます。
これは、決して甘やかしているのではありません。
”学び”は、本当はとてもとても個人的で主観的な活動だと思っています。
他人が、「これがいいだろう」と、一方的に
押しつけられることしかやらせてもらえず、
それを「学習」だと思っている子どもに、
もう一度、
「自分はどう感じるのか」を
しっかり意識してもらいたいって思っています。
だから、決めるのは子ども自身。
そして、選択するのも子ども自身です。
自分で自分の学びを客観的に見れるようになって、
自分でコントロールできるようにになって欲しいのです。
読み書きは、基本的に「五感」を意識して、指導します。
この子は、目からの刺激が一番強いかな?
だったら、イメージ化する方法でやってみようか。
あるいは絵を描かせる、造形させる・・・
運動が入るともっと覚えやすいようだったら、
指でなぞる、空に書かせる・・・
色をつける、
紙ヤスリのようなざらざらした感覚を加える、
語呂合わせのような言葉でつなげる、
などなど。
ですが、チャレンジ国語教室、始まったばかりでまだそこまで至っていません。
夢は一杯なんですが、これからで~~す。
最初は、子どもを見る、話を聞く、人の手がたくさんいります。
先生一人では、時間がかけられなくて、思ったように進まない。
いつも同じ悩みを抱えています。でもがんばるぞ。
前回の授業では、課題図書をみんなで順に読みました。
『佐賀のがばいばあちゃん』です。
これは、大人用の単行本と、小学生用にルビを売って漢字も減らしたバージョンと出ていて、
子どもたちに「どっちを読みたい?」と聞いて選んでもらいました。
主人公の気持ちがよく表現されているのと、
年齢も近いので、彼の苦労も共感しやすいかな。
佐賀弁の面白さ、また、戦後という時代背景についても
子どもたちが知りたいことがたくさんあります。
なにより、ばあちゃんの素晴らしいメッセージを子どもたちにも届けたかった。
これは、ゆっくり読んでいきます。
次回、宿題ちゃんとやってきてくれるかな?
ディスカッションできるかな。
楽しみです。











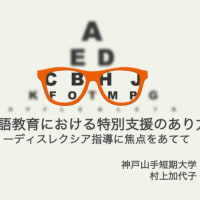



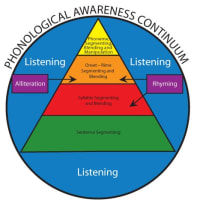
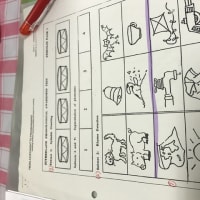



今日のお話
学校での国語教育課程そのものの
問題と共通するように思いました
国語の時間に文法を大事にしてくれる
先生をあまりお見かけしません
文法がわからなくても読めている
(先生目線で)から
必要性を感じにくいことが
理由なのかなと思っています
でもなんとなく読めるってのと
意図的に言葉を分解したり
くっつけたりして
自力で文章を再編集したり新たに
作り出したりってのとは
だいぶ違うと思いますし
実際文部科学省の指導要領も
そちらをゴールに設定しているように
読めます
それと現場の先生との
文法の役割への意識のギャップが
大きいなと感じていました
そしてそのまま中学へ進学して英語が
始まる
それまで文字を表現したい内容と
文法に沿ってセレクトするという作業を
無意識でしかやってこなかった子は
そらつまずきますよね
変なことしてるなあと
前から思っていたので
英語の教室が国語をすること
大賛成です
外国語語を教える立場から見て、母語の理解があまりにもなさすぎることが困る、というところを補いたいだけなんですよ。
たくさん読んで書けば国語力アップするのは当たり前なんですが、それができない子にできるようにするのも国語でないと、ダメなんです。英語じゃないんです。
「チャレンジ英語」を支えるための、「チャレンジ国語」ですが・・・さて結果はどうなるでしょう。