
批評家の宇野功芳氏がその著作のなかで、ショパンならワルツがいちばん好き、とおっしゃっていたことが以前ありました。
宇野先生とは意見がことなることがわりに多いイーダちゃんなんですが、先生のこの見解にはまったくもって大賛成---本をほっぽりだして思わず拍手を送りたくなったくらい、このときは嬉しかったんです。
批評家の先生ともなると意見をいうのにもいろいろ体面とか面子とかややこしい事情が絡んできそうじゃないですか。
たとえば、ショパンなら「ソナタ3番」がいいとか「幻想ポロネーズ」が格別だとか、そんな風に答えたほうが多分しかめっつららしいマニア連は感心してくれやすいんじゃないかと思うんですよ。
ところがこのとき先生はそうされなかった。
受け狙いめいたことなんかてんでいわず、非常に正直に自分の気持ちを打ち明けてくれました。
素晴らしい、いいですね、そういうひとが僕は好きです。
で、フレデリック・フランソワ---グールドはショパンのことをこう呼ぶんですよね、この衒学趣味が気に入ったんでちょっと盗用をば---の作品なんですが、イーダちゃんの好みも宇野先生といっしょで、とにかくワルツ! ショパンではワルツがいっちゃん好きなんです。
ショパンのワルツってホントにいいですもん。
あれって心のなかから湧きでてきたばかりの獲れたてインスピレーションを、そのまま切って握ってカウンターに「はい、お待ち!」の世界じゃないですか。
力みがなくて、へんな気取りもぜんぜんなくて---。
なるほど、ワルツはポロネーズやバラードなどの大作とくらべると、貴族のサロンなどで受け入れられやすいように---特に地元有力者の奥さん連中あたりをくらくらっと一瞬でたらしこめるように!---なるたけキャッチーに分かりやすく書かれているっていうのは事実です。コケテッシュな媚びテクも、思わせぶりな流し目も、それこそもうてんこ盛り状態。でも、ショパンって凄い盛りつけ上手のシェフだからほとんど胃にももたれない、そのへんすっごくワザ師的に書かれているわけなんですよ。
それは、唖然とするほど見事な手腕というしかない。
ところがこのワザ師ぶりにケチをつけるひとがいる、効果を狙いすぎててあざとい、それに、構成が単純すぎるっていうんですよ。
----構成が単純じゃなぜいけないんでせう?
僕は、複雑で深遠なほうが藝術として上だなんてまったく思いませんが。
僕にいわせれば、ショパンのバラードなんかのほうがむしろ装飾過多ですよ。それとスケルツォも。あれは、たぶんベートーベンからの悪影響じゃないのかしら?
ショパンみたいな天性のメロディー・メイカーには、ほんとは形式なんか通り一遍程度のもので充分なんですよ。
ベートーベンは当人もいっていたようにメロディー・メイカー・タイプの音楽家ではなかった、だもんで、その短所を補うためにいろいろ頑張っていたら、ああした形式で音楽をがちがちに締めあげるっていう独自路線をたまたま発明してしまった、というだけのもんであってね。
あの芸風はあくまで彼一代限りのもの、あんな理詰めで窮屈な、拘束器具みたいな重苦しい枠組のなかに、メロディー・メイカーたちの自由でみずみずしい歌心を押しこめちゃあイカンですよ。スポイルされ音楽嫌いになっちまう。
武術的な視点からいわせてもらえば、ショパンのバラードはちといかんですな。
あれ、構えが大きすぎるし、力みもそうとう入ってる。実力でいえばせいぜい初段クラスの感じ。むろん、稀有の素質と天才をもっているのは認めますが、でもこーんな大仰な、これからさあ襲いますよ、みたいな攻撃じゃ見え見えもいいとこ、これじゃあ勝負には勝てません。
ワルツのが厄介ですね---いかにもこっちは手強そう。
なによりワルツはフットワークがいいですよ。それに、軽みとしなやかさとが実にうまく同居してる。要するに限りなく達人ぽいわけ。
こんな塩田先生みたいなの相手にするのはいやだなあ、はなから勝てっこないですもん。(^.^;>
てなわけでやっぱりショパンはワルツでせう。(ト独断的にほくそ笑む)
で、ワルツといえば、でてくるのはフランスの大御所であるところのこのひと、アルフレッド・コルトーかと。
徒然その1で紹介したホロヴィッツよりもさらに古い時代のひとですけど。
今回は、ガス灯時代のピアノの詩人---マエストロ・コルトーのお話です---。
アルフレッド・コルトーは、1877年の9月20日、スイスのニオンの生まれ。
ドゥコンブとディエメっていう、なんでもショパンの最後の弟子だったというひとにピアノを習ったそうです。
でも、ピアノといっしょにこの人、若いころは指揮もやってて、フランスでワグナーの「神々の黄昏」や「トリスタン」「パルジファル」を初演しちゃったりもしている。
要するにピアノだけじゃない、幅広い音楽性をもっていたってわけですよね。
チェロのパブロ・カザルス、ヴァイオリンのジャック・ティボーと組んだ「カザルス・トリオ」はあまりにも有名。
ただ、第二次大戦でフランスがドイツに占領されたとき、このひと、占領軍のヴィシー政権に非常に協力的だったんですよね。
だもんで戦後は音楽界から追われたり、カザルス、ティボーからも絶縁をいいわたされたり(もっとも、後年に友情は回復したようですが)……けっこう苦い目にもあってるおひとです。
以上がダイジェストの経歴なんですが、こうした百の能書きよりやっぱ一の現物。
というわけでここの冒頭にアップしたコルトーの写真をもういちどじっくりとご覧あれ。
これって凄くないですか? 僕は個人的にこれを、霊感がひとの脳髄をずるずるーっと音を立てて上ってくる瞬間をまざまざと捕らえた非常に貴重なフォトだと思っているのですが。
とても美しい写真ですよね---これは、コルトーが自分で設立したパリのエコール・ノルマル音楽院で、生徒に音楽の教授をしている際の映像です。ピアノを弾きながら、音楽について喋っているところ、まあ弾き語りみたいなもんですかねえ。弾いてる曲はシューマンの「子供の情景」のなかの1曲<詩人のお話>---。
で、コルトー教授は、これを弾きながら「ここは迷いながら、何かを探すように……」とか、「さあ、最期は夢のつづきに浸ってください……」とか詩的なことを呟きつつピアノの和音を奏でているんですが、そのピアノも言葉もどっちとも、なんというか超絶品なんです、これが……。
文字で書くと、「えー ちょっとくさいよ」とかいわれちゃいそうだけど、見てもらえば必ず分かるから。
スローな曲なのにもの凄い迫力なんです。貴方のなかの「子供の情景」観ががらがらと音をたてて崩落していくこと、間違いなし!
ま、これはジョークですが、ぜひにも一聴をお薦めします。
ちなみにこの貴重映像、ワーナーヴィジョン・ジャパンから出ているDVD「アート・オブ・ピアノ-20世紀の偉大なピアニスト-」のなかに収録されております。こんなプログを見ているよりも、いますぐ銭をもって大都市のCD屋に走れ、と僕はいいたい。金額は3,800円くらいだったと思います。
たしか youtube でも視聴可能だった気がします---。
コルトーの特徴をひとことでいうなら、「即興的な感興を思いきり生かした草書体のピアニズム」とでもいうべきでせうか。
もう、ルバートかけまくりのピアノなんですよ。いまじゃかえって誰もこんな風には弾けないはず。
あと、特徴的なのはミスタッチ---このひと、ミスタッチがとても多いの。♪ツララツララでしっ……ツララツララげしっ……。コンクール予選落ち100パーセント間違いなしのピアノなんですが、なぜかこのがたぴしピアノがとてもいいんです。
ミスタッチまでが音楽的なんですよ---聴いてるうちに黄昏色のノスタルジーが胸いっぱいに広がっていくんです。
ラフマニノフはコルトーがそうとう好きだったみたいですね。
「ねえ、ゴロヴィッツ」とある日彼はラジオを聴きながら若いホロヴィッツに向けていったそうです。「このコルトーってピアニストはうまくないけど、とても音楽的じゃないかい---?」
ふわーっとコルトー発のむせるほど濃い詩情に包まれたら、たぶん、貴方はもう一生コルトーから離れられなくなると思います。
ただ、コルトーの欠点は、音がわるいこと!(xox;>
このひと、録音がひどいんですよ---まあ、全盛期が1930年代ですからむりもないんですけど---率直にいって、いまのデジタル録音に慣れたひとはとても聴いてられないかと。
そんなコルトーのベストテイクを探してイーダちゃんがみつけてきたのがこれ、
コルトー77才のときのショパンのワルツです。
変ニ長調「小犬のワルツ」作品64-1 と 変イ長調「別れのワルツ」作品69-1
これ、世界中にありとあるショパン録音のなかでの最高峰ではないか、とイーダちゃんは思っています。
特に「小犬のワルツ」なんて、これ聴いて僕泣きますから。マジで。(ToT;>
「小犬のワルツ」で泣かせる……そんな荒業をかませるピアニストは世界広しといえどもたぶんこの方のみでありませう。
なお、前述したショパンは---1954年の5月---コルトーがEMIのスタジオで録音したものです。(^^;












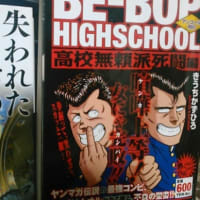




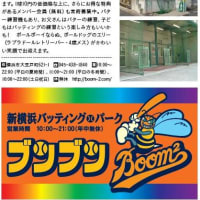

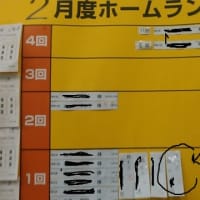
最近はジョン・レノン(ビートルズ)を久しぶり~に聴いたり、ショパンのワルツを練習したり・・・自分で弾くなら5番が好きかな。
イーダちゃん、ギターも上手そうですね。
今週末は、鳴子温泉に行ってきます。天気は良くないみたいですね。冒険をするつもりだったので。
ワルツの5番ってAフラットのやつですよね?
音がずれたり、それからコーダがとても派手なやつ---あれはまちがいなく傑作だけど、あの難しそうなのが好きだなんてスゴイな。僕はピアノはダメなんで羨ましいです。
鳴子に行かれるんですって?
気をつけていってらっしゃい、です。僕も鳴子は大好き。niftyのクチコミ楽しみにしていますね。ただ、冒険は天候をよく見てご用心。(^.^;>
ここまで僕と好みが合ふひとを、初めて見つけました。
あまりに嬉しいので、コメントさせてくださいね。
まづ、僕もショパンならワルツがいちばん好きです。
とくに好きな曲となると、34-2、64-2、69-1、69-2、70-1、70-2、・・・・・・。
ほぼすべてになってしまひますね(笑)
次に好きなのが、ノクターンかマズルカかな。
プレリュードもすてがたい。
スケルツォやバラードは、ほとんど聴きません。
ソナタも、もう久しく聴いてないですね。
「ベートーベンの悪影響」、おっしゃる通りだと思ひました。
”大作”で好きなのは、舟唄くらゐでせうか。
あれは傑作だとおもひます。
晩年のショパンの”悟り”ですよね。
ワルツを寿司にたとへたふみを、僕は初めて読みました(笑)
なるほど、たしかにあれは新鮮だ。
気取りも衒ひもありません。
塩田先生にたとへたふみも、初めてです(笑)
なるほど。
そして、コルトー先生!
あの濃い感じ、たまらないですよね。
もう10年以上のつきあひになりますが、いまだに時々はCDに手をのばしてます。
今も、コルトーが流れてゐます。
ノクターンです。
大好きなのは、55-2。
ちょっと弾けもしますが、むつかしい。
今日は物憂げな雨なので、27-1も合ひますね。
これは私のレパートリーに入ってます。
濃い音がほしい! といふ箇所を、コルトー先生はドンピシャで濃く弾いてくださる。
それも、ねっとりとルバートをきかせて。
55-2は、もともとスッキリした曲なんですが、そのスッキリをねっとり熱く弾けるのは、さすがだと思ひます。
コルトーのショパンを聴くと、心のほむらが立つかのやうです。
イーダさんのおっしゃるとほり、もう一生手放せませんね。
まだまだ御話はつきませんが、今日はこのあたりで。
またブログ読ませてくださいね。
僕も、あんまり好みが似ているんで、なんか、嬉しさ半分/びっくり半分のような感じです。(笑)
変ホ調のワルツ、いいですね---僕もあれは大好き。
ふとまろびでた言葉を次々とつむいでいくようなあのワルツは、僕も、コルトーのフェヴァリアットのひとつです。
フランソワとかピリスとか、ほかにもいろいろ聴いたんですけど、あの「朗々としていつつ繊細」みたいな独自の自由な感覚は、いまだにコルトー以外のピアニストからは感知できておりません。
27-1もいいですね。
僕の座右のノクターンは、37-1かなあ?
誰の演奏で聴いてもあれは染みるのですよ。
ノクターンにマズルカ、プレリュードに舟唄---僕もショパンの真骨頂はそこにあると大賛成です。
ただ、ふしぎなことに、ピアノをやってる友人にコルトーを薦めても、なぜか反応あまりないんですよねえ。
いまのメソッドとはあんまりちがうから、戸惑ってしまうみたい。
あれにこめられた「ポエジー」を聴きのがしてなんの音楽教育かと僕なんかは思うのですが、どうもピアニスト連中には、ポエジーよりスポーティーなメカニックのほうにいってしまいたがる性癖があるようですね。
塩田先生をご存知とはなおさら嬉しい。
万葉のころと同様、歌っていうのは、青空にむけて朗々と歌うのが正式の作法だと思うんです。
聴いていてコンクールの会場やスタジオの密室なんかが連想される録音は、僕は苦手かなあ。
僕も今度長友さんのブログに遊びにいかしてもらいますね。
あ。僕、人麿狂デス(^o^)/