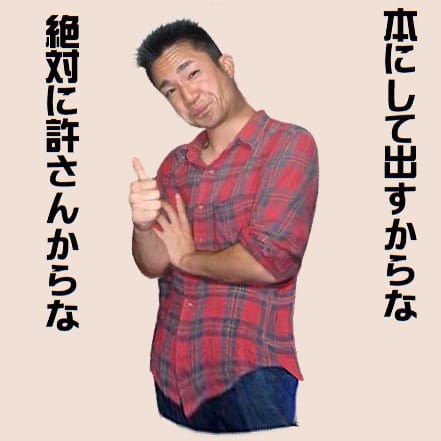
※この記事は、およそ10分(課金コンテンツを加えると15分)で読めます※
さて、続きです。
もし前回記事、動画をご覧になっていない方がいたら、そちらの方をご覧いただくことを強く推奨します。
【反フェミはこれ一本でおk!】風流間唯人の女災対策的読書・第11回『「許せない」がやめられない』(その2)【ゆっくり解説】
・第五章 弱者憎悪がやめられない
――さて、実際の本では第五章のタイトルは「ジェンダー依存がやめられない」。これに短い終章が続き、結論めいたことが書かれているので、まとめて論じましょう。
今までさんざん好き勝手に罵ってきた本書ですが、先にも述べたように、ぼくはかなり最後の方まで、少々の期待と共に本書のページをめくっていました。
本書はテーマをジェンダー関連のものに限っており、序章においてそれは、「万人が当事者性を持ち得る問題だから」と説明されます。
これは本書でやり玉に挙がる「ツイフェミ」や「ツイクィア」には大いに当てはまりましょう。しかしそれはフェミニズムというものが最初から内包しているものです。
先にも述べたとおり、「個人的なことは政治的なこと」というのがフェミニズムのキャッチフレーズです。男と女を雑に分け、男に悪とのレッテルを(まさに坂爪師匠がそうしているように)貼り、女性側に属する自分はいついかなる場合も正義だと言い続けてきたのがフェミニズムなのです。フェミニズムは、「ジェンダーに依存する資産、即ち女子力を持たない女性が、何とかジェンダーに依存しようとする過程」そのものでした。
また一方、これは「ミソジニスト」とやらには当てはまらないでしょう。「男はエラい、女は下等」などと言っている「アンチフェミ」なんて、少なくともぼくはそうそう見ませんから。
つまり、この「ジェンダー依存が止められない」というのは、どう考えても「ジェンダー強者」、「一人称強者」の女性にこそ多く当てはまることは疑い得なく、中でもフェミニズムはその最悪の形でした。となればこのタイトル自体に、フェミニズム批判が内包されているはずであり、そこに一定の期待をせずにはおれなかったわけです。
まあ、そんな期待は無残に打ち砕かれ続けたわけなのですが……。
「当事者性の二次利用」、「怒りの万引き」といったキーワードもそうで、まさにフェミニストを斬る鋭利なワードであり、それらを不用意に振り回して、全てブーメランになって自分自身を斬り刻んでいるというのが、本書の最大の特徴です(何しろ本人もセックスワーカーでもないのに、その位置からの物言いをしているのですから)。
いえそもそも、「男は当事者になれないジェンダーであった」→「ところが人権意識が浸透し、また何より男の立場が本当にどうにもならないほど弱くなったことで、とうとう、男もまた当事者性、一人称性を持ち始めた」というのが今、ネット上で起こっている現象なのであり、しかし坂爪師匠がそうした経緯を理解しているかははなはだ疑わしい。何しろ男がちょっと文句を言う度、本書ではそれらを全て「ミソジニー」の一言で切り捨てているのですから。
ぼくは本書を読んでいて、「ネトウヨ」という言葉が出てこないのが、何だか不思議でした。が、この「ジェンダー依存」の章の最後でようやっと「彼ら彼女らはネット右翼と同じだ(282p・大意)」とのフレーズが登場します。ネトウヨが自分が日本人だという生まれながらにして持っている属性しか誇るものがないのと、ジェンダー依存症者は同じなんだそうな。
まあ、いずれにせよ「当事者性」を錦の御旗にするのは「マイノリティ」の代表をもって任ずる者のお決まりの戦術です。だからそこを批判していれば、ぼくは坂爪師匠にも一定の評価を与えることができるのですが、本書では度々「ツイフェミは当事者でもないのに文句をつけた云々」といった記述が顔を見せ、要は「偽者が当事者を名乗ることは本物様に失礼なのでけしからぬ」なのか、「当事者性を特権として振り回すのは好ましくない」なのかが最後まではっきりしません。本人も、わからないまま筆を進めているのでしょう。
佐賀県のネットやゲームを制限する案を盛り込んだ条例についても、語られます。前章では表現の自由クラスタの味方に思えた坂爪師匠です、さぞかし佐賀県の旧態依然とした偏見に塗れた見識を鋭く切ってくれるのだろうな……と期待していると、何とそれに対し、基本、賛成ムードなのです。
例によって自らのスタンスについては曖昧なのですが、ともあれこのトピックスを「ゲーム依存は病気だ」という話につなげていき、同時に「SNS依存もまた」と言い出します。
ジェンダー依存の背景にも、発達障害や精神疾患などが隠れていることがある。ツイフェミ及びアンチツイフェミには、「発達障害」「毒親」「メンヘラ」といった属性をプロフィールに明記しているアカウントが散見される。
(254p)
(254p)
はい、とうとう「俺の気に入らない者は精神病なのだ」とまで言い出しました。
正直、どんなツイフェミの「男死ね」発言よりも、坂爪師匠の筆致の方が、ぼくには胸糞悪いです。
また、ツイフェミのプロフには確かにそうした傾向がある気はしますが、アンチツイフェミの方はどうでしょうか。少なくともぼくは、そうした印象がありません。
つまり、病気なのはツイフェミの方だけでは……?
いえ、もちろんここには大前提として、プロフにそうしたことを書きたがるか否かのジェンダー差がまず、横たわっているのですが。
後はお定まりの「あなたのジェンダー依存チェック」。
ツイッターで「嘘を吐いたことがある」人は「ジェンダー依存」要注意w
また、「togetterをまとめ(られ)たことがある」人もまた、要注意だそうです。
そもそもtogetterは別に議論色、攻撃色の多いものばかりではないのですが、それには言及されません(当然、坂爪師匠自身がそうしたものしか見ていないからなのでしょう)。
さらにそもそも、坂爪師匠は「ジェンダー依存」という言葉をひたすら振り回しますが、ジェンダーとは全く関係のない、例えば政治関連の議論、或いは趣味についての議論で熱くなってる連中についての言及は、全くありません(当然、坂爪師匠自身が「ジェンダー依存」であるがため、他のトピックスなど目にも入らないのでしょう)。
「そこは本書のテーマ上、省略しただけであり、文脈でわかろうから、言葉を尽くさなかっただけだ」ということなのかもしれませんが、とにもかくにも本書は全体的に説明不足。例えば本書のタイトルがずばり『ジェンダー依存』であれば、まあ、わからないでもないのですが……。
また、この病気認定についても例えばですが、坂爪師匠が臨床医で、「最近、こういう症例が増えていて、そうした人たちはネット依存で……」といったところから話が始まるのであれば、一応傾聴に値しましょう。
しかし端っから、最初っから、坂爪師匠は自分の気に入らない連中を扱き下ろし、とうとう病気だと言い立てだしたというだけなのです。香山リカ師匠が診察すらしていない(自分の気に入らない)有名人を勝手に「診断」して顰蹙を買ったことがありますが、坂爪師匠は「精神科医」ですらないのだから、それ以下でしょう。
坂爪師匠は「社会運動のソシャゲ化」との説をぶち上げます(251p)。
社会運動は青二才たちの「はしか」であったが、SNS時代にはは同志と群れ、NGOを作ることができる。ソシャゲが終わらない娯楽であるように、社会運動もまた、というわけです。が、先にも書いたように、この人の立場でそれを批判するのは、どうにも理解に苦しみます。
以前の章でも時々見られたように、坂爪師匠は幾度も社会運動を批判してみせます。
これは師匠の「ツイフェミ」評と構造が全く同じです。「ツイフェミ」に向けて投げたブーメランが自分を含むフェミニスト全体を完全否定しているのに、しかしご当人だけはそれに気づかず、スケープゴートをできたと胸を撫で下ろしている……この幾度も見た「ブーメランによる自死」が、「社会運動」を語る場においても展開されているのです。
何しろ終章において、坂爪師匠はいきなり、自分はネットに溢れる「許せない!」との声を社会運動に昇華させますた、などと自慢を始めるのですから(291p~)。
風俗関係者に給付がなされない法案(曖昧な表現ですが、恐らくコロナ関係の件でしょう)を、ネット署名で改めさせたぞとおおせなのですが……あれ、ということは碧志摩メグをネット署名で叩いたのも正義なんですかね? と慌てて読み返したら、やっぱり否定的に書いてありました。
全くもって不可思議……と言いたいところですが、この節のタイトルは「「許せない」という怒りを「国に対する声」として昇華させる」。
なあんだです。
「国に文句をつけるのであれば正義」が坂爪師匠の基準であるようです。
いえ、確かにぼくも「ツイフェミ」など叩いても仕方がない、国家が男女共同参画局に莫大な予算を投じていることを批判することが先だ……と思いますが、それに坂爪師匠が同意するとも思われません。
結局、「ミソジニー」と同じで、「社会運動」も、そして「ネット利用」も「自分がやれば正義/敵がやれば悪」ということのようです。
最終章では(今まで変わり身の術ばかり使っていた)坂爪師匠本人が妙に前面に出てきて、饒舌に自分語りを始めます。
自身も八年間、アンチにネット上で誹謗中傷を続けられていたそうで、それはご同情申し上げます。
しかしそれに続いての口上が衝撃的です。「分析していて気づいた、一年間だけ、誹謗中傷の止んだ時期があった。その時期、相手はフェイスブックなどに恋人とのツーショット写真を掲げていた」。
本当に、何というか、ため息が出ます。
ぼくたちが自明視し、まず一番最初に言っていることに、長い長い本の最後の最後に至って、坂爪師匠も思い至ったようです。
非モテのやっていることであると。
言わば『非モテ論壇を斬る!』というタイトルの本の最後の最後で、「非モテブログ の運営者は非モテだった」とさも大発見のように、得意げに結論づけているようなものです。
もちろん、この両者の揉めごとの詳細についてぼくは知らないし、興味もありません。坂爪師匠がどれほどの被害を受けたのか、或いは相手にも理があったのかなどは知ったことではありません。
ただ、弱者の弱者性を、坂爪師匠はただ、嘲弄する対象でしかないと思っていることが、ここでも窺い知れたのです。
フェミニズムが「男らしさ/女らしさ」の否定、男女関係の否定の思想である以上、それによって被る被害は「非モテ」と密接にかかわっているのは当然のことです。
「表現の自由クラスタ」はその結果萌えオタになった者の声を代弁すると称しているのだし、「ツイフェミ」はフェミのために婚期を逃した女性である可能性が高い。
端的にはフェミニズムが、自分の生み出した非モテから逆襲を受けているというだけのことなのです。
もちろん、その「逆襲」の中には不当なものもありましょう。坂爪師匠が被害を受けた事例に関してはおそらく、相手側に非があったのでしょう。しかしネット上の「アンチフェミ」の書き込みの多くは、そのようには思われません。
本書は、その理路が理解できない筆者の、自分が何故怒られているんだろうとの、戸惑い顔の配信の記録だったのですが、最後の最後でようやっと、ことの次第に思い当たったようです。
いや……坂爪師匠がその結果、反省してフェミニズム信仰を止める、というオチがつくわけでは、残念ながらないのですが。
何しろ坂爪師匠は
裁判の結果、被告の年収に匹敵する金額を和解金として支払ってもらうことで決着がついた。被告側の弁護士費用も含めれば、確実に生活が破綻するレベルの経済的打撃になったと思われる。
(299~300p)
(299~300p)
などと随喜の涙を迸らせながら、語っているのですから。
本書は「ネット民けしからんですよね」と言っているだけだ、といった説明は動画でもしました。その本音が、まとめに入っていよいよ露わになっていく様子がご覧いただけたかと思います。
しかしでは、師匠はどうしてここまでネット民に対して「許せない」がやめられずにいるのでしょうか……?
以降はnoteでカネを取ってご説明申し上げるのですが、あ、いや、何、結論はいつも言ってるようなことです。
もし興味がおありの場合は、以下をクリックして、どうぞnoteをご覧ください。
・終章「マインドコントロール」から「ポア」へ












