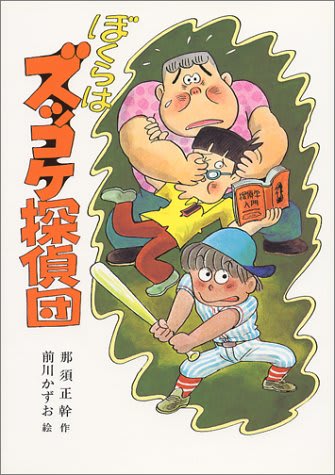続きです。
正直、ニーズがあるのかどうかわかりませんが、今回は五作を採り上げます。
相変わらず、「普通のブックレビュー」寄りの内容になりますが『宇宙大旅行』において当時の女性観、また『結婚相談所』について女災が語られますので、よければそこだけでも読んでみてください。
後、性質上、ミステリなどもネタは全部バラしていますので、そこはお含み置きください。
『花のズッコケ児童会長』
●メインヒロイン:荒井陽子
例えば、藤子不二雄Aの『魔太郎がくる!』。
これは周知の通りいじめられっ子の復讐をテーマにした漫画ですが、お決まりのパターンとして、スポーツマンが登場すると必ず「本人としてはよかれと思っているのだろうがスポーツ至上主義を押しつけてくるイヤなヤツ」として描かれ、魔太郎の復讐の対象となってしまいます。
本作もそれに近しく、品行方正な柔道家の男子、津久田が弱虫の章にリンチまがいの稽古をつけていたのを目撃したハチベエが怒る、というイントロダクションから始まります。
津久田が児童会長に立候補することを知ったハチベエは対抗馬としてクラス一の美女、荒井陽子を担ぎ出す――というのが前半のプロット。
津久田も陽子も、選挙活動期以前の事前運動としてファンクラブまがいの活動を行い、しかしそれがやり過ぎと言うことで先生にお目玉(実際、少額とは言え、現金が動いてしまう)。陽子はそれがショックで泣きながらハチベエを責め、一転して立候補を取り下げます。
おい、いくら半ば強引に担ぎ出されたとは言え、何て無責任な!!
後半はハチベエ自身が立候補し、選挙活動を始めます。
「あぁ、最後の最後、陽子が応援演説でもするところがクライマックスかな……」と思ったのですが、陽子は存外に早く機嫌を直して、選挙活動に協力するように。しかし今度はハチベエが陽子人気に苛立って応援を断ってしまいます。こうなるとハチベエのわがままさも大概です。
最終的には選挙当日の演説会で、緊張したハチベエは惨憺たる演説をしてしまうが、章が応援演説に立ち、冒頭の一件をぶちまけます。
結局、ハチベエが当選することはありませんでしたが、津久田も当選ならずという痛み分け。まあ、悪は滅びたわけでグッドエンディングです。
面白い話ではあるのですが、この津久田はちょっとないくらいゲスな人間として描かれていて、あまりにもストレートな勧善懲悪は『ズッコケ』としてはちょっとどうなんだという感じです(同時に、ゲスな本性が出るまでは、劇中で「ひょっとしていい人かも……」と人物評価が二転三転するのもいささか凝りすぎです)。
本作のテーマは「体育会系の否定」でしょうか。章が「スポーツをやれば根性がつくなんてウソだ」と絶叫するシーン、また応援演説に柔道道場の子供たちが現れ、「スポーツによって礼儀と度胸が養われる」と演説する中学生は舞台度胸がなく目を白黒させ、次に出て来た小学一年生はお辞儀もしない、といった小ネタに那須センセの体育会系への憎悪を見て取ることができます。
が、基本、それと政治とは関係のない話であって、話が政治のことに至るや、ちょっと内容が怪しくなります。
中盤、事情を知ったモーちゃんが津久田不支持を表明する場面で、「立派すぎる津久田はダメな人間の気持ちがわからない」と主張。いや、そこまではいいのですが、ハカセもそれに同調、「そうした視点こそ民主主義の本質だ」と語ります。
そうか……?
『ズッコケ宇宙大旅行』
●メインヒロイン:タウ星系第二惑星人
子供の頃、次はSFだとの予告に期待して『時間漂流記』を読んでみたら、江戸時代が舞台でがっかり、といった経験をしました。
恐らく、そうした感想が当時から多かったのではないでしょうか。本作の読後感は『時間漂流記』を、子供が喜ぶジャンルでリライトしたもの、という感じなのです。それは同時に、当時の「SFっつったらアレだろ、UFOだろ」という空気を如実に表した結果でもあります。
プロット自体は大したものではありません。近所の山にUFOを発見した一同。宇宙人とファーストコンタクトを果たし、また宇宙人の危機を救って友好関係を築き上げる。
それだけです。
ただ、(レビュアーブログなどによると)那須センセは蘊蓄シュミがあるようで、本作でも児童文学にあるまじき、UFO研究家のハイネック博士(文中では「ハイネク」)の名前(と、イラスト!)が出て来たりします。
他にもマニア的視点で細かいツッコミを挙げていくなら、まずUFOの形状がキューブとされ、シャンデリア型UFO全盛の時代に独自性を出そうという気概を感じさせますが、逆にUFO底部よりの牽引光線で内部に入る点は、当時のイメージを忠実に踏襲しています(このビジュアルは繰り返し挿絵に描かれ、「UFOにさらわれる」イメージを当時の子供が共有していたことが窺い知れます)。またこのUFOの内部があまりメカニカルでない辺りも、実際のアブダクティ(UFOにさらわれた人)の体験談に近しいように思います。UFOは偵察艇、大型の母船が月の裏側に待機している点は、アダムスキのイメージでしょうか。
アダムスキと言えば、本作に登場する宇宙人は、三人組と変わらぬ年頃の美少女として描かれます。これもまたアダムスキ的コンタクティ的な宇宙人像と一致しますが、肌は褐色で地球のさまざまな人種のハイブリッドに見える、とされます。この種の美形宇宙人は北欧系が多いことを考えると、独自性を出そうとしたとも思えますし、単純に「人種差別を克服した未来の地球人の姿」を見て取ろうとしているようにも思えます(もっともこの美少女宇宙人については二重、三重、四重のどんでん返しが用意されているのですが)。
そう、本作は第三章のタイトルが「スター・ウォーズ」となっていることが象徴するように、当時のスペースオペラブームを受けた作品であることは疑うべくもないのですが、どちらかと言えば全体にニューエイジっぽさが満ちているのです。
宇宙人は将来、地球人と友好関係を築くため、まず地球の子供と接触を求めてきます。三人組は「ぼくたちが大人になった頃、彼らと本格的な友だちになるのだ」と気負い、また宇宙人側も「彼らが成人する頃には、地球も我々宇宙連盟の仲間入りを果たせるだろう」と語ります。
『未知との遭遇』の宇宙人が象徴するように、この当時の「宇宙人」とはニューエイジ的な「穢れない子供」のメタファーそのものでした。この美少女宇宙人もまた、『時間漂流記』の若林先生に連なる、「80年代SFによくあった女性聖化型美女」の系譜であることは、言うまでもないでしょう。
その意味である種、当時よくあった(言っては悪いけど)『未知との遭遇』劣化版の一つとして、本作も位置づけられるように思えます。
『うわさのズッコケ株式会社』
●メインヒロイン:荒井陽子、榎本由美子、安藤圭子
面白いです。
レビューブログでも最高傑作、株式会社のシミュレートをしてみせる小学生向けとは思えないリアルな内容が見事、といった評であり、その通りだと感じました。
お話としては近所の港が釣り客で賑わうのを見て、三人組が弁当や飲み物を売ろう、と思い立つ、というものです。資金繰りのためクラスメイトたちを相手に、株式会社を立ち上げる。が、釣りシーズンが過ぎ、経営難に……。
ここで株主たちにつるし上げられるも、ハカセが口八丁で場を収めてしまうのがすごい。
そして一転、お話はモーちゃんの姉の学校の文化祭でラーメンを売る、という話に。
と、今まで株主としてハチベエを冷たく吊し上げるのみだった美少女勢が「私たちも働いてみたい」と言い出します。高校の文化祭というのが、彼女らにとっては魅力的に映ったのでしょうか、楽しそうに接客します。
メイド喫茶回ですよ、メイド喫茶回!!
いや、メイド服は着ませんけどね。そして商売は成功を収め、また一時期はハチベエを責めた陽子が照れくさそうに謝罪するのです。
今までの『ズッコケ』では、女子はそれこそのび太にとってのママと大差ない、「外敵」でした。が、今回の女子たちは当初は株主という立場だったが、三人組の行動に興味を持ってこちらへと歩み寄り、共に働き、株主たちに「あんたたち、カネを出して文句を言ってるだけじゃない、ハチベエたちは汗を流して働いているのよ」とまで言うのです。
まあ、作者の(労働者は尊い、株主は悪者、という)イデオロギーを代弁させただけとも言えますが、同時に『ズッコケ』史上初、女の子たちと本格的な「ファーストコンタクト」を成し得たのが本作であったとも言えるのです。
仮にですが、これをオタクネタに喩えるならば、『ズッコケ同人サークル』で、美少女勢が同人誌即売会に参加、「オタクたちの方がリア充よりいいわ」と理解を示してくれる話、とかそんな感じかも知れません。
もう一つ。流浪の画家島田淡海の存在も三人組を助ける一因となっており、また彼の浮世離れした生き方をハカセが「一番正しいお金の使い方」と評する辺り、やはりちょっと、「金儲け」というテーマに対する作者の屈折が見て取れます。
『ズッコケ恐怖体験』
●メインヒロイン:おたか
ハチベエがとある閉鎖的な田舎で女幽霊に取り憑かれてしまうお話なのですが、レビューなどでも書かれる通り、怖いと言うよりもの悲しい内容です。
心霊現象を謎解きしていき、合理的に解明できたかと思いきや、最後に「いや、でも不思議なことは本当にあるのだ」とひっくり返す展開は鉄板ですが、それが幕末の、権力者に翻弄された哀れな母子の話へとつながっていきます。幽霊話が「迷信深い人々による、故人への冤罪」とオチがつくのは時折見るパターンですが、それが更に故人が生前にかけられていた冤罪の解明へとつながって行く様は見事です。
不満を挙げるとすれば三人組があまり活躍をしないことでしょうか。とは言え、閉鎖的な村の迷信を新任の若い教師が打ち破る展開は面白いし、逆にこの謎解きをハカセたちがやってもそれほど面白味もないだろうし、仕方のないところでしょう。
いずれにせよ、こうした母子関係を神聖視するムードは『ズッコケ』では珍しく、次回作のドロドロした母子関係とは対照的です。
那須センセには日常を書くと辛辣なものになり、翻って非日常系では理想的な母子関係、理想的な美女を描こうとする傾向があるように思われます。つまり今回の女幽霊、おたかもある意味では『宇宙大旅行』的な「異界の美女」のバリアントと言えるのではないでしょうか。
『ズッコケ結婚相談所』
●メインヒロイン:奥田タエ子
「D」「V」「冤」「罪」

――そうか、わかったぞ!!
というわけで『ダンガンロンパ』風にお送りしました。
すげえ。すげえええええええええええええええええええええええええええええええええ。
これ、何なんだ。
実は出だしはあんまりいい印象がありませんでした。
イントロはハチベエの発案で子供電話相談室を始めるというものですが、そのきっかけが新聞で小学生の自殺の記事を見たから、というもの。どうでもいいけど要るか、その自殺って話題。
その後、ページの1/3近くをこの相談室で消費するのですが、このエピソード、本筋にはかかわりません。本筋は「モーちゃんのお母さんの再婚話」。
実はこのシリーズ、結構タイトル詐欺の傾向があります。恐らく方針としてあとがきに次回タイトルの予告を書くようにしているため、そうなってしまうのではという気がします。想像ですが、『結婚相談所』と予告したので前半でつじつまあわせをしたんじゃないかなあ。
さて、モーちゃんの家は母子家庭です。モーちゃんが物心つく前、母は父親と離婚。それもお父さんが酒に浸って妻子に暴力を振るうようになったからです。その後、お母さんは女手一つでモーちゃんと姉とを育ててきました。
そこに現れたのが裕福なスポーツマンの再婚相手。モーちゃん同様のデブに描かれている(もう四十を超えた)お母さんにとっては、二度とない、それも理想的な再婚のチャンスでしょう。
しかし、モーちゃんはいつまで経ってもグズグズと割り切れない。
そこでハチベエとハカセは東京に住む元・父親の久村を訪ねようと発案します。
モーちゃんが一歩踏み出すためには、最初の父親への感情を精算した方がいい、と考えたのです。モーちゃんのお姉さんであるタエ子もこの計画に協力して、旅費を捻出するという活躍ぶりを見せます。
そして、いざアポなしで突撃した元・父親との再会は――。
当たり前ですが、久村も今となっては新しい家庭を持っています。彼はモーちゃんを丁寧に迎えつつ、その対応はよそよそしい。もう親子ではないと言い切ります。
この新しい妻との間に子供も生まれているのですが、ここでモーちゃんは初めて「自分には実の兄がおり、この家で暮らしている」と知らされ、その兄からの「何だコイツ?」といった無愛想な対応を受けてしまいます。
ついには久村も「これから家族で出かける予定だ、そろそろ帰ってくれないか」。
同席していたハカセが切れます。最初は「おじさん、もうお酒飲んで暴れたりはしないんですか?」と不躾な子供を装い、最後は「とぼけないでください、さんざんモーちゃんのお母さんをいじめておいて!」と。
ここ、ハカセが言うからこそ感動するのですが、それにしてもキャラクターを考えれば、ハチベエこそが切れるのが自然でしょう。このハカセ、「普段は冷たいがいざとなると友情に厚い」というキャラクターで、大体美味しいところを持って行ってしまいます。『ジェットマン』の竜が凱を抑えて一条司令を殴るシーンを想像しなくもありませんが。
しかしそれに対する元・父のリアクションは「困惑」というもので、同席していた妻が見兼ねて説明します。「酒乱になったのは夫ではない。あなたのお母さんの方だ」。
彼女は元々お母さんの同僚で、結婚後も三人でのつきあいが続いていたが、その内にお母さんが彼女と久村の仲を怪しむようになり、精神が不安定になって酒に浸るようになった。長男(つまり、モーちゃんの兄)すらも不倫の末の子供だろうと疑い出した。
久村はやむなくお母さんと離婚し、嘘から出た誠という形で今の妻と再婚したのだと。
その告白に圧倒されたまま、三人組は久村の家を出ます。
その後もハチベエとハカセがモーちゃんを気遣う描写が続くのですが(ハチベエはハチベエでぶっきらぼうな中にモーちゃんへの友情を覗かせ、それはそれでいいシーンです)、帰りの新幹線で、モーちゃんは「ぼくには父親はいないし、要らない。お母さんの結婚に反対もしないが、ぼくは家を出て親戚の家にでも身を寄せる」と決意します。
大人たちのちゃらんぽらんさに比べて、子供たちの聡明で清廉な姿に、ただ圧倒されます。
このモーちゃんというのは自己主張の強いハカセとハチベエの調停役に徹することが多く、普段は目立たない存在です。それで主役話を、といったことで本作は始まったのでしょうが……しかしこのモーちゃんの老成した態度に、頭が上がりません。いえ、それを支えるハチベエとハカセの大人な対応も決して負けてないのですが。
冒頭の人生相談で、鼻を摘んだだけで「ぼくはモーちゃんじゃありません」とバレバレの相談電話をかけてくるというアホなシークエンスは、一体何だったのでしょう。
さて……みなさん気になっているかと思います。
この久村は本当にDV夫だったのか、モーちゃんのお母さんこそがDV冤罪犯だったのか。
ハチベエとハカセは「どっちとも言えないよな」と中立的な会話を交わすのですが、帰宅したモーちゃんを迎えたお母さんは「(久村たちから)離婚の理由も聞いたの?」とさりげなく尋ねてきます(三人は「ただの東京見物」との名目で出かけたのですが、お母さんはお姉さんに聞いて事情を知ってしまっていたのです)。その様子から想像するに、やはり久村の主張が正しいのではないでしょうか。
その後、彼女は「久村とのことは、自分が正しいと今でも思っている」とも言うのですが、ここは「DV」についてか「離婚したこと」についてか或いはまた「長男が不倫の子だ」という思い込みについてかは判然としません。そもそも自分で産んだ長男を不倫の子だと言い立てていたのですから、この時期のお母さんが正常な精神状態でなかったことは明らかです。いえ、それすらも久村の妻のウソ、という可能性もあるとは言え。
見ていくに、作者の意図としては子供の読者にはどちらとも取れるように描き、しかし読み返した後ではお母さん側が怪しいと判断できるように持っていく、といったものだったのではないでしょうか。
ヒントとなる描写があります。
今までムダだと繰り返していた冒頭の「電話相談」。これは無残な失敗で終局を迎えるのですが、それは以下のようなものでした。
ハチベエが電話相談に対応していると、可愛らしい女の子の声で電話がかかってくる。「恋愛について相談したいんです。私、隣のクラスのハチベエという男の子に恋をしていて……」。
舞い上がったハチベエはその子と会う約束を取りつけ、約束の場所で待つのですが、いつまで経っても相手が来ない。その時、クラスの美少女トリオが現れ、妙になれなれしくしてきます(ハチベエの手を取ったりすらします!)。普段なら舞い上がるハチベエですが、他の女の子(何しろ隣のクラスと言っていましたから)との約束があるからと我慢していると……美少女トリオは吹き出して、あの電話の主は私たちだ、あなたをからかったのだと告げます。
「モテない男の子って悲惨ね」と言い捨て、美少女トリオは去っていきます。
むろん以上は、全体の話には一切関わってはきません。
那須正幹は言いたかったのではないでしょうか。
「女災」には二種類あり、一方は能動的女災である。これも悪質ではあるが、ある意味、目に見えやすく、また「女子力」の高い者のみに使える技である。
もう一方は受動的女災であり、しかしこれこそが目に見えにくい、「女子力」の低い者にも使用可能な、だからこそ本当にタチの悪い、本質的な女災である、と……。
一応書いておくと、お母さんはモーちゃんの決意を聞いて、「あなたが認めない男と結婚なんかしない」と宣言し、また再婚によって(モーちゃんが仮に親戚の家に身を寄せるとしても)引っ越してしまうのではと危惧していたモーちゃんがこの場に留まってくれることを知り、喜ぶハチベエとハカセの姿で話は終わります。
「完璧でないながらも、息子を愛そうとする母」。読後感は、非常にさわやかです。