
土器に繊維が含まれる
苗ケ島 大畑遺跡「赤城山の南麓にある早期の遺跡では、大型の土器をつくるために、粘土のなかにススキなどのイネ科植物の繊維を混ぜている。その理由は不明な部分が多いが、土器を焼くときにイネ科植物に多く含まれるガラス分が溶けて土器を硬くさせる効果があるのかもしれない。早期、鵜ケ島台(うがしまだい)式土器。」ネットより引用、参照
このように繊維を塗り込んだ土器があるのは確かです。
ところが、北黄金貝塚の前期の土器に繊維が入っていると、大島直行氏(前噴火湾研究所所長)が口にしたのを記憶しています。

これを証明するかのように、大島所長の恩師でもある、北黄金貝塚の発掘を最初にされた峯山巌さんの発表物にレントゲンで写した土器の画像がありました。
手元にないので信ぴょう性に欠けますが、確かに繊維も網目の文様がかすかに判断できました。
この尖底土器を つくるのに最初に網で形を作り、粘土を表、裏より張り付けて成型したように想像できました。
再度 レントゲン写真を撮ってみたいものです。MRIも無理でしょうね
50年以上も前の事です。斬新的な発想をされた方でした。
この土器は、北黄金貝塚情報センターに鎮座しています。
土器を眺めていると、「そうかな・・」とも思うようになりました。




















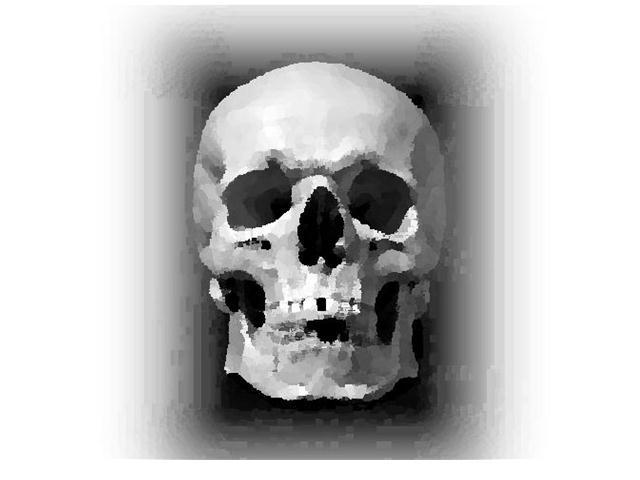





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます