
火焔型土器の解明 2
「水」に関する土器ということで解明を進める。
火焔型土器の部位の名称(小熊2003)の図形で上下の四段階にして眺めていた。
四段階は、土器にきちんと示されている。
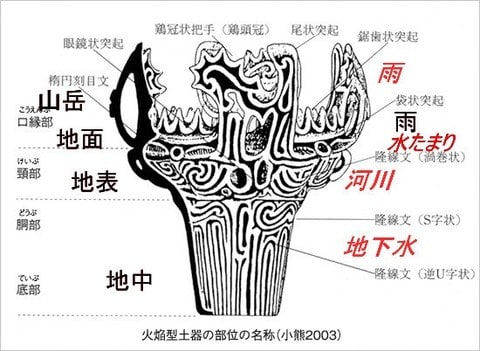
上から
♢鋸歯状突起
雨(大きなポイント)水
♢口縁部
山を流れ地上にたまる水
♢頸部
大きな川を流れる水
♢胴部
地下に浸透する水
だが、
♢「願」を 伝え 聞く 等の仕組みは考察中
これが「火焔式土器」の大まかな仕組みです。
雨が降り、谷間を水が下り、平地に水たまりをつくる。
それが、大川に流れ込んだり、地下に染み込む。
願いとして、荒れた水の流れを治めるようにお願いしていると想像できそう。
縄文楽 浄山


















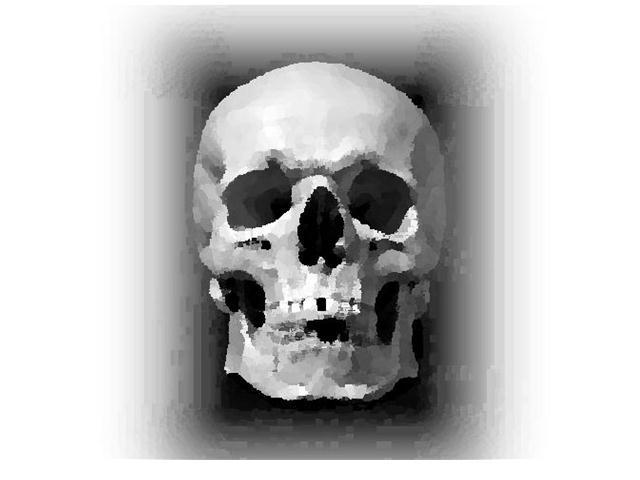






とってもいいブログありがとうございます。とくに火焔型土器の解明 2は大変面白かったです。(ライクしたいけど外国から登録はかなり難しいです。)
一つの質問です、「小熊2013」という資料はどの本でしょうか?
よろしくお願いいたします
この資料は岩野原遺跡出土の火焔型土器群(1)-火焔型土器群の研究でしょうか?