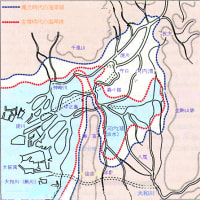神戸新聞は『遺族が語る』という特集を組み、残された家族の声を掲載し続けています。「大丈夫やから、こっち来るな!炎の中から聞こえたその言葉が父の最期の言葉でした」「娘の足が瓦礫の下から見つかった後に成人式(当時は15日が成人式でした)の晴れ着姿の写真が届いた」「母の遺体が作ってくれたわずかな隙間で僕は助かった」など、あの日の記憶が語られています。
今回は淡路島の洲本市で、長男:比呂文さん(当時15歳)長女:さゆりさん(当時13歳)を失われた東さん夫婦の声を掲載します。
◇
《まだ強くは生きられない 》東昇さん(58歳)・東里美さん(51歳)
もう十年。夫婦だけの生活にも慣れました。
あの日、一階で寝ていた子どもたち二人は抜けた二階の下敷きになりました。ふすま一枚隔てた隣室で寝ていた私たち夫婦も、タンスや梁(はり)に押しつぶされました。助けにいくことができず闇の中で何度も子どもたちの名前を呼びました。でも返事はありませんでした。長男の比呂文は当時中学三年生。料理が得意で台所の手伝いもよくしてくれました。だから「高校では食品加工を学ぶんだ」って。震災の前日には参考書も一緒に買いに行きました。さゆりは笑顔の明るい子。だれとでも仲良くなりました。近所の小さな女の子たちをまるで妹のようにかわいがって。将来の夢は保育士になることでした。
二人とも友人に恵まれていました。神戸や大阪に就職した友達も、帰省したときにはよく自宅に立ち寄ってくれます。比呂文の友達は、誕生日がくると毎年お墓にメッセージカードを供えてくれます。二十歳を過ぎてからは、そこにお酒も加わりました。さゆりの友人も優しくって。三年前の「成人の日」でした。門出を祝おうと、私(母親の里美さん)が二十歳のときに着た晴れ着をタンスから引っ張り出して仏壇のある部屋に飾ったんです。「一人きりの成人式」の予定でした。でも、地元の成人式を終えた友人たちが大勢自宅に来てくれたんです。「一緒に祝いたかった」って。みんなが二人のことを覚えてくれている。周囲の支えがあってこその十年でした。
だけど、まだ強くは生きられません。「希望を持って生きて」と励まされるけど、子どもを失った親の「希望」って何でしょうか…。十年が過ぎても答えは見つかりません。遺品はすべて段ボールにしまっていますが、開けてみることはありません。悲しくて、涙が出るから。節目の日なんて来ないと思うんです。二十年たっても、三十年たっても。(神戸新聞2005/08/28)
◇
子どもを失った親の「希望」って何でしょうか。私は、この問いに対する答えを見つけることができません。何十年たとうが節目の日なんて来ない、という声は震災の記憶を心に留めておくことの大切さを訴えているようでした。
今回は淡路島の洲本市で、長男:比呂文さん(当時15歳)長女:さゆりさん(当時13歳)を失われた東さん夫婦の声を掲載します。
◇
《まだ強くは生きられない 》東昇さん(58歳)・東里美さん(51歳)
もう十年。夫婦だけの生活にも慣れました。
あの日、一階で寝ていた子どもたち二人は抜けた二階の下敷きになりました。ふすま一枚隔てた隣室で寝ていた私たち夫婦も、タンスや梁(はり)に押しつぶされました。助けにいくことができず闇の中で何度も子どもたちの名前を呼びました。でも返事はありませんでした。長男の比呂文は当時中学三年生。料理が得意で台所の手伝いもよくしてくれました。だから「高校では食品加工を学ぶんだ」って。震災の前日には参考書も一緒に買いに行きました。さゆりは笑顔の明るい子。だれとでも仲良くなりました。近所の小さな女の子たちをまるで妹のようにかわいがって。将来の夢は保育士になることでした。
二人とも友人に恵まれていました。神戸や大阪に就職した友達も、帰省したときにはよく自宅に立ち寄ってくれます。比呂文の友達は、誕生日がくると毎年お墓にメッセージカードを供えてくれます。二十歳を過ぎてからは、そこにお酒も加わりました。さゆりの友人も優しくって。三年前の「成人の日」でした。門出を祝おうと、私(母親の里美さん)が二十歳のときに着た晴れ着をタンスから引っ張り出して仏壇のある部屋に飾ったんです。「一人きりの成人式」の予定でした。でも、地元の成人式を終えた友人たちが大勢自宅に来てくれたんです。「一緒に祝いたかった」って。みんなが二人のことを覚えてくれている。周囲の支えがあってこその十年でした。
だけど、まだ強くは生きられません。「希望を持って生きて」と励まされるけど、子どもを失った親の「希望」って何でしょうか…。十年が過ぎても答えは見つかりません。遺品はすべて段ボールにしまっていますが、開けてみることはありません。悲しくて、涙が出るから。節目の日なんて来ないと思うんです。二十年たっても、三十年たっても。(神戸新聞2005/08/28)
◇
子どもを失った親の「希望」って何でしょうか。私は、この問いに対する答えを見つけることができません。何十年たとうが節目の日なんて来ない、という声は震災の記憶を心に留めておくことの大切さを訴えているようでした。