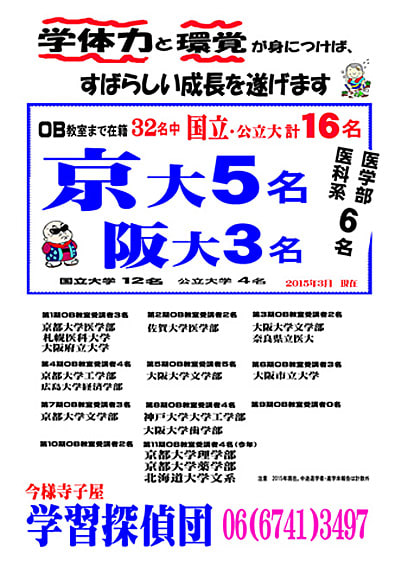「うんこ」の世話は誰がする?
ここで、「子育て」や「しつけ」について、団の考え方を少し紹介、補足しておきます。まず、その大切さです。 「しつけ」とは何なのか? そんなに軽んじられるべきものか? 少し振り返ってみます。

社会と個人、ぼくたちは「社会」から逃れるわけには行きません。孤島のロビンソン・クルーソーでさえ一人ではありません。ひとりでは生きていけません(これは恋人同士や家族のことを言っているわけではありません)。
日々の生活を虚心に振り返れば、どんな意味においても、ぼくたちは「誰かに何らかの世話になっている、ならざるを得ない」あるいは「何らかの迷惑をかけてしまっている」存在、「影響を受けざるを得ない」存在、ありきたりの言葉で言えば「社会的存在」です。
例えば、「うんこ」はひとりでどこでもできます。だからといって、それはできないし、やってはいけません。また介護が必要になれば、うんこの処理も誰かの世話にならなければいけない。
もっと辿れば、「うんこ」を流す下水を作ったり修理したりする人もいるわけです。さらに、迷惑にならないように、きれいにするように薬品を作ったり、考えだしたりする人も必要なわけです。ぼくたちは、それぞれ意識無意識は別として、網の目のように絡み合った生活を送っています。
ところが、赤ちゃんや子どものときからそんなことがわかるわけはありません。それらを教えなければなりません。見境なく「うんこ」をしたり、垂れ流していてはいけないことを教えなければなりません。もちろん、垂れ流すのは「うんこ」だけではありません。他にも、知らなければ、様々に「迷惑なもの」を垂れ流してしまいます。
今は「勉強」に「特化」していますが、子どもにおしえなければならないことは勉強だけではありません。「一人ではないという社会的意識やたしなみ」、社会のルールなど、たくさんあります。それらをすべてひっくるめて、文字通り『みそ』も『くそ』もひっくるめて、否定され、あるいは敬遠されがちになっているのが現在の傾向ではないのか。その結果、教えられない・知らないから、「欲望」や『うんこ』を平気で垂れ流してしまう、それらの「放任」の集約が育児放棄やいじめをはじめとする犯罪の遠因のひとつだとぼくは思っています。
つまり、子どもの「しつけ」は、「意識ができている、いないを問わず」、人は生きているかぎり、だれかの世話になったり(ならなければいけないし)、何らかの迷惑をかけてしまうのだから、「できるだけ世間様(つまり社会)に迷惑をかけないようにしよう、させようということを教えるしくみ」だったと考えられます。かつては、その意識が日本社会には根づいていました。いや根づいていたはずです。
どうしてわかるか? ぼくは歴史家でも日本文化の研究者でもなく、巷のただの「おじ兄ちゃん」ですが、明治維新前後の欧米人の回想録等、当時の日本人の人間性や礼節・生活習慣などの観察記録の「驚嘆」や「絶賛」を読めば、その意識が、その教えが社会の底辺まで浸透・徹底していたことが一目瞭然です。
「この国では、どんなに貧しく疲れきった人足でも、こうした作法(礼儀・注南淵)のきまりからはずれることがけっしてない。しかもこうした作法には、奴隷的なところや追従的なところはまったくなく、それはむしろすべての階級の日本人相互の関係に、一種独特の文化の匂いをそえるものなのだ」(「回想の明治維新」メーチニコフ著 渡辺雅司訳 岩波文庫p122)
「・・・とにもかくにも子どもが彼らをひきつけている。英国の労働者階級の家庭を往々にしてビアガーデンに変えてしまうような喧嘩騒ぎや口答えは、従順と服従が揺り籠の時分から当然のこととして教えこまれているこの国では、見ることができないのだ」(「逝きし世の面影」渡辺京二著 平凡社p412)
当たり前ですが、従順と服従を目指しているわけではありません。子どもに対するきちんとした取り組みが機能していたことを紹介したいのです。(注・まだ原文で辿れてはいません)
「素晴らしい芸当を演じる滑稽で巧妙なからくり玩具は、最も単純な機械原理を応用し、わずかな水道水の補助やろうそくの熱によって動きます。これらの玩具は竹ひご、細い松材、紙や藁の繊細なもので、米国の子供らが触るとすぐに壊れるような代物です。それでも文明日本の幼き国民は、幾週間もこれらの玩具と親しみ、熱心に遊びます」(「シドモア日本紀行」エリザ・R・シドモア著 外崎克久訳 講談社 p90・文責南淵)
明治時代、先進国であるアメリカの人文地理学者が日本を「文明日本」と呼称しています。文脈から決して皮肉でもお世辞でもありません。単純な機械原理やわずかな水やろうそくの熱によって面白く遊べるものを作り出したことが、「文明」なのです。
このように、当時の日本人に対する感動や賞賛は探せば切りがありません。近年の外国のサッカー場での日本のサポーターに対する「賞賛」どころではありません。日本人は「素晴らしかった」のです。
古いものにも「切り捨ててよいもの」と「できるだけ残しておいた方がよいもの」があります。みなさんは、これらの賞賛を可能にした「しつけ」や「子育て」と教育をどう思いますか? 外国にその「国民性を賞賛されること」と「非難されること」の価値のちがい、どちらがよいかは「年長児」でもよくわかることです。
また、本当にグローバルに活躍できる人材は、その国の国民としての長所や誇りを身につけ主張できてこそ、外国で対等の付き合いも可能になり、尊敬もされるのではないでしょうか? 
日本人の「しつけ」が涵養した、「誇るべき人間性」は決して忘れてはならない、「うんこの世話は誰がする」を忘れてはならないと思います。基本の基本です。もちろん、先述したように、これらの「定着」は、目には見えなくとも、指導の過程で「学体力の養成」・「学力の伸長」にも大きく関わります。

基礎の徹底とレジェンド参考書・Z会
さて、M君にすすめた学習参考書・学習法について紹介します。
M君には積み上げた学習体験がありません。また、理科系に、という希望をもっていたので、確固とした数学の基礎の習得は欠かせません。まず基礎の徹底です。僕が独力で一年間の大学受験学習を始めた時のことを思い出していました。どんな場合も、拠って立つべきは基本です。 高校生の時、学校指定で使っていたK社の教科書ではなく、数研出版の教科書を中高6年分取り寄せ、巻末の練習問題まで徹底的に反復演習した時のことを思い出していました。
幸いなことに、今は6年間を視野に入れたテキストが出版されています。「中高一貫校をサポートする」体系数学シリーズです。まず、これの徹底理解を進めることにしました。その後は、「レジエンド」参考書とZ会。あとの展開は、その進み具合で考えることにしました。