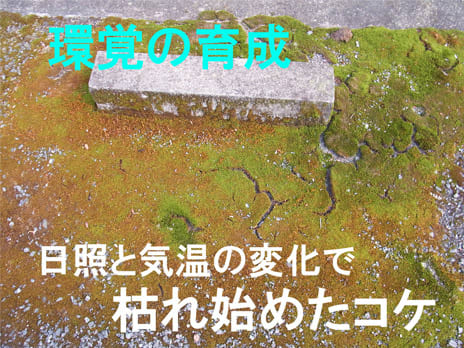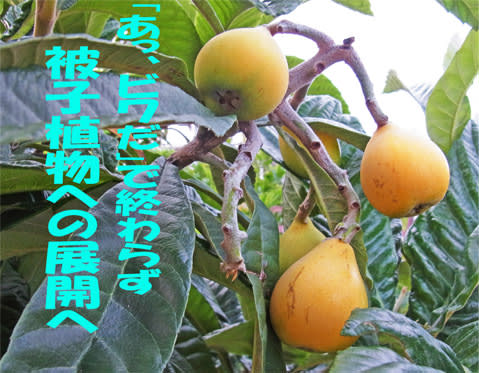今週の写真は蛍狩りでのスナップ。そして、久しぶり(お正月以来)に「学探三兄弟」太郎・次郎・吾作、エイミーの登場です。また、「田植え」のとき団員(Kさん)が飛鳥川で作った「亀の池」も、本人の強い要望(笑)でアップしておきます。
やんちゃで勉強もできないけど、ほんとはやさしい長男・太郎、一見おとなしそうだけど勉強がよくできて喧嘩もべらぼうに強い二男・次郎。いつも大きな声で文句が多い三男・吾作。そして「豪放磊落」な「と~ちゃん」が、いつの間にか(?)妹だと連れてきた生意気な末っ子エイミーです。
「と~ちゃん」がゴリラなのに、子どもは太郎だけがゴリラで、次郎とエイミーがチンパンジー、吾作はニホンザルという不思議な家族。三兄弟の「かーちゃん」と、エイミーのママ、「と~ちゃん」の「初恋の彼女」は、次週もう一度紹介します。

デモとバイトの狭間から
もう、手をかざしても目を凝らしても見えなくなった昔・・・。目標も夢も見失っていた貧乏学生のぼくは、バイト以外、教育大のキャンパスで読書と昼寝が日課でした。
わきあがる元気や力を持て余して、今とはちがう一日が過ぎていきました。熱病のように、マルクスやエンゲルス・サルトル・吉本隆明・・・を「理解」しようと、有り余る力の大半をつぎ込んでいたような気がします。それでも、よくわからなかった・・・。若い時間の使い方、学生時代の本・出会いや出会う人はかけがえがありません。
当時の時間と情熱の半分でも、無性に読みたくなっている道元に、今費やすことができれば・・・と後悔が時々胸をかすめます。こうした後悔や反省も、子どもたちへのアドバイスや指導の底流になっているかもしれません。
避けることができない経年。年をとるということ。
「老婆心」と言われようと、よけいなことと思われようと、伝えておきたいことがたくさんあります。子どもや若者たちにはもちろん、年若いお父さんやお母さん、そして先生方にも。 
あの頃の誰彼と同じく、「世界をよくする」、「日本をよくしたい」という思いはあっても、戦う相手や倒す相手が、結局ぼくにはまったく見えてきませんでした。しかし、そんなものは、誰にも見えていなかったのではないかと、今思います。
実は自らの「怒り」と戦っていたのではないか。敵は自分たちの中にあったのではないか。
それは「戦うもの」ではなくて、「掘り出すもの」「見出すもの」ではなかったのか。ぼくたちは一部の『賢人(?!)』を除いて、「見えざる敵」に独り相撲をしていたのではないか。
少し何かが見えてきた今、過去から、見落としていたもの・見過ごしていたものの一部でも掘り出すことができれば。
さて、その頃読んだ「共産党宣言」に、こんなフレーズがありました。「・・・妖怪が一つ、ヨーロッパに現れている―共産主義という妖怪が・・・」。共産主義という妖怪がヨーロッパに現れたのは19世紀でしたが、21世紀の日本には、どんな妖怪が現れはじめたのか。「妖怪が二つ、子育ての現場に現れている―『子人(ことな)』と『大供(おども)』という妖怪が…」。
共産主義という妖怪はいつの間にか消えていきましたが、この妖怪たちは、今後も日本ではどんどん拡散、拡大再生産されていく可能性が大です。
道路とガードレールの話―子育てのルールとは
「大人」がいて「子供」がいて指導や教育が成立します。そして、ぼくは、よく、こういう例えを使って、しつけや指導・教育の意味や役割を、お母さん方に話します。道路とガードレール…。
生まれたばかりの子どもたちは、どこを歩けばいいのか、どこを、どう走ればいいのか、どこを通れば目的地へ行けるのか、まだまったくわかりません。前回も述べたように、そんなとき、借り物の「自由や自主的」「ほめて育てる」という考え方や方法を金科玉条、無批判に使えば、野原を我が物顔に駆け回り、人家や敷地に平気で侵入する野獣を育てているようなものです。そんな気配はないですか?
世の中には人が通る道がちゃんとあり、そこを通らなければ、他人の田んぼや畑を荒らしてしまう。庭を横切ってしまう。「どこでも自由に走ってよい自由」はありません。ガードレールを「意識」できなければ社会は成立しません。ガードレールの存在を教えなければなりません。「自由人」だからと、「縦横無尽に」余所の田んぼや畑、隣の庭を走ってよいわけではありません。
道路やガードレールの存在を教えたのちも、道路には対面交通、交差点も信号もあり、時には電車と交差する踏切もある。その道路を通るのは、もちろん自分だけではなく、老若男女、体の不自由な人や信号もわからない小さな子が通ることだってある。それらがよく見えて、それに応じた行動をとれることが大人になる、成長する、ということです。
さらにガードレールを意識しながら、道を自由に走れ回れるようになっても、スピードの出しすぎやジグザグ運転をするのが子どもたちです。これらも笑って見過ごすことはできません。一人で走っているのではなく、その道路では他のみんなも走らなければならないからです。
他の人をひいてしまうかもしれないし、ガードレールに激突し自らが命を落とすかもしれません。つまり、まだ安心はできないわけです。教育と指導は、まだかかわってきます。
自由や自主性はもちろん最大限に尊重しなければならないし、その大切さを口を酸っぱくして強調することも欠かせません。大いに褒めることも、子どもたちの可能性の発現に大きな影響があるはずです。しかし、団のOB諸君の成長を見る限りでは、叱らなければならない時に厳しくしかって、その推移をよく見て、「出来栄えと努力」をほめ続けることが、成長の礎でした。
これらの指導はいつまでかかるか? 経験上、家庭の理解と協力があれば6年生までに一定の成長は成就します。先週紹介したA君がその典型です。
逆に、理解がない場合、いつまでたっても治りません。そして、そこには必ず二つの妖怪が跋扈しています。

「子人(ことな)」と「大供(おども)」と子育て
21世紀の日本に忍び込んできた「子人(ことな)」と「大供(おども)」という、二つの妖怪。
「子人(ことな)」。大人になり切れない大人。それなりに「高い学歴」もあり世間の覚えもよい職業に就き、、「受験勉強」や『学習』のたいせつさは痛いほどわかっているが、大人になり切れていないので、本当に子どもに伝えなければならないことや「ガードレールの指導」がわからない大人。守られてばかりいる環境で育ってきたので子どもを守ることを知らず、危機管理やTPOでの正確な判断が整っていない大人。
もう一つの妖怪は「大供(おども)」です。
「子ども」を育てているという自覚や責任が整っていない、大きい人(大人ではないからです)。自分のことや趣味に精いっぱいで、子どもを客観的に見ることもできず、思いつきや感情に任せて、一貫性なく怒鳴り散らす人。したがって、子どもはいつまでたっても、言うことを聞きません。聞いてくれません。そして、自分も根は『子ども』なので、結局子供に阿ってしまう。これでは満足な教育や指導ができません。
「子どもをつくった、しかし親が親として成長しないまま子どもを育てて・・・」となれば、社会の根幹が揺らぎます。二つの妖怪は恐ろしい妖怪です。
「最大多数の最大幸福」を願って社会の変革を続けていくのが多くの人の願いのはずです。
それに向かっての努力の必要性も言うまでもないことですが、中心になるべき肝心の次代を担う人を育てる大人が子どものままであったり、個人としての「拵え」に、あちこちほころびがあるようでは、それらも成就しません。小さい子どもたちがいるお父さん・お母さん、どうか一度振り返って、考えてみてください。
「子人(ことな)」と「大供(おども)」の子育てとは、どういうものか? 例を挙げて考えてみましょう。