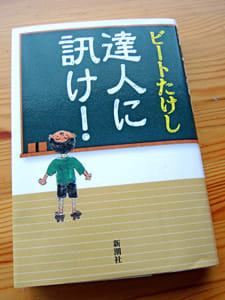この「夢の教科書を求めて」では先々週から、子どもたちの現状・特にそこから生まれる学習上の問題点について考えています。
今後、子どもたちへの今までの学習指導に対する疑問点とその改善案、学ぶ面白さを中心に据える学習指導へのシフトチェンジの可能性などについて、団で順調に育ってくれた子どもたちとの経験をもとに継続的に考えていきます。
教育界とは無縁の暢気さと気楽さ、「井の中の蛙、大海を知らず」かもしれません。しかし「銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも」。子どもたちの現状を見る限り、憶良に倣って、もう一度「社会にとって、いちばんたいせつなものをたいせつにすること」を、みんなで真剣に考えなければいけませんね。その小さなきっかけにでもなってくれればよいと、前に進みます。

自らの理想から見ても、ぼくの指導法もよちよち歩き始めたばかりです。暗中模索の日々です。
しかし少なくともフォアグラ指導や缶詰授業で、子どもたちにとって必要のない労力・可能性・時間という無駄遣いだけはしていない、そして「ガス欠」にはしていないことは、ご理解いただけると思います。

こうしている間にも、世の子どもたちはどんどん育っていきます。少しでも「脂肪肝のガチョウ状態」から抜け出せるようなアイデアをともに考えていきませんか。「勉強する子どもたちの学び」が、肝硬変の致命傷状態」にならないように。「学ぶことに対する意識」が崩壊してはよくありません。
先週はOB諸君の偏差値についてお伝えしました。「偏差値を頼りにフォアグラ指導・缶詰授業をつづけること」に対する問題提起でした。今週と次週は団で過ごした彼らの学習期間・学習時間・学習内容そして指導方法について紹介します。
さて、右は先に紹介した十三名の団在籍年数のピックアップです。
左から進学大学・入団時期・小学生時の在籍年数・六ヶ年私立中学進学後のOB教室在籍年数(一名は公立)・合計在籍年数を表示しています。小学生入学時からの団在籍年数が7年以上の諸君の枠をピンクで色づけしてあります。
団に7年以上在籍して現在まで大学受験を終えたのは右の8名だけです。ごらんのように8名の進学先は京都大学2名、大阪大学3名で、後は広島・神戸の両国立大学と大阪市立大学です。そして、赤い枠の三人は進学先の授業と月四回のOB教室だけ。つまり8名の内5名が京大・阪大で、内京大の2名と阪大の1名は「自学」で合格しました。
先月ご紹介しましたように、自宅浪人でまったく一人で受験準備をした自らの経験があるので、最近の予備校頼りの風潮を不思議に思い、以前、友人の県立奈良高校や私立一貫校の先生にたずねたことがあります。
「今は学校の指導だけでは難関大学受験は無理なのか? たとえば、よい参考書で自分だ けで勉強するという・・・」
すると答えが
「ちゃんとした指導ができる学校に行けば大丈夫なんだけど、必要もないのに、わざわざ予 備校に行って、学校に来たら寝てる子がたくさんいる・・・」
何をか言わんや。何のための中学・高校受験なのか。
そんなことであれば、中学受験・高校受験、そしてそのためのハードな受験勉強なんか、まったく意味がないと思いませんか? しっかりした指導があり、勉強もできる学校へ行くために受験勉強したのではなかったのか? そういう子に限って、あなた任せのまま、予備校でもきっと「鼻提灯」でしょう。それでは合格できません。

十八歳になっても「学習は自らすすんでするもので、教えてもらうものではない」という意識がもてない本人。それを当然のこととして、「疑問視しない、できない」ようになってしまっている周囲の教育環境。
その問題点にみんながもっと注意を向けるべきだと思います。学ぶ意味もわからず目的もなく、ただ良い成績をあげるために追いまくられた「なれの果て」が、こういうところにも現れています。
「自ら学ぶこと」、どんな意味から考えても、それは「生きていくこととは切り離せない」ことです。子どもたちには、小さいころから、かみ砕いてそう伝えておかなければならないと考えています。
一度しかない自らの人生を大切にするために「学び」はあります。活躍するOB諸君は、そのたいせつさを十分わかってくれたからだと信じています。
無理をしなくても、すこぶる順調に育ってくれた彼らの学力養成経過を、よりご理解いただけるように、団のクラス編成・指導内容・指導時間・指導方法について、すこし紹介します。
(1) クラス編成
団には腕白ゼミ(原則三年生)・基礎課程(同四年生)・充実課程(同五年生)・発展課程(同六年生)の四つのクラスがあります(クラス名のあとの「原則」の意味は、他の子より学習が進む子が出ますから、そういう子は特進生として上のクラスに進級するからです)。
その間、後で述べる卒業生のOB教室もふくめ、指導はすべてぼくひとりです。一人の子どもの成長を一人で6~7年間も見続けることができるわけです。

また課外学習や立体授業等、宿泊や野外での活動もつぶさに見ることができますから、子どもの成長というより、一人の人間としての成長にも関わることができます。ちなみに、そのとき心しているのは、以前米作りのところで紹介しました学探三訓、「嘘をつくな・狡をするな・楽をするな」というシンプルな標語です。シンプルなものほどたいせつで奥が深いものです。
各クラスそれぞれ一クラスで、今まで多いときでも十名以内にとどめています。それ以上になると目が届きません。課外学習・立体授業の安全面の確保・十分な指導もできません。
小学校卒業後、また私立中学に進学して、さらに団で学びたいと通ってくれる諸君のために前述のOB教室を用意しています。中学以降の在籍年数は、このOB教室で学んでくれた年数です。
たとえば7期生の京都大学へ進んだY君は小学校4年生で入団し、高校3年まで、都合9年間団で学んでくれたことになります。次週は指導内容と指導時間等についてお話しします。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
立体学習を実践 学習探偵団 http://www.gakutan.com/
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////