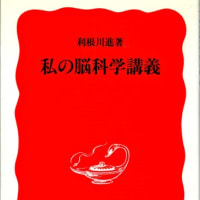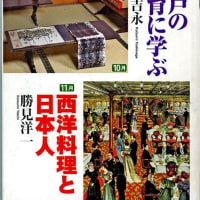教科書をしまって、野道を歩こう。
かつて一世を風靡した寺山修司の「書を捨てよ、町へ出よう」(角川文庫にあり)のイメージからです。単純に「教科書は要らないのか?」と考える人がいるかもしれません。
しかしこの台詞のもとになったアンドレ・ジッドの作品(「地の糧」)はもちろん、寺山修司の作品からうかがえる教養の深さを見ても、決して『書を捨てた』わけではありません。「『書を捨てよう』と云えるほど多く、『書を読んだ』人たち」です。
「教科書がまったく要らない」と言っているわけではありません。ただ、「『教科書に書いていることを教科書だけから学ぶ』ことはやめよう」と云いたいのです。おもしろくないからです。
そういう学習をすれば、教科書どころか、いつのまにか「膨大な書の大海(知の宇宙)」にも乗り出す大きな可能性がある(エジソンは、図書館の本を全部読もうとしました)、学習指導の方法(論)を再考しよう、「新しい学習指導の道に踏み出しましょう」、という提案です。
「発想の転換」によって、「学習内容・学習対象に対する親近感」や「なじみ」が増し、それらを明確に「イメージ」できます。その前提があって初めて、「考えること」ができます。まず学習対象を『知っている』どうかの確認がたいせつです。
「知っている」と「見たことがある」の大きなちがい
「何も(知ら)ないところから、『言葉で表現されたもの』の代表的特徴・性質・エキスだけ」をできるだけ「うまく」理解し記憶に残してゆく、というスタイルが今の学習です。しかし、「まったく手がかりのないもの」や「類似の対象も知らない、新しく聞いたもの」を想像して「イメージを形成し、理解を進める」などと云うことが、「子どもたち(経験値の少ない学習初心者)」に、そんなに「うまく(!)」できるわけはありません。「知らないこと」を最初から興味深く学べる子は少ないでしょう。特に学習を開始する小学校では大いに問題ありです。
「何十年も生きてきた成人(私たち)の経験知の積み重ね」と、「高々10年足らずの乏しい経験で抽象(文字や数字)を頼りに学習を進めなければならない子どもたち」の間には、どの科目においても、(学習)対象のひとつひとつについて、「計り知れない認知度のちがい」があることに、指導する側は、もっと注意を払うべきだと思います。
春、孫娘を「筍掘り」に連れていくことに決めて、「筍って知ってる?」と聞くと、娘(お母さん)が「知ってるよ。この間絵本を見てて、『筍や』ゆうてた・・・」。
これは『知っている』とは言いません。学習するために大切な、「知っている(to know well)」と「見たことがある(to have seen)」の区別がきちんとできていません。このまま学習を進めれば、理解は行き届かず、親近感も持てません。だからおもしろくないのです。子どもたちの大きな「落とし穴」になります。
子どもたちもよく云う、「知ってる!、知ってる!」という返答。その「知っている」はほとんどの場合、「見た
ことがある」だけです。子どもたちは(実は、ぼくたちも)知らないのに、「知っている!」と思って(しまって)います。
「『知っている』を、その程度の『知り方(?!)』でよいもの」と理解し、「実は知らない、ということ」に疑問をいだくまで至りません。「見たことがあって、名前がわかっていれば、知っている」と「思い込んで」います。そういう認識がほとんどです。
「知っている」をそのレベルで納得してしまうと、「おもしろいこと」は始まらず、「好奇心」は育ちません。追求すべき理想は、「みんなが知っている対象知の『一歩先』」です。おもしろさや学習内容への知的探求心の喚起は、現実・実際の姿からうかがえる、その『奥』に隠れています。
指導者には、たとえば「ほんとかなあ? 知ってるかなあ?」という問いかけから始まる、「知のおもしろさ・深さへ子どもたちを誘導する」さまざまな『指導の工夫』や『仕掛け』が欠かせません。
「『竹の子(学習対象の「現物」)』については何も知らない、その『知らないこと』を学べばおもしろくなる、そして『奥のある学習』に波及していく・・・」。指導者は、いつも、そのイメージをもたなければならないと思っています。そういう指導を経て、子どもたちは「学習に、『より』おもしろさを感じて」育ちます。
環覚を育てられる指導者に
「子どもたちの感覚」を実感するには、たとえば「日ごろ、自分たちが通勤するときに、実際に周囲の対象にどれだけ目が届いているか、どれだけ対象を見極めているか」をていねいに振り返ることです。
日々、何か「おもしろいもの」を見つけていますか? ふだんの環境から、何かおもしろいものが立ちあがってきますか? 「みんな知っているもの」と思って、あるいは日々の雑事に追われて、よく見もしないでしょう?
周囲が雑事に追われていても、少し子どもたちに環境のSOMETHINGに注意を向けるようアドバイスすると、子どもたちはさまざまなものに気づき、目を留めて学ぶものです。「おもしろいものがたくさん見つかる年齢」なのです。そのおもしろいものを見つけるセンスが『環覚』です。
おとなのぼくたちは、「『知っている』と思ってしまえば、ほぼ見ない」ように育ってしまっています。その環覚が子どもたちに移れば、『おもしろいもの』があっても、『おもしろいものは何もない』という子に育ちます。周囲がおもしろがらなければ、好奇心は育ちません。おもしろいことが始まらず、学びは広がりません。
まず対象を「きちんと」見て、色や形、そのしくみや変化・推移に目を向ける、観察する。それが「環覚」を育てる指導者としてのスタートです。
通勤途上、雲の流れや、いつも見慣れたはずの景色のそれぞれに視線を移してみる。雲の高い低いや、雲が浮かんでいるようすに、はじめて気づいたりします。少し注視するだけで次第に空に溶け込む山並みのグレーのグラデーションが明らかになります。その色の『気づき』を子どもたちに話します。
「対象」までの大気の層の厚さのちがいに想いが至り、そのかかわりがもたらす「見える色の変化」から、「大気と光のしくみ」というテーマが現れてきます。調べることも出てくるかも知れません。
「大気はふだん意識せず、見えない」がゆえに、その話題は、子どもたちには新鮮な驚きです。
陽光・夕焼けから星の光にも指導展開できるでしょう。何万光年という光の旅路から、「宇宙のとんでもない大きさ」と、「地球の過去の歴史や時間」にイメージが広がります。
夏に捕まえたホタルの発光や、玉虫の発色の秘密。その秘密は、「色が光によって見えている」という事実をはじめて学ぶためには、恰好のテーマです。光の三原色と色の三原色も、彼らには新鮮です。それらは、虫を追いかけ捕まえているから、さらに心に響くのです。光は「ほとんどすべて」にかかわる『切り口』です。あらゆる学習に関係します。葉緑体の緑と光合成と光はそこで結びつきます。
部屋の外では、街路樹や木立が微妙に色や姿を変え、季節を先取りしていきます。ゲームばかりしている場合ではありません。
よく使う大阪線では、大阪から奈良への県境で、春から夏にかけ貴重な笹ユリやきれいな雉子を目にします。秋になると、ひときわ早く、ハゼや漆の鮮やかな紅葉が目に止まります。
自らの日々の発見を子どもたちに伝え、彼らの反応から手応えを探り、次の指導に想いを向ける。子どもたちとの、そうしたやりとりが彼らの「環覚の発達」に大きく貢献します。子どもたちの周囲で、学習対象が少しずつ意味をもち、立ちあがってきます。立体授業の王道です。
空気感・気温・風の音、途中の植え込みや街路樹・飛び交う小虫や舞う落ち葉・鳥のさえずり、庭石や塀の素材や造り・・・これら「ひとつひとつ」の中に、軽視すべからざる成り立ちとしくみ・それぞれのエピソードや歴史が存在します。
指導する側が、日ごろの自らの、それぞれの対象への視点を転換、また逆転することで、指導の方法は大きく広がります。その「ひと味(!)」を子どもたちは、待っています。
現在、小学校や中学校では、「理科や算数を、それぞれの『専門家』の先生にゆだねる」方法が一般的のようです。しかし、ぼくは「専門家であるがゆえに、その視点が画一化し、概して抽象的な指導や解説で終わってしまうことが多い、子どもたちも結局そのままディレッタントで終わってしまう。そういう例も多いのではないか」と想像しています。
「知っているという、その専門性の自覚(自負?)」ゆえに、往々にして、指導の内容が『日常の発想 (ピュアな発想)』ではなく『学習・勉強の範疇』に入ってしまうのではないか。「観察」ではなく、「まとめ」に終わってしまうのではないか。そんな懸念があります。
指導のイメージは、教科書の学習からではなく、「日常生活からさかのぼって学習内容に至る指導」。そう考えるようになりました。まず、「ものの存在」・「もののありよう」に気づいてから指導、という「逆転の発想」です。
専門家ではなくて、謂わば『素人(!)』の先生が、周囲の(学習)対象や(指導)内容に興味をもち、自らの疑問や不思議を発見・解明していくことでこそ、たいせつではないのか。素人的発想(!)や、単純な疑問の「膨らみ」が、子どもたち(私たち)の「環覚」を養う指導の大きなターニングポイントになるのではないか。「環覚の立ちあがり」を誘い、学習をおもしろく変えていく。そう感じています。
専門家が専門を教えることで『天才』が生まれるわけではなく、あらゆる『心ある』先生が子どもたちに「『天才』に育つきっかけ」を与える。日ごろ子どもたちにいちばん長く接する機会のある先生たちが、そういう発想と視点をもち指導にあたることで、子どもたちの、「頭一つ越えた成長」への道が開ける、その後彼らは自ら「天才」を育てる。そう考えています。教科書をしまって、野道を歩こう。