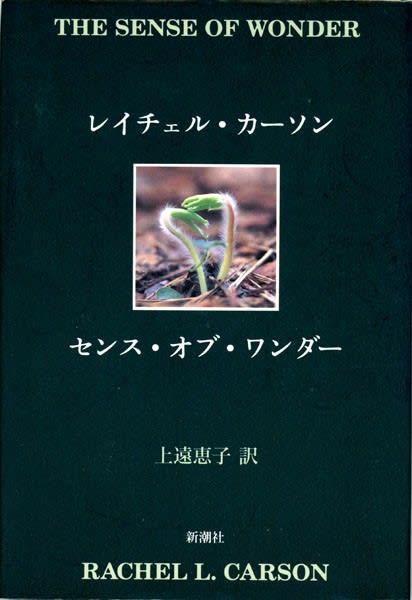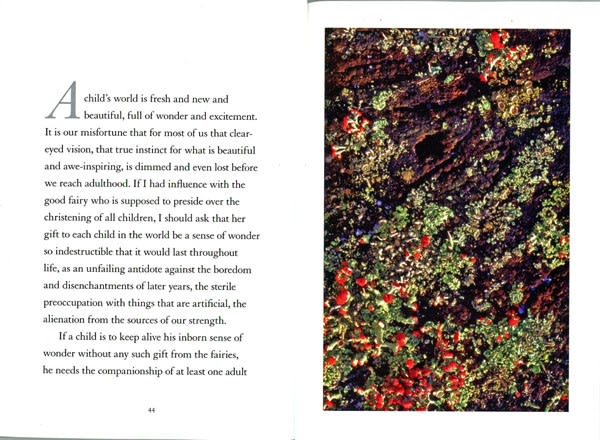今回は十年近く前のノートの一節を紹介します。「環覚」や「学体力」という発想が生まれたころです。
・・・ファインマンの場合は、自然あるいは日々の生活の中で、動植物の生態や自然現象の観察から、「ふしぎや謎を追究するおもしろさ」をお父さんに開示されたこと。それによって「環覚」が養われ、周囲に潜む「ふしぎ」や「謎」の「おもしろさ」に目覚めました。
益川博士のお父さんも、「ものの成り立ちやしくみ(月の動きや自動扉の原理など)」や「科学が応用されている現実」に目を開かせ、子どもの「科学への興味」を喚起しました。
ファインマンのお父さんは、動植物の生態や自然現象の観察から、それらの「成り立ちとしくみ」を問いかけ・考察・反証・再考察・・・という問答で子どもの理解をはかりました。それによってファインマンは自然現象のふしぎや奥行きを追求していく姿勢を身につけました。加えて、小さいころから、超一流の筆者が執筆する大英百科事典を身近に、「科学する」際に欠かせない「調べ、考える習慣」も準備しました。
その結果、ファインマンは「環境を科学すれば、いつもとは限らないが『かけがえのない宝物・ご褒美』を手に入れることができるという実感」を手にしました。同時に、「がまんして努力をつづければ、やがて努力やがまんは報われるのだという確信」が手に入りました(「学体力」の定着)。
「こうして僕はその後の人生を決定づけられ、あらゆる科学に興味をもつようになった。物理が得意なのは偶々なんだ。小さいころにすばらしいものをもらった人が、もう一度それを見つけたいと探しつづけているかのように、僕は科学に魅了されてしまった。まるで子どものように、いつもすてきなものを探しつづけているんだ。探しても、必ず見つかるとは限らないだろうな、きっと時々だろうなということをわかりながらも、ね」
(“What Do You Care What Other People Think?” R.P. Feynman W.W.NORTON 拙訳)
優先すべき「学ぶおもしろさ」
注目すべきは、ファインマンの発言「ぼくはその後の人生を決定づけられ、あらゆる科学に興味をもつようになった。物理が得意なのは偶々なんだ(下線部)」のなかの、「あらゆる科学に興味をもった」というひと言で、「ここから環境に対する興味や好奇心を喚起したお父さんの指導方法」の正しさ・たいせつさを感じとることができます。名称や知識・事項の記憶に終わるのではなく現実世界の対象の「成り立ちやしくみ」の考察や追究をつづけることで、あらゆる科学への興味、つまり「『学ぶおもしろさ』を手に入れることができたのです。
さらに、「学ぶことをつづけていく力(学体力)・好奇心の行方またその延長線上にある科学者(スペシャリスト)」は、「教室での『テキストを使った抽象学習』からではなく、興味をもった対象のおもしろさを追求するところから生まれる」という、「ごくわかりやすい経過と結果」を見ることができます。
エジソンやアインシュタインまた益川博士などの回想から、学校での勉強に対して「肯定的な感じ」はあまり見えてきません。歴史に残る偉人たちに、その無二の業績をもたらしたのは、残念なことに「学校の授業や指導・教育環境であるとは決していえないこと」に注意が必要です。
現状は、経営的にも成果的にも「教育熱心な(?!)」保護者の願望や希望に添い、それらを「頼りにする(せざるを得ない)」システムが目指す指導方法は、目先が少し変わっても「受験というシステムを乗りきるためだけの学習指導のバリエーション」にすぎません。
「『学体力』をつけるための、『学ぶおもしろさ』の習得に心を砕く」のではなく、「受験学習の『手順』や『テクニック』を伝えること」に、多くの時間と神経が使われている現状から、現在はさらに否定的な事態が進んでいるのではないでしょうか? 「いや、うちの学校では『先端科学』や『宇宙工学』だって取り入れている」。そういう方々には、ぼくより説得力がある益川博士の次のコメントに注目してください。
科学教室などで、目を引く実験をしているところもあります(南淵・今は花盛りです!)が、単に見せ物だけで終わってしまっては意味がありません。そこから自然のどんな性質や現象がわかるのか、というところまでつきつめていくのが大切です。それが「手品」と「科学」の違いだと思います。
(「益川博士のロマンあふれる特別授業」益川敏英著 朝日学生新聞社 p37)
これは、偶に「手品や目玉イベントで集客をはかる『学習遊園地(?)』へ連れて行くだけではだめだ」ということでしょう? 子どもたちとその学習観・学習環境の改善を心から願うのであれば・・・。
『自然や環境の、身近なふしぎやおもしろさに気づくことも(でき)ない子どもたち』に、さらに「受験以外の」学習しなければならない意味や「何のための勉強か」も伝えないまま、「抽象的な受験学習を抽象的に詰めこみ」、受験学力と「大学進学実績」を誇るだけの現状とシステム。
そこでは眼をキラキラと輝かせ、「次のおもしろい学び」や「大きくなったときの自らの夢」に夢中になる子どもの姿・そういう子どもたちに育てることを目標にする姿勢はほとんど見えてきません。早急に、子どもたちへの指導方法・指導内容をもう一度振り返り、教育本来の目的を現実化する方向に指導をシフトするべきだと考えます。
ほんとうに教育熱心な親の行動は
この課題の解決には、学校や教育機関ばかりではなく、「子どもの成長にもっとも夢を抱くべき、そして責任がある」保護者の「意識の変化」が欠かせません。それがなければ永遠に変わりません。
多くの保護者は「勉強する(させる)のは有名進学塾で、有名中高一貫校で」という認識です。それがうまくいかなければ、塾を変える、あるいは学校にねじ込む(?)というスタイルです。
もちろん、信用するに足りない塾や学校も数多くあるでしょう。しかし、そこで忘れ去られているのは、そうであれば「自分自身で」、という選択肢ではないでしょうか。
敢えてその方法を選択したのがファインマンやエジソンなど数々の偉人たちの親です。子どもが生まれたときの嬉しさは「万人共通」だと信じていますが、「成績がよくなってほしい」や「元気に育ってくれればよい」という自らの願いや思いの「絵空事」で終わるのはなく、「自らの責任と努力の必要性の自覚」が子どもの能力の発揮と成長をしっかり「後押し」したのだとぼくは考えます。
親はみんな、子どもに「賢くなってほしい!」ものですが、自覚しなければいけないことは、そうであれば、まず「今自分が何をすべきか」です。ファインマンのお父さんもエジソンのお母さんも、自らそれを実践しました。
どちらも、もちろん最初は手探りだったことでしょう。しかし、最後まで(実るまで)やり遂げました。「なってほしい」のに「あなた任せ」はそぐいません。親が「実らせる努力」を続けたから実りました。
ファインマンのお父さんは「子どもが科学者になる夢」を描き、エジソンのお母さんは「子どもの可能性を信じ、立派な人に育ってほしい」という大きな夢がありました。そのために二人が、まず始めたことはなにか?
エジソンのお母さんは、好奇心旺盛だったエジソンが「抽象学習」やエングル先生の指導方法に嫌悪感を抱いたので、退学させました。学校や塾をはしごしたのではありません。「他人の」指導方法に見切りをつけたのです。そして子どもが自然や環境で見つけてきた謎やふしぎ(「環覚」の発現です)を「こどもと二人で」解決することに心を砕きました。
ファインマンのお父さんは、まず自然環境や周囲に関心をもたせ、観察をさせて、そのおもしろさを知らせ、成り立ちとしくみの考察や追究を日々つづけました。もちろん、これら二人の指導は日ごろの生活の雑事もあるでしょうから、『できるだけ心がけた』ということでしょう。ところが、当の子どもはうれしくて、いつも「そうしてもらっていた」ような回想になっています。一人のときでも、そうしたことが続けられるようになっていたのでしょう。
いずれも「学習すること」「学ぶこと」の正統です。それによって「考え、理解することのおもしろさ」と「わかることでの自信」という「人生でかけがえのないもの」を手に入れました。もう一度ファインマンとエジソンのお母さんの指導方法をたどって参考にしてください(旧ブログ「ファインマンの父とエジソンの母~参照」)。
おそらく現在でも、彼らは同じような指導を優先したのではないかと考えます。「他からの、半ば強制的に与えられるもの」では得られない、「自らに身についていく『力の自覚』」が、子どもにとっては何よりの喜びです。「自らが使って生きていかなければならない力だから」です。
もうひとつ注目すべきは、ファインマンのお父さんは小さいころから、またエジソンのお母さんはエジソンの退学後、ブリタニカなどの定評ある本を手元に、「子どもたちに生まれた謎」の解明を進めています。正確な知識と「学問」の奥行きや広がりを小さいころから伝えているわけです。
「知らないことだらけの子どもたち」に、まず「知らないことに気づかせる、発見させる」。それが『環覚育成へのきっかけ』です。そこで発見した「謎を解明していくおもしろさ」によって、自らの環境こそ「とっておきの遊園地」「ワンダーランド」であることがわかってきます。子どもたちは「自らの周囲は『おもしろいことだらけ』であること」に気づいていったのです。自らのまわりが「夢の教科書」であることに・・・。ニュートンの云う、「真理の大海」の別名です。
好奇心を刺激してやまない日々、知りたくてたまらない日々こそ、「学体力」の発動です。「学体力」が機能すれば、「受験学力」「受験勉強」もその一部分として必要(悪?)であるという状況判断が成立します。「学ぶこと」の重要性と展望が開けるからです。これは、現在の多くの子どもたちのように、すべて「抽象から入る」という「本末転倒」の学習とは真逆の方法です。
先ほどの益川博士の引用のコメントの前に、こういう一節があります。「教科書に書かれていることをそのまま理解するだけではなく、おもしろいなと思ったことやふしぎだなと感じたことについて、ちょっと背伸びをして、自分なりに考えたり調べたりするのもいいでしょう」。
偉人や先達のアドバイスで注意をすべき点は、引用の下線部です。
たいせつなことは、まず、「教科書に書かれていることを『おもしろいな』と思ったり、『ふしぎだな』と感じることができるかどうか」という点です。偉人や天才たちの多くは、「おもしろいな」「ふしぎだな」と感じることが「ふつうだった」ので、そこに至るまでのアドバイスは、たいてい抜けています。「一般の子どもたちが一般ではなくなるきっかけ」についてのアドバイスや条件までは考慮(感覚)の外です。
たとえば「不思議を感じるようになるには、どれだけよく現実を見ているかによる」はずです。教科書に「書かれている内容」に対して、「興味をもったり、ふしぎに感じたりする感覚」、つまり、それらが「現実のもの」としての「思い」・「なじみ」が、日ごろからどれだけ手に入っているか。そうでなければ「あたりまえ」と「ふしぎ」の比較も区別もできません。比較判断する材料がありません。
今の子どもたちの生活環境の諸々は、テレビであったり、ゲームであったり、つまり「加工されて」、「作られているもの」がほとんどです。さらに悪いことに、それらの中身はほとんどすべて「ブラックボックス化」されていて、「興味をもつチャンス」が生まれにくくなっています。
また今、「周囲のsomethingにふしぎを感じる視点や考えるきっかけが生まれる環境・日常がどれだけあるか」。つまり以前考察した「振りかえリズム」や「ゆっくリズム」があるか? そういう環境であることを周囲がどれだけ意識しているか。
それらを強く意識しないと、「環覚の育成はなされにくい」ということを忘れることはできません。そのためにたいせつである条件の一つが、「振りかえリズム」と「ゆっくリズム」です。旧ブログの一部を再録します。
「ゆっくリズム」と「振りかえリズム」
最近課外学習の移動で自転車を利用することが多くなり、その「スピードと快適さ」の一方で、「たいせつなもの」が失われてしまう(見過ごしてしまうだろう?)懸念も増えました。『ゆっくリズム』と『振りかえリズム』の喪失です。『ゆっくリズム』は「周りを見ながらゆっくり歩く」という、身体を移動させるときのリズム。そして通り過ぎてからも、ふと振り返ってみる『振りかえリズム』。
さまざまな変化や推移に気づき、不思議を見つけ、その謎から子どもたちが「成り立ちやしくみ」をたどっていけるためには、『ゆっくリズム』や『振りかえリズム』がかかせません。
日々の生活でも、交通手段の発達につれ、「移動」は足を離れました。夏休み・春休み、「渋滞でのイライラ」は経験しても、道すがら、目敏く自然に気づき、興味をもつこと、興味をもったものに、ふと手を伸ばすというような体験はほとんどできません。
目的地への直行。外出時に見るものといえば、高速道路や混雑した車の列と見慣れた車内。「ゆっくり道端のものを愛でる」体験はほとんどなくなりました。「スローウォッチング」・「スローシンキング」が、お父さんとファインマンが避暑地で繰り返した体験です。
身体が移動する速さはどんどん増していきますが、視力や感覚はそれにともなって発達したでしょうか? 逆に「視力も感覚もかえって減退(!)」が実態です(眼鏡やエアコンの使用等)。つまり『鈍感』になってきているのです。
自然を知らず、「ゆっくリズム」や「振りかえリズム」のペースを知らなければ、「気づき(finding things out)」は生まれません。周囲に「思いを馳せ」、「気づき」「見て」、そして「考える」という「ゆとりの時間」・「体験の喪失」によって、子どもたちは「おもしろいものを感じるアンテナ(環覚)」を育てる機会・「ものに感じる、子どもだからこその時間」を奪われていきます。ファインマンのお父さんの指導とは正反対です。
自然の諸相に気づかず、その微妙な変化も見る(感じる)ことができない。そのため「自らの周り、自然や社会環境を学習するはずの学習内容」に現実感が乏しく、親近感を次第にもてなくなってしまっている・・・最近の子どもたちを見ていると、そんな気がします。
「自然の『ゆっくリズム』にあわせ、百様に生きているさまざまな植物・動物に触れられる時間」と、車内でお父さんやお母さんと『成績の日常会話』に終始する『移動だけが目的の時間』。それぞれについて『環覚の育成』という点から振り返れば、比較にさえなりません。
次は、「ゆっくリズム」と「振りかえリズム」の典型、「かつては当たり前だった道草」の効用です。
道草の効用
高度経済成長の前までは、子どもたちが車で移動する機会は少なく、遠足も電車と徒歩が中心でした。あちこちにまだ自然の景観が残り、その中を歩く機会がありました。ファインマンがお父さんと森を歩いて観察したような「おもしろいことども」はひとりでも見つけられるような環境と時間の豊かさがありました。
通学路でも自然のありさまや動植物に興味をもつ(つまり、授業の復習になったり、逆に教科書で再発見したりする)きっかけになる「道草」という極上の機会もありました。帰り道の、一跨ぎできる川幅でも、豊かな自然の中を流れる季節の変化や近辺でくりかえされる生物の営み(生死の営み)、自らもその中に位置する五感からの膨大な情報は、至高の学習情報です。「生ける博物館」です。総合的に考えれば、それらの体験は商業ベースで運営されているエアコンの効いたけばけばしい装飾のイベントとは比較にならない貴重なものでした。
今、そういう体験をできる子がほとんどいなくなりました。さまざまな表情・百様の姿も見せてくれる生物たちも、「テレビに出る虫」と「ゴキブリ」にわかれ、植物などは「ただの木」や「名もない草」に『分類(!)』されていきます。いずれにしろ、「動物や植物とともに生きているという感覚」は鈍麻してしまったようです。周囲の街路樹も今では、ほとんど「落ち葉でやっかいな存在」になってしまったのではないでしょうか。
生きている樹木が季節を通して教えてくれる冬芽・新緑・紅葉・落葉・・・身近で気づくその変化は、ぼくたちの人生のあり様も示唆してくれました。生活していれば「やむを得ず」取り組まなければならない「片づけ」や「掃除」。そうした日々の「習慣」さえ、落ち葉は教えてくれました。
「たき火の灰」は鉢植えや庭木の肥料になることを知り、小さな「消し炭」は木炭の生成のイメージを容易にします。お手伝いや体を動かしたあとの、ご褒美の焼き芋の「おいしさ」は格別です。グルメツアーでは手に入れようのない「味わい」です。
たき火と焼き芋は消えてしまっても、「季節の移ろい」で覚える「命の姿」や「生きていくこと」は永遠に子どもたちには伝えなければなりません。
都会の風景・「瞬時に通り抜ける景色」ばかりでは、環境(自らの立ち位置)に眼を留めて観察する子どもたちのアンテナは立ちようがありません。「気づくもの」の損失・「気づく機会」の紛失です。
街中でひっそりと生えている「見知らぬ花」に気づくことができる。「学ぶおもしろさ」を手にできる子はそんな小さな積み重ねをつづけていける子です。自らの立ち位置で環境に興味をもつことができなければ、それだけ学習に対する親近感や「学ぶおもしろさ」の成立はむずかしくなります。
子どもたちの学習はふつう、文字や簡単なイラストだけのテキストを使って学習事項の再構成やイメージの再現をおこなうわけですから、体験・知悉感に応じて理解の深さ・イメージの広がりは大きく変わってきます。「見たことのあるもの」・「通ったことのある場所」・「触れたことのある対象」という条件は、記憶の定着にはもちろん、「学習がおもしろくなるためのかけがえのない条件」のひとつです。ちがいがわかるようになるからです。「身近」への「入り口」です。
たまには、子どもと「道草をする」機会をつくってみてはいかがでしょう。こちらがおもしろくなることで、子どもたちは感応します。それが、ファインマンのお父さんやエジソンのお母さん、レイチェル・カーソンへの第一歩です。