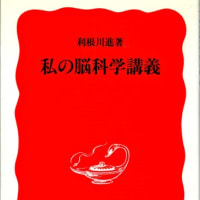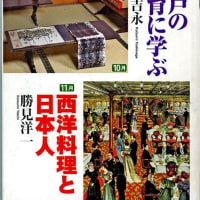がんばって、と言ってますか?
かつて、ひとりのお母さんが
「先生、この子、宿題に時間がかかってしょうがないので、減らしていいですか」。
また、別の日、同じお母さんが
「怖がるので、身内の葬儀には連れて行かないし、死に顔も見せたことがない」。
育てられた男の子は他の子に比べてなかなか成績が上がらず、中学受験した数校すべて不合格でした。ランクを落とした最後に何とか滑り込めたのですが、苦戦の原因はどこにあるかわかりますか?
団の宿題は、学力や志望校、不得意科目、性格などすべてを考慮し、「必要最小限のもの」を提案しています。受験するにはこれくらいはおさえておかなくてはならないという程度です。大手進学塾や他の受験塾とは比べものにならない少量です。その準備ができないのですから、結果が芳しくないのは当たり前です。

受験に限らず、何か願いを叶えたかったり、目的を達成しようと思ったら、レベルに応じた我慢や努力は欠かせません。他の諸君とおなじように合格したければ、少なくとも彼等と同程度の努力や我慢が必要だということを教えなくてはなりません。まずお母さんがそのことを理解していません。
「我慢をさせず」ほしいものは何でも与える。「意見を聞いて、すべて子どものいうとおりにする」というように育てた「軟弱さ」が、入学試験など一人でパフォーマンスしなければならないときに、「詰めの甘さ」や「精神的な弱さ」して露呈するのは当然です。
意見を聞いて自主性に任せるのは中学生になってから。小学生時代に教えるべきことを教え、きちんと判断力や理解力を身につけてから。当然の指導やしつけをしないから中学生になってから、手の打ちようがなくなってしまうのです。指導やしつけの順序が逆です。
こういう文書があります。(以下はNHK「知るを楽しむ―江戸の教育に学ぶ」のテキスト、河合敦さんのコラムを参考にさせていただきました)
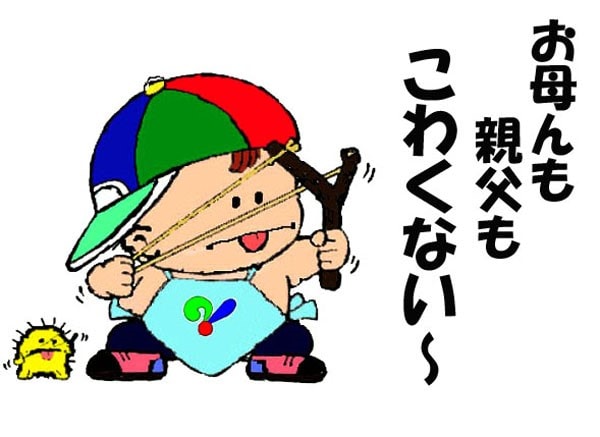
一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ。
二、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ。
三、虚言(南淵注 うそ)を言うことはなりませぬ。
四、卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ。
五、弱いものをいじめてはなりませぬ。
六、戸外でものを食べてはなりませぬ。
七、戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ。ならぬことは、ならぬものです。
これは江戸時代、会津藩で子どもたちが唱和した「什の掟」と呼ばれるものです。
会津藩では六・七歳になると子どもたちは城下の寺子屋や私塾に入りましたが、同時に「什」と称する十名前後のグループに属し、行動をともにしました。そのリーダーは9歳(小学校3~4年生です!)でした。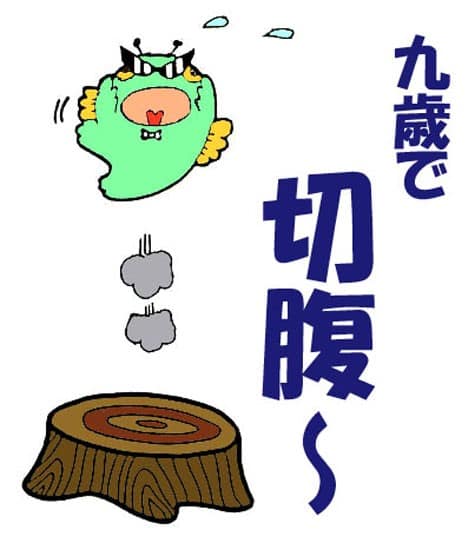
毎日遊びを始めるときは仲間(今でいえば幼稚園の年長児(!)から2年生)に向かって、「什の掟」を読み上げ、子どもたちは一条終わるごとに返事をし、お辞儀をしなければならなかったといいます。
掟を読み終えたリーダーが「昨日より今日まで掟に背いたものはあるか」と尋ね、違反を誰かに告訴されたり告白したものがいたら、みんなの制裁を受け、罰則が待っていました。 
河合さんは、こうした規範があったため、会津藩士は掟を破らず武士らしく行動する習慣が身についたといいます。 また、寺子屋や私塾から戻った子どもたちは、羽織袴姿のままで仏間に入り、「いつ藩主から切腹を申しつかってもいいように」切腹の練習もしました。
江戸時代には一般の寺子屋で使われている教科書も、三行半と呼ばれる離縁状をはじめ各種の契約書など、日常生活で大人が使用するものを教材にして学んでいました。
もちろん、こうした例を挙げたからといって「什の掟」や「切腹」がすばらしいという意味ではありません。現在の子どもたちが、年齢よりいかに幼く、「超保護!」に育てられているかの参考にするためです。

小学校の運動会も、ほとんど個人レベルの競争・競技がなくなりましたが、それが極端に過保護で一面的な考え方だという認識はないようです。足の速い子や遅い子、勉強のできる子できない子、喧嘩の強い子弱い子、力の強い子や弱い子、歌のうまい子、絵のうまい子等、それぞれちがいがあるから人間らしい社会です。
「こっちで負けたけど、あっちで頑張ろう」という意欲、「その差を克服する努力」が個としての存在を確立し、個性を育み、お互いを尊重し合う結果になります。協力関係が成立します。

正々堂々の競争は自らを鼓舞し、さらに自らのレベルを上げていくための原動力になっていくはずです。いいかげんなレベルでのお互いの「傷のなめあい」ではなく、強さ・弱さを自覚し、それぞれが補い合うことで、より親近感が増し、社会全体のバランスもしっかりとれるようになります。
いくらオブラートに包んでも、ぼくたちの社会の根底には、いたるところに競争の網があります。動物の進化を考えても、受精や誕生そのものが競争の原理に基づいています。廃用萎縮というからだのしくみは、「それを避けては順調に生き延びられない」ということを表しています。
また、「健康」状態一つとってみても、身体は日々数多の悪性細胞やウィルス、病原菌と競争しています。「戦って勝ち抜いて」健康でいられるわけです。競争もない無菌状態の中では健康を維持する免疫機能さえ成立しません。
競い合うことの大切さ、自分が競争できるものを見つけることの大切さ、しっかり目を見開いて、競争に旅立つ子どもたちを勇気づけて送り出してあげましょう。「頑張ってね」と。子どもは、ひとまわりもふたまわりも大きく育つはずです。
死を見つめる目がたいせつなことを教えてくれる
先に「身内の死を怖がる」という話が出ました。ずっと子どもたちに話してきたことですが、「死」について考えてみます。そこからすべてが始まります。
有名な秦の始皇帝のエピソードをはじめ、死ぬことを厭い、不老不死を望んだ人はたくさんいます。また、ぼくたちも命の短さを儚みます(この「はかない」という字が人の夢と書くのはほんとうにいいですね)。
もし、不老不死であれば、この世の中に「愛」や「努力」、「成長」や「進歩」という前向きの姿勢や概念は生まれなかったのではないか、 「いつでもできる」「いつでも手に入る」という前提の下ではこうした行動や概念は生まれません。
限りある命を意識し、死を見つめることで、生を共にしている人へのいとおしさや愛が生まれます。一人では限りがあり営みを完結できないが故に、ぼくたちは完全なもの・より良きものにあこがれ、目標を決め、努力できます。 つまり「寿命があることで、ぼくたちはかけがえのないものをたくさんもらっている」わけです。
生命に限りがあるので退屈な日々ではなく、苦しみながらも人生に幅ができ、心豊かな日々を送ることができます
ところが、高齢社会にもかかわらず、「死を見たくない」ばかりではなく、「できるだけ忘れるように」、病・老・死を表面上はともかく、「できるだけ隠そう、排除しよう」とする社会になってしまっているのではないでしょうか。若い人は死を知らない・考えない。ニュースで報じられる様々な事件は、そうした傾向の典型だと思います。核家族化が進み、少年たちは自らも「年をとること」、「弱くなること」がイメージできず、また「老いること」、「醜くなること(彼等が考える)」、「死ななければならないこと」が分からずに育ってしまった。
もちろん環境の変化や教育機関、保護者の指導や躾(これもいい字ですね。「しつけ」とは「身」を美しく保つことです)等、様々な原因が輻輳していることは否定できません。しかし、根源にあるのは、「成長の過程で人の死や老いに向き合う環境がなくなってしまったこと」にあると思っています。自然体験の不足も大きな原因のひとつでしょう。
貧しかった日本では、かつて家で病人を囲い、家族全員で病気の成り行きを見守り、その症状に一喜一憂するということが一般的でした。一人が病気になることで、その人が家族にしめる「重さ」が分かりました。
子どもたちは「病む苦しみ」を側で見て、「つらさ」を感じながら育ちました。家族の絆を保ちつつ、やさしさを身につけて育ちました。そして、一つの命が終わったとき、「生きること」の確認と「生命のたいせつさ」を考える機会がありました。優しさや思いやり、「人間らしい」感情は、「死」を見つめ、死を考える環境や経験、意識があってこそ豊かに育ちます。
当時は「生命の限り」が一定の重みと迫力をともない部屋の片隅に鎮座していました。教壇で先生が漏らす「少年老いやすく学成りがたし」という言葉や「人生五十年・・・」という謡、方丈記、平家物語の冒頭・・・卑近な例でも「命短し、恋せよ乙女・・・」と歌われた歌謡曲等、考えてみればきりがありません。
小さいときから子どもたちに死や老いをしっかり正面から見つめさせること、考えさせることによって、命の大切さを想い、他人を大切に考えられる愛情豊かな子が育っていきます。自らの生命、他人の生命が年とともに衰え、やがては必ず消えてなくなるということが分かったとき、ほんとうに大切なものがはっきり見えてきます。
ところが、今は「死」も「病」も「日常からなくなった方がいいもの」、「特殊なもの」になってしまいました。「死」を医師や病院にゆだねたことで、「死」は常にぼくたちの元にあるにもかかわらず、意識だけ遠ざかった。「死」は他人事、単に「医療技術上のこと」になりはて、助かりたいという意識ばかりが先行します。きちんと死と向き合い見つめることをしなくなっているため、そのぼんやりした死の不安が逆に増幅し、さらに「病」を生むようになってしまった。「死」はどこかへいってしまいましたか。
ぼくたちは常に「今ある自分」から出発しなければなりません。病の床にあろうと、年老いていようと、悩みを抱えていようと、事情がどうであろうと、今ある自己、やがては虚空に消える自己が唯一の自己、もとにしなければいけない自己です。逃げることはできません。
まだ知らないけれど、子どもだって同じです。厳しい現実ですが、みんな平等です。
人は「死なないこと」を前提にはできません。それができるのは映画のなかだけです。平均寿命が延びようと、医学がいくら発達しようと死は厳然と確実に訪れます。さらに日々身体の中では生と死が繰り返されています。皮膚、内臓では肝臓や腸、酸素をはこんでくれる赤血球など、さまざまな細胞が死んでいき、かつ生まれています。意識をしなくても死は思ったよりも「身近な」存在なのです。
ノーベル賞受賞の利根川博士のことばです。

「・・・人間、時間なんて限られているでしょ。自分はあと20年生きるとすると、このあいだに何をするかということさえ、本当なら考えをめぐらすべきでしょう。がんを宣告されて、あと二年しか生きられないと言われた人は、もっとシビアな立場に立つ。この二年間どうやって生きようかと、真剣に考えます。そういう極限の状態にない人は、ずっと生きると思っているから、ゴールがはっきりしない。とくに若い人はそうです。それで、くだらないことでもおもしろいというふうに誤解するのです。やってみれば別にたいしたことでもないことをね。」
( 「私の脳科学講義」利根川進著 岩波書店)
「死」を見つめることをしないと、「今、命があること」が分からず、「今、生きていること」をたいせつにはできません。「今生きているからこそできること」、「いま生きているうちにしなければならないこと」を忘れ、悩まなくてもいいことや悩んでもしょうがないことを悩む無為な時間が増え、「ほんとうに生きているはずの時間」が大して意味をもたないまま闇に消えていきます。
「死ぬこと」を忘れると、「生きていること」も忘れます。「人生の先輩」としてこの厳粛な事実は、子どもたちにきちんと伝えなければなりません。「人間は死ぬからね、今が大事なんだよ」という現実です。
アンチエイジングがブームですが、「いつまでも若く元気で幸福に」というアンチエイジングの考え方の足下を死は容赦なく掬っていきます。アンチエイジングの考え方が悪いのではなくて、もしそういう言葉があるとすれば「ナチュラルエイジング」を忘れてしまっていることが良くないのです。
死について話す機会、死について考える時間はぼくたちにとっても子どもたちにとっても、とてもたいせつです。そうした経験を経て子どもたちは、人間として身につけなければならないものをしっかり身につけ、心豊かに育ってくれると信じています。
なおTo teachers all over the worldは休載します。