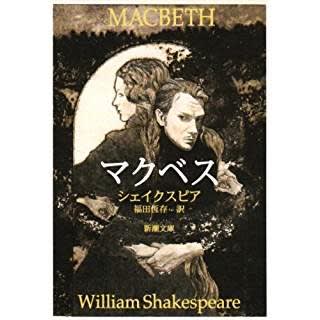ゾラ『居酒屋』(新潮文庫、古賀照一訳)

洗濯女ジェルヴェーズは、二人の子供と共に、帽子屋ランチエに棄てられ、ブリキ職人クーポーと結婚する。彼女は洗濯屋を開くことを夢見て死にもの狂いで働き、慎ましい幸福を得るが、そこに再びランチエが割り込んでくる……。〈ルーゴン・マッカール叢書〉の第7巻にあたる本書は、19世紀パリ下層階級の悲惨な人間群像を描き出し、ゾラを自然主義文学の中心作家たらしめた力作。(内容案内より)
◎酒飲みの男に翻弄される
エミール・ゾラは1840年にパリで生まれました。文筆家としては不遇な時代を重ね、名声を得たのは第7作の『居酒屋』(新潮文庫)からでした。それ以降はフランス自然主義文学の大家として、やがてもう一つの代表作『ナナ』(新潮文庫)へとつなげます。
『居酒屋』の舞台は、19世紀半ばのパリの裏町です。ゾラの最大の武器は、巧みな描写力にあります。まるでパリの下町の風景を、目の当たりにしているような感じがします。登場人物のセリフも一つひとつが心に響きます。洗濯女同士の乱闘場面がありますが、迫力に満ちた素晴らしい筆運びです。
働き者で器量のよい、洗濯女のジュルヴェーズは22歳。10歳のときから、洗濯女として働いています。彼女は愛人ランチェとの間にできた2人の子供を連れて、ランチェとともにパリに転居してきます。ある日ジュルヴェーズは安宿「親切館」で、ランチェの帰りを待ちながら朝を迎えます。ランチェは戻ってきません。女と失踪してしまったのです。
パリの朝の喧騒。待つ人の戻らぬ安宿の窓辺。泣きぬれるジュルヴェーズ。エミール・ゾラはそんな場面から、物語を動かします。酒飲みで浮気者のランチェが失踪した後、ジュルヴェーズは同じ屋根裏部屋に住む、実直なブリキ職人のクーポーと結婚します。
2人の間に、ナナという娘が生まれます。夫婦はそれぞれ勤勉に仕事をし、少しばかりの蓄えもできます。ジュルヴェーズは、将来洗濯屋を開業したいと夢見ています。
◎母と娘の物語
『居酒屋』はジュルヴェーズとナナの物語です。本書では子供時代のナナが、描かれています。ゾラはその後ナナを主人公に据えた、『ナナ』(新潮文庫)という作品を発表します。
ある日ブリキ職人のクーポーは、屋根から落下して働けなくなります。治療費で蓄えが、底をついてゆきます。回復したクーポーは酒を覚え、居酒屋に入り浸ります。実直なブリキ職人の面影は消え失せ、働こうとはしません。
ジュルヴェーズはそんなクーポーを許しながら、健気に働き続けます。そんなときにグージェがお金を貸してくれます。ジュルヴェーズの奮闘で、店は再び隆盛を取り戻します。そこへクーポーが失踪した愛人ランチェを連れてきます。
3人の不自然な生活がはじまります。働く意欲のない2人の男のために、ジュルヴェーズの生活はすさんでゆきます。ナナが家出をします。
家出前のナナは、自由奔放な子供でした。その後のナナについては、『ナナ』で詳しく描かれています。ちょっとだけ文庫案内で、紹介させていただきます。
――名作『居酒屋』の女主人公の娘としてパリの労働者街に生れたナナ。生れながらの美貌に、成長するにしたがって豊満な肉体を加えた彼女は、全裸に近い姿で突然ヴァリエテ座の舞台に登場した。パリ社交界はこの淫蕩な〈ヴィナス〉の出現に圧倒される。高級娼婦でもあるナナは、近づく名士たちから巨額の金を巻きあげ、次々とその全生活を破滅させてゆく。(文庫案内より)
『居酒屋』はどん底に落ちていく、パリの下層階級の物語です。本書でのナナは、なぜか鮮明には描かれていません。おそらく『ナナ』への、伏線のつもりだったのでしょう。『居酒屋』は暗い話なのに、明るい仕上がりになっています。パリの下町の酒を、居酒屋で十分に堪能してください。
(山本藤光:2011.06.09初稿、2018.02.22改稿)

洗濯女ジェルヴェーズは、二人の子供と共に、帽子屋ランチエに棄てられ、ブリキ職人クーポーと結婚する。彼女は洗濯屋を開くことを夢見て死にもの狂いで働き、慎ましい幸福を得るが、そこに再びランチエが割り込んでくる……。〈ルーゴン・マッカール叢書〉の第7巻にあたる本書は、19世紀パリ下層階級の悲惨な人間群像を描き出し、ゾラを自然主義文学の中心作家たらしめた力作。(内容案内より)
◎酒飲みの男に翻弄される
エミール・ゾラは1840年にパリで生まれました。文筆家としては不遇な時代を重ね、名声を得たのは第7作の『居酒屋』(新潮文庫)からでした。それ以降はフランス自然主義文学の大家として、やがてもう一つの代表作『ナナ』(新潮文庫)へとつなげます。
『居酒屋』の舞台は、19世紀半ばのパリの裏町です。ゾラの最大の武器は、巧みな描写力にあります。まるでパリの下町の風景を、目の当たりにしているような感じがします。登場人物のセリフも一つひとつが心に響きます。洗濯女同士の乱闘場面がありますが、迫力に満ちた素晴らしい筆運びです。
働き者で器量のよい、洗濯女のジュルヴェーズは22歳。10歳のときから、洗濯女として働いています。彼女は愛人ランチェとの間にできた2人の子供を連れて、ランチェとともにパリに転居してきます。ある日ジュルヴェーズは安宿「親切館」で、ランチェの帰りを待ちながら朝を迎えます。ランチェは戻ってきません。女と失踪してしまったのです。
パリの朝の喧騒。待つ人の戻らぬ安宿の窓辺。泣きぬれるジュルヴェーズ。エミール・ゾラはそんな場面から、物語を動かします。酒飲みで浮気者のランチェが失踪した後、ジュルヴェーズは同じ屋根裏部屋に住む、実直なブリキ職人のクーポーと結婚します。
2人の間に、ナナという娘が生まれます。夫婦はそれぞれ勤勉に仕事をし、少しばかりの蓄えもできます。ジュルヴェーズは、将来洗濯屋を開業したいと夢見ています。
◎母と娘の物語
『居酒屋』はジュルヴェーズとナナの物語です。本書では子供時代のナナが、描かれています。ゾラはその後ナナを主人公に据えた、『ナナ』(新潮文庫)という作品を発表します。
ある日ブリキ職人のクーポーは、屋根から落下して働けなくなります。治療費で蓄えが、底をついてゆきます。回復したクーポーは酒を覚え、居酒屋に入り浸ります。実直なブリキ職人の面影は消え失せ、働こうとはしません。
ジュルヴェーズはそんなクーポーを許しながら、健気に働き続けます。そんなときにグージェがお金を貸してくれます。ジュルヴェーズの奮闘で、店は再び隆盛を取り戻します。そこへクーポーが失踪した愛人ランチェを連れてきます。
3人の不自然な生活がはじまります。働く意欲のない2人の男のために、ジュルヴェーズの生活はすさんでゆきます。ナナが家出をします。
家出前のナナは、自由奔放な子供でした。その後のナナについては、『ナナ』で詳しく描かれています。ちょっとだけ文庫案内で、紹介させていただきます。
――名作『居酒屋』の女主人公の娘としてパリの労働者街に生れたナナ。生れながらの美貌に、成長するにしたがって豊満な肉体を加えた彼女は、全裸に近い姿で突然ヴァリエテ座の舞台に登場した。パリ社交界はこの淫蕩な〈ヴィナス〉の出現に圧倒される。高級娼婦でもあるナナは、近づく名士たちから巨額の金を巻きあげ、次々とその全生活を破滅させてゆく。(文庫案内より)
『居酒屋』はどん底に落ちていく、パリの下層階級の物語です。本書でのナナは、なぜか鮮明には描かれていません。おそらく『ナナ』への、伏線のつもりだったのでしょう。『居酒屋』は暗い話なのに、明るい仕上がりになっています。パリの下町の酒を、居酒屋で十分に堪能してください。
(山本藤光:2011.06.09初稿、2018.02.22改稿)