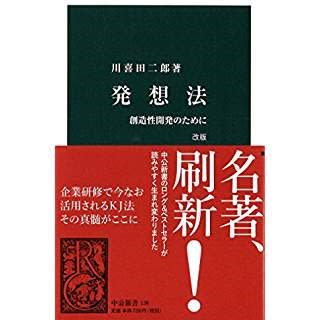柏葉幸子『霧のむこうのふしぎな町』(講談社文庫)

ファンタジー 永遠の名作! 少女の夏の楽しい冒険。心躍る夏休み。6年生のリナは、たった1人で旅に出た。不思議な霧が晴れた後、きれいだけどどこか風変わりな町が現れた。めちゃくちゃ通りに住んでいる、妙ちきりんな人々との交流が、みずみずしく描かれる。『千と千尋の神隠し』に影響を与えた、ファンタジー永遠の名作! 講談社児童文学新人賞受賞
◎小6の一人旅
柏葉幸子は東北薬科大在学中の1974年に、『気ちがい通りのリナ』で講談社児童文学賞を受賞しデビューしています。この作品はのちに、『霧のむこうのふしぎな町』とタイトルを改めて出版されました。柏葉幸子は1953年生まれの児童文学作家です。
本書は『千と千尋の神隠し』に影響を与えた作品として、話題になりました。一人の少女が不思議な異世界へ入り込み、そこで働き、住人との交流を通じて成長していく。基本骨格は同じです。
柏葉幸子『霧のむこうのふしぎな町』は、講談社文庫と青い鳥文庫の2種類が存在しています。2つは挿絵が違います。前者は竹川功三郎、後者は杉田比呂美のものです。
講談社文庫は、絶版で入手が難しいと思います。青い鳥文庫はkindle版になっており、入手は容易です。
物語の冒頭は、次のように展開されます。
主人公の上杉リナは小学6年生。夏休みに父の勧めで、
一人で「霧の谷」へ向かいます。静岡から東北までです。
最寄り駅に着いても、誰も迎えてくれていません。先方に連絡しておくといった父の言葉を思いだして、リナは不安で泣いてしまいます、
そのとき、そばを女の人が通りかかります。「あのう、霧の谷へはどういったらいいんですか?」とリナは尋ねます。女の人は「知らない」と答え、近くの交番へリナを案内します。
リナは赤いかばんとピエロの顔をした柄のついた傘を持ち、
教えられた方向へ歩き出そうとします。そこにリヤカーつきの耕うん機がやってきます。おまわりさんは運転しているゲンじいさんに、途中までこの子を乗せて行ってもらいたいと頼みます。
◎エピソードの宝箱
ゲンじいさんと別れたリナは、教えられた方へと歩き出します。森のなかを奥に進みながら、リナは途方にくれます。そのとき、
――とつぜん、風がプワーとふいた。森はいっせいにガサゴソといい、かさがぱっとひらいて、風にとばされた。(本文P23)
傘については、最後の方で種明かしがなされます。物語の大切な小道具なのです。傘を追っているうちに、リナは「霧の谷」に入りこみます。
――森の深い緑の中には、赤やクリーム色の家があり、石だたみの道は雨がふったあとのようにぬれていた。森の中に、たった六けん。(本文P26)
飛んで行った傘は、大きな邸の玄関前にありました。その家がピコットばあさんの下宿だったのです。ピコットばあさんはリナを冷たく迎え、下宿人にするにはここで働かなければならないと告げます。
下宿には発明家のイッちゃん、名コックのジョン、手伝いをしているキヌさん、ねこのジェントルマンなどがいます。そしてリナは、めちゃくちゃ通りにある様々な店の手伝いに出されます。
本屋、雑貨屋、瀬戸物屋、玩具店などで、リナは転々として働きます。それぞれの店の店主は変わり者で、リナは悪戦苦闘しながら店や店主に溶けこみます。
これ以上、本書に入りこまないでおきます。柏葉幸子は一つひとつの騒動を、実にこまやかに描き出してくれます。『霧のむこうのふしぎな町』は、極上のファンタジーです。ちょっとだけ哀しくて、ちょっとだけ愉快な「霧の谷」は、たくさんのエピソードが詰まった宝箱のようです。
本書を読んでから、また「千と千尋の神隠し」のDVDを観ました。ピコットばあさんと湯婆などの人物造形は、ぴったりと一致していました。そして「霧の谷」も、みごとにアニメーションとして再現されていました。「千と千尋の神隠し」に感動した方には、
お勧めの一冊です。
山本藤光2017.07.31初稿、2018.03.03改稿

ファンタジー 永遠の名作! 少女の夏の楽しい冒険。心躍る夏休み。6年生のリナは、たった1人で旅に出た。不思議な霧が晴れた後、きれいだけどどこか風変わりな町が現れた。めちゃくちゃ通りに住んでいる、妙ちきりんな人々との交流が、みずみずしく描かれる。『千と千尋の神隠し』に影響を与えた、ファンタジー永遠の名作! 講談社児童文学新人賞受賞
◎小6の一人旅
柏葉幸子は東北薬科大在学中の1974年に、『気ちがい通りのリナ』で講談社児童文学賞を受賞しデビューしています。この作品はのちに、『霧のむこうのふしぎな町』とタイトルを改めて出版されました。柏葉幸子は1953年生まれの児童文学作家です。
本書は『千と千尋の神隠し』に影響を与えた作品として、話題になりました。一人の少女が不思議な異世界へ入り込み、そこで働き、住人との交流を通じて成長していく。基本骨格は同じです。
柏葉幸子『霧のむこうのふしぎな町』は、講談社文庫と青い鳥文庫の2種類が存在しています。2つは挿絵が違います。前者は竹川功三郎、後者は杉田比呂美のものです。
講談社文庫は、絶版で入手が難しいと思います。青い鳥文庫はkindle版になっており、入手は容易です。
物語の冒頭は、次のように展開されます。
主人公の上杉リナは小学6年生。夏休みに父の勧めで、
一人で「霧の谷」へ向かいます。静岡から東北までです。
最寄り駅に着いても、誰も迎えてくれていません。先方に連絡しておくといった父の言葉を思いだして、リナは不安で泣いてしまいます、
そのとき、そばを女の人が通りかかります。「あのう、霧の谷へはどういったらいいんですか?」とリナは尋ねます。女の人は「知らない」と答え、近くの交番へリナを案内します。
リナは赤いかばんとピエロの顔をした柄のついた傘を持ち、
教えられた方向へ歩き出そうとします。そこにリヤカーつきの耕うん機がやってきます。おまわりさんは運転しているゲンじいさんに、途中までこの子を乗せて行ってもらいたいと頼みます。
◎エピソードの宝箱
ゲンじいさんと別れたリナは、教えられた方へと歩き出します。森のなかを奥に進みながら、リナは途方にくれます。そのとき、
――とつぜん、風がプワーとふいた。森はいっせいにガサゴソといい、かさがぱっとひらいて、風にとばされた。(本文P23)
傘については、最後の方で種明かしがなされます。物語の大切な小道具なのです。傘を追っているうちに、リナは「霧の谷」に入りこみます。
――森の深い緑の中には、赤やクリーム色の家があり、石だたみの道は雨がふったあとのようにぬれていた。森の中に、たった六けん。(本文P26)
飛んで行った傘は、大きな邸の玄関前にありました。その家がピコットばあさんの下宿だったのです。ピコットばあさんはリナを冷たく迎え、下宿人にするにはここで働かなければならないと告げます。
下宿には発明家のイッちゃん、名コックのジョン、手伝いをしているキヌさん、ねこのジェントルマンなどがいます。そしてリナは、めちゃくちゃ通りにある様々な店の手伝いに出されます。
本屋、雑貨屋、瀬戸物屋、玩具店などで、リナは転々として働きます。それぞれの店の店主は変わり者で、リナは悪戦苦闘しながら店や店主に溶けこみます。
これ以上、本書に入りこまないでおきます。柏葉幸子は一つひとつの騒動を、実にこまやかに描き出してくれます。『霧のむこうのふしぎな町』は、極上のファンタジーです。ちょっとだけ哀しくて、ちょっとだけ愉快な「霧の谷」は、たくさんのエピソードが詰まった宝箱のようです。
本書を読んでから、また「千と千尋の神隠し」のDVDを観ました。ピコットばあさんと湯婆などの人物造形は、ぴったりと一致していました。そして「霧の谷」も、みごとにアニメーションとして再現されていました。「千と千尋の神隠し」に感動した方には、
お勧めの一冊です。
山本藤光2017.07.31初稿、2018.03.03改稿