芥川龍之介『羅生門』(新潮文庫)
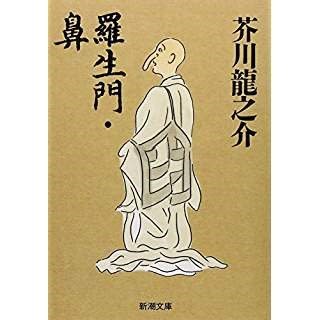
ワルに生きるか、飢え死にするか、ニキビ面の若者は考えた……。 京の都が、天災や飢饉でさびれすさんでいた頃の話。荒れはてた羅生門に運びこまれた死人の髪の毛を、一本一本とひきぬいている老婆を目撃した男が、生きのびる道を見つける『羅生門』。あごの下までぶらさがる、見苦しいほど立派な鼻をもつ僧侶が、何とか短くしようと悪戦苦闘する『鼻』。ほかに、怖い怖い『芋粥』など、ブラック・ユーモアあふれる作品6編を収録。(アマゾン内容紹介より)
◎芥川龍之介のこと
電子書籍に、『芥川龍之介作品集成155』(kindle)がはいりました。短篇小説を150作品収載しており圧巻です。300円で購読できます。私は1日1篇ときめて、寝ころびながら再読しています。「羅生門」は7日目に読みました。経営していた会社を譲渡し、素浪人の心境だったので、追い詰められた老婆と下人の心情が手にとるように理解できました。まったくちがった作品として、「羅生門」がよみがえりました。
『羅生門』は高校の教科書にのっていました。感想文を書かされた記憶もあります。おそらく下人のエゴイズムを、糾弾した内容だったと思います。5年前に書いた『羅生門』の書評を読み直してみました。味気のないものでした。高校時代に読んだときと、寸分違わぬ感想の羅列でした。全面改稿することにしました。
自分の読書力の貧しさに恥じて、識者はいかに『羅生門』を読んでいるのか、それを検証してみることにします。書棚から30冊の関連本を引き抜いてきました。全部を読み通すのに、1か月を要しました。
芥川龍之介の生涯を手短にまとめてありますので、阿刀田高の著書から引用させてもらいます。
――大学在学中に『鼻』という名作をかいて夏目漱石に認められ、さらに『羅生門』によって、一気に文壇の寵児としてデビューしました。それからは一貫して人気作家としての道を歩み続け、最後はいろいろな意味で行き詰まって自殺という形で自らの生涯を閉じました。(阿刀田高『日曜日の読書』新潮文庫P15)
朝日新聞の特集(「はじめての芥川龍之介」2012.1.16朝刊)に、芥川に関するわかりやすい図解がありました。ちょっと紹介させていただきます。図は芥川龍之介を中央にして、上下左右に文人の似顔絵が配されています。
・上段
芥川→室生犀星:自分とは異なる才能を高く評価
芥川→泉鏡花:芥川の葬儀で先輩代表として弔辞
芥川→谷崎潤一郎:小説の「筋」をめぐる文学論争
芥川→高浜虚子:句の添削を受ける
・左右
芥川→菊池寛:同級生
芥川→夏目漱石:師と仰ぐ(夏目と高浜は親友)
・下段
芥川→堀辰雄:芥川を慕う。芥川文学を継承した人
芥川→萩原朔太郎:その詩に感激し寝間着姿で家を訪ねる
芥川→川端康成:後輩作家。関東大震災後,共に市中を見て回る
芥川→宇野千代:送られた小説を厳しく批評
芥川龍之介の実母は、彼が10歳のときに死去しています。母親の愛情を知らないことが、芥川龍之介作品に大きな陰を落としているとする文献は数多くあります。新潮文庫の解説でも、「生いたちの秘密を隠そうとする禁忌の感覚は、実生活の告白をこばむ虚構性を芥川文学の本質として決定することになった」(三好行雄)と断言しています。
◎『羅生門』のこと
芥川龍之介の小説『羅生門』は、『今昔物語集』を素地にした作品です。映画「羅生門」(黒沢明監督)は、国際グランプリを獲得した作品です。ここまでは、誰もがご存知のことと思います、
正確に記せば、『羅生門』は、「今昔物語集」の「羅城門の上層に登りて死人を見たる盗人のこと」(巻29第18)からヒントを得た作品です。黒沢明映画は、芥川龍之介『羅生門』を映画化したものではありません、と書かなければなりません。
そのあたりについて紹介している、文章を引用させていただきます。
――この話(補・今昔物語巻29第18)に取材して、芥川龍之介は傑作『羅生門』を書いた。そこでは男の屈折した心理が細密に解剖されているが、『今昔物語集』は、彼が老婆の懇願を無視して、奪い取った品物を淡々と書き並べるだけである。まるで取り調べの調書のような、無味乾燥が、かえって不気味なほど迫真力を感じさせる。(ビギナーズ・クラッシックス日本の古典『今昔物語集』角川ソフィア文庫P216)
芥川龍之介は素材を『今昔物語集』に求めたものの、まったく異なった作品を書き上げています。関口安義は著書のなかで、「素材は古典に求めながらも、そこには近代人の心理が描かれている」(「関口安義『芥川龍之介』岩波新書P51)と書いています。また黒沢明監督もまったく同様で、タイトルのみ借用し、別物の『羅生門」という映画を完成させました。
――これは(補:黒沢映画)『今昔物語集』の本話や芥川龍之介の『羅生門』とは別のものだ。ただプロローグとエピローグの舞台として、この羅城門が使用されている」(ビギナーズ・クラッシックス日本の古典『今昔物語集』角川ソフィア文庫P216)
『羅生門』の舞台は、平安時代です。下人は「盗人の道」と「餓死の道」の二者択一を迫られています。賞味期限が切れた、食料が棄てられている現在とはちがいます。ホームレスなどという「第三の道」などは考えられません。私はあえて、二者択一と書きました。しかし、常識的に考えるなら、「餓死」などという道を選ぶ人間はいないと思います。
死体から髪の毛を抜く老婆がいてもいなくても、下人は「盗人」の道を選んでいるはずです。今回読み直してみて、このような一本道であるべき展開に、芥川は下人の微細な感情で揺れを巧みに操り、朦朧としたものに仕上げていることを理解しました。また
『羅生門』関連の本を読んでいて、つぎのような記述ともであいました。
――老婆の行為に「あらゆる悪に対する反感」を抱く下人の感情は、合理的には割り切れない。「悪」そのものへの反応であり、死体損壊という具体的な行為に還元され得ないものだった。そこにはカニバリスムのタブーを侵犯するものへの憎悪が見て取れる。(黒田大河「カニバリスムの彼方へ・芥川龍之介と我々の時代」、『国文学解釈と鑑賞』2010年2月号)
芥川の小説からテーマを概念的に抽出する傾向については福田恒存がつぎのように警告しているそうです。孫引きになります。図書館で原書を探しましたが、見つけられませんでした。少し長いのですが引用させていただきます。
――「初期の作品を見てもすぐわかることは、人間の善良さとその醜悪さとを両方同時に見てとる作者の眼であります。ぼくが読者諸君にお願いするのは、さういう龍之介の心を味わっていただきたいといふ一言につきます。『羅生門』や『(「)偸盗(ちゅうとう)』に人間のエゴイズムを読みとってみてもはじまりません。(中略)多くの芥川龍之介解説は作品からこの種の主題の抽出をおこなって能事をはれりとする。さういふ感心のしかたをするからこそ、逆に龍之介の文学を、浅薄な理智主義あるいは懐疑主義として軽蔑するひとたちもでてくるのです。(『名指導で読む筑摩書房なつかしの高校国語』ちくま学芸文庫P042、福田恒存「芥川龍之介」)
短篇小説はさらさらと読み流してはいけない。それをしみじみと感じさせてくれたのが、今回の関連本30冊の完全読破でした。
(山本藤光:2009.06.02初稿、2015.01.18改稿)
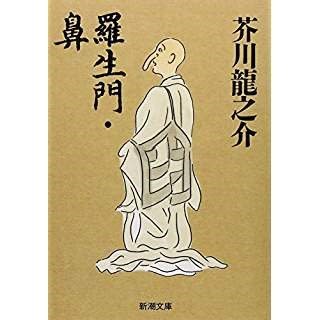
ワルに生きるか、飢え死にするか、ニキビ面の若者は考えた……。 京の都が、天災や飢饉でさびれすさんでいた頃の話。荒れはてた羅生門に運びこまれた死人の髪の毛を、一本一本とひきぬいている老婆を目撃した男が、生きのびる道を見つける『羅生門』。あごの下までぶらさがる、見苦しいほど立派な鼻をもつ僧侶が、何とか短くしようと悪戦苦闘する『鼻』。ほかに、怖い怖い『芋粥』など、ブラック・ユーモアあふれる作品6編を収録。(アマゾン内容紹介より)
◎芥川龍之介のこと
電子書籍に、『芥川龍之介作品集成155』(kindle)がはいりました。短篇小説を150作品収載しており圧巻です。300円で購読できます。私は1日1篇ときめて、寝ころびながら再読しています。「羅生門」は7日目に読みました。経営していた会社を譲渡し、素浪人の心境だったので、追い詰められた老婆と下人の心情が手にとるように理解できました。まったくちがった作品として、「羅生門」がよみがえりました。
『羅生門』は高校の教科書にのっていました。感想文を書かされた記憶もあります。おそらく下人のエゴイズムを、糾弾した内容だったと思います。5年前に書いた『羅生門』の書評を読み直してみました。味気のないものでした。高校時代に読んだときと、寸分違わぬ感想の羅列でした。全面改稿することにしました。
自分の読書力の貧しさに恥じて、識者はいかに『羅生門』を読んでいるのか、それを検証してみることにします。書棚から30冊の関連本を引き抜いてきました。全部を読み通すのに、1か月を要しました。
芥川龍之介の生涯を手短にまとめてありますので、阿刀田高の著書から引用させてもらいます。
――大学在学中に『鼻』という名作をかいて夏目漱石に認められ、さらに『羅生門』によって、一気に文壇の寵児としてデビューしました。それからは一貫して人気作家としての道を歩み続け、最後はいろいろな意味で行き詰まって自殺という形で自らの生涯を閉じました。(阿刀田高『日曜日の読書』新潮文庫P15)
朝日新聞の特集(「はじめての芥川龍之介」2012.1.16朝刊)に、芥川に関するわかりやすい図解がありました。ちょっと紹介させていただきます。図は芥川龍之介を中央にして、上下左右に文人の似顔絵が配されています。
・上段
芥川→室生犀星:自分とは異なる才能を高く評価
芥川→泉鏡花:芥川の葬儀で先輩代表として弔辞
芥川→谷崎潤一郎:小説の「筋」をめぐる文学論争
芥川→高浜虚子:句の添削を受ける
・左右
芥川→菊池寛:同級生
芥川→夏目漱石:師と仰ぐ(夏目と高浜は親友)
・下段
芥川→堀辰雄:芥川を慕う。芥川文学を継承した人
芥川→萩原朔太郎:その詩に感激し寝間着姿で家を訪ねる
芥川→川端康成:後輩作家。関東大震災後,共に市中を見て回る
芥川→宇野千代:送られた小説を厳しく批評
芥川龍之介の実母は、彼が10歳のときに死去しています。母親の愛情を知らないことが、芥川龍之介作品に大きな陰を落としているとする文献は数多くあります。新潮文庫の解説でも、「生いたちの秘密を隠そうとする禁忌の感覚は、実生活の告白をこばむ虚構性を芥川文学の本質として決定することになった」(三好行雄)と断言しています。
◎『羅生門』のこと
芥川龍之介の小説『羅生門』は、『今昔物語集』を素地にした作品です。映画「羅生門」(黒沢明監督)は、国際グランプリを獲得した作品です。ここまでは、誰もがご存知のことと思います、
正確に記せば、『羅生門』は、「今昔物語集」の「羅城門の上層に登りて死人を見たる盗人のこと」(巻29第18)からヒントを得た作品です。黒沢明映画は、芥川龍之介『羅生門』を映画化したものではありません、と書かなければなりません。
そのあたりについて紹介している、文章を引用させていただきます。
――この話(補・今昔物語巻29第18)に取材して、芥川龍之介は傑作『羅生門』を書いた。そこでは男の屈折した心理が細密に解剖されているが、『今昔物語集』は、彼が老婆の懇願を無視して、奪い取った品物を淡々と書き並べるだけである。まるで取り調べの調書のような、無味乾燥が、かえって不気味なほど迫真力を感じさせる。(ビギナーズ・クラッシックス日本の古典『今昔物語集』角川ソフィア文庫P216)
芥川龍之介は素材を『今昔物語集』に求めたものの、まったく異なった作品を書き上げています。関口安義は著書のなかで、「素材は古典に求めながらも、そこには近代人の心理が描かれている」(「関口安義『芥川龍之介』岩波新書P51)と書いています。また黒沢明監督もまったく同様で、タイトルのみ借用し、別物の『羅生門」という映画を完成させました。
――これは(補:黒沢映画)『今昔物語集』の本話や芥川龍之介の『羅生門』とは別のものだ。ただプロローグとエピローグの舞台として、この羅城門が使用されている」(ビギナーズ・クラッシックス日本の古典『今昔物語集』角川ソフィア文庫P216)
『羅生門』の舞台は、平安時代です。下人は「盗人の道」と「餓死の道」の二者択一を迫られています。賞味期限が切れた、食料が棄てられている現在とはちがいます。ホームレスなどという「第三の道」などは考えられません。私はあえて、二者択一と書きました。しかし、常識的に考えるなら、「餓死」などという道を選ぶ人間はいないと思います。
死体から髪の毛を抜く老婆がいてもいなくても、下人は「盗人」の道を選んでいるはずです。今回読み直してみて、このような一本道であるべき展開に、芥川は下人の微細な感情で揺れを巧みに操り、朦朧としたものに仕上げていることを理解しました。また
『羅生門』関連の本を読んでいて、つぎのような記述ともであいました。
――老婆の行為に「あらゆる悪に対する反感」を抱く下人の感情は、合理的には割り切れない。「悪」そのものへの反応であり、死体損壊という具体的な行為に還元され得ないものだった。そこにはカニバリスムのタブーを侵犯するものへの憎悪が見て取れる。(黒田大河「カニバリスムの彼方へ・芥川龍之介と我々の時代」、『国文学解釈と鑑賞』2010年2月号)
芥川の小説からテーマを概念的に抽出する傾向については福田恒存がつぎのように警告しているそうです。孫引きになります。図書館で原書を探しましたが、見つけられませんでした。少し長いのですが引用させていただきます。
――「初期の作品を見てもすぐわかることは、人間の善良さとその醜悪さとを両方同時に見てとる作者の眼であります。ぼくが読者諸君にお願いするのは、さういう龍之介の心を味わっていただきたいといふ一言につきます。『羅生門』や『(「)偸盗(ちゅうとう)』に人間のエゴイズムを読みとってみてもはじまりません。(中略)多くの芥川龍之介解説は作品からこの種の主題の抽出をおこなって能事をはれりとする。さういふ感心のしかたをするからこそ、逆に龍之介の文学を、浅薄な理智主義あるいは懐疑主義として軽蔑するひとたちもでてくるのです。(『名指導で読む筑摩書房なつかしの高校国語』ちくま学芸文庫P042、福田恒存「芥川龍之介」)
短篇小説はさらさらと読み流してはいけない。それをしみじみと感じさせてくれたのが、今回の関連本30冊の完全読破でした。
(山本藤光:2009.06.02初稿、2015.01.18改稿)












