
最近読んだ本にフェミニズム系文学者の下河辺美知子さんが、篠原沙里のペンネームで書いた「スマップ・ウォッチング」がある。スマップ・ファンではないが、サブタイトルの「アイドルで平成日本社会を読み解く」に惹かれた。老若男女幅広いファン層を持つスマップの話で、芸能界に疎い小生でも名前と顔が一致するくらいの国民的なアイドルだ。歴史を動かしてきたイデオロギーは、大衆文化の中にこそ息づいてきたという著者の観点からスマップを観察していて興味深い。
グループの場合、メンバーの名前が売れると直ぐに独立というケースが多い中、不動のメンバーで活躍しているのは驚異なのだが、それでいてドラマ、CM にとメンバー個々の活動にも制約がない。 MJQ の名で知られるモダン・ジャズ・カルテットと似ている。52年に発足以来、55年にドラマーがケニー・クラークからコニー・ケイに変わっただけで74年に解散するまで不動のメンバーで活動していた。MJQ 以外でもジョン・ルイス、ミルト・ジャクソン、パーシー・ヒース、ケイ、それぞれセッションは数多い。
近年、多様化するジャズ界だが、MJQ はどの時代を聴いても大きな音楽的変化はなく、グループ表現は揺るぎのないものだ。4半世紀にも及ぶ MJQ の活動期間にはスタイルや音楽性の変遷もあり、変貌を遂げたプレイヤーも数多い。時代の流れに迎合したり、自らの音楽的発展により変わることも必要だろうし、それもジャズが発展、進化するうえでは重要なことだとも思う。が、時として変わらないスタイルも切要でもある。それが完成されたフォームなら尚更だ。
大学でも教鞭をとっている篠原さんの、やや追っかけ的な著書によると、全国どの地方都市に行っても会場周辺に見られる現象で「スマップ渋滞」というのがあるそうだ。今日、我妻は「世界に一つだけの花」を歌いながら足取りも軽やかに、その「スマップ渋滞」の札幌ドームに朝早くでかけた。当分我が家では、「キムタクがねぇ・・・中居君がさぁ・・・」が続きそうだ。
グループの場合、メンバーの名前が売れると直ぐに独立というケースが多い中、不動のメンバーで活躍しているのは驚異なのだが、それでいてドラマ、CM にとメンバー個々の活動にも制約がない。 MJQ の名で知られるモダン・ジャズ・カルテットと似ている。52年に発足以来、55年にドラマーがケニー・クラークからコニー・ケイに変わっただけで74年に解散するまで不動のメンバーで活動していた。MJQ 以外でもジョン・ルイス、ミルト・ジャクソン、パーシー・ヒース、ケイ、それぞれセッションは数多い。
近年、多様化するジャズ界だが、MJQ はどの時代を聴いても大きな音楽的変化はなく、グループ表現は揺るぎのないものだ。4半世紀にも及ぶ MJQ の活動期間にはスタイルや音楽性の変遷もあり、変貌を遂げたプレイヤーも数多い。時代の流れに迎合したり、自らの音楽的発展により変わることも必要だろうし、それもジャズが発展、進化するうえでは重要なことだとも思う。が、時として変わらないスタイルも切要でもある。それが完成されたフォームなら尚更だ。
大学でも教鞭をとっている篠原さんの、やや追っかけ的な著書によると、全国どの地方都市に行っても会場周辺に見られる現象で「スマップ渋滞」というのがあるそうだ。今日、我妻は「世界に一つだけの花」を歌いながら足取りも軽やかに、その「スマップ渋滞」の札幌ドームに朝早くでかけた。当分我が家では、「キムタクがねぇ・・・中居君がさぁ・・・」が続きそうだ。










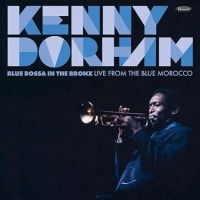

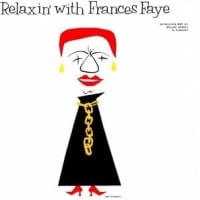

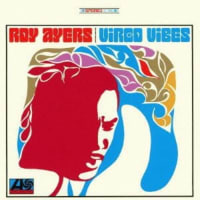

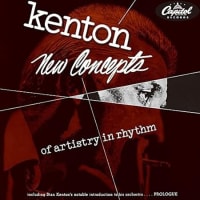


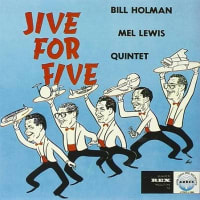





どちらかというとMJQのユニットの中での
プレイよりも、フリーブローイングなセッションでの
彼のヴァイブのほうを、より好みます。
MJQをジョン・ルイスとミルトの双頭リーダー・コンボと
見る向きもありますが、私から見ればあれは
明らかにジョン・ルイスがリーダーのグループという印象。
「野人ミルト」の魅力は、MJQという規制が
外れた時のほうがより発揮されていますね。
スタイルが変わる、変わらないという話題が出ていましたので、
ちょっと私見を(以前にも、どこかで書いたと思いますが)。
(1)MJQのように、いつの時代も頑固なまでに
演奏スタイルを変えないで、ファンの気持ちを
惹きつけている人たち。
例えば、ソニー・スティット、ズート・シムスなんか、そうでしょうか。
(2)逆に、時代を先取りして、常に変化していく
ことによって自らの音楽性を高め、成功しているジャズメンもいます。
なんたって、マイルスがその筆頭でしょう!
トレーンもしかり、一時期のゲッツもそうかな?
ああ、ウェイン・ショーターも忘れてはいけません。
(3)変化することに失敗して、人気が下落した人もいますね。
ジョー・ヘンダーソンなんか、そうかなという気がします。
(4)また、変化しないことで飽きられてしまった人。
ほんの短い期間しか表舞台にいれなくて消えていった
人々っていうのは、たいていこれに入るのでは?
ジャズメンを大雑把に分類すると、上記4種類に
たいがいは入るんじゃないかな、と思っていますが
如何でしょう?
MJQはジョン・ルイスが音楽監督でしたので、ルイスのスタイルをコンボで具現したものです。ライブでミルトが乗ってファンキーなソロを展開すると、ルイスに制されたそうです。そういう規制、規律が寿命の長かった一因だとも思います。
スタイルの変化という観点で分類するなら確かに 25-25 さんの仰る通りですし、さらに枝をつけますと・・・
一時変わっても、また元のスタイルに戻るケース
アート・ペッパーやジャッキー・マクリーンでしょうか。マクリーンはフリーで吹いたらファンに殴られたそうです。
マクリーン独白 「度々殴られてもなぁ・・・受けも良くないから前のスタイルでやるか」
金儲けのために思慮分別のないケース
ウエス・モンゴメリー 独白 「次はストリングスをバックにジャズファン以外にも売るか」
ドナルド・バード 独白 「俺もリー・モーガンの真似してジャズロックでもやるか」
「じゃ俺も付き合うか」とはルー・ドナルドソン
二人して「柳の下にどじょうはいなかったか」
フレディ・ハバード 独白 「ストリングスもソウルもファンクもごちゃ混ぜが一番よ」(笑)
アート・ペッパーやジャッキー・マクリーンでしょうか。マクリーンはフリーで吹いたらファンに殴られたそうです。
うん、なるほどそうですね~!
スタイルを変えて、一般受けは良くなったけれども、
真正ジャズ・ファンからは、「ちょっと、ねぇ」
という感じで見られた人もいますね。
例えば、ケニー・ドリューとか。
MJQは、タキシードでバッチリ決めた格調高いグループと言う印象があり、なんとなく敷居が高いなと感じていました。(音楽的には素晴らしいと思うのですが・・・)
個人的には、25-25様同様、ミルト・ジャクソンがグループを離れて出したアルバムのほうが解放された演奏と言った感じで好みです。
ところで昔「誰が来たのかと思って見るとジャクソン(ミルト・ジャクソン)」と言う駄洒落がはやった事を思い出しました。
こんな下らない駄洒落は誰が言い出したのでしょうか。
では、では、
「見るとジャクソン」は、猿の芋洗い現象のようなものでジャズ・ミュージシャンとジャズ喫茶で発祥したのでしょうね。
「こんにちは、 KAMI さん、薄い髪(失礼!)をチック・コリアみたいに決めていますね」
「ええ、韓国製の整髪料を使ってみました」
「ところでデューク、海に行ったの?顔が貝殻みたいですよ」
「シェリー・マン聴いていたら貝殻人間になってしまいましたよ ランチセットのバジルトマトと珈琲ゼリーお願いします」
「今、サラ・ヴォーンかけましたので、皿に入れてお盆でお持ちします」
「こんなに安くて良いの?」
「物価も低落していますからねぇ・・・」
「それでブッカー・リトルかけたんだぁ」
てっきり「ジャンゴ」あたりから聴いていらっしゃるのかと思っておりました。「ピラミッド」を初め MJQ のジャケットはシンプルで、落ち着いたデザインが殆どなのですが、「 Plastic Dream 」には驚きましたよ。本当に MJQ かなぁ?あの堅くて融通が利かないルイスが許したものだと・・・イラストとはいえビーチク・ポロリですから。(笑)
残念ながら私はミルトを生で聴いておりません。マレット・ポロリ(笑)とは驚きですね。今、かみさんがスマップ公演から帰ってきまして随分興奮しておりました。札幌ドーム5万人とか・・・ミルトが稼ぎを嘆くのもわかりますね。
(詳しくはnaruさん掲示板へ)
ミルト・ジャクソンですが、前も書いたと思いますが、僕がマリンバを叩いてたので、ヴァイブのミルト
を聴いた時は感動しました。それまではヴァイブといえば、ハワイアンぽいイメージでしたから、その後、
ハンプトン。バートン。ハッチャーソン。聴きましたが、ミルトジャクソンが一番好きです。初めて聴いたのは、「バグス・グループ」で初めて行ったコンサートは、naruさんと場所は違いますが(虎ノ門ホール)で
やはりレイ・ブラウンとのデュオでした。メーカーはディーガンでしたが、マレットの色までチェックしてるとはnaruさん凄い!そういえばパブロレーベルで「ミルト&ベイシーオーケストラ」(ベイシー物をミルトがメロディー奏でてる)のレコード持ってたのですが、ビッグバンドやってる先輩に貸したまま帰ってきません。これCD出てるんですかねえ~?
ヴァイブのメーカー名まで覚えておられるとは、
よほどヴァイブがお好きなんでしょうか?
ミルト愛用のDeagan 社製のヴァイブは今はもう
製造されていないようです。
現在の最大手は、ゲイリー・バートン使用の
ブランド、Musser を製造するラディック社、
それに対抗するのがYAMAHAなんだそうです。
Deagan は会社としては存続してはいるものの、
楽器は今はわずかにチャイムを作っているだけとか。
>nobu さん。
ミルトwith ベイシーはLPでVol.1 だけ持っていますが、
確かCDでも見たような気がします。
が、自信はありません。
内容的には、期待した割には刺激に欠けるもの
だったように思いますが。
ミルト個人名義のアルバムでは、次のものを
よく聴いています。
○「Much In Common/ Milt Jackson & Ray Brown」
Wild Bill Davis(org), Kenny Burrell(g)参加で
ブルージーそのものの内容。
ゴスペル歌手マリオン・ウィリアムスが数曲に
フィーチャーされていて、これがまた痺れる!
数年前にコンプリートのボックスCDが出たようですが、
ありゃ通して聴くとゲップが出るかも。
LP収録分くらいが、丁度いいようにも思います。
○「Very Tall/ Oscar Peterson 3 with Milt Jackson」
オス・ピのピアノが珍しく控えめなのが、いい!
○「Bags Opus」
ゴルソン、ファーマー、トミ・フラとの共演。
I Remember Clifford が素晴らしい!
○「Soul Fusion」
ジャマイカ出身のピアニスト、モンティ・アレキサンダー
との共演。
スティーヴィー・ワンダーのIsnt She Lovely
なんて、やってます。
○「モントルー75」
オスピとの再会セッション。
ブルー・ミッチェルのオリジナル「ファンジ・ママ」が
絶品です!