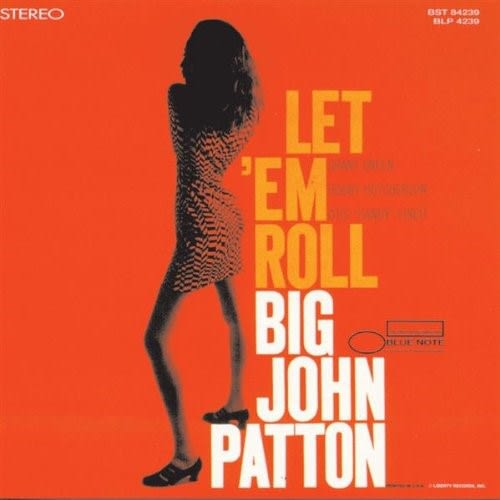CD店の棚を漁っているうち「Trombone for Lovers」というグレン・ミラーかトミー・ドーシーのベスト盤や、ムード・ミュージックのコンピにありそうなタイトルを見付けた。プレイヤーは「Roswell Rudd」とある。これは「あの」ラズウエル・ラッドか?サングラスで目元は分からないが、トロンボーンを吹いているジャケットから察すると「あの」ラッドに間違いなさそうだ。それにしてもタイトルは怪しい。
収録曲はというとカントリー・ミュージックの「Ghost Riders In The Sky」にはじまり、ビートルズの「Here, There & Everywhere」、クリスマス限定の「Baby, It's Cold Outside」、ニーナ・シモンの十八番「Trouble In Mind」、サッチモの代表曲「Struttin' With Some Barbecue」・・・どこが「for Lovers」なんだと思ったところで、サント&ジョニーの「Sleepwalk」に、この手のタイトルの定番「Autumn Leaves」、「September Song」、エリントン楽団にいたアル・ヒブラーの熱唱というより映画「ゴースト/ニューヨークの幻」で有名な「Unchained Melody」と並ぶ。更にブッカー・T&MG'sの「Green Onion」に「Tennessee Waltz」、「Come Sunday」と何でもありだ。
ほとんど知らないメンバーばかりだが、ジョン・メデスキとボブ・ドロウも参加している。「あの」ラッドと言ったのは、60年代前半に「New York Art Quartet」のメンバーとしてニュー・ジャズを推進したトロンボーン奏者だからである。フリージャズ全体の評価はどうであれ、「Everywhere」はコンボ型即興演奏の極致として輝きを失わないし、参加した「The Jazz Composer's Orchestra」の活動はジャズ史に残る。「その」ラッドならM-BASE派のようにスタンダードを切り刻んでいるのではないかって?そんな危惧は1曲目で消えた。アルバムタイトルに相応しい演奏は逆に意表を突く。
ジャズファンなら一度は観た映画「真夏の夜のジャズ」に、エール大学の「Eli's Chosen Six」というディキシーランド・ジャズ・バンドが出てくる。このトロンボーン奏者は長らくラッドだと言われたが、何かのインタビューで本人が否定していた。出演していなくても伝統あるバンドに参加していたのだからスタートはトラディショナル・ジャズであることに間違いない。フリージャズ・ファンは手にすら取らないアルバムも「あの」ラズウエル・ラッドなのである。
収録曲はというとカントリー・ミュージックの「Ghost Riders In The Sky」にはじまり、ビートルズの「Here, There & Everywhere」、クリスマス限定の「Baby, It's Cold Outside」、ニーナ・シモンの十八番「Trouble In Mind」、サッチモの代表曲「Struttin' With Some Barbecue」・・・どこが「for Lovers」なんだと思ったところで、サント&ジョニーの「Sleepwalk」に、この手のタイトルの定番「Autumn Leaves」、「September Song」、エリントン楽団にいたアル・ヒブラーの熱唱というより映画「ゴースト/ニューヨークの幻」で有名な「Unchained Melody」と並ぶ。更にブッカー・T&MG'sの「Green Onion」に「Tennessee Waltz」、「Come Sunday」と何でもありだ。
ほとんど知らないメンバーばかりだが、ジョン・メデスキとボブ・ドロウも参加している。「あの」ラッドと言ったのは、60年代前半に「New York Art Quartet」のメンバーとしてニュー・ジャズを推進したトロンボーン奏者だからである。フリージャズ全体の評価はどうであれ、「Everywhere」はコンボ型即興演奏の極致として輝きを失わないし、参加した「The Jazz Composer's Orchestra」の活動はジャズ史に残る。「その」ラッドならM-BASE派のようにスタンダードを切り刻んでいるのではないかって?そんな危惧は1曲目で消えた。アルバムタイトルに相応しい演奏は逆に意表を突く。
ジャズファンなら一度は観た映画「真夏の夜のジャズ」に、エール大学の「Eli's Chosen Six」というディキシーランド・ジャズ・バンドが出てくる。このトロンボーン奏者は長らくラッドだと言われたが、何かのインタビューで本人が否定していた。出演していなくても伝統あるバンドに参加していたのだからスタートはトラディショナル・ジャズであることに間違いない。フリージャズ・ファンは手にすら取らないアルバムも「あの」ラズウエル・ラッドなのである。