
この2つの回路は、もう皆さんおなじみの「非反転増幅回路」と「反転増幅回路」ですね。そしてゲイン(eo/ei)は、非反転の場合:1+R2/R1、反転の場合:-R2/R1と機械的に求まりました。しかし実は、これはあくまでもオペアンプの開ループゲイン(ネガティブフィードバックしていないときの裸ゲイン)=∞と仮定した場合に成り立つ公式なのです。実際には開ループゲインは有限値であり、入力電圧が直流の場合は110dB~120dBです。120dBとは、さて何倍でしょう。そう、100万倍ということですね。
左下のグラフを見てください。これはLM358の周波数に対する開ループゲインを示しています。電源電圧=30Vの場合を見てみましょう。入力電圧が約8Hzまでは110dBのゲインを有していますが、8Hzを超えると-20dB/decで落ちていきます。100kHzのときはどうでしょう。開ループゲインは20dBしかありません。
さて、では「非反転増幅回路」と「反転増幅回路」の厳密なゲインを求めてみましょう。
①非反転増幅回路のゲイン
A=オペアンプの開ループゲイン(裸ゲイン)、β=R1/R1+R2とします。
eiA-eoβA=eo
eiA=eo+eoβA
eiA=eo(1+βA)
eo/ei=A/(1+βA) ――― ①
右辺をβAで割ると
eo/ei=1/β(1/βA+1)
A=∞とすると
eo/ei=1/β
eo/ei=(R1+R2)/R1
よって
eo/ei=1+R2/R1
このように、A=∞であれば、確かにeo/ei=1+R2/R1となります。
②反転増幅回路のゲイン
0A-{ei+(eo-ei)β}A=eo
-eiA-(eo-ei)βA=eo
-eiA-eoβA+eiβA=eo
-eiA+eiβA=eo+eoβA
-ei(A-βA)=eo(1+βA)
eo/ei=-(A-βA)/ (1+βA) ――― ②
右辺をβAで割ると
eo/ei=-(1/β-1)/ (1/βA+1)
A=∞とすると
eo/ei=-1/β+1
1/β=1+R2/R1であるから
eo/ei=-1-R2/R1+1
よって
eo/ei=-R2/R1
このように、A=∞であれば、確かにeo/ei=-R2/R1となります。
しかし! 非反転増幅回路の厳密なゲインはeo/ei=A/(1+βA)であり、反転増幅回路の厳密なゲインはeo/ei=-(A-βA)/ (1+βA)なのです。
R1=10kΩ、R2=100kΩとして、非反転増幅回路の厳密なゲインを求めてみましょう。
β=10k/(10k+100k)=0.091 となりますね。
入力電圧がDC~8Hzの場合
A=110dBですから開ループゲインは316228倍であり非反転増幅回路のゲインは、
eo/ei=316228/(1+0.091×316228)=10.99となり、ほぼ公式通りの11倍となります。
では入力電圧の周波数が高くなるとどうでしょう。
入力電圧が100kHzの場合
A=20dBですから開ループゲインは10倍であり非反転増幅回路のゲインは、
eo/ei=10/(1+0.091×10)=5.24となります。公式で得られるゲインよりもずいぶん小さな値になりましたね。このように、「非反転増幅回路」「反転増幅回路」のゲインは入力電圧の周波数が高い場合は、十分注意して設計する必要があるのです。
右下のグラフはナショナルセミコンダクタ社のLF355、LF356、LF357の開ループゲイン特性です。LF357の100kHzでのゲインは約40dB(100倍)です。つまり先のLM358に比べて10倍改善されることになりますね。さっそく非反転増幅回路のゲインを求めてみましょう。
eo/ei=100/(1+0.091×100)=9.9となります。まずまずの値ですね。このようにLF357は高周波の用途に向いていますが、LM358に比べるとアイドリング電流が10倍以上大きく、単電源駆動もできません。つまり、オペアンプは用途によって使い分ける必要があるということですね。
関連記事:
オペアンプとは何か? 2007-09-02
スルーレート 2010-01-06
イマジナルショート① 2008-02-01
左下のグラフを見てください。これはLM358の周波数に対する開ループゲインを示しています。電源電圧=30Vの場合を見てみましょう。入力電圧が約8Hzまでは110dBのゲインを有していますが、8Hzを超えると-20dB/decで落ちていきます。100kHzのときはどうでしょう。開ループゲインは20dBしかありません。
さて、では「非反転増幅回路」と「反転増幅回路」の厳密なゲインを求めてみましょう。
①非反転増幅回路のゲイン
A=オペアンプの開ループゲイン(裸ゲイン)、β=R1/R1+R2とします。
eiA-eoβA=eo
eiA=eo+eoβA
eiA=eo(1+βA)
eo/ei=A/(1+βA) ――― ①
右辺をβAで割ると
eo/ei=1/β(1/βA+1)
A=∞とすると
eo/ei=1/β
eo/ei=(R1+R2)/R1
よって
eo/ei=1+R2/R1
このように、A=∞であれば、確かにeo/ei=1+R2/R1となります。
②反転増幅回路のゲイン
0A-{ei+(eo-ei)β}A=eo
-eiA-(eo-ei)βA=eo
-eiA-eoβA+eiβA=eo
-eiA+eiβA=eo+eoβA
-ei(A-βA)=eo(1+βA)
eo/ei=-(A-βA)/ (1+βA) ――― ②
右辺をβAで割ると
eo/ei=-(1/β-1)/ (1/βA+1)
A=∞とすると
eo/ei=-1/β+1
1/β=1+R2/R1であるから
eo/ei=-1-R2/R1+1
よって
eo/ei=-R2/R1
このように、A=∞であれば、確かにeo/ei=-R2/R1となります。
しかし! 非反転増幅回路の厳密なゲインはeo/ei=A/(1+βA)であり、反転増幅回路の厳密なゲインはeo/ei=-(A-βA)/ (1+βA)なのです。
R1=10kΩ、R2=100kΩとして、非反転増幅回路の厳密なゲインを求めてみましょう。
β=10k/(10k+100k)=0.091 となりますね。
入力電圧がDC~8Hzの場合
A=110dBですから開ループゲインは316228倍であり非反転増幅回路のゲインは、
eo/ei=316228/(1+0.091×316228)=10.99となり、ほぼ公式通りの11倍となります。
では入力電圧の周波数が高くなるとどうでしょう。
入力電圧が100kHzの場合
A=20dBですから開ループゲインは10倍であり非反転増幅回路のゲインは、
eo/ei=10/(1+0.091×10)=5.24となります。公式で得られるゲインよりもずいぶん小さな値になりましたね。このように、「非反転増幅回路」「反転増幅回路」のゲインは入力電圧の周波数が高い場合は、十分注意して設計する必要があるのです。
右下のグラフはナショナルセミコンダクタ社のLF355、LF356、LF357の開ループゲイン特性です。LF357の100kHzでのゲインは約40dB(100倍)です。つまり先のLM358に比べて10倍改善されることになりますね。さっそく非反転増幅回路のゲインを求めてみましょう。
eo/ei=100/(1+0.091×100)=9.9となります。まずまずの値ですね。このようにLF357は高周波の用途に向いていますが、LM358に比べるとアイドリング電流が10倍以上大きく、単電源駆動もできません。つまり、オペアンプは用途によって使い分ける必要があるということですね。
関連記事:
オペアンプとは何か? 2007-09-02
スルーレート 2010-01-06
イマジナルショート① 2008-02-01
















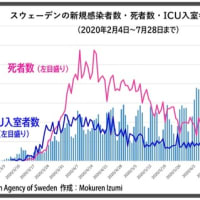










これらの品種は「アナログシンセ」の修理用と考えても特性を理解しておいて損はないと思われます。
特にLM358は未だに海外製の安い電子工作キットでも使われているので入手もしやすいほうです。ベルギー製のバルマンというメーカから出ているキットで使っていますよ!
しかし、今は「RailToRail」のオペアンプが主流なんで、時代は変わってしまいましたねぇ~!
私はオーディオ系にオペアンプを使うのは好きではないので、あまり意識はしていませんが・・・。
テープイコライザとかRIAAイコライザとかにオペアンプを使うとどうしても音が硬くなるんでキライなんです。
(^^)
オーディオ系といえば、昨今のMUSESというオペアンプはどうなんでしょうね。ちょっと気になってます。
http://semicon.njr.co.jp/jpn/MUSES/MUSES01.html
C-MOSじゃダメなんですねぇ~、FETは。
ギターアンプの初段をバイポーラから2SK30Aに作り変えただけで、なんとも音がやわらかくなった・・・という経験もあるんで、初段はやっぱりJ-FETでしょうね!
ギターアンプの初段をバイポーラから2SK30Aに変えて、音が柔らかくなりましたか。う~む、今更ながら興味深い。
よろしいでしょうか? ダメ元でいちおう質問内容を書いておきます。以下のところです。
②反転増幅回路のゲイン
0A-{ei+(eo-ei)β}A=eo
上式の第2項 -{ei+(eo-ei)β} がなぜこうなるのかがわかりません。これを言葉でわかりやすく解説していただけると助かるのですが・・・
それから帰還率が反転、非反転を問わずR1/(R1+R2)になる理由もできれば知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
さて、非反転増幅回路の最初の式
eiA-eoβA=eo も、もう少し細かく書くと
eiA-(eo-0)βA=eo なのです。
これでご理解いただけますでしょうか?
また帰還率βは
β=R1/(R1+R2) と「定義」されますが、反転増幅回路の方が「あれ?」と思うわけですよね。
反転増幅回路も、出力eoから入力eiを引いて、R1/(R1+R2 をかければ、イマジナルショートの値になりますね。